婦人相談所・保護施設・相談員について
この記事では、婦人相談所・婦人保護施設・婦人相談員について書かせていただく
婦人相談所
◆売春防止法第34条に基づき、各都道府県に必ず1つ設置されている(指定都市も設置可能)。
◆元々は売春を行うおそれのある女子の相談、指導、一時保護等を行う施設。婦人保護事業の中で、女性に関する様々な相談に応じる中で配偶者間の暴力に関しても配偶者暴力防止法成立前から相談・保護に取り組んできた。
◆2001年4月に成立した“配偶者暴力防止法”により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとして位置づけられた。
なお、配偶者暴力相談支援センターが行う業務のうち、一時保護については、婦人相談所が自ら行うか、婦人相談所から一定の基準を満たす者に委託して行うこととなる。
◆2013年6月の“ストーカー行為等の規制等に関する法律”改正により、ストーカー被害女性の支援を婦人相談所が行うことについて明確に位置付けられた。
婦人保護施設
◇売春防止法第36条により、都道府県や社会福祉法人などが設置できる施設。
◇もともとは売春を行うおそれのある女子を収容保護する施設だったが、現在では、家庭環境の破綻や生活の困窮など、様々な事情により社会生活を営む上で困難な問題を抱えている女性も保護の対象としている。
◇2001年4月に成立した“配偶者暴力防止法”により、婦人保護施設が配偶者からの暴力の被害者の保護を行うことができることが明確化された。
婦人相談員
◆売春防止法第35条に基づき、社会的信望があり、熱意と識見を持っている者のうちから、都道府県知事又は衣装から委嘱され、要保護女子等の発見、相談、指導等を行う。
◆“配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律”第4条により、配偶者からの暴力被害者の相談、必要な指導を行う。
以下に厚生労働省のHPに載っていた婦人保護事業に関するPDFを画像化したものを載せる
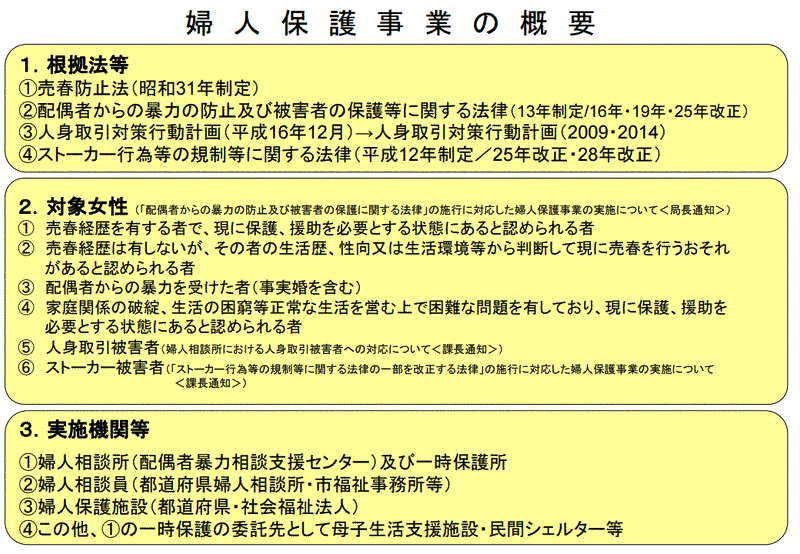

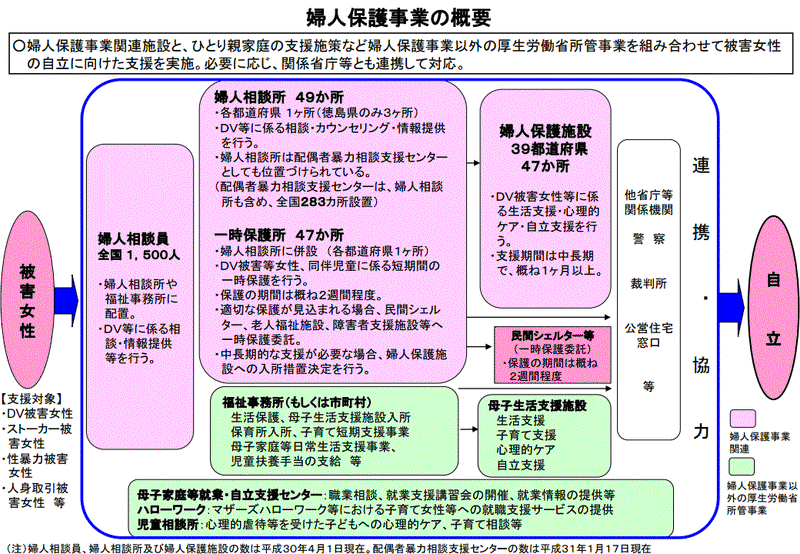


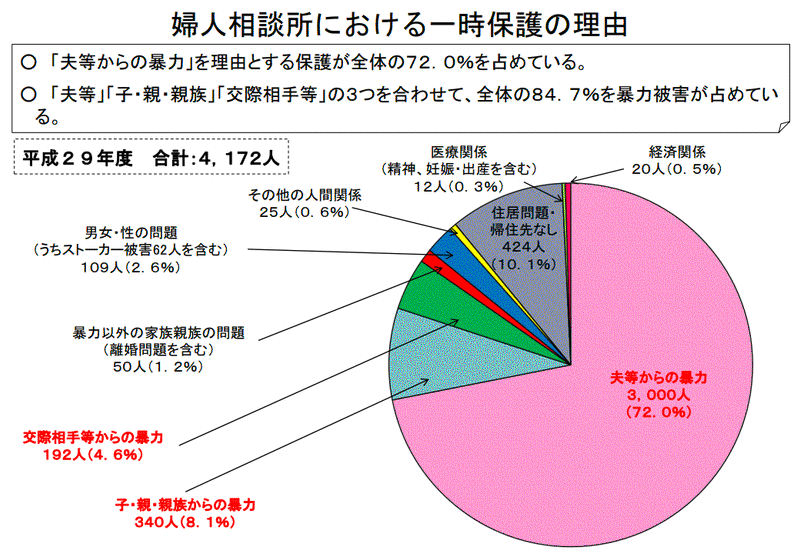


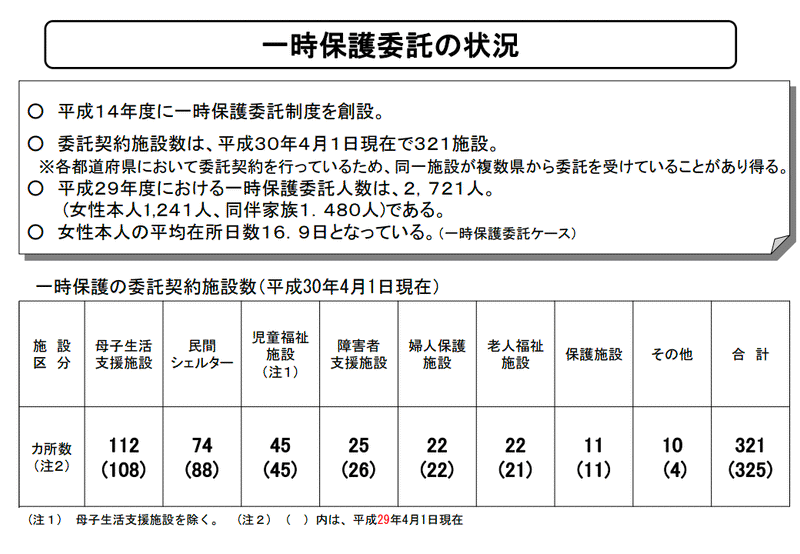




厚生労働省は2019年6月に、“婦人保護事業の運用面における見直し方針について“を発表している。
婦人保護事業の運用面における見直し方針について 令和元年6月21日 厚生労働省子ども家庭局
婦人保護事業は、これまで、DV、性暴力、貧困、家庭破綻、障害等、
様々な困難を複合的に抱える女性の支援を行ってきた。
2018 年7月からは、「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関
する検討会」(以下「検討会」という。)を開催し、婦人保護事業の見直
しを進めている。
これまでの検討会での議論等を踏まえ、当面の対応として、他法他施
策優先に関する取扱いの見直しや一時保護委託の積極的活用等をはじ
め、婦人保護事業の運用面の改善について、次の各事項に速やかに取り
組むとともに、2020 年度予算に向け、その具体化を図る。
その際、地方自治体に対しては、今回の改善等を通じて、相談から心
身の健康の回復や自立支援に至るまで、すべての過程における支援が、
より当事者本位なものとなるよう、それらの趣旨を丁寧に説明し、理解
を深めるとともに、その後の状況に応じて、必要な対応を行う。
さらに、制度のあり方については、同検討会において引き続き議論を
行い、本年8月を目途に議論の結果を取りまとめる。
内容の見出しを並べると以下のようになる。
1 他法他施策優先の取扱いの見直し
2 一時保護委託の対象拡大と積極的活用
①一時保護委託の対象拡大等
②一時保護委託契約施設における一時保護開始手続きの再周知
3 婦人保護施設の周知・理解、利用促進
4 携帯電話等の通信機器の使用制限等の見直し
5 広域的な連携・民間支援団体との連携強化
6 SNSを活用した相談体制の充実
7 一時保護解除後のフォローアップ体制等の拡充
8 児童相談所との連携強化等
①DV対応と児童虐待対応との連携強化、体制強化
②婦人相談員の処遇について
9 婦人保護事業実施要領の見直し
10 母子生活支援施設の活用促進
詳細はPDFを載せるので確認いただければと思う
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
