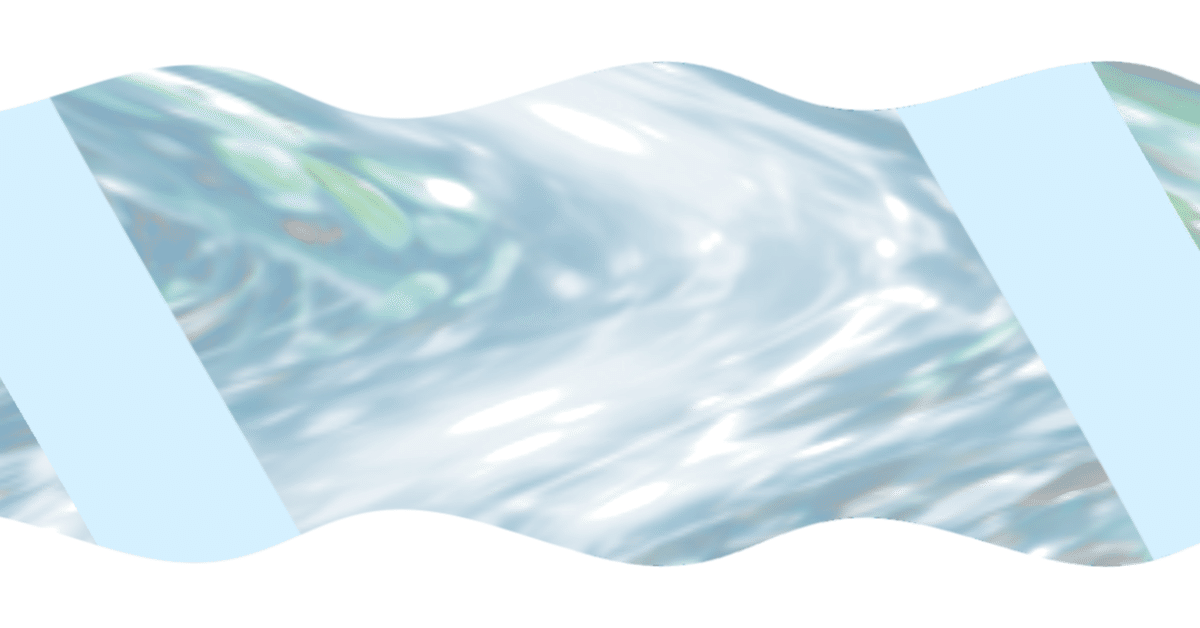
春の庭 後編 【隠岐】
「ね、とりあえず先生来る前にインスタの垢教えてくんない?」
「あー、インスタやってないです」
水曜放課後、委員会で出会い厨する先輩に平然と嘘をつく。私は本日星占い5位の人、ラッキーアイテムはお気に入りのクッション、微妙に持ち歩く術がない。
情けない話だけど、先週と同じ手口で委員会の罠に引っかかってしまった。きっとあの女3人は口裏を合わせてじゃんけんで出す手を揃えている。
『嘘だろ…暇な時何してんの?』
「空とか眺めてますね」
『ハイジかよ。もっと楽しい遊びしようぜ、何なら先輩と青春エンジョイしちゃう?』
うるせぇな私のアルプスに入ってくんなよと言い捨てるのを何とか我慢して、追い払う方法を考えているとさっきまで傍観してたギャルっぽい女の先輩が男の方に軽く蹴りを入れた。唐突に差し込んだ一筋の光。
『いてっ!』
『後輩口説くなカス』
『いやいや、学年の垣根を越えて交流して何が悪いん?構われないからってヤキモチ妬くなよな〜』
『はぁ?自意識過剰すぎ、死ね面喰い』
いやいや援護下手すぎ〜。その言葉を使うと私まで被爆するんだけど。早くどっか行ってくれないかな、そんな視線を送っても気付きやしない。
『あ、てかインスタないならLINEでもいいよ〜』
「いやだからさぁ…」
イライラ階段を一段ずつ登り、ついに頂上まで辿り着いて敬語を飛び越えそうになった時。先輩と私の間にスッと誰かの手が割り込んできた。おい誰だ邪魔すんな、と私と先輩が同時に顔を上げる。
「先輩、すいません。そのへんで勘弁しといてください。3年に迫られると後輩は断り辛いんで…」
先週木曜日ぶりの隠岐くんは突然入ってきて喧嘩を仲裁するように、まずは後輩らしい低姿勢で先輩を諭した。そんな様子を見てあちこちの女子から小さな歓声が上がる。
『うわ男子助けに来た!少女漫画じゃん、かっこい』
『え〜待って、これ俺当て馬内定?』
『おつ。爽やか度で負けたな』
『ショ〜ック』
そして私達より一年長めに生きてる先輩方は隠岐くんの登場に驚きつつも、それさえ青春のひと時としてネタにして楽しんでいる。
人の人生勝手にエンタメにしてんなよ。焦点を合わさず背景を呆然と眺めてた私の視界に、不法侵入してきてごめんねって感じで手を合わせた先輩を、今度は悪意を込めて睨む。
『まぁ今回は諦めるわ、まじで嫌だったんならごめんね〜』
流石に人目を気にしたのか、元々物分かりのいい性格なのかは定かではないけど、さっきまで押し強めだった先輩があっさりと身を引いた。
…まぁ、あんなに下手に出られたら折れないと逆に悪い奴みたいになっちゃうし、無理もない。ていうか多分意図してそういう態度取ってる彼の方がよっぽどバケモンでしょ。
「部外者が出しゃばってすいません、ありがとうございます」
隠岐くんは困ってる女子を助けるだけに留まらず、あろうことか先輩に対して返事をサボった私の代わりに律儀に頭まで下げた。ただの人助けにサービス精神旺盛っていうか…自分を差し出すのに何の躊躇いもないのかって突っ込みたくなるくらいのレベル。この人、マジで素で正義感強いタイプなのかな。
先輩が3年の輪の中に戻っていくと彼は頭を上げ、こちらに向かってにこりと笑いかけた。
「大丈夫?困ってたっぽいからつい割り込んだんやけど…」
「ん、平気。ありがと」
「良かった」
一方私は、無駄に絡まれたり注目されたせいで機嫌も気分もかなり悪くなってしまい、上手く対応する余裕が残されていなかった。
必要最低限の文字数で返事しても彼は笑顔を崩さない。そればかりか、心情を素早く察知して話を広げる事なく立ち去ってくれた。
『やばすぎん?隠岐くんかっこよすぎ』
『それな。私ならあんな助けられ方されたら即オチだわ』
『普通そうだよ。まぁ、めちゃめちゃ反応薄かったけど』
聞こえてるけど。声の大きさを自覚していない野次馬たちがコソコソ話をスタートさせる。どうやら隠岐くんは私が思ってた以上に人気者らしい。そして、彼女たちはそんな彼に助けられたくせに無愛想な態度をとった私のことが気に入らない。
『案外満更でもなかったんじゃない?先輩多分めちゃくちゃ遊んでるけど、実際顔はかっこいいし』
『あー、まぁ確かに。誰だってイケメンにチヤホヤされるのは気分良いよね』
くだらな。的外れすぎてびっくりする。自分の小さいものさしで人のこと測るなよ。
でも、ここでこの子達に何か言い返すつもりも初めから無かった。誰だって経験したことない痛みはわかるはずないし、そのことを咎めたりするのは可哀想だ。酷いことをされればされるほど、その痛みを知ったなら、人には優しくしてあげなくちゃ。まぁムカつくけど。
『隠岐くんごめんね〜うちのクラスの馬鹿が絡んで』
ちょうど前の時計で時刻を確認しようとした時、左端の最前列の席に座った隠岐くんのもとへ、生徒会長が絡みに行ったのが見えた。そんなに広くもない教室だから、少し意識をそっちに向れば会話は筒抜けで聞こえてくる。
「いや、絡まれたの俺じゃないんで」
『まぁそうだけど〜。でも相手の子の反応見てたけどさ、微妙な感じだったじゃん?隠岐くんが折角助けてあげたのにあの対応じゃ可哀想だなぁ〜って』
「あ〜…そうですか。わざわざお気遣いどうも」
『え、なに?もしかして今日機嫌悪い?』
何だあの女、人のこと踏み台にしやがって。私がこれ聞いて何を思おうが関係ないし興味ないってワケ?いい度胸してやがる…流石この学校の生徒会長だ。もしこれから私の前を歩く機会があったら、その時は3回連続で靴の踵踏んでやる。
表情はここから見えないけど、隠岐くんはやたら簡潔に返事をして会話を終わらせようとしてるみたいだった。この前は仲良さげに会話してたのに、何なんだろう。会長から出てる矢印は誰がどう見ても明らか隠岐くんに向いてる。でも彼は対照的っていうか…本当に今日は機嫌が悪そう。
どうやら2人の様子が気になるのは私だけでは無いようで、他の女の子達もちらちらと目配せして時々注意を払っていた。
彼の平然とした声が教室に響いたのは、何も言わなくても場に緊張感を与える存在だったからかもしれない。
「いや、みんな実際困ってる子おっても知らんふりしてるのに、口だけは達者やなぁって思って。俺に同情してくんのも意味わからへんし」
シン。教室が一瞬にして雪の中に埋まってしまったかのような静けさが訪れる。誰もが無駄話をやめて隠岐くんと会長に注目する。
心の中が読めなくても、この人はこういう言い方するからこんな風に考えてるのかな、ってことくらいは割と予想がつく。でも隠岐くんにはそれを全部飛び越えてくる一瞬があった。
今もそう。この前話した時は、感情を抑えたり、遠回しに話したりするのが得意な人なのかなと感じた。でもさっきの発言は誰にでもわかるくらい不快感が露出している。
『え〜待って、なに?私なんか悪いことした?もしかして責められてる?』
「別に責めてないですよ。何か言うてきたから返事しただけです」
『も〜。なんか隠岐くん私の扱いだけ雑くない?他の女の子にはもっと優しいのに〜』
「先輩が知らんだけで、俺普段から結構こんなんですよ」
『はい絶対ウソ笑』
…すごいな、会長。私ならあの場所に立ってられない。まぁ言ってることは全部空回りしてるけど。でもそれがこんなに際立つのは相手が一切フォローしてくれないせいでもある。もし私が隠岐くんの立場なら、会長にもっと優しくしてあげてただろう。注目されてる中、誰かに対してあんな態度を取れるほど私は気が強くないし。
『はーい、みんな何処でもいいから座って〜』
時計の針が大きい5と6のちょうど真ん中あたりを指した頃、ガラッと先生が教室の扉を開けて入ってきた。春になって積もっていた雪が溶けるように、教室にじわじわと温度が戻ってくる。立ってた人はみんな何故か後ろの方の席を選んで座り、会長も静かに彼の傍を離れた。
隠岐くんの周辺には誰も座ろうとしなかった。ポツンと1人だけ残された背中を見て、私は少し彼のことを気の毒に思った。
本日の放課後、先生が生徒に課した任務は以下の通りだ。
2人1組で校内を回り、窓や教室の設備状態を確認してチェックシートに記入。担当区域が終わったら職員室にいる担当の先生にシートを提出してから解散。ペアは好きに組んで良し。
説明が終わると、みんなそれぞれ近くの席の人や知り合いとペアを作っていく。私は最初から隠岐くんに声をかけようと決めていたから、すぐに席を立って彼のところに行った。
「組まない?」
ペア探しに焦る素振りなんて一切なく、我関せずといった様子で机の下でスマホをいじっていた彼がふ、と静かに顔を上げる。
「ありがとう。待ってた」
「待たれてた」
交わす言葉はそれだけで充分足りる。
私達は各々の担当区間を見せ合い、とりあえず現在地から近い場所から順に回ろうと決めて教室を後にした。
「学級代表ってこんな雑用までやらされるんやなぁ、びっくりしたわ」
廊下を歩きながら、隠岐くんはまずこの仕事に対しての不満をそれとなく溢した。そういえば彼はもともと私と同じように代理として来ていたはずだ。2週連続でここにいる理由って何なんだろう。じゃんけんめちゃくちゃ弱いのかな。
「隠岐くん代理で来てるんだよね。何でいつも学代が来ないの?」
「あ〜、なんか結構サボり癖ある子で。先週はその子の友達に押し付けられて渋々〜みたいな」
何処かで聞いた話だな。A組もロクなクラスじゃなさそうだ。
「まぁでも、今週は結構ノリ気で引き受けて来ました」
「へぇ、雑用好きなんだ」
「なわけ。ここ来たらまた会えるかなぁ〜って思ったからやん」
「…私に?」
含みのある言葉に意識を引っかけられて、聞き返せば「他におらんやろ」なんて軽く笑い飛ばされる。
「うわ〜」
なんかそういうテクニックで口説かれてるみたい。好意も義理もないって先週言われたばっかりだけど。でもその言葉があったから、今こうやって自然に話してるんだろうな。
「うわって何ですか〜?こうでもせんと多分もう接点ないまま卒業してたで、俺ら」
「だろうね。私基本自分から行かないし」
「そんな感じやなぁ。でも、何で俺と組んでくれたん?」
また唐突に、こちらを試すような質問。にやけた顔しやがって。逆に何て言って欲しいんだ。
「孤立してて可哀想だったから」
「えぇ〜まさかの同情?」
「嘘。なんか楽そうだったから」
「あははっ、何やそれ。仕事はちゃんとしてや〜」
「全部花丸つけてもう帰ろうよ」
「あか〜ん」
わかりにくい冗談が通じるからかな。
マンボウパン意外と美味しくてびっくりしたとか、この付近を縄張りにしている野良猫の中にどうやら三毛猫がいるらしいとか、そんな寝ながらでもできるようなどうでもいい会話をしながら校内を回って、チェックシートにどんどん○印を付けた。この調子でいけば4時半には帰れそうだとおおよその目処を付けて、最後のチェックポイントである視聴覚室まで辿り着く。
「じゃあ、俺照明とコンセントのチェックするから、窓とカーテンよろしく」
「了解」
部屋に入るとすぐ二手に分かれてチェックを始める。
分厚い遮光カーテンはどれも異常なし、窓も破損なし。鍵も大丈夫。ここはそんなに頻繁に使う教室でもないし、埃っぽいことを除けばなかなか綺麗な状態を保っている。こちらのチェックはかなり手っ取り早く終わった。
カーテンの裏に隠れて見えないのを良いことに、私は一足先に休憩タイムに入ることにした。窓を開けて、外の匂いを嗅ぐ。ここは三階だから結構遠くの景色まで見える。
「おじゃましま〜す」
しばらくその場でぼうっとしていると、隠岐くんが暖簾をくぐるようにカーテンを下から捲りあげてこちら側に入ってきた。1人分くらいの距離を空けて、窓の縁に手を置く。
「何してたん?」
「空見てた」
「俺も見よっと」
そうして彼は本当に空を眺め始めた。これの何が楽しいんだ?
「隠岐くんって人懐っこいね」
人の行動をさらっと真似しちゃうところとか、彼が今まで身につけてきた対人スキルの1つなんだろう。
私はこれ以上近寄られるのが怖いから、ここには壁があるんだよと彼にも確認して欲しかった。だから今の言葉はちょっと嫌味でもある。
「んー、そうでもないよ。気合いそうな人だけ」
真意が伝わったのかはわからない。掴んだと思っても、するりと手の中から滑り落ちていく、そんな表現が彼には相応わしい。少し話したくらいの私には、彼が本当はどんな人なのかはわからない。
「さっき助けてくれたの、嬉しかった」
でも確かに、隠岐くんは心が優しい人だ。ちょっと関わっただけでも充分それは伝わってきた。あんな風に周りの人を大切にできるから、きっとみんなにも大切にされるのだろう。
「んー?気にせんでもいいのに」
感謝の言葉をかけられても、彼は何でもないように笑った。今までそうやって何でも当たり前に変えて、透明にして消してきたのだろうか。
「そっちこそ、わざわざ敵作るようなこと言わなくていいのに」
明確な言葉で示さなくても、私が何の話をしたいのか彼はすぐ理解してくれた。
「…だって普通ムカつくやん、あんなん言われたら」
あの時あの場所で聞こえた心ない言葉の数々を思い出して隠岐くんは表情を曇らせる。きっと君が感じた悪意は君に宛てられたものではないと思う。本当に傷付けたかったのは、君の後ろにいた私。
「まぁわかるけど。でも隠岐くんは周りの人をちゃんと大事にしてる人だから、あんな風に言い返すのほんとは辛いんじゃないかって思った」
優しい笑顔も冷たい態度も、全部彼を構成する一部だから、1つだって蔑ろにはできない。でも、彼の中にある天秤は常に自分より他人の方に傾いているのかもしれない。見ていて思った。
しばらくの沈黙の後、…そんなん言うたら自分もそうやん、と。ぼうっとしてたら聞き逃してしまうくらいの小さな声で彼が呟いた。ちゃんと聞こえたけど何も言わないでいると、次は普通に聞こえるトーンで文句を言うように続ける。
「全部言わせっぱなしにしてるし、いっこも言い返さへん」
呆れているみたいだった。どうして隠岐くんがそんな不満そうな顔するのか、私にはよく理解できない。だからきっと彼も、私のそういうところが理解できない。
「言い返すのは可哀想だから」
わからないなら別に、わからないままでもいいなと思って単的に答えた。きっと隠岐くんは私のこういう“諦めてるところ”が気に食わないのだろう。だって、こちらとしては「ふーん」とだけ言って流して欲しかったことに対して「何でそう思うん?」ってさらに突っ込んでくるし。
めんどくさい人だな。説明するのが難しいことだってあるのに。私の思想なんて聞いてどうするんだよ。聞いたって反応に困るに決まってる。まだ何も言ってないのにもう半分くらい諦めながらなるべく頑張って、自分の行動を説明する言葉を絞り出した。こんなことに意味があるとは思えない。
「傷付けられたら痛いみたいに、傷付けた方も多分何処かが痛んでて、誰かに同じ傷を与えることでわかってもらおうとするんだと思う。でもそんな方法しか使えない人って頭弱くて可哀想じゃん。だから私は酷いことされた分だけ仕返しに優しくするんだよ。それが私のマイスタイルってワケ」
言い終えても自分が何を言ってるのか全然わからなかった。でもなんとなく雰囲気で誤魔化せたと思う。どうだい、と隣の彼を見てみると、、、ポカン…そんな効果音がピッタリの顔。
あーー…はい、しくじった。
シャッ、と素早くカーテンを引っ張って体ごと隠す。無理、だるい、恥ずい。変に語っちゃったし、オチ付けようとしてスベったし。ていうか聞いたのそっちなんだから1秒以内に反応しろよ。
「待って待って、あー…何処から突っ込もかな……も〜情報量多すぎて頭痛が痛いわ…」
「おい」
こっち側にくるな。
カーテンに手を掛けてこちらの様子を窺おうとする隠岐くんに対抗し、私も必死でカーテンを引っ張ってなけなしの尊厳を死守する。
「変なオチ付けたこと後悔してるやろ?」
「超してる」
「あははっ、俺はわりとああいうの好きやで、全然おもんなかったけど」
まったく心の籠っていない笑い声が聞こえる。鬼か?
「今ハッキリわかった、私隠岐くん苦手だわ」
「えぇ〜?それは好きってことで受け取っていい?」
「マ〜ジで話通じねぇなコイツ…」
人を散々煽って満足するまで笑うと、カーテンを掴んでいた彼の手がパッと外れる。
「でも俺、勘違いしてたわ」
反射的に手の力を緩めると、窓から入ってきた風がふわりとカーテンを攫っていく。
隠岐くんはちゃんと私の方を見てこう言った。
「人一倍自我強そうやのに変なとこで大人しいから、気ぃ弱いのバレたくなくてわざと虚勢張ってるんかな、と思ってたけど…」
頭の周辺にもやもやと漂っていた熱い蒸気も風に飛ばされて、騒がしかった鼓動がだんだんと落ち着きを取り戻す。
「ほんまはびっくりするほど性格捻じ曲がってて、どうしようもないくらい優しい子なんやね」
彼の瞳の中で私は私と目が合って、体から出た棘が自然と抜け落ちていく。どんなに頑張って生きてみても、彼の目に映るのは滑稽な私。
「…馬鹿だと思う?」
正解不正解を追い求めてるわけじゃなくて、この人がどんな風に考えるのかを知りたいから質問をする。
「馬鹿やとは思わへんけど、生きるのめっちゃ下手なタイプやなぁとは思う」
彼は迷う事なく、優しい表情で答えた。
それを馬鹿って言うんじゃない?でも、まぁフォローしてくれてありがとう。
「たしかに。隠岐くんは生きるの上手そうだね」
「あはは、まぁそっちに比べたらまだマシやろな」
今度はフォローしろよ、と思いながら窓を閉めた。さっきまでひらひらと楽しげに波打っていたカーテンが急に大人しくなる。
ちょっと悔しいから平静を装っているけど、情けない奴だってことが予想以上にバレていて内心恥ずかしいし、今すぐ家に帰ってお気に入りのクッションに顔を押し付けたい。
「はい、出て出て。もう帰るよ」
「え〜…あと10分くらい休憩してから行かん?」
「いかん」
「あーもうわかってんねんで!このまま絶交する気やろ俺と〜!」
「本気でしようか迷ってるよ、今」
急にぎゃいぎゃい騒ぎ出したかと思えば、今度は「ほんまひどいわ〜」とか全然平気そうに言ってカーテンの裏から出た。情緒ビュッフェか。わざとなら大根役者にも程がある。
私達は行き道より口数を減らして、職員室に寄ってチェックシートを提出し、無事任務を終えた。学校を出る頃、時計の針は17時を示していた。
「隠岐くん何で付いてくるの」
「いやいや、俺も方向こっちやねんって」
さっきまで影みたいに半歩後ろを付いてきてた彼が、人聞き悪いわぁ〜と文句を垂れながら私の隣に並ぶ。本当かコイツ…と若干疑いながら、いつもより3割増の速さで歩いているのは多分彼も勘付いていることだろう。
別に本性を隠してたわけでも無いけど、自分の不器用なところを簡単に見抜かれてしまったことがちょっと悔しいし決まりが悪い。これから何を言っても彼に心の中で嘲笑されてそうな予感がする。泣き顔見られた後みたいな気まずさと、敗北感。
私がそんな気持ちでいることをわかっているのかいないのか、隠岐くんは何でもないような顔でくだらない無駄話を続けた。私はそれに適当な相槌を打ったり、時々一言二言返したりして、何とか時間をやり過ごした。
「じゃあ、また来週」
別れ道、隠岐くんが先に立ち止まって手を振る。今週はまだ半分も残ってるのに。来週からもう委員会には行かないよ。どちらの台詞も声になるにはまだ早かった。私は彼のように何でもないような顔でじゃあね、って手を振り返した。
誰に対してもこんな風にしてきたから、いつの間にか別れ際ばっかり上手になってしまった。期待して待ってしまうのが怖いから、『またね』って言葉を素直に受け取ることができない。
**
『ねぇすごいゴシップ手に入れたんだけど聞く!?』
焼きそばパンを夢中で頬張っていた昼休み。友人は部活のミーティングから帰ってくるなり、興奮気味に私の机に手をついた。彼女の大きな声で放たれた“ゴシップ”という単語が周囲の視線を集める。
この先の会話は周りに聞かれてしまう意識を一応持ちながら、特段気に留めずに焼きそばパンの袋を折り畳む。
「パンダの赤ちゃんでも産まれた?」
『パンダの繁殖でJKがうまい飯食えんのかよ。てか口にソース付いてる』
彼女は私のボケに華麗に突っ込みをキメた後、ポケットティッシュを一枚取り出してぐいぐいと口元を拭ってくれた。されるがままの赤ちゃんな私。好きな食べ物は人の噂話を肴に食ううまい飯。
『女バスの先輩に聞いた話なんだけど、3年の生徒会長が昨日うちの学年の男子に告ってあっさり振られたって」
「え〜その話ここでしてもいいやつ?」
『いいんじゃない?何かもう自分でネタにしてるらしいし』
「へぇ。ネタ告とかまだする奴いたんだ」
中学生かよ、なんて突っ込みながら自販機で買った天然水のキャップをカチッと開ける。
『あ〜多分わざとだよ。相手がA組の隠岐くんなんだって』
聞いたことある名前だな、そういえば昨日水曜日だったけ。でも他人事だから、飲み口にストローを入れて素知らぬ顔で話を続行。
「へぇ、何かそういう決まりとかがあるの?」
『私もよく知らないんだけど、女子の間では隠岐くんはみんなのもの〜ってのが暗黙のルールらしいよ』
ぬるい水が喉を通って体の中に落ちていく。拒絶する一歩手前の不快感。
「1人じゃ買えないもの割り勘で買おうとしてるみたいな?」
『あははっ、多分そういう感じ。だからずっと彼女いないんだって。ほんとかよって〜』
“みんなのもの”とか“推し”とかいう免罪符切って悪意なく崇めてるつもりでも、本人からすれば他の人と平等に扱って貰えない時点で腫れ物扱いされてるのと一緒だ。
隠岐くんが何であの時不満そうな顔をしたのか、今になってようやくわかったような気がする。
「その子、いつもどんな気持ちで学校来てるんだろね」
『え?』
無意識に言葉が零れたのに気付いて、あ。と思った。咄嗟に目の前の彼女の表情を覗くと、不意を突かれたような顔で私を見ていた。
ぎこちなく視線を逸らせば、視界の端で微かに微笑まれる。
『…まぁ私はそんな待遇受けたことないからちょっと羨ましいって思っちゃうけど、何処行ってもそういう扱いされたら流石にしんどいかもね』
きっと想像ではなくて、私の方を見て言ってくれた。彼女はじゃんけんの時は私を裏切るけど、それ以外はいつも味方でいてくれる。思考が読まれてる気がするし、私は体質上こういうむず痒い状況に陥ると喉が渇いてくる。あー、なにこれ居辛い。雰囲気変えなくちゃ。
「全然関係ない話なんだけど、今日起きたら7時50分でさ」
ストローから口を離すと、強引に話題を変えた。こちらの性質に理解のある彼女は止める様子もなく相槌をくれる。
「あと1回遅刻ついたら指導だって脅されてるからめちゃくちゃ焦って初めてチャリで学校来たんだけど、学校の前の坂道キツすぎない?立ち漕ぎしながら勾配何%だよって無意識に突っ込んでたし」
『は?死ぬ気?あれはみんな押して登るもんなの。てかうちの学校チャリ通って生指の許可いるんじゃなかった?』
「だから今日闇チャなんだよね。バレたら普通にやばい」
『いや無断でチャリ通デビューすんなし笑 マジでダッシュで帰れ?』
見つかったら冗談抜きで怒られるよ、私それで停学になった先輩知ってるもん。と軽く脅される。嘘かもしれないけど本当なら結構ガチめにやばいな。
脅されてすっかりびびってしまった私はHRが終わると、一刻も早く違法チャリを回収するため爆速で教室を出た。朝、人目のつかない場所にひっそりと停めていたチャリはその場でお利口に私の帰りを待っていた。素知らぬ顔でそのままチャリを引いて門を出る。すり抜けは難無くスムーズに、そして呆気なく成功した。
やってやたわ!と高笑いしたい気持ちを抑えてチャリに跨る。空が綺麗だし空気も澄んでいる。徒歩で帰る生徒たちをすいすい気分良く追い抜いていると、ふとしたタイミングで歩いてる人と目が合った。
「あ」
先に声を上げたのは向こう。知り合いだと気づいても私はブレーキをかけなかった。景色と一緒に彼が後ろに流れて行く。
「え!ちょ!無視はないやろ!?」
後ろでそんな声が聞こえるけど、自転車にバック機能はないからと心の中で言い訳をしてガン無視でペダルを漕ぐ。
するとそのまま20mくらい走ったところで、グンッ!と自転車が後ろに引かれた。バランスを崩しそうになって慌てて地面に足をついて振り返ると、息切れしながら荷台を掴んでる隠岐くんがいた。
「なに」
「はぁ…ちょお、待って……今、息整えてる」
聞かなくてもわかる。息が整うまで30秒くらい待つと、彼はムスッと不満そうに私を見た。というか睨んだ。
「何で昨日来やんかったん?」
先に文句を言おうとしていたのはこっちだったのに、すっかり圧に負けてしまった私は言い訳になる言葉を探した。昨日…あぁそういえば、私が代理で来てたことを隠岐くんは知らないんだっけ。
「だって私、もともと学代じゃないし」
「えぇ!?嘘やん!」
カミングアウトすると彼は面白いくらいに表情を変えて驚いた。
「ほんまやん。私もずっと代理で来てただけ」
「そんなんもっと早く言うてや〜!うわ〜何なんほんま…めっちゃ恥ずかしいねんけど…」
さてはこいつ昨日も行ったんだな。
「なに、昨日も私に会いに来てた?」
どんな反応するだろうと揶揄ってみれば、彼はん"〜…とまた不満気に唸りながら学ランの袖であからさまに顔を隠した。女子かよ、そんな突っ込みを心の中で入れてチャリから降りる。
「…仲良くなりたいと思ってんの、俺だけ?」
ちら、とこちらを窺いながら小学生みたいなこと聞いてくる。こっちまで恥ずかしくなるシチュエーション。
「…よくそんな恥ずかしいこと言えるね」
ちょっと、素直すぎないか。君、本当に高校生ですか。
「だって腹割って喋らんと、一生仲良くなられへん」
ここで問題。隠岐くんの方から私に歩み寄ってくれていることが明白となった今、私は一体何て返せば良いか。ア〜エの中から選べたら簡単だけど、いつだって記述問題しかない人生。わからなかったらわからないが私の答えです。
「あのさ…隠岐くん、そういう風に真っ直ぐこっちに向かってこられても反応に困るっていうか…私そういうの慣れてないから、どうしていいかわかんなくなるんだよ。逆にどうすればいいか教えてくれない?」
「え〜…自分はどうしたいん?」
言葉を詰まらせた私と一緒に、隠岐くんも悩ましげな顔をする。
「ん〜じゃあ質問変えるわ。俺と仲良くなりたいって気持ちはある?」
マジか…友達になる時ってこんなこと聞かれんの…?今までこんなに苦労して仲良くなった人いないんだけど。
「あ、る」
喧嘩した相手に「ごめんなさい」って言う小学生みたいな辿々しさで小さく頷く。結局思惑通り動いちゃった私と、にっこり嬉しそうに笑う彼。
「どれくらい?」
「お茶碗3杯分くらい」
「結構欲張るなぁ」
「基準がわからんって。多いのこれ」
「少なくはない、2回おかわりできるってことやろ?」
「じゃあもうちょい減らす」
「あかん笑 嬉しいから」
揶揄いやがって…居ても立っても居られなくなって自転車を引いて歩き出すと、彼は当たり前に隣に並んで付いてくる。
「何なん隠岐くん。何でそんなに私にこだわるの」
「え〜聞きたい?」
「は?うざ」
「ごめんて」
「早く言って。さーん、にー、」
「これ顔とか言ったらしばかれるやつやんな?」
この状況でまだボケるか?
「流石にウケないわ、それ隠岐くんが一番嫌なタイプでしょ」
「んふふ。そういうのわかってくれてるとことか、ほんまに好き」
「好きって…大袈裟すぎでしょ」
逆にウケるわ、と呟いてから…私は自分で自分の言葉の意味をもう一度よく考えてみた。
違うよね、と確認する意味で隠岐くんの方を見ると、口をポカンと開けたまま「え?」って自問するように首を傾げてその場に立ち尽くしていた。何その顔。
「は?」
思わず口を出た一文字。それが聞こえた瞬間、彼はバッ!と両手で顔を隠して背を丸め、痛みに悶える怪物のように唸り始めた。
「あ"ぁぁぁ〜〜〜……」
一体どこから出てるのかと問いたくなるその声は、穏やかでどこか品のある隠岐くんのイメージから逸脱したものだった。気の毒すぎて私は咄嗟に彼を庇った。
「いや、わかってるよ。友達としてでしょ?」
「………」
「は?何で黙るん」
「…………」
いやマジかこいつ。
「え、ガチで私のこと好きなの?」
「………ごめん」
指の隙間から一瞬こっちを見たかと思えば、また逃げるように逸らされる視線。その謝罪は肯定を意味するのだろうか。いずれにせよ私は勿論、彼にとっても予定外の事態が起きている。
どうしたらいいんだろう、と戸惑っていると、隠岐くんが本当に申し訳なさそうにおずおずと手を挙げた。
「あの…とりあえず、今起こったこと一旦全部忘れてくれへん?」
「いきなりすごい無茶言うね。まぁいいけど」
「ありがとう…」
「ん、何が?」
「めちゃくちゃ完璧に忘れてくれるやん…」
こんな時でも突っ込みを忘れないのはある種の病気なのかもしれない。しかし、茶番すぎる。忘れるわけないのに私は綺麗さっぱり忘れてしまった設定で事を進めなければならないから、この空気を変えるのは隠岐くんの役割だ。
「…帰ろか」
「あ、うん」
力が抜けたように微笑んで、彼の方から先に歩き始める。私は形容し難いもやもやと、若干の安堵を抱えながら半歩後ろで彼の影を踏んで歩いた。
今朝、勾配何%だよと突っ込みながら登った坂道をブレーキをかけながら徒歩で下る。キィィ、とぎこちない音が鼓膜に響いている間は何も話さなくても許される気がした。
なんだか急に、彼が自分とは全く別の生き物のように思えた。どことなく自分と似ていると思ったし、意思疎通もしやすかったけど、彼が私に好意を抱いていると思うと一気に何を考えてるのかわからない。ただ、嬉しいとか嫌とかそういう感情よりも何故という疑問が頭の大半を埋め尽くした。
隠岐くんが歩調を緩めたせいか、いつの間にか私たちはまた隣に並んで歩いていた。
「あの時、声かけてくれてありがとう」
視線を道の先に向けたまま感謝の言葉を口にした彼は夕陽の色に染まって、このまま空気に溶け出して消えてしまいそうだった。でも、この世界に彼を繋ぎ止める言葉が私の中には無いような気がした。
1ヶ月前まで知らない人だった私達が今、こんなにも自然に隣にいることを少し不思議だと感じる。
「あの時孤立してたのがほんまの俺やったから…嬉しかった」
表現も言い訳も使わない飾り気の無い台詞は単純明快で、たったそれだけなのに、それが全てでいいと思えた。
坂道が平坦な道に変わるとゆるやかに、一呼吸置いて彼が立ち止まる。私も同じように足を止めて彼の瞳を覗き込んだ。
「好き」
目を合わせて彼が告げたのはたった2文字の、世界中で使い古された言葉だった。毎日何処かで耳にしているはずで、別の人から貰ったこともあったし、あげたことも、失ったこともあった。
「もう、それ以外ないんやと思う」
私達2人を象るように風が吹いた。春なのに此処には雪が降っている。彼の真剣な眼差しに突き刺された私は鼓動を高鳴らせながら、この雪を溶かすための言葉を一生懸命に考えた。
「って…こんなんいきなり言われても困るやんな、ごめん。まだ言うつもりなかってんけど……言ってしまいました」
はい。と、これにて告白は締め括られたようだ。謝罪会見みたい。普通返事も聞かずに謝るか?
誰がどう見ても負け確の告白をしてしまった隠岐くんは首の後ろに手を当てて、居心地悪そうに俯く。
彼を通して、私は私を見つめていた。めちゃくちゃ天邪鬼なところ。びっくりするほど性格が捻じ曲がってて、生きるのが下手。ほとんど悪口じゃないか。
でも彼が自らの壁を壊して私に会いに来てくれたなら、私も私の壁を壊したい。腹を割って喋らないと仲良くはなれないと、君が言ってくれたから。
「付き合おっか」
「はい?」
「私も多分、そのうち隠岐くんのこと好きになると思うし」
「え?」
「隠岐くんが私のこと好きだから、とかそういうのじゃなくて。私も隠岐くんの人間性に惹かれてるから」
「ちょお待って、」
言葉を遮るように隠岐くんからストップが入る。何だ、今ちょうど良い感じの波に乗っていたのに。
「ほんまに…待って。とりあえずチャリのスタンド止めてくれへん?」
「そこ気にする?」
言うことが予想外すぎて思わず突っ込んでしまった。彼は理由をつけるようにあたふたと手を振る。
「あの、あれです。握手を、させてください…今、心がとても穏やかでない」
「口調どこ行った。いいよ」
言われた通りその場でスタンドを止めて、ハンドルを握っていた両手を彼の方に差し出した。
「…ほんまにいいん?…正直今、俺のことそんなに好きじゃないやろ?」
真っ赤な顔をしてるわりに頭の中は冷静だった。彼は友達になったばかりの私にうっかり口を滑らせて告白をしてしまった男だけど、差し出された手をすぐに取らない慎重さがある。
「苦手とは言ったけど好きじゃないって言ってないよ」
「いやいや、よう言うわ!俺のことなんか超どうでも良さそうやったやん…!チャリで通り過ぎようとしとったやろ!?」
次々と繰り出される鋭い突っ込み。きっと自分にとって都合が良すぎるこの展開がどうしても納得いかないのだろう。
「あ〜……あれはまぁ、なんて言うか…顔合わせるの恥ずかしかったから」
「嘘やん…俺のこと騙そうとしてない?モニタリングとかじゃないやろなこれ」
隠岐くんは私が何を言っても信じようとしないし、挙げ句の果てにはカメラまで探し始めた。これはこれで面白いけど、もうそろそろ落ち着いて話をさせて欲しい。
「いやガチだって。冗談でこんなこと言うタイプに見える?」
「見えへん……でも俺とこんなすぐ付き合うタイプにも見えへん…」
「それはごもっとも」
私の言葉を簡単に信用しない彼の信頼度だけがどんどん上がっていく。だよね、私もなんでこんなことになってるかまだよくわかってない。
「けど…この先どういう結果になっても、私は今隠岐くんに言ったことを言わなきゃよかったとは思わない。それだけは約束する」
これ以上ないくらいにはっきり宣言すると、彼は目を瞬かせた。
「…プロポーズ?」
「馬鹿なの?」
尽きないな。本格的に私と漫才コンビ組みたいのかなコイツ…
「嘘、ありがとう……じゃあこのチャンス、有効活用させてもらっていいですか?」
呆れかけている空気を察したのか、隠岐くんがそっと大事なものを受け取るように私の手をようやく握った。
「はい、よろしく」
よろしくぅ…と消え入りそうな声で、手を握ったまま深々とお辞儀する隠岐くん。暖かいを越えて熱い手のひらに、思わず笑ってしまいそうになる私。
「……ほんまやばいどうしよ。今育ててくれた親への感謝の気持ちでいっぱいやねんけど」
「あはは、電話すれば?」
「後でする。えぇ〜マジでヤバい…幸せすぎて怖…」
「背後に花畑背負った男、通りま〜す」
「はぁい、道開けてくださ〜い」
そんなに幸せオーラ全開にされると、なんかこっちにまで移ってきそう。
「隠岐くん、」
「ん?」
「大切にしてくれる?」
試すような質問に彼は大きく頷いて即答する。
「する、めっちゃする。ていうかもう別れへんと思う」
「あはは、いいの?そんなこと言って」
「いいです、もう決めたんで」
調子良いな。今なら何のパスワードでも教えてくれそうだ。
「人生ってこんなことあるんやな…えぇ〜俺いつ何処でこんな幸せルートに入ったんやろ…」
何の因果で私たちが結び付いたのかは知らない。でも、もしこれがテストの何問目で、自由に考えて述べよって言うなら私はこう答える。
プリントの隅に小さく書いた私の名前を、君は一度見ただけで覚えてくれたから。
隠岐くんと歩く3度目の帰り道。彼は今までで1番口数が少なかった。黙ったまま時々私の横顔をじっと見つめて、目が合えばふんわり笑う。
柔らかい春の光に溶かされた雪は透明になって消えていくけど、草木を育てて、いずれ花を咲かせる。
彼の横顔をそっと盗み見る。視線に気付いて照れくさそうにこっちを見た彼に、今度は私の方が先に笑みを溢した。
「隠岐くん」
「はぁい」
名前を呼べば返事が返ってくる。
誰の声も届かないように一人で水中に沈んでいた時、彼を見つけた。彼の隣は他の場所より息をするのが楽だった。
「ありがとう」
たったそれだけのことでも、私にとってはそれが全てだったよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
