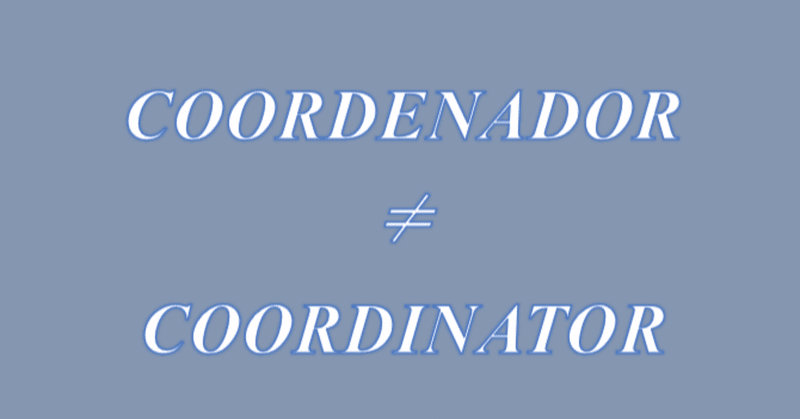
こんなのもあるから困ってしまう…
昨日はタイピング室のコーディネーターのおばちゃんの話をしました。
日本語の記事なので、彼女の仕事からして「コーディネーター」
という単語が一番しっくりくるかなと思い、
そう表現したのですが、
現地での彼女のポストの名称は
「Supervisora【スペルヴィゾーラ】=監視員」だったか
なんだったか覚えていないのですが、
最低限
「coordenadora【コオルデナドーラ】(直訳するとコーディネーター)」
でなかったことだけは確かです。
というのも、ポルトガル語の
「coordenador【コオルデナドール】」という単語は、
英語の「coordinator」同様に、
「coordenar【コオルデナール】」動詞 = ”to coordinate"」
から派生したという点では
「coordinator」に匹敵する単語ではあるものの、
実際の意味はというと、
英語の場合のような「調整役」的なものではなく、
「総支配人」のような、グループのトップを指すものなのです。
*****
ある時私は、
アンゴラ共和国の地雷除去に関する事前調査に参加しました。
あ、事前調査ですし、通訳ですし、ダイアナ妃でもないので(笑)、
地雷原に足を踏み入れたりはしていません。
当時は 国連人道問題調整事務所
(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: OCHA)が
アンゴラの地雷除去に係る調整を行っており、
地雷原の多い各地に現地事務所と
現地人「コーディネーター」を置いていたんです。
人選は現地自治体に任せ、「コーディネーター」は、
自らの管轄区域で活動する各国の地雷除去NGO等の
振り分けや進捗状況の把握を行い、
本部に報告を上げるという役割の人員です。
OCHAの共通言語は英語ですから、
各自治体に事務所スペースの確保と
「coordinator」の人選・配置をお願いしました。
すると、何が起きたか。
・
・
・
*****
私たちは、いくつかの現地事務所を訪問して、
現況についての聞き取りを行うことになりました。
ある現地事務所には、
「今、現場から戻ってきたところです」
という、
地図や現場用チェックシートを抱えた
若くてきびきびした青年が、
「私がこの事務所の『コーディネーター』です」
と言って、事務所とは名ばかりの小屋に通してくれました。
そして、
現状について、いろいろ話を聞いて
とても有意義な訪問となりました。
一方、
次の現地事務所を訪れてみると、
冷房がガンガン効いた「コーディネーター室(=所長室)」から
ビシッとしたスーツ姿で出てきた人物が、
最初の事務所と同様に
「私がこの事務所の『コーディネーター』です」
と言います。
面食らいつつ、現場のことを聞いてみると、
何を聞いても
「それは現場へ行ってお聞き頂ければと」
の一点張り…。
「ご自身は現場へは行かれないのですか」
と訊ねてみれば、
『何を馬鹿なことを聞くんだ、コイツらは』
と言いたげに
「私はこの事務所の『コーディネーター』(所長)ですから」
と…。
要は、これ ↓ は関係ない拾い物の写真なので実際とは異なりますが、
イメージとしては、この手前の2人(なんなら全員)が、
それぞれの現地事務所で
同じポストに就いていたような様相だったのです。>爆!

というわけで、
各地方自治体が OCHA の指示をどう理解したかによって
ありとあらゆる「コーディネーター」がいることが判明したわけでして、
ま、言うまでもなく、
現場にバンバン足を運ぶ若者がいる方が
OCHAの意図を正しく理解した自治体だったわけですが、
面白いのは、
その若くてきびきびと働く青年が担当するのは、
極めて貧しい地域で、
読み書きができる村民も少なく、
「コーディネーター」などという言葉の意味についても、
知らなかったり、
聞いたことはあっても既成概念を持っている人もいないような
地方自治体だということです。
そんな自治体だからこそ、
OCHAの説明をよく聞いた上でこの青年を抜擢したわけですね。
一方、
さも偉そうな「コーディネーター」が担当する地域はというと、
ある程度財政力もあり、
自治体もしっかりしているとされる地域です。
その「しっかりした自治体」では、
ポルトガル語の知識も豊富ですから、
中央レベルを介して届いたOCHAの指示書を斜め読みして、
「要は、事務所スペースを用意して、
『コーディネーター』(=所長)を選んで
座らせとけって話っしょ?」
と手配した結果が、「アレ」だった…
というわけです。
*****
日本からの調査団には(いや、日本のでなくてもですが)、
必ず調整業務を行う人がいるわけですが、
英語版の団員リストを事前に提示して、
各団員に見合う担当者を指名してくれるように
頼んだりすると、
一番ランクが下でパシリ的役割をこなすことになり勝ちな
調整員のカウンターパートとして
先方側のトップの名が入っていて、
到着するや否や誤解を解いて
再配置をお願いするなんてことも
しばしばあります。
リストの下に書いてある「coordinator」は「coordenador」ではないと
熟知している先方組織もありますが、
その場合は先方から
「この『coordinator』っていうのは、要は『administração』を
する人って理解でいいんだよね?」
と、確認してくれたりもします。
慣れっこの私の場合は、
ポル語版を併せて提示できる場合は、
「coordenador (administração das actividades)」等、
但し書きをするよう心がけていました。
*****
この「administração」という単語は、
これはこれで問題ありなのですが、
それについては、またいずれってことで!
そんなこんなで、
普段は2つのポルトガル語間の「トラブル」について
書くことが多いのですが、
今回は、両ポルトガル語で一致して、
しかも英語にもそっくりなのに、
そしてその英語とは語源まで一緒なのに、
何故か実生活では意味が異なる
という、
なんとも厄介なケースについて書いてみました。
ワケワカラン語のワケワカラン事情についての記事だというのに
お読み頂き、誠にありがとうございました!

※ 「ああ、やんなった!」、否、「だらだらネコその2」は
こたつぶとんさんの作品です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
