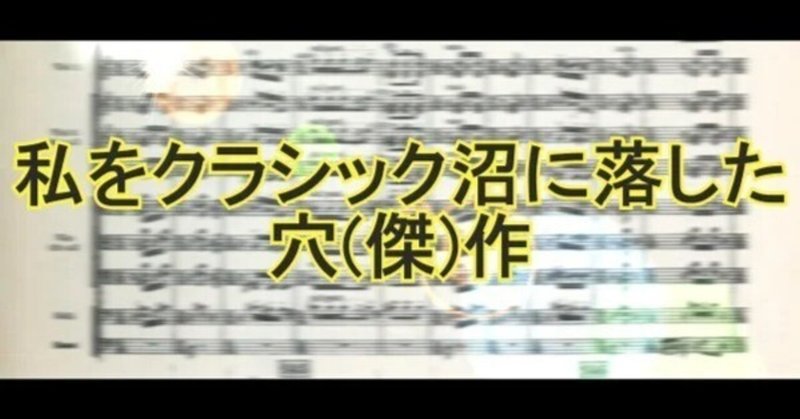
連載:私を「クラシック沼」に落した穴(傑)作~その6
これまでは、中学生から高校2年生まで、私がハマってきた音楽を、その都度時系列順に、お話してきた。
今回は、《英雄の生涯》や《春の祭典》のように、私の音楽趣向を上書きし、決定づけて来た作品ではなく、そのレベルまでいかずとも、私の魂をある程度揺さぶってきた作品を、落穂拾い的に取り上げていく。
■チャイコフスキー:幻想曲《ロメオとジュリエット》
カラヤン指揮ベルリン・フィルの、一番新しい録音。
エアチェック・テープには、「1987年2月8日録音」とあるから、ヤンソンス指揮レニングラード・フィルの来日公演を聴いてチャイコフスキーに興味を持ち、放送があるのを知ってテープを用意していたものと思われる。
曲の筋立ては、概ね原作に沿ったものだが、22分程度に凝縮され、コンパクトに纏められている。ベルリオーズや、プロコフィエフを聴くのはもっと後の話だ。
作曲時期は、交響曲第1番と第2番の間くらいだが民族色は少なく、緩-急-緩-急-緩の構成的バランスが良く、聴くものを飽きさせない。
■R・シュトラウス:歌劇《影のない女》交響的幻想曲
上記は、メータ指揮ベルリン・フィル
私が聴いたのは、ホルスト・シュタイン指揮N響の1987年11月12日の第1035回定期公演の実況放送。
《エレクトラ》《サロメ》《薔薇の騎士》に続く、R・シュトラウスの大規模オペラ。作品の規模が大きい割に、内容が難しく、《薔薇の騎士》などに比べるとコスト・パフォーマンスが悪いため、名曲ではあるが、それほど上演されない。近年まで、大幅なカットも慣習的に行われてきた。
そのためか、日本初演は作曲から70年ほど経った1984年。
この交響的幻想曲は、上記のような理由から、作品のエッセンスを少しでも理解してもらおうと、声無しの管弦楽のみで演奏してもらおうと作ったものだ。作風としては、《エレクトラ》や《サロメ》のような不穏な雰囲気の場面(冒頭とか)もあるが、《薔薇の騎士》や《ドン・ファン》に近く、極めて聴きやすい。
しかし、N響はこの後、1999年にR・シュトラウス没後50年の演奏会で一度取り上げただけで、もう20年以上演奏記録がない。
私は、むちゃくちゃ好きなんだけどなあ・・・。
■フランク:交響詩《呪われた狩人》
クリュイタンス指揮ベルギー国立管
なぜ、この曲を知ったのか、今では定かでない。
しかし、結構早い段階から聴いていたような気がする。
N響は、2005年の定期演奏会で一度だけ取り上げているだけなので(マジか!?)、そっち経由ではないだろう。
「あまり知られていない曲だけど、良い曲だよ」とどこかのインタビューで、指揮者の誰かが答えていたようなことはうっすらと覚えているのだが、それを思い出して、マルティノンの「オネゲル管弦楽曲集」の中古LPを買った際に、いっしょに購入したのだろう。
曲は、確かに面白い。ホルンのユニゾンで奏でられるファンファーレで始まり(これはチャイコフスキーの第4番と同じ)、迫真と熱情ほとばしる楽想、最後の部分の、鐘が連打されるベルリオーズ風の急速なアッチェレランドと、聴きどころ満載だ。
■レスピーギ:《ローマの祭り》、《ローマの松》~アッピア街道の松
スヴェトラーノフ指揮ソヴィエト国立響[ライヴ]
レスピーギの《ローマの祭り》は高校2年の時、吹奏楽部の定期演奏会で「目玉」として取り上げられたもの。その年度の、夏の全国吹奏楽コンクールで流行していた曲だが、うちの高校は違う曲を選んでいたので、遅ればせながら(定期演奏会は三学期)流行に乗って演奏したという感じ。
まあ、うちの高校のトランペットは少数精鋭で、舞台横のファンファーレ部隊が必要な《ローマの祭り》は、人数不足で、やろうと思っても人数的に不可能なのだが(定期演奏会は、OBも参加する)。
《ローマの松》~「アッピア街道の松」は、高校の卒業式で、卒業生退場の音楽として、毎年吹奏楽部が演奏する伝統となっていた(今はどうか知らない)曲。
当時聴かされたデモ演奏は、演奏者は教えてもらえなかったが、恐らくデュトワ指揮モントリオール響盤。
しかし、後に(といっても1988年の夏前まで)このスヴェトラーノフ盤を聴いて、ぶっ飛んだ。
もちろんデュトワ盤も、本曲の録音の中ではトップクラスの名盤だが、スヴェトラーノフ盤は次元が違う。
同じ曲でも、演奏によってこんなにも曲の評価が変わるのかと驚かされる。
■R=コルサコフ:交響組曲《シェエラザード》
プレヴィン指揮ウィーン・フィル
前回にも出てきた、通学経路上にあった割り引き店で購入したもの。
なぜこの曲を買おうとしたのか、全く覚えていない。
たしか、吹奏楽部でリムスキーの《スペイン奇想曲》を演奏した記憶はあるのだが、このCDを買った時期より後だし、それまでリムスキーの名前はストラヴィンスキーの先生ということでかろうじて知っていたが、曲を聴いたことはなかった(はず)。
とはいえ、このCDを聴いて、作品と演奏、そして録音の魅力にとりつかれたことは確かだ。
社会人になってからは、《シェエラザード》の録音は手当たり次第に集めたが、今でもこのCDがベストだと思っている。
■オネゲル:劇的オラトリオ《火刑台上のジャンヌ・ダルク》
上記は、ジャン=ピエール・ロレ指揮リヴィウ・レオポリス交響楽団
私が聴いたのは、小澤征爾指揮ウィーン・フィルで、1988年8月20日、ザルツブルク音楽祭での演奏会の同時生中継。恐らく、当曲の初演50周年を記念して取り上げられたのだろう。
この曲は、その後、若杉弘指揮N響の1989年12月07日、第1098回定期公演での演奏の模様がN響アワーで放送された際にヴィデオ撮りしている。
ちなみに、N響は、この後1996年にデュトワ指揮で演奏したきり、現在まで一度もこの曲は取り上げていない。
そういえば、《パシフィック2.3.1》も、1969年に岩城宏之指揮で一度演奏したっきり、交響曲第1番、第4番、《ラグビー》は一度も演奏していない。
曲は、火刑を間近に迎えたジャンヌ・ダルクが、過去の思い出を回想し、火刑台のつゆと消えるまでを描いた、現代の「受難曲」である。
音楽は、終始陰鬱とした空気に包まれ、唯一、「動物による裁判」の場面のみコミカルに描かれる。
現代人たるもの、一度は聴いておきたい、正に穴(傑)作中の傑作だと思う。
■メシアン:トゥランガリーラ交響曲
上記はチョン・ミョン=フン指揮ソウル・フィル
私が聴いたのは、サロネン指揮N響で、1988年9月の第1059回定期公演。
N響は、この後おおよそ10年ごとにこの曲を取り上げていて、2019年には、パーヴォ・ヤルヴィと演奏した。
この曲は、一応、現代音楽の古典とされており、春の祭典と同等の複雑なリズムをもつが、聴き応えは十分。曲の構成も「循環主題形式」をもち、同じ主題がところどころに出てくるし、「愛の歌」というタイトルからもわかるとおり、ロマンティックな旋律にも満ち、全体的にはマーラーやR・シュトラウスなどの後期ロマン派の延長という印象。

ピアノと、オンド・マルトノという電子楽器のソロが付き、音だけでなく、見た目も楽しませてくれる。
■ペンデレツキ:広島の犠牲者に捧げる哀歌(52の弦楽器群による弦楽合奏曲)
1988年12月、N響の第1068回定期公演にて、マレク・ヤノフスキの指揮で。
映像は、ルバンスキ指揮フィンランド放送響
こちらは、《トゥランガリーラ》とはうってかわって、トーン・クラスター(音の塊)と特殊奏法が跋扈するバリバリの現代音楽。
ちなみに、広島云々はタイトルに困った作曲者が、音楽のイメージに合うタイトルを考えた末に思いついたもので、原題の「8分37秒」が示しているとおり、本来、音楽とタイトルの有機的な結びつきはない、「純音楽」である。
「実験音楽」や「チャンス・オペレーション(偶然性の音楽)」を除き、後の現代音楽の書法の基礎となるものが詰まっている重要な作品。
現代音楽を聴くなら、まずはここから。
■ストラヴィンスキー:《プルチネッラ》組曲
上記は、ネヴィル・マリナー指揮アカデミー室内管
これも、一番最初に聴いたのはいつだか定かでないのだが、1988年春のアバド指揮ヨーロッパ室内管の来日コンサートでこの曲が取り上げられた際、実演を聴きたくて足を運んでいるので、それ以前であることは確かだ。他のプログラムは、確かシューベルトの悲劇的とアイヴズの《答えのない質問》だったので、完全にこの曲一点狙い。マリナーのアカデミー室内管は1959年設立の老舗だが、当時はヨーロッパ室内管、オルフェウス室内管(指揮者なし)、シンフォニア・ヴァルソヴィア(メニューイン指揮)、モスクワ・ヴィルトゥオージ(スピヴァコフ指揮)、オーケストラ・アンサンブル金沢と、室内管弦楽団設立真っ盛り。その中でも、ヨーロッパ室内管は、1986年にウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任したアバドが設立した団体ということで、注目された。
アバドは、《プルチネッラ》全曲版を含めたストラヴィンスキーの室内音楽を、1978年にロンドン響と既に録音している(下記は全曲版のライヴ録音)。
曲は、ペルゴレージの作品を中心として、ガッロ、チェレーリ、パリソッティなどのイタリア前古典派作曲家の作品の編曲という形をとっている。
イタリアならではの明るさと躍動感、愉悦感に富み、これが《火の鳥》や《春の祭典》と同じ作曲家なのかと驚きを隠せない。
そういえば、《プルチネッラ》と同じ頃、ストラヴィンスキーが学生時代に作曲した交響曲(第1番)変ホ長調[1907年]を初めて聴いたときも驚かされた。
メンデルスゾーンともR・シュトラウスともR=コルサコフともグラズノフとも聴ける楽天的な作品で、ここから《火の鳥》や《春の祭典》がどうして出てくるのか・・・???
下に、ストラヴィンスキーが1945年に初演した、「交響曲」と題される最後の作品を置いておくが、なんとこの後、十二音技法に傾倒していくんですぜ・・・。
■プロコフィエフ:《スキタイ組曲》
ということで、今回最後の曲は、プロコフィエフの《スキタイ組曲》。
このCDも、割り引き店で入手したもの。確か、出たばかりの新譜だったと思うが、プレヴィンといったら、《シェエラザード》でお気に入り指揮者の一人になっていたので、迷わず購入。
まあ、今風の演奏を挙げるなら、ゲルギエフの演奏か。
この曲は、確かにディアギレフの言うように、音楽的には《春の祭典》の「二番煎じ」なのだろう。
しかし、この曲が作曲された二十世紀前半は、フランス音楽が印象派に進み、ドイツ音楽が十二音技法に傾倒し、イタリア、スペイン音楽が没落して、頼みの綱のイギリスが未だにパッとしないといったヨーロッパの音楽状況の中で、ロシア音楽だけが、前衛音楽の中に後期ロマン派の音楽を引き受けて、それらを「アウフヘーベン(相反する要素の相乗効果によって、また別の新しい要素が建設的に発展していく様)」していく可能性を秘めていた。
《スキタイ組曲》の誕生は、正にその象徴的現象だった。もし、プロコフィエフが、《スキタイ組曲》を破棄し、ディアギレフの言いつけを守って《春の祭典》の二番煎じにならにように、当時のヨーロッパ音楽の方向性(例えば古典交響曲の音楽形態)に合うように自分の音楽性を転向――10年後にはそうなるのだが――していたとしたら、交響曲第2番や第3番、ピアノ協奏曲第3番やオペラ《炎の天使》のような名作は生まれなかったかもしれない(《炎の天使》がなければ交響曲第3番も自動的になくなる)。
《スキタイ組曲》は、演奏時間20分ほどの短い作品だけれど、その中にロシア音楽の「未来の姿」が詰まったタイムカプセルなのだ。
というところで、以上です。
さて、次回からも加速して参ります!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
