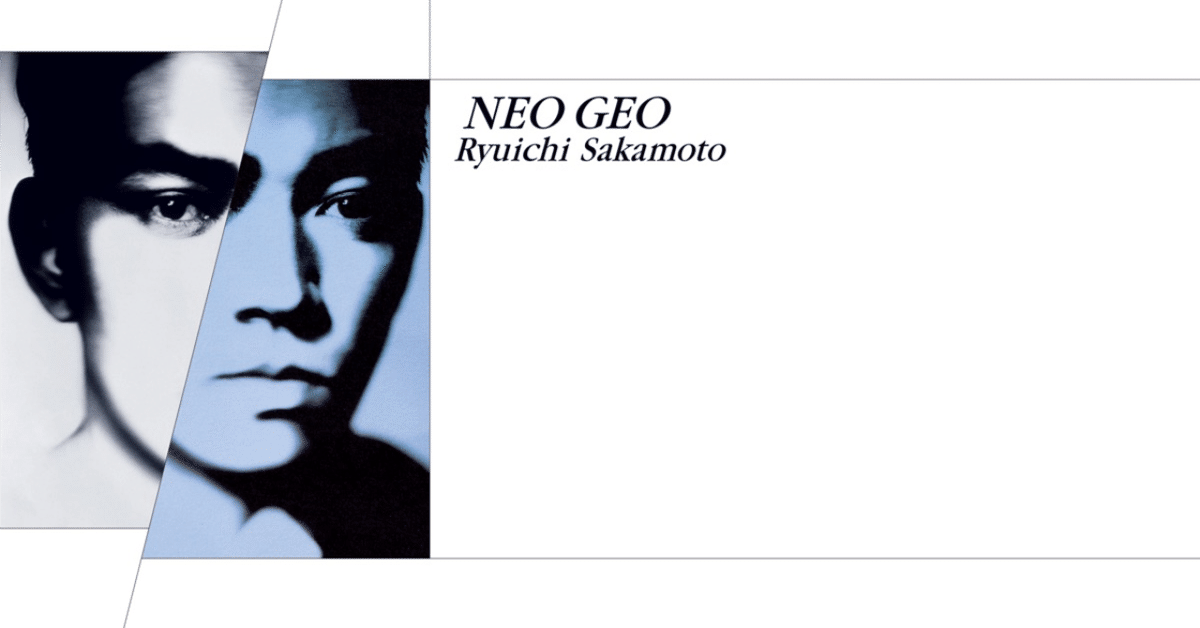
坂本龍一『NEO GEO』のリイシューに寄せて①
『NEO GEO』をアップデートする
ネオジェオという建築のムーブメントがあるという記事を読んで、Neo Geographyということだと僕が勝手に解釈し、面白いなと思いました。実際の地理的な位置関係と、日々暮らしている感覚的な「Distance(遠さ)」というのはずいぶん違うなと。例えば東京にいても、バリ島よりNYが近く感じられる。人々は皆、そういった心理的な遠近、心理的なGeographyを持っているということが面白いと思いました。『NEO GEO』は、音楽の中でそれをやってみようと試みたアルバムです。『Beauty』もその世界観に近いアルバムです。
晩年、坂本龍一は1987年リリースのオリジナル・アルバム『NEO GEO』について、上記の貴重なコメントを残している。
『NEO GEO』について、物理的距離と心理的距離の捻れにクリエイティビティを見出し、それを自身の音楽で表現しようと試みた作品であると回顧しているのである。
2007年にYCAMの委嘱で制作された『LIFE—fluid, invisible, inaudible...』以降、インスタレーションを中心として現代アートに寄り添いながら活動を続けてきた坂本龍一を考えれば、このような抽象度の高い見方は深く納得できるものであろう。
もっとも『NEO GEO』がリリースされて、37年の時間が経過している。その間のグローバリゼーションの進展による地政学的状況の変化や、インターネットの普及による情報空間の拡張についてはあらためて論じるべくもないが、冷戦によって世界が二分されていた『NEO GEO』制作当初と現代とでは、坂本龍一が『NEO GEO』通じて描こうとしていた世界を取り巻く状況は一変している。
そうであれば、新たなアクチュアリティをもって、『NEO GEO』を捉え直す機会があってもいいだろう。本稿では『NEO GEO』のリイシューを契機に、本作について新たな視点を与えることを目的としたい。サウンドのみならず、作品を取り巻く批評もアップデートされて然るべきだろう。
次節以降では、『NEO GEO』が制作された経緯や、生田朗やビル・ラズウェルなど制作にかかわった人物を取り上げていくことで、作品について深く分析していきたい。
当事者不在での『NEO GEO』のリイシューという試み
『NEO GEO』が2024年7月24日にリイシューされる。今回のリリースは、2021年の『Beauty』(1989年作品)に次ぐリイシューとなる。近年では、坂本龍一のオリジナル・アルバムのリイシューが活発化していてが、『NEO GEO』については、坂本の没後はじめてのリイシューとなることから、新たなチャレンジでもある。
それは本来ジャッジを下すべき当事者が不在であるからだ。今後、様々な形で旧作のリイシューが進むことが予想されるが、本作はそのファーストケースとなる。
ソニーミュージックによる特設サイトもオープンし、ギターで参加した窪田晴男のインタビュー動画や、『NEO GEO』に関連した年表が公開されている。
共同でプロデュースを務めたビル・ラズウェルが闘病中であること、坂本龍一のマネージメントを担当し、アルバム制作に深く携わっていた生田朗が亡くなっていることを考えると、当時の状況を知る窪田晴男の証言は貴重な史料となる。
本稿では上記サイトのコンテンツに加えて、リリース当時のインタビューなどの資料を参照することで、可能なかぎり詳細に、坂本龍一の7枚目のオリジナル・アルバムとなる『NEO GEO』について、多角的に分析をしていきたい。
まずは本作の概要について解説していこう。本作は海外でリリースすることを前提に、ビル・ラズウェルとの共同プロデュースで制作。ビル・ラズウェルがCBS・ソニー(現在のソニーミュージック)に設立した「TERRAPIN」レーベルの第1作目として、1987年にワールドワイドでリリースされた。
レーベルの名前を考えながら、ビル・ラズウェルが日本のスタッフとスッポン料理を食べたことがきっかけで、ビル本人の発案により、英語でスッポンを意味する「TERRAPIN」がレーベル名となった。
上記のとおり、レーベル名の直接的な由来はスッポン料理によるものだが、坂本龍一はTERRAPINレーベルのコンセプトについて、当時のインタビューで次のように解説している。
テラって地球のことでしょ。そこにピンを差す。アジアから出てくるエスノ・ロックのセンターになれるように。だから意識的にアジアの要素を入れたんですけど。実はスッポンのことだけどね。
レーベル設立の話は1985年10月くらいから始まり、坂本龍一もビル・ラズウェルからレーベルについて相談を受けていたことから、アルバムを作る前よりレーベルの構想についても聴いていたという。
2009年刊行の自伝『音楽は自由にする』で坂本龍一が語るところによれば、本作は、バリや沖縄の音楽を採り入れた民族的色彩が強いアルバムであり、アフリカやアイヌの音楽的要素の入った1985年リリースの『エスペラント』が、本作の引き金になったという。
もっとも時系列に目を向ければ、『エスペラント』(1985年)の翌年にリリースされた6作目のオリジナル・アルバム『未来派野郎』(1986年)を挟んで、『NEO GEO』(1987年)が制作されている。
前作『未来派野郎』ではトレヴァー・ホーンとビル・ラズウェルのどちらかに、プロデュースを依頼することを検討。実際にトレヴァー・ホーンにオファーしたものの、スケジュール上の事情で半年待つ必要があったことから実現していない。ビル・ラズウェルへのオファーも、セールス上の理由により一度は見送られている。このことについて、坂本龍一は当時の雑誌で次のように発言している。
ビル・ラズウェルっていう線も考えたんですけど、今回はある程度コマーシャルなものを作りたかったんで僕とビルがやると、音楽に純真な2人ですから、どんどん行っちゃって歯止めが利かない心配が…」
しかし、自身のオリジナル・アルバムのプロデュースを他人に委ねるという発想は自作に引き継がれ、『NEO GEO』ではビル・ラズウェルにオファーし、共同プロデュースが実現することになる。
坂本龍一とビル・ラズウェルが出会った経緯は、1984年に近藤等則が主催した「東京ミーティング1984」に遡る。「ビル・ラズウェルには生田朗に引き合わされて、ぼくも彼のやっていたマテルアルというユニットは好きだった」と坂本龍一が語るように、坂本のマネージャーを務めていた生田朗が両者を引き合わせている。
そして生田朗は坂本龍一をマネージメントしているだけでなく、実はビル・ラズウェルと共同でレーべルを設立した人物でもある。これを踏まえると、レーべル第1作目がビル・ラズウェルの共同プロデュースによる、坂本龍一のオリジナル・アルバムであったことは、自然の流れであったと考えられる。
実際に坂本は次のようにコメントしている。
「そしてこうしていろいろ一緒にやっていくうちに、なんとなく次のソロ・アルバムは彼にプロデュースを頼むんだろうなという意識になっていました。」
ここでレーベルが設立された経緯について言及すると、1983年にハービー・ハンコックの『フューチャー・ショック』をビル・ラズウェルがプロデュースし大ヒットを記録。これを受けて、CBS・ソニーがビル・ラズウェルのインディーズレーベル「セルロイド」と契約。交渉の為に来日したところから、日本との接点が生まれたようだ。
ビル・ラズウェルの日本との密接な関係について、生田朗は次のように証言している。
ビルが日本に初めて来たのは、「ロック・イット」の直後のことで、その後もう10数回、日本に来続けてるって感じなんだけど
このコメントを元に、ここまでの話をまとめると、ビル・ラズウェルは、1983年の「ロック・イット」を契機に発売元のCBSソニーがある日本との関係が深くなり、坂本龍一のマネージメントを手掛けていた生田朗や、近藤等則などのミュージシャンとの交流する機会が多くなる。1984年には近藤等則によるイベント「東京ミーティング1984」が開催され、坂本龍一と始めての共演を果たしている。1985年には、レーベル設立が検討され、1987年には記念すべきレーベル第1作の『NEO GEO』がリリースされている。
「NEO GEO年表」というものを考えたとき、その起点は「ロック・イット」がリリースされた1983年と想定することが出来るだろう。奇しくもYMOの散開コンサートが開かれ、坂本龍一がポストYMOとしてのキャリアを本格始動させたのも同年である。
次節以降では、この1983年から『NEO GEO』がリリースされる1987年までの坂本龍一とビル・ラズウェルの活動を仔細に検討することで、『NEO GEO』の持つ多面性を浮き彫りにし、作品をより深く分析することを試みる。
出典
(1)『ONBEAT』 2023/5, P.31
(2)『キーボードスペシャル』1987/6
(3)『キーボード・マガジン』1987/7
(4)『宝島』、P.29
(5)『キーボード・マガジン』1987/7、P.27
(6)『キーボード・マガジン』1987/7
(7)『音楽は自由にする』P.186
(8)『キーボード・マガジン』1987/7、P.27
(9)『Yearbook 1985-1989』ブックレット、P.16
(10)『Yearbook 1985-1989』ブックレット
(11)『キーボードスペシャル』1987/8、P.56
(12)『キーボードスペシャル』1987/8、P.58
(13)『Yearbook 1985-1989』ブックレット
(14)『Yearbook 1985-1989』ブックレット
(15)『キーボード・マガジン』1987/7、P.6
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
