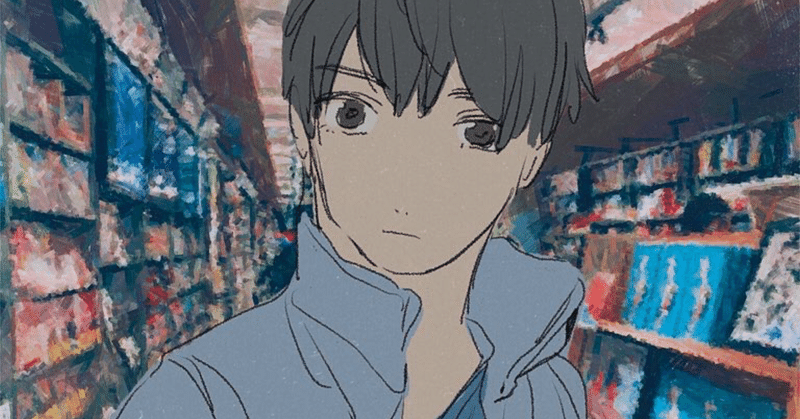
ドアノブ
今日こそ折れてしまうかと思いながらパワポを作っている。
ものすごく頑張って、無理矢理チケットを買わないと映画が見れなくなった。ドラマをチェックすることは愚か、最後にテレビをつけたのはいつだったっけ。去年の末、M1グランプリ以来だな。そうだ、年の瀬の頃だ。
年末のことはあまり思い出さないようにしていた。親の離婚をきっかけに断絶していた父方の実家に連絡をとったら、電話越しに「もうあなたと話すことはないでしょう。話したくありませんし、会いたくもありません」と言われたのが31日だ。震える声で名乗ったのを、嘲笑うような響きがあった。人を傷つけることに優越感を覚えているかのような、してやったりという冷たさに心臓がどっと冷え込んだのを覚えている。記憶の中で祖母は優しかった。小金井公園でソリを引っ張って歩く私を、楽しそうに呼ぶ姿がまだ残っている。泣くことすらできず、一人で朝ごはんの皿を片付けた。
今日こそ堕ちるんじゃないかと思いながら自分の操縦をする。
虐待されて育ったせいで、実家を逃げ出した今も毎晩親の夢を見る。疲れ切ってあさ目を覚まして、どうしよう一日が始まると思いながらロフトを這い出る。昨年から勤めている会社では、しっかりリモートワーク環境が整っているから出勤の必要がない。それが幸か不幸かはわからないのだが。
たった一人でクライアントに放り込まれ、右も左もわからぬまま孤独に仕事をしている。毎日8時間、見えない敵に監視されているような気持ちになりながらパソコンに向かうのは辛かった。能無しの上にうまく頭と心が働かないせいで、お世辞にも仕事ができるとは言えない。いつ、誰が、私の不出来を非難するかと怯えながら床に蹲る。蹲っている間にも給料は発生していて、それを思うたびに罪悪感で死にそうだった。
チャットの音が鳴るたびに泣きたくなる。別に、難しい仕事ではない。ただ、誰かにジャッジされる立場に、ひとりで立ちすくんでいることが怖い。
仕事の選択はといえば、完膚なきまでに間違えた。ビジネスもITも興味がないから、三年後に自分が同じ会社で働いている姿が想像できない。新卒切符って恐ろしい。間違った駅で切ったら最後、違う路線には乗れないね。転職サイトからくるオファーは、バカの一つ覚えみたいに同業種ばかりだ。エリート揃いの同僚に「はたらくのが辛い」なんて言えず、そもそもオンラインでしか話したことのない彼らにどうやって悩みを吐露すればいいのかもわからない。「私もめっちゃしんどくて〜」という返信、私は本当に苦しくて書いたけど、みんなはどう?打ち終わった後、キッチンの床に頭をぶつけながら泣いてたんだけど、みんなもそういうこと、ある?
ないんだろうということだけはよくわかっていた。
学校はプールだった。どんなに深く見えようと底はあったし、五十メートルならそうと最初からわかっていたから。社会は海。それを大海原と呼んで水面の煌めきに目を細められるのは、船に乗れた人たちだけだろう。私は水にぼやけた目でそれを見上げている。
父親は失踪中、生まれてからの二十数年を虐待で彩ってくれた母親とは絶縁状態だ。撃ち殺されないように走って逃げて、着の身着のままに飛び込んだ水だ。貯金も身内もないまま、泳ぐのをやめればすぐに沈むそれはもう、遭難なのだ。
足のつかない海に放り投げられて、死ぬまで泳ぐのか。ばしゃりと腕をかくと、姿勢が崩れて顔が半分くらい水に浸かってしまう。慌てて顎を上げて、水面から鼻を突き出して空気を吸う。それでも下唇くらいまでは水がちゃぷちゃぷと迫っていて、恐怖に強張った舌が塩味を舐める。水温は限りなく低い。習っていない立ち泳ぎで無様にばたつく足は、動かし方を知らないせいで攣りかけている。それでも人は、立派に海へ旅立って、と私を褒めた。体中に纏わりついた衣服が水を含んで、今にも溺れそうなこの姿が見えないのだろうか。……泳げているのだから大丈夫?手をバタつかせていないと、沈んでしまうんだ。これで泳げているように見えるなら、コンタクトを買ったほうが良い。
「休職、しましょ」
カウンセラーが言った。
やけに長いテーブルの向こう、小柄な初老の女性だった。いかにも心配という顔つきで、仕事を休めと繰り返す。
「今ね、もう限界なんだと思うよ。一度お休みとって、ゆっくりして、鬱の治療に専念しない?このままじゃ、苦しいままでずっと良くならないと思うの」
精神科医も同じことを言った。
「診断書はすぐ書きますからね。そうしたら、すぐに休めるんですよ」
私はもう、疲れ切って床を見るしかなかった。下北沢の雑居ビルの一室、狭い診察室でくらくらと診察台が回って見えた。比喩表現ではない。何かの隙に変な眩暈がするのが、ずっと癖になっていた。
「仕事は休めないの」
「休め……るんですかね」
「休めるよ。ちゃんとね、正社員なら手当もあるし」
でも、今の給料の六割で生活できる?プロジェクトから抜けて、休んで、その後復帰してまた新しい仕事を覚える方が負担かもしれない。何より、逃げ出すみたいで恐ろしかった。逃げるは恥だが恥なのだ。役になんて立たない。私は知らない。逃げとは悪で、辛くて楽しくなくて社会的に立派な道を選ぶこと、その線上を歩き続けることしか知らないから。折れたら二度と立てない予感もしていた。だいたい、ズルをするみたいで恐ろしい。休職って、大袈裟な。甘えているみたいで、やっぱり許せなかった。
滑舌の悪い担当医は、とにかく休めるならすぐにそうしなさいと言って私を帰した。帰り道、薬を買った足でふらふら歩いて、ヴィレッジヴァンガードに行った。知らないキャラクターのぬいぐるみを撫でて、ああ何をしているんだろうと思ってものすごく苦しくなった。情けない、という気持ちだけが頭に充満していて、涙が出て、マスクの中で鼻水まで出た。
文章が書けなくなったのは一年前くらい前のことだ。
通っていた脚本学校のプロットが書けなくなり、書けない本を見るのが辛くてコンクールの予定を塗りつぶした。書くと約束した原稿にいざ取り組んでも、文章を書かなくてはという圧で頭の中が真っ黒になる。魚が、するりと逃げる感覚。手を伸ばしても、水圧が腕に重くて動きはひどく鈍い。そういう感覚が、頭にへばりついて駄目だった。というか、仕事が終わってから、座り込む以外のことができない。集中して絵を描くこともできなくなった。時々調子が良いと、簡単な落書きができるくらい。一生懸命線を引くことが、物の形を考えることが、びっくりするくらいできなくなっていた。
何も書けないということは、私が私に対する価値をつけられなくなったことに等しい。
人生で、文章を書いていない時期がなかった。だから、どうやって生きればいいのかわからない。
社会人は日曜日の夜に、サザエさん見ながら絶望するというけれど、その憂鬱はどれほどのものなのだろう。明日から五日間、どうやって泳ぐかと思うと気が遠くなって、腹を壊した。トイレットペーパーをぐるぐる引き出しながら、やっぱり情けなくて頭がぼうっとした。
この生活の先に何があるんだろう。生きるために働いているのか、働くために生きるのか。眠るたびに会う母が、会社から届くメールが、タスクリストのTODOが、締め切りをとうにすぎた原稿が、私を見限った友人の楽しそうなツイートが、できなかったこと、叶わなかったこと、諦めないことを諦めてしまった過去への罪悪感が、手を取り合って私を責める。苦しかった。苦しかったけれど、誰が、いつ、どうやって私を助け得たのだろう?何を間違えなければ、ここに行きつかなかったのだろう。
夢を見ていた。
何十年かのローンで両親が買った一軒家の、ドアノブを握ったまま動けない。
夢だが、これはフィクションではなかった。悪夢から覚める前に、記憶を再生しているだけである。
今思えば、存分に格好つけた家だった。三階建ての二世帯住宅で、玄関は重たい木造のーーその呼び方が正しいかは知らないけれどーー重たい扉で閉ざされていた。黒いドアノブは、鍵がぶつかるせいで少し禿げていて、ところどころ銀色の本性を露わにしている。私はそれが握れなかった。ノブを回したらすべてが終わり、始まってしまう。ただいまと告げてから身体検査をされ、一挙手一投足を監視され侮辱される生活が。冷たい秋風に身震いしながら、自宅の前で二十分ももじもじとした。確か、中学生の頃だったと思う。
私の母は、毒親という言葉が認知され始める以前には正しいカテゴリーを持たなかった。彼女は教育熱心で、生活の基盤をふたりの我が子に置いていた。ゆえに、子供というのは全て己の意志が反映されるものであると考えた。彼女の価値にそぐわない子供自身の自由意志は、全て瑕疵なのである。父親のいない家庭は小さな帝国だ。母の価値観と感情が法であり、それに抗うことは悪であった。
私は、その帝国に生まれるにふさわしくない性分をしていた。または、この国で生まれたがゆえに反発の末、そういう気質を手に入れたのかもしれない。どちらにせよ、簡単な話、私と母は敵同士であった。
母の教育は隅々まで行き届いていて、暴力と体罰を自在に使い分ける他に、言葉で嬲ることも忘れなかった。私の家には父がいない。生まれた時から別居状態で、会うのは年に数回、3ヶ月遅れの誕生日祝いのときだけであった。私は3歳の頃からぶたれ、殴られ、蹴られ、死ねと言われながら育った。
それで、ドアノブである。
ある平日の夕方、私は部活動を終えて帰路についていた。その数日は、母の機嫌が悪かった。足取りが重い。私は次の日の登校まで、奴隷として生きねばならない。当時の私にとって、家族の住む家に帰ることは絶望を意味した。
ドアノブに触れては引き返す手が、わなわなと震えていた。毎日行う動作が、突然にできなくなる。家の中で物音がした。母の音だ。恐怖が、より大きな恐怖に玉突きされて喉が詰まる。私は膝が赤くなるくらいその場に立ち尽くした挙句、門限ギリギリにどうにかノブを押した。門限を破って詰問される恐怖が、ドアをくぐる恐怖を無理にかき消したのだった。
目が覚める。
我ながらよくできた夢だと思った。
夜逃げのように母から逃げても、結局彼女の帝国は頭の中に堅牢で、おまけに私はせっせと新しい母を作っていた。仕事という母だ。新しい母は、かつての王からしっかり役目を引き継いだらしい。
私を否定し、非難し、逃れることのできない重たい壁のような存在。その表面に、つるりと黒いドアノブがついている。私は布団の中で、できるだけ小さく丸くなった。死にたいわけではないけれど、どうすれば生きたいと思えるのかもわからないくらいには疲れていた。
己を毀損する存在を作り上げては囚われてひとり追い詰められる癖。人はそれを鬱に分類するが、薬でなんとかなるものではないのだと、頭の冷静な部分ではよくわかっていた。
深夜0時過ぎ、やってきた月曜日を前に目を瞑るのは、ドアノブを掴むあの感覚とひとしく恐ろしかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
