「教えの精髄」各節紹介その5
「オンライン・ラマナ・サットサンガ」プログラムAで詠唱されている、「教えの精髄(ウパディーシャ・サーラム)」の概要解説&各節紹介シリーズです。
第13節

ラヤヴィナーシャネー ウバヤロダネ
layavināsane ubhayarodhane
ラヤガタン プナー バヴァティ ノ ムリタン
layagatam punar bhavati no mrtam
【柳田訳】
没入にはラヤとナーシャという二つの形がある。たんにラヤに没入しただけのものは蘇生するが、もしそれが死滅しているならば、蘇生することはない。
【福間訳】
心の沈静には没入と消滅の二種類がある。一時的な心の没入は、再び現れるが、消滅すれば、二度と現れない。
【おおえ訳】
融合には二つの形がある、ラヤとナーシャである。単にラヤに融合した心は再び戻るが、滅却したならば戻ることはない。
(注釈)
ラヤは一時的融合であり、ナーシャは永遠の融合、すなわち滅却である。
第十一詩句で語られる融合は一時的なものである。霊的修行者はこれだけで満足して落ちつくべきではない。彼はマノーアーシャ、永遠なる融合(滅却)へと進んでゆかなければならない。マノーアーシャについては第十四、十五詩句で語られる。
マノーアーシャは、文字どおりには、心の死であるが、それは知覚力のないものになるという意味ではない。
マノーアーシャとは、自分がほんとうはアートマンであることを観るのを防げ、多かれ少なかれ自分を肉体と同一化する狭くて遮られ、そして歪んだヴィジョンを持つ現在の心のあり方の喪失を意味する。こうした形の喪失とは、実は獲得であり、それは有限で障害のある心の、万象を包摂し、外には何一つ残さない純粋意識、完全なる実在、アートマンあるいはブラフマンへの転移を意味する。純粋意識の意識という言葉が必然的にある形をとった「心」の存在を意味するととられるならば、人は入門から解脱に達するまでの全過程において、決して心なしには存在できないというのが正しいであろう。
実際、宗教経典の中には、ジュニャーニ、あるいはジーヴァン・ムクタの心に関連した表現が見いだされる。偉大な賢者たちはこの問題について、非常に価値ある示唆を与えている。彼らはサット・チット・アーナンダ(存在・意識・至福)の至福の歓喜について語りつつも、それは言葉では表現しえないものであるという。
シュリ・ラーマクリシュナ・パラマンサは、この状態による心は、ちょうど水に描かれた細い線とか、焼けて灰になった縄のように捕え難い存在であると語っている。このような縄は、外観は確かに縄の形をしているけれども、何も結ぶことはできない。こうした心はシュッダ・サットヴァ(清浄なるもの)として述べられる。
とはいえ、三種のグナ(要素)のほかには何一つ存在しないとする『バガヴァッド・ギーター」の考え方からすると、おそらくこれさえもいささか修正される必要があろう。 聖者の心がシュッ ダ・サットヴァの状態にあるという描写は正しいといえる。というのはその中でサットヴィック (清浄、プラクリティーの一つ)の要素は他の要素に圧倒的に勝るので、消滅させないまでも、他の要素を埋没させ、見えなくするからである。
聖者とはかくも柔和(サララ)であり、かくもサットヴィック(清浄)である。彼の意志は明け渡されている。彼にはいかなる欲望も執着もなく、彼の行為は世俗の人のようないかなるヴァーサナー、すなわち枷も生じることはない。霊性には法律と同じく「実質的応諾」の教えがある。宗教も法律もとるにたらぬことは取り上げない。物理的な科学においてさえ、実質的に真空であるもの(エアー・ポンプで作り出されたもの)は真空として扱われ、また実際的な目的のためにも真空として用いられる。この対比は「ジーヴァン・ムクタのサットヴィックな心」や「消滅を被ることのない人格を超越した魂」を理解する上でよく用いられる。
第14節
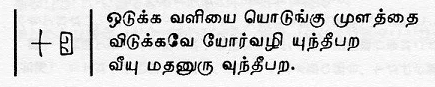
プラーナバンダナー リーナマーナサン
prānabandhanāl līnamānasam
エカチンタナーン ナーシャメッティャダハー
ekacintanān nāsametyadah
【柳田訳】
呼吸の制御によって心が没入させられたとき、もしそれが一点に固定されたならば、それは「死滅」するだろう(すなわちその形は消滅するだろう)。
【福間訳】
呼吸制御によって静められた心は、内面に向かい、一つの想念をとらえることで消滅する。
【おおえ訳】
呼吸の抑制によって、心が融け去るとき、一点に集中されれば、それは滅却しよう。
(注釈)
探求者は呼吸を抑制している間のみ心を沈めるプラーナーヤマ(調息) で満足すべきではない。彼は「心を殺す(滅却する)」段階にまで進まなければならない。それは、至高なるものへの揺るぎない精進によってなされる。
心の「死」(あるいは一時的合一)はサマーディと呼ばれる。 その至高の形は個のブラフマンへの永遠の融合、あるいは合一であり、他のいっさいの形はこれに次ぐものである。しかしそれらの間には段階がある。
(一)スシュカ・サマーディ(不毛の三昧)やジャダ・サマーディ(鈍い三昧)は精神生理的、あるいは精神的な訓練によって、自然に生み出される特定のタイプの感覚的、心的恍惚もしくは陶酔を指す。しかしこの状態の中ではアートマンやブラフマンやサット・チット・アーナンダは実現されることも到達されることもない。しかしこのサマーディを適切に利用するなら真理への、また至高のサマーディへのよき準備となる。
心の合一はいわば芸術である。しかしその価は彼がどのような対象に合一してゆくかによる。数学的問題や音楽や恋愛などへの没入は、 それらがもたらす歓喜ばかりでなく、至高者への合一へと到る準備としての価値を持っている。
それぞれの崇拝するイシュタ・デーヴァタ、あるいは人格神への合一(すなわち聖像や光や焰などの象徴の助けを借りてなされる合一)は洗錬され純化された愛への真の合一であり、次なるより高次の一歩である。
それは(二)サヴィカルパ・サマーディ(分別のある三昧)と呼ばれる。これは心が心以外のものを知覚するかぎり、心はヴィカルパ、すなわち識別作用を伴っている。これが集中され、わずかな対象、すなわち属性を持つ神やその象徴のみにまで至るならば、それはサヴィカルパ・サマーディとなる。多くの帰依者が礼拝や他の宗教体験の過程でこのサマーディを享受している。
しかしながら非常に高められた帰依は神の中に個を喪失させてしまう。そしてそれは(三)ニルヴィカルパ・サマーディ(無分別三昧)となる。それは描写することの不可能な識別作用の失せた意識の果てしない大海である。このサマーディについては次のような表現で暗示することしかで きない。そこにおいては、人の真我は神となり、人格神はたやすく非人格的ブラフマンと名づけられる本性の中に透入し、差別が立ち現われた最初の感覚は滅却して一つに融合し、あるいは再び現われることはない。
このような現成(完全な実現)のひらめきが捉えられ、しばし享受され、そして再び前段階もしくはこのサマーディに準じる状態に戻るとき、これらのひらめきはケーヴァラ・ニルヴィカルパ・サマーディ(身心融合無分別三昧)と呼ばれる。
この状態では(個人の)ヴァーサナー(慣習的思考)はしばらくの間は抑制されてはいるものの、いまだ滅却されてはおらず、それらはより低い境地に彼を引き戻すかもしれない。そしてこのヴァーサナーを完全に滅し尽くすまでは、意志はこうした力を持ち続ける。
ヴァーサナーを滅した後に、個(?)は(四)サハジャ・ニルヴィカルパ・サマーディ (俱生無分別三昧)に達する。彼は真我、あるいはブラフマンの永遠なる実現、タンマヤ・ニシュタのうちにあり、ここからはいかなる状態にも引き戻されることはない。「彼の肉体」と人が呼ぶものは、その肉体があらしめられた行為の連鎖が終わるときまで生き続け、感覚や知性とともに活動しよう。しかしこれは傍観者的な見方である。成就者はもはや肉体や行為と自分を同一化することなく、行為にも無為にも、またそれに伴う快楽や苦痛にもいっさい執着や関心を持つことはない。これは次の詩句で語られることである。
第15節

ナシュタマーナソークリシュタヨギナハー
nastamānasotkrstayoginah
クリッティャマスティ キン スヴァスティティン ヤタハー
krtyamasti kim svasthitim yatah
【柳田訳】
その心が消滅させられ、ブラフマンの中に安息している偉大なヨーギーは、彼の真の本性(ブラフマン)に到達しているので、カルマをもたない。
【福間訳】
心が消滅し、真我の境地に達した偉大な賢者に、もはや為すべき行為はない。
【おおえ訳】
心が滅却され、ブラフマンに住する大ヨーギは彼の本性(ブラフマン)を成就しているので、いかなるカルマも持たない。
(注釈)
彼はカルマに対して何一つ必要も欲求も感じない。たとえ行為がなされるときでも自分を行為者とは感じない。行為の結果さえも彼には何の影響も与えはしない。従って彼にはカルマがないといわれる。カルマの束縛はその創造主である神(人格神、非人格神によらず)にも、成就の境地タンマヤ・ニシュタにある真我の成就者にも影響を与えることはない。
神とジーヴァン・ムクタ(生前解脱者)の行為は世俗の人々の行為と同じように見えるかもしれないが、それは実に独特なものであって、彼らの行為はいかなる業果も反動も生じることはな い。たとえば創造の源初の行為やそれに引き続く創造過程、そして化身(アヴァターラ)は過去のいかなるカルマやヴァーサナーの結果でもなく、それらは神の自由に影響を与えるいかなるファラ(業果)もヴァーサナーも生じることはない。自らの意志を全面的に至高者に明け渡した聖者は次のように語っている。
「私は、私ではなく、私のうちにいる至高者なのだ。」また『バガヴァッド・ギーター』Vの7-14の言葉に見られるように、彼は自分は行為者ではないと自覚しているので、肉体から離れたままで肉体のヴァーサナーや行為の連鎖に動揺させられることも接触することも全くなく、内なる平和と幸福にとどまる。このような聖者はここでは「自我、あるいは心を滅却し」、カルマの束縛を脱した者(ムクタ)として語られる。
次の詩句では、賢者はどのようにしてこの束縛を脱するかが明らかにされる。
行為が、直接に意図された結果を超えて、行為者の意志を打ち負かし、すなわち彼を変えて不本意な再誕生を課する、意図されず願われない結果と罰に従属させる結果を生み出すならば、それは束縛と呼ばれる。欲望がその原因なのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
