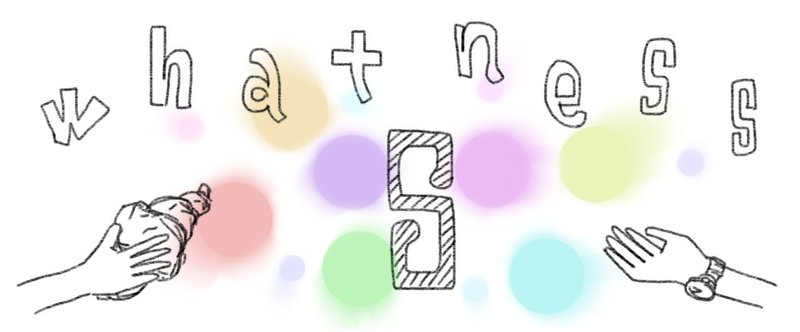
whatness ~S~
1
入社と共に買ったピカピカの時計は、二年間ですでに傷だらけになっていた。仕事で外回りをしていた俺は、いつも休憩に使う公園のベンチから空を仰いでいた。まるで何かの神にでも信仰心を送るように空をながめる。そのことにどれだけの意味があるかわからないが、俺は空を眺めずにはいられなかった。
「あっ、いたいた」
コウジ、と高い声が俺の耳に飛びこんでくる。公園入口のほうを見ると今年入社してきた新人の高岡ユミだった。彼女は社交的で、どんな人とでも気軽に喋る姿を社内でもよく見かける。口下手な俺でも、驚くほど彼女の前では口を開いてしまう。ユミは俺の隣に腰掛け、持っていた紙袋から焼きたてのクロワッサンを取りだした。はい、と言いながら手渡してくるので礼を言いながらそれをかじってみる。パリッという香ばしい音と共に焼きたての熱が薫りとなって鼻をくすぐる。
「やっぱここは穴場だよね。ずっと歩き続けるなんて出来ないもん」
「あんま頻繁に使うなよ。バレたら使えないんだから」
「わかってるわよ。あっ、そうだ。今日飲み会あるんだけど、来る?」
ユミは何も悪びれる様子もなく催促してくる。しかし俺にとって人と付き合うというのは、他の人より疲れることであった。
入社当時、新入社員歓迎の飲み会を先輩社員が企画したことがあった。俺は行く気がなかったのでそれを拒んだ。別に用事があったわけではないが、単に人と関わるのがしんどいと思ったからだ。俺も適当に理由を言えばよかったのだが、素直に行きたくないだけです、と言ってしまった。その件から先輩とは何とも言い難い距離感が生まれ、まるで霧の中で仕事をしているような気分だった。たかがお酒のことでギクシャクする先輩ってロクでもないよね、と1人でいる俺に平気で話しかけてくるのはユミ1人だった。
「……おまえさ」
「なに?」
「俺が誘いに乗らないってわかってて誘ってないか?」
「まさか」
ユミは食べかけていたパンを口に放り込む。手に持っていたインスタントコーヒーを飲んでから彼女は俺のほうに向き直す。
「私はコウジが来るまで折れないわよ」
「そういうのってさ、なんか古くないか?」
「古いって、どういうこと」
「みんな飲むことなんて、そんな望んでないだろ」
「そうだと思う」
こいつ、なに言ってんだ。そう思ったが俺は言葉にしなかった。あの先輩の前では口にできても、彼女にはそれができなかった。俺が黙り込んでいるとユミが言葉を続ける。
「でもね、誰かとつながったり普通に話したりすることは望んでいると思う」
「そんな、もんかな」
「少なくとも、私はそう思う」
ユミは自信たっぷりに、しっかりと俺の目を見ながらそう言ってのける。しかし俺にはユミのやっていることは、強引に酒の席に呼ぼうとした先輩と変わらない様な気がしてならなかった。結局は会社という集団の中で自分の居場所を作ることに必死で、そのやり方や規模が違うだけのような気がしてならない。人なんて、最後には我が身が大事なのだ。そのためなら、人は何だってやるさ。
「……わるい、先に会社帰る」
ちょっと、とユミは俺を止めようとするが鞄を持ってベンチから立ち上がる。出口に向かってひたすら歩いていくとき、背中に視線が刺さるのがわかった。もう人と関わって生きることは止めたほうがいいよな。俺は視線を振り払う御呪いを呟いてから、彼女の元をあとにした。
2
仕事が終わりひとり会社をあとにした。いつもならアパートにすぐ帰るのだが、昼間のユミとの会話が頭から離れなかった。蜘蛛の巣のように粘り付き、払おうとすればするほど絡みついてくる。俺は少しでも忘れるため、ひとり晩飯を兼ねて酒を飲もうと街をぶらつくことにした。
街の繁華街にある飲み屋で、俺はカウンター席でひとり晩飯と酒を飲み食いすることにした。テーブル席では学生や40代以降の大人たちが酒を共にして騒いでいた。今頃ユミも別の店で、いま目の前にいる人たちのようなことをしているのだろう。彼女もあと二十年もすればあの大人たちと同じような存在になってしまうのだろうか。それとも全く別の、たとえば誰かと結婚とかして家庭を持ったりしているのだろうか。どこに転んだとしても人とのかかわりは消えない。何処まで行っても、人と関わり続けている。俺が想像する未来とユミの未来に、交わるところなんて何処にもなかった。
飯を食べたあと、俺はいつもの公園にやってきて1人缶ビールを煽ることにした。グビグビと喉を鳴らして飲むが、その音が公園に虚しく響き渡っていく。俺を照らすのは月だけで、音を鳴らして飲んでもみてもその光がスポットライトのように俺だけを照らすことはなかった。
いつからこんな風に、俺は孤独を愛するようになったのだろうか。
思えば小学校高学年あたりから、俺は人と群れることを止めた気がする。中学、高校と上がっていくに連れてその孤独さには磨きが掛かったと思う。俺はだれよりも人と関わることを止めて、ひとりで生きていくことを望んだ。その理由はもう思い出せない。いや、思い出さないようにあえて忘れているのかもしれない。
忘れた結果、俺の景色からは色が消えていった。同じような毎日を選択し、何の変化もないことを選んだ。キリキリと万力のように締め付けられた心は摩耗していく。その度に心から色が消えていった。
「このまま摩擦し切って、消えたほうが楽だな」
そう口ずさんだ途端、風が花びらを唇に運び栓をするように留まる。
条件反射的に身体を起こし、声を出しながら口元を拭った。
「あはは、なにその声」
花びらが飛んできた方向。そこにいたのは色を失っていない彼女だった。
「ユミ、今日は飲み会なんじゃ」
「一次会でお開き。てかそんなに人も集まらなかったから、仲いい人だけで飲んだだけ」
そう言いながら彼女の隣に腰掛ける。少しだけ酒の匂いがしてむせ返りそうになったが、ユミ独特の風が俺を包み込んでくる。
「どうしてここに」
「あんたが行くとこなんて、ここしかないでしょ」
「でも、どうしてここにー」
「今日のあんた見てると、イライラしたから」
今までに何度か言われた一言。その目は座っていて、おそらく酔っていると予想される。俺がはいはい、と答えると同時にユミは言った。
「私ね、しばらく引きこもりだったの」
引きこもり。思わずつぶやきそうになって口を防ぐ。それはユミからは程遠い言葉で、あまりに唐突で、俺は唖然としてユミをみる。
「コウジと同じように就職活動してることがあって、そのときある企業から内定もらったのに突然取り消されてさ」
「それって、内定取り消しってやつか」
こくり、とゆっくりユミは頷く。試験や面接を通して企業が入社希望者に内定を出したにも関わらず、不当な理由で企業が合格者の内定を取り消すケース。自分が就職活動しているとき聞いたことはあったが、実際に被害にあっている人にあったのは始めてだった。掛ける言葉に困っていると、ユミがぽつぽつと話を続ける。
「その内定出たのが大学卒業間際で、私は訳がわからなくなってさ。結局そんなことする会社に入社するのも嫌だから蹴ったんだけど、卒業してからだとぜんぜん就職決まらなくてさ。だれも私のこと相手にしないんだよ、卒業生だけってことでね」
「じゃあ、ユミは」
「ほかの同期とは年ちがうよ」
そうか、とだけ漏らす。それ以上の言葉は出なかった。もっと掛けるべき言葉があるはずなのに、どうしてか何も生まれなかった。
もどかしい。
他人にこんな感情を抱いたのは久方ぶりだったかもしれない。
「親は私のこと理解できなくてさ。ただ私に非があって、会社から落とされたとしか思わないの。そのまま家に引きこもったってなると、周りからの目も厳しくなるじゃん。だから私の心配なんて全くしてないんだよ。結局は自分のことだけ。あのとき私も余裕なかったから、親のこと考えることなんて出来なかったけど、それ差し引きしても私より世間体のことばかり考えてたと思う」
「お前は」
「なに」
「それだけ絶望してたのに、どうして会社にまた」
ユミはゆっくりとベンチに背を預け、空を仰ぎながら長い呼吸をする。そのまま独白するように言葉をもらす。
「とりあえず私は外に出るようにはした。家の中に私がいると親も険悪になるばかりで、針のむしろって感じ。特に行きたい場所なんてなかったけど、街中で知り合いに会うのも嫌だったから、とにかく歩いた。でもすぐ疲れちゃって、こういう公園でよく休むようになったの」
その公園のひとつでさ、と一呼吸おいてユミはもう一度俺を見据える。その目に思わず逃げ出したくなるほど、その目は真っ直ぐだった。
「あんたをみつけたの」
「……おれ」
「スーツ着てるアンタがいた。同い年ぐらいのアンタが、もうスーツを汚してて。私とあんたは同じぐらいのときスタートしたはずなのに、どこで間違えたんだろうって。同じ公園のベンチに座ってるのに、私とアンタでこんなに境遇が違うんだろうって。片方はベンチに座ってる間にもお金もらえて、もう片方は何も生み出さない」
「おれは、そんなつもりは」
「わかってる。だけどそうやって他人を恨まないとやっていられないぐらい参ってた。でも何度かこの公園にくるようになって、またあんたを見かけた。そうやって何度かアンタを見てたら、また会社入れるような気になったの」
「なんで、おれなんか見てて?」
ふふっと笑って、彼女は答えた。
「やっぱ、覚えてないよね」
ユミは先ほどまでの鋭い視線を下げ、目元を緩める。落胆、という文字を絵にすれば彼女のような姿だと思ってしまう。何に気落ちしているのだろうか。俺と彼女の接点などあっただろうか。クラスメイトであった記憶もない。名前は覚えていなくても顔は少なからず覚えているつもりだったが、彼女のことは会社で出会うまで記憶にない。
「……ごめん、変なこと聞いちゃって」
ユミはそう言い残して立ち上がる。その寂しそうな顔を見たとき、白黒の記憶の中に色がついた人間が現れた。
確か一年前だった。今いる公園にいつものようにさぼろうとやってきていた。しかしその日は先客がいた。灰色のパーカーと紺色のジャージを着た同い年ぐらいの女だった。彼女は暗いというよりすでに燃え尽きた灰のように色が無くて、俺の中に色がないことなんて関係なく彼女に色はなかった。俺は少しだけ距離を取って座った。しかし彼女は何の反応も示すことなく、ただぼうっと佇んでいた。
俺は適当に会社の資料に目を通しながら買った菓子パンを口にした。しかし一向に彼女は動く気配がなく、まるで石像のようだった。30分ほど時間を潰してから、俺は資料を片付けてベンチを離れようとした。そのとき鞄に以前買った菓子パンが入れっぱなしだったことに気が付いた。
「……ほら」
俺はパンを取りだして彼女に差し出していた。どうしてそうしたのか、自分では全くわからなかった。どうせ食べないものだし、鞄に入れっぱなしで捨てるのももったいないという気持ちがないわけではなかった。俺としては本当にそれだけだったのかもしれないし、別の何かが俺にそうさせたのかもしれなかった。それが何かはわからなかったが、パンを差し出した瞬間、そのときの彼女の目は会社で出会ったユミの目と同じだった。
「まてよ」
俺はベンチから離れるユミの手を取る。振り向いた彼女の顔は、どうしてユミの顔はこんなに暗いんだ。今まで他人なんてどうでも良かったのに。俺なんかをみて、気持ちを奮い立たせる人間がいることなんてどうでもいいはずなのに。俺を動かした力は軽い力のはずだった。それでも川に堰き止められた葉を動かすことはできた。手を触れた場所から少しずつだが景色にも色が戻っていく。虚を突かれた彼女は間抜けな声と共に俺を見つめる。彼女の視線を受け取る事で、ふわりと花が咲き乱れるように世界に彩を引き寄せる。ユミの目を見つめながら、川に笹の葉をそっと漂わせるように呟く。
「もう少し、一緒にいないか?」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
