SALEM "Fires in Heaven"
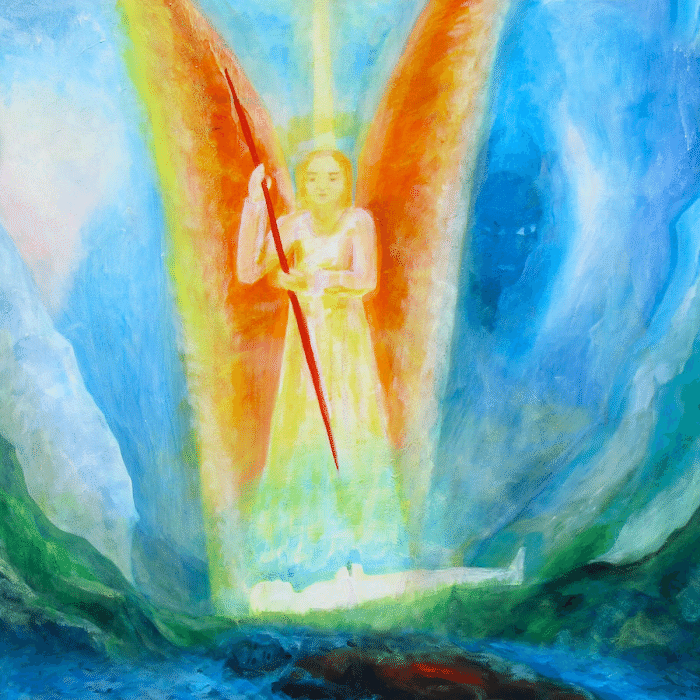
アメリカ・トラバースシティ出身のエレクトロデュオによる、約10年ぶりフルレンス2作目。
ウィッチハウス。この単語を聞くたびに、自分は怖いもの見たさにも似た好奇心を掻き立てられる。それはヴェイパーウェーブに接する時とほぼ同種のものである。どちらも音楽的な発端は共通していて、ヒップホップ界隈にて誕生したチョップド・アンド・スクリュードの手法を駆使し、サンプリングの元ネタに対する敬意があろうがなかろうが、素材を自分の思うがままに捻じ曲げて楽曲の一部分として転生させるという、極めてラディカルな姿勢が基盤となっている。なおかつウィッチハウスの場合は、アクトによって作風の細かな違いはあれども、基本的には退廃的、呪術的な空気感が共通コードであり、言わば古くから続くゴスミュージックの最新型と捉えることができる。SALEM はそのウィッチハウスの代表格として好事家に認知されているわけだが、ウィッチハウスというジャンルが勃興してからおよそ10年が経った今、あの頃の界隈の賑わいはもはや時流とともに消失してしまった。もちろん現在でも活動を継続しているアクトはいるが、あまりにもリリースが散発すぎるのもあり、表立って注目されることはほとんどなくなっているのが実情だと思う。
ところが、その SALEM が今になって新譜を発表したのだ。前作から10年越しに。この10年の間に彼らがやってきたことと言えば、数枚の EP やミックステープの制作、あとは外部のリミックス仕事くらい。特にテン年代後半はこれといって目立った活動はしておらず、てっきり空中分解したのだと思い込んでいた。生きていたのか…という事実だけでも何だか笑ってしまうものがあったが、実際の内容を聴いてさらに笑ってしまった。ウィッチハウスである。まさしく。10年前の好奇心が胸の内にジワジワと蘇るのを感じた。
そもそも、自分はビジュアル系から音楽を聴きだした人間なので、音楽の良し悪しを判断する際に "ゴス的かどうか" というのは結構根深い価値観として備わっている。ゴスの匂いを発している音楽に条件反射で手を伸ばしてしまう癖が今でも抜けていない。なのでウィッチハウスにも注目していたわけだが、それまで自分の中のゴスミュージックと言えば、まず BUCK-TICK 、そしてその直系の祖先に当たる Bauhaus や The Cure など、いわゆるポジティブパンク勢が第一のイメージにあったので、それらと比べると SALEM の音楽は同じゴスでもかなり様相が異なり、初めは正直、かなり面食らった。先述のバンド達はどちらかと言えば繊細に、慎重に、内省的な印象を保ちながらゴスの世界観を構築していたかと思うが、対する SALEM の手つきはかなり暴力的に感じるのである。シンセもボーカルも原型をとどめないほど大胆に変調され、リズムはグネグネとうねりまくり、そこに閉所恐怖症的な圧迫感や恐怖感が付与されるという構成。それは非常に野蛮で、粗野で、ともすれば下世話にも受け取れるものだった。しかも今回の "Fires in Heaven" は、重厚で濃密な印象があった前作 "King Night" と比べてみても、その野蛮さに拍車がかかっている。11曲30分というショートカットな尺も含め、ある意味でパンキッシュと言うべきか、良くも悪くもインターバル10年の重みを感じさせない、ライトかつシャープ、それでいて胡散臭さ全開の仕上がりになっているのである。これにはますます当惑するばかり。
しかしながら、今作の趣向は "ゴシック" というジャンルの本質、そのど真ん中を綺麗に射抜いたものであるとも言える。そもそも "GOTHIC" という言葉の起源を辿っていけば、いびつで不揃いな外見を持つヨーロッパ北方の建築様式を、均整こそが美と捉えるルネサンス期の文化人は "奇怪で不気味なものだ" として認めず、ローマ帝国を侵略するなどで猛威を振るったゴート族のイメージになぞらえ、ゴート的だと侮蔑したのが由来である。その奇怪さとはすなわち "野蛮" のタームにも置き換えることができる。その "野蛮" 性は音楽のみに範囲を限定したとしても、現在でもその野蛮たる本質を維持したまま様々なジャンルをウィルスのごとく巡り渡っており、パンクと交配して Misfits 、メタルと交配して Type O Negative 、インダストリアルと交配して Nine Inch Nails 、エモと交配して My Chemical Romance 、ポップと交配して Billie Eilish を生んだ。そしてここ日本ではヤンキーと交配してビジュアル系となり、ロリータと交配してゴスロリとなるなど、世界的に見ても特に異様な例を実現しており、その "野蛮" 性は一層強固なものと化している。つまり何が言いたいのかというと、"ゴシック" の本質とは何がしかのノーブルな定型ばかりを指すのではなく、むしろそのマナーを根底から覆してしまうような、別種のものと交わることで生まれるグロテスクな混沌、混淆にこそある、ということである。
ちなみに言ってしまうと、以上の論理は後藤護著 "ゴシック・カルチャー入門" からのそっくりそのままな受け売りである。ごめんなさい。
ともかく、その話の筋で言えば、混淆まっしぐらな今作はゴス以外の何物でもない。ギチギチに歪曲されたヒップホップが怨霊のごとく浮遊し、そこにシンセやビートが無造作に添えられ、サイケやノイズ成分は大盛り、時にはクラシカルネタも突っ込んだりで、フリーキー極まれりだ。しかし全体には退廃、不穏といった雰囲気だけが共通しており、まるでブラックホールのような奇妙な引力を放っている。この道なき道を突き進む粗削りさ、洗練や優美などとは程遠いグロテスクさ。これこそがゴシックをゴシックたらしめている所以だろう。この深遠なるカオスに身をうずめる時の心許なさは、それこそ自分がかつて BUCK-TICK や Bauhaus に初めて触れた時の違和感を思い出させるし、それと同時に、ゴシックと言えば BUCK-TICK や Bauhaus だといった旧来的な認識に囚われっぱなしのロートルの脳細胞をグリグリと蹂躙していくような、サディスティックな痛快さも同時に覚えるのである。
ウィッチハウスはジャンルとしての勢いは死んだかもしれない。しかし当のウィッチハウスにとって、そんなことは問題ではない。そこで鳴っている音楽自体が、混淆であるがゆえの刺激、ステレオタイプを打ち破るパワーに満ち溢れている限り、いつの時代でもその魅力は有効に機能し得る。少なくともこの "Fires in Heaven" はそれを証明している。今作はゴスミュージックならではのイズムを現代なりの形で確かに継承し、異形の火を不敵にゆらめかせているのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
