
GSG国内諮問委員会×金融庁「インパクト投資に関する勉強会」フェーズ1終了。座長・水口剛先生にインパクト投資の将来を聞く
SIIFが事務局を務めるGSG国内諮問委員会が金融庁と共催する「インパクト投資に関する勉強会」が、2021年9月3日開催の第7回でフェーズ1を終了し、区切りを迎えました。この勉強会は、GSG(Global Steering Group for Impact Investment)国内諮問委員会と金融庁の共催で、主に金融関係者が集まって、インパクト投資への理解を深め、その意義と課題について議論するものです。2020年6月から2ヶ月に1度のペースで開催し、参加者はオンラインも含め毎回約90〜100人に上りました。ここでは、勉強会の座長を務めてくださった高崎経済大学学長の水口剛先生に、勉強会の振り返り、今後の展望を伺います。先生のインパクト投資観、資本主義の将来についても語ってくださいました。
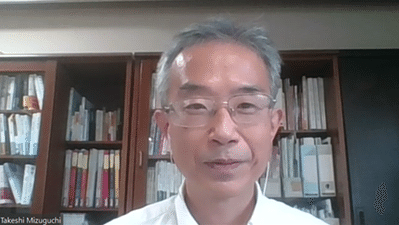
高崎経済大学学長 水口 剛氏
聞き手)SIIFインパクト・オフィサー 小笠原 由佳
インパクト投資には、二通りの概念がある
小笠原 水口先生は長年、責任投資・ESG投資の研究に取り組んでこられました。今回の勉強会を通して「インパクト投資」についてのご認識に変化はありましたか?
水口 ちょうど同時期にESG金融ハイレベル・パネルにポジティブインパクトファイナンスタスクフォース(環境省)が置かれて、そちらでも座長を務めたんです。ESG投資がESG金融に広がり、その発展形という意味でインパクトファイナンスを捉えていました。インパクト投資にも同じイメージを持っていましたが、こちらの勉強会に参加して思い出したのは、2015年にイギリスで出会った社会的インパクト投資の事例です。
小笠原 どのような事例でしょう?
水口 日本にもホームレスの自立を支援する雑誌を発行している「ビッグイシュー」という社会企業がありますが、本国のイギリスには「ビッグイシューインベスト」という投資部隊があって、インパクト投資をしています。その投資先の視察に同行したんです。ホームレスの人が空き家の改修を通して職業訓練を受け、さらに改修した空き家を低廉な家賃で貸すというプログラムで、とても感銘を受けました。
小笠原 すでにインパクト投資の現場を見ておられたんですね。
水口 UNEP FI(国連環境計画・金融イニシアティブ)のいうインパクトファイナンス、すなわち、自社のポートフォリオ全体においてネガティブなインパクトを減らし、ポジティブなインパクトを増やす、という考え方と、具体的な社会課題を解決するためのプロジェクトに積極的に資金を提供する方法との二通りがある。どちらもインパクト投資という概念だと思いました。
目的志向のインパクト投資「Theory of change」
小笠原 全7回の勉強会のうち、最初の数回はインパクト投資についての概念的な議論で、委員の間で意見の相違も多かったように思います。
水口 おそらく、当初はインパクト投資に対する認識も異なっていたし、議論も抽象に傾きがちだったと思います。後半、各回でPE(プライベート・エクイティ)や上場企業株式・債券、地域金融といった具体的な商品を取り上げて議論していくなかで、相互の理解が進んだのではないでしょうか。
小笠原 勉強会全体を通して、特に印象に残っている論点やトピックはありますか。

水口 大きくは二つあります。一つは、オランダ・トリオドス銀行傘下のインパクトファンドについての話題です。このとき紹介していただいた「Theory of change(変化の理論)」は、とても興味深いものでしたね。
小笠原 このファンドは「食の移行(Food Transition)」をミッションに掲げ、そのための先駆的な事業を定義して支援する、というものです。このミッションを達成するために、あらかじめ、投資テーマを「オーガニックで持続可能な食品会社」「持続可能な食糧への移行」「公正な流通のための方策」「廃棄問題の解決や循環システム」に設定しています。投資を通じて起こしたい変化が先にあり、そのために投資活動を行おうとすること、そのセオリーが「Theory of change(変化の理論)」です。
水口 多くのインパクト投資は、すでに起きている社会課題の解決を目指すものです。例えば、受刑者の再犯率を下げる、貧困層の子どもに教育を授ける、といったプログラムです。もちろん、それぞれとても有益ですが、それ以前に、そもそも、なぜ罪を犯すに至ったのか、どうして貧困に陥るのか、という原因にアプローチするものはなかなか出てこないな、という問題意識を持っていました。翻って、トリオドスのファンドは食の全体を変えていく、そのストーリーをつくっていく、という。個別の課題ではなく全体を考える、新しいアプローチだと思いました。それが一つ。
小笠原 もう一つは何でしょう。
水口 かねて、上場企業株式や債券によるインパクト投資は真に可能なのか、いささか疑問に感じていました。ですから、これらを議題に取り上げた第5回は特に印象に残っています。実際に国内で上場株式インパクト投資に取り組んでおられる方々からその意義を聞くことができました。事業規模の大きさや活動領域の広さ、リソースの豊富さから創出できるインパクトが大きいこと、インパクト投資の機会を広く個人投資家に届けられること、などが語られましたね。
気候変動や格差への危機感がESG投資に向かわせる
小笠原 水口先生は、最近のESG投資やインパクト投資のある意味ブームのような状況を、どのように見ておられますか。
水口 ESG投資に注目が集まっている一番の理由は、危機感ではないでしょうか。今年は地中海のあちこちで山火事が起きたり、豪雨でライン川が氾濫したりして、大きな被害を引き起こしました。日本国内も、毎年のように豪雨被害に見舞われます。気候変動に対する危機感が、非常に高まっている。
小笠原 確かにそうですね。
水口 さらに、アメリカの政権交代によって、世界中が「2030年温室効果ガス40〜50%削減」「2050年カーボンニュートラル」に向かって舵を切ったことが、金融にも影響を与えていると思います。また、経済格差の拡大や世界の分断に対する問題意識が共有されてきたことも背景にあるでしょう。
小笠原 こうした社会課題をESG投資やインパクト投資によって解決していくために、私たちは何を考えるべきでしょうか。
水口 ESG投資は、投資判断に環境や社会への影響を組み込むものです。その先に、リスクとリターンだけでなくインパクトを考える、リスクとリターンが同じなら、よりインパクトの大きいものに投資する、という考え方が確立されました。それが、広い意味でのインパクト投資です。ただ、リスクとリターンは測れても、インパクトを測るのは難しく、IMM(Impact Measurement and Management 、社会的インパクト評価・マネジメント)やImpact-Weighted Financial Accounts(インパクトを考慮した会計基準)が議論されてきました。けれども、インパクトを測る以前に、「リスク・リターン以外にインパクトを考える」という規範が本当に根付いているでしょうか。あらゆる金融には必ずインパクトがあり、ネガティブなインパクトを減らし、ポジティブなインパクトを増やすという規範を、今の金融の仕組みのなかに、いかに組み込むかがポイントだと考えています。
経済と社会の向かう方向を、二つの軸で考える
小笠原 最近、資本主義には限界があるので、仕組み自体をつくり替える必要がある、という議論があります。一方で、今、さまざまな問題が生じているのは、市場メカニズムが不完全だからであって、資本主義あるいは市場経済の枠組みのなかで修整していけばよいという考え方もあります。
水口 前者は例えば、斎藤幸平さんの「人新世の『資本論』」(集英社新書)ですね。私もおもしろく読みました。特に前半の現状分析は明晰で分かりやすい。ただ、後半のソリューションについては、やや楽観的すぎるというか、飛躍があるのではないかという感想を持ちました。
小笠原 「脱成長コミュニズム」ですね。
水口 「ワーカーズ・コープ」のような運動は古くから行われてきました。しかし結局、それが今の市場メカニズムを凌駕することにはなっていないのが現実です。理想は理想でしかなく、どんな仕組みなら社会に広がるのかが重要でしょう。それはウイルスの変異にも似ています。私たちはつい、ウイルスを擬人化し、ウイルスの変異を人類との戦いのように捉えがちですが、ウイルスの変異は人間の意思とは関係のない、単なる自然現象です。さまざまな変異が起きる中で、より環境に適したものが広まっているのです。市場メカニズムも同様で、意図して変化を押しつけようとしても、社会に受け入れられなければ広がりません。
小笠原 では、資本主義の将来はどうなるのでしょう。
水口 二つの軸で考えてみましょう。一つは、「市場経済か、統制経済か」という軸です。欧米や日本は市場経済に軸足を置き、中国のような全体主義国家は統制経済を重視してきました。今、中国は経済が非常に好調なので、統制経済も悪くないのでは、と考える人もいます。

小笠原 もう一つの軸は何ですか。
水口 「個人の利益を重視するか、社会全体の利益を重視するか」です。これまで欧米や日本は個人の利益を重視する市場経済を選択していて、これを株主資本主義と呼びます。けれど、このまま経済の分断が進めば、うまく機能しなくなるでしょう。いっぽうで、中国が選んだ統制経済も、結果的には格差を広げています。そこに問題があることは彼らも気付いていて、先日「共同富裕」という政策を打ち出しました。ただ、全体主義の仕組みで共同の利益を重視すると、さらに統制色が強まります。果たして中国の人たちはついて行けるでしょうか。
小笠原 現状では、西側諸国の市場経済にも中国の統制経済にも格差の問題が起きているわけですね。
水口 これからの可能性として考えられるのは、市場経済に軸足を置きながらも、社会全体の利益を志向する仕組みでしょう。それが、ESG投資やインパクト投資が目指す方向だと思います。資本主義かどうかではなく、市場メカニズムに依拠しながら社会全体の利益を守ることが可能なのかどうか。それは、原理原則として社会全体の利益を考慮しつつ、具体的な行動は個人の自由に委ねる社会だと思います。自由でありながらも、全体利益に反する行為は倫理的にできない、そんな社会を想像しています。
勉強会はフェーズ2へ。融資のマインドセットに変革を
小笠原 最後に、勉強会の次のフェーズへのご期待をお聞かせください。
水口 インパクト投資・インパクトファイナンスが広がるフレームワークをつくれるといいですね。分野毎にTheory of changeを設定して社会を改善していく動きと、上場企業株式・債券のようなメインストリームのお金の流れが両輪で動くような。IMMも重要ですが、技術論に終わることなく、社会の規範を変えていかなくてはならない。そのためには、やはり制度設計が必要です。EUのSFDR(Sustainable Finance Disclosure Regulation、サステナブルファイナンス開示規則)は、金融機関に「サステナビリティへの配慮は義務」という認識を浸透させるもので、日本もそういう方向に向かうといいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
