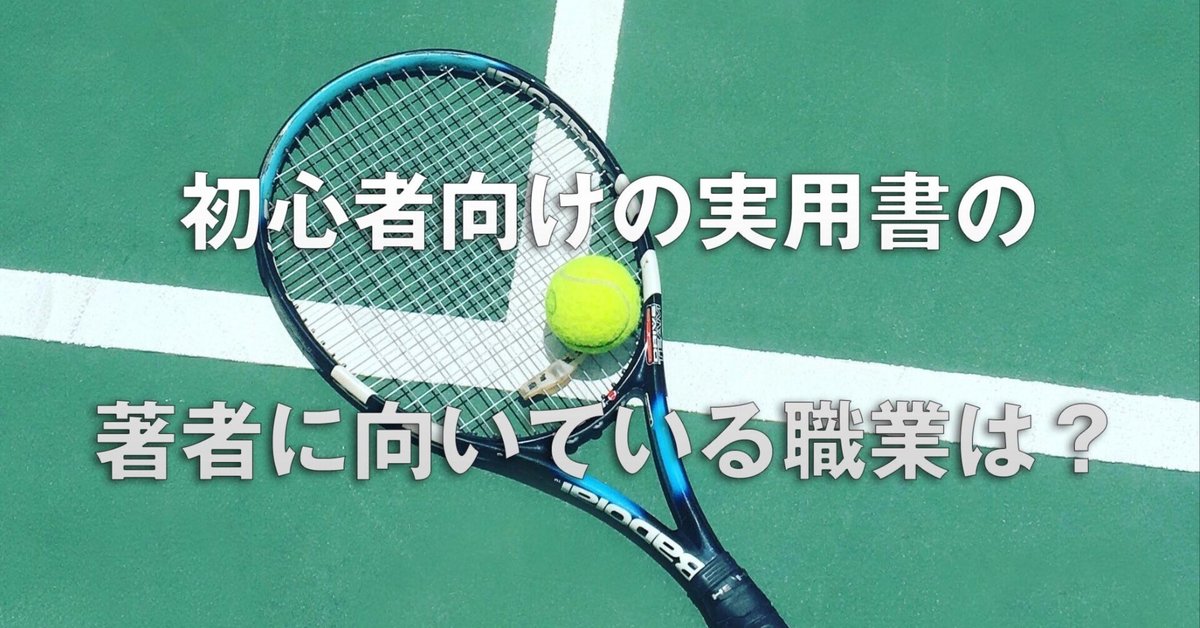
初心者向けの実用書の著者に向いている職業は?
私が作っている実用書は、ほとんどが初心者と初級者向けです。
このようなターゲットを対象にした実用書の場合、著者に向いている職業があります。
インストラクターです。
インストラクター、コーチ、先生……
インストラクターは初心者や初級者に教えることが多い方々です。
たとえば、スポーツのインストラクター。
テニス、ゴルフ、水泳、スキー、スキューバダイビング、サッカーといったスポーツを教えている方々です。
健康・美容分野もインストラクターがたくさんいらっしゃいます。ヨガ、エアロビクス、ダンス、ピラティス、スポーツジムなどのインストラクターです。
パソコンやIT系のスキルもインストラクターが多数いる世界。ExcelやPhotoshopのようなアプリケーションや、プログラミングなどを教えている方もたくさんいらっしゃいます。
このようなインストラクターは実用書の著者に向いています。
また、インストラクターという名称がついていなくても、初心者や初級者に教えている機会が多い方は、実用書の原稿を書くことができます。
「先生」と呼ばれている方です。
たとえば、英会話、音楽、絵画、手芸、料理、アロマ、ネイル、カメラなどを教えている方々です。
このような方々も、実用書の原稿を書くことができるでしょう。
インストラクターは初心者にやさしい
なぜ、インストラクターや先生のような方が、実用書の著者に向いているのでしょうか。
繰り返しになりますが、それは初心者や初級者に教えている機会が圧倒的に多いからです。
その経験から、以下のことを身につけているのです。
①日頃からわかりやすい言葉を使っている
②初心者がつまづきやすいポイントを知っている
③繰り返しや言い換えに慣れている
それぞれ見ていきましょう。
①日頃からわかりやすい言葉を使っている
まず、初心者は専門用語を知りません。
インストラクターは、それを実感しているため、日頃から初心者でも理解できる、平易な表現を使用する癖が身についています。
それが原稿にも出るのです。
生徒さんが言葉だけでは理解できない場合、図版を使うことにも日常的でしょう。
なんとか理解していただくために、やさしい言葉や図解を駆使し、スポーツのようなジャンルでは、実際に体を使って説明します。
これらの経験から、初心者向けのテキスト原稿や図版原稿を作ることができるのです。
②初心者がつまづきやすいポイントを知っている
インストラクターは、何十人、何百人、何千人という生徒さんと向き合ってきたため、多くの人がつまずくポイント、理解しにくいポイントをわかっています。
そして、そのような部分は、ていねいに時間をかけて教えなければいけない、と理解しているのです。
テニスのボレーを例に考えてみましょう。
ボレーでは、ラケットにボールが当たる瞬間に、ボールを弾くことが大切なのですが、インパクトの前と後のラケットを振るスピードが一定で、力を入れるべきタイミング(インパクト)で力を入れることができない方がたくさんいらっしゃいます。
テニスのインストラクターは、そこを詳しくていねいに教えることができるのです。
③繰り返しや言い換えに慣れている
上記②のつまづきやすいポイントを、初心者に理解・習得してもらうためには、時間を長く割いて教えるだけでなく、同じ説明を何度も繰り返すことが大切です。
いくらていねいに教えたとしても、一度だけで理解・習得するのは容易ではありません。
何度も繰り返すことが必要なのです。
もうひとつ、大切なコツがあります。
それは、異なる表現を使って伝えることです。
人によって、腹落ちする表現や納得できる教えられ方が違います。
インストラクターは、このような個人個人の理解の差を日頃から体験しています。
繰り返しそういう場面に遭遇しているからこそ、異なる表現を使うことが自然とできるのです。
先ほどのテニスのボレーの例で挙げた「ボールを弾く」という説明を別の表現に変えてみましょう。
「インパクトでボールを弾く」という表現を何度も繰り返す以外に、「インパクトの瞬間にラケットを『ぎゅっ』と握る」「当たった瞬間にラケットを止める」「インパクトのときに『パンっ』と言う」「ヒットのタイミングでは一気にラケットをボールの下に入れる」「インパスは、前脚にグッと力を入れると同時にボールを打つ」などです。
同じ動作を説明しているのに、あえて別の表現を使って説明します。
インストラクターや先生と呼ばれる方々は、このようなことを繰り返し実践しています。
それが原稿を作るときに活かされるのです。
ですから、インストラクターは実用書の著者に向いているのです。
実際、初心者に教える経験をお持ちの方が著者の場合、わかりやすい原稿が上がってきます。図版原稿も工夫されているケースが非常に多くなっています。
実は、私が出版業界に入る前は、テニスのインストラクターをしていました。
そのときに、上記のような、さまざまな表現を使い分けていました。
人によって、納得される言い方が異なるのを実感していたのです。
その経験が、私が実用書を編集している際、とても活きています。
「初心者でもわかるように」を常に考え、「ここは理解しにくいのでは?」と、自分に問いかけながら編集作業を行っています。
もし、あたなが初心者や初級者に教えているインストラクターやコーチ、先生でしたら、実用書の原稿を書くノウハウはすでに身についています。
一方、初心者や初級者に教えた経験が少ないのでしたら、周囲の親しい方に真剣に教えてみてください。
そうすることで、初心者向けの実用書に必要な伝え方を身につけることができます。
このスキルは、書籍の著者になるだけでなく、さまざまな場面で活かされるモノです。
著者になることに興味がないという方も、ぜひ一度トライしてみてください。
きっと、役に立つスキルが身につきますから。
文/ネバギブ編集ゴファン
実用書の編集者。ビジネス実用書を中心に、健康書、スポーツ実用書、語学書、料理本なども担当。編集方針は「初心者に徹底的にわかりやすく」。ペンネームは、本の質を上げるため、最後まであきらめないでベストを尽くす「ネバーギブアップ編集」と、大好きなテニス選手である「ゴファン選手」を合わせたもの。
本づくりの舞台裏、コチラでも発信しています!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
