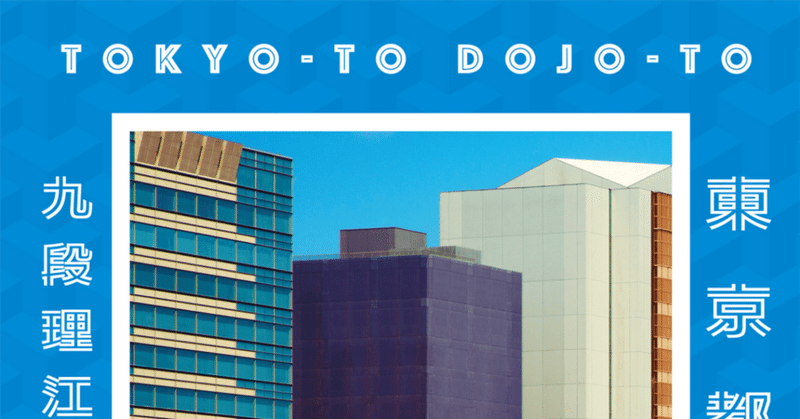
芥川賞受賞作・東京都同情塔と考える「平等とは何か」
最近は仕事やプライベートに忙しくめっきり小説は読めてなかったんですが、久しぶりに食指が動いて読んだ話題の芥川賞受賞作「東京都同情塔」。めちゃくちゃ面白かったので、個人的に特に面白かった点「平等性」というテーマについて綴りたいと思います。
前提として、この本はこんなあらすじで紹介されています。
ザハの国立競技場が完成し、寛容論が浸透したもう一つの日本で、新しい刑務所「シンパシータワートーキョー」が建てられることに。犯罪者に寛容になれない建築家・牧名は、仕事と信条の乖離に苦悩しながら、パワフルに未来を追求する。ゆるふわな言葉と実のない正義の関係を豊かなフロウで暴く、生成AI時代の預言の書。
あらすじを見て分かる通り、輪郭が非常に曖昧な、何をテーマにしているかがわかりづらいのが本書。というか、僕の理解ではこの本は「テーマ」がたくさんありすぎる本になっている。例えば、登場人物の仕事観や美学について焦点が当たったかと思えば、次の瞬間にはAIの話、恋愛の話、幸福の話、、、とテーマが移ろうスピードが非常に速くて読んでいると振り落とされそうになる。あれ?今何の話題だったっけ?となること幾たびか。144ページの中編小説にしては話題が多すぎる。
ただこの本がすごいのは、たくさんのテーマがひしめき合う中でそれでも一定のまとまりがあるというか、何か一貫した より高次元なテーマ(ちゃんと言語化できないけど、現代社会でしばしば取り上げられるトップトピックたち、とでも言っておこうか)で括られたものであるという感じられるところ。普通これだけ詰め込めば内容が破茶滅茶になってもおかしくないのに、なぜか整然としてる。それが小気味いい。
そんなたくさんある本書のテーマのうち、僕は特に「平等性」というテーマに着目した。その話をするにはこの本の内容を少しバラさなきゃいけない。
この本のタイトルにもなっている通り、この小説は2020年に(コロナなど発生せず)オリンピックが執り行われたパラレルワールドの東京を舞台に「東京都同情塔=シンパシータワートーキョー」という全く新しい刑務所を取り巻く物語になっている。
普通の刑務所と比べて何が新しいかって、この東京都同情塔は「犯罪者のために」作られる建築という点が全く新しい。「そりゃあ犯罪者を収容する建築なのだから犯罪者のための建築なのは当然じゃないか」と思った方、甘い。
何が特殊って、この東京都同情塔は犯罪者に対して刑罰を与えるのを目的としておらず、むしろ幸福を享受させるために作られているということ。本来の役割である罰というより、むしろアメを提供する施設なんです。具体的にいうと、この刑務所はいわゆるみんなが想像するあの要塞のような・独房が設置されているような無機質な外観・内観の刑務所なんかではなく、(冗長なので作中表現をあえて引用しないが)めちゃくちゃ綺麗で誰もが住みたくなるようなジムとか図書館とか娯楽設備まで完備しているいわば高級タワマンのようなつくりになっている。
なぜ犯罪者のためにそんな建築物を作ったのか?なぜ罪を犯した悪者に対して公費である多額の税金を投入して建設するのか?
その背景として、皮肉的に「行きすぎた平等性」「行きすぎた忖度」が描かれている。作中で登場する幸福学者マサキ・セトの論理では、犯罪者は同情(=シンパシー)されるべき存在であると論じられる。なぜなら犯罪者は加害者である前に被害者ともいえ、たいていの犯罪者は生まれた環境などによって、犯罪を犯さざるを得なかった人が多いからである。むしろ犯罪を犯さずに生きてこられた人は、幸福な特権を持っていて、それと同様に犯罪者も幸福を平等に享受できるべきである。
そんな論理でこの世界線の日本では犯罪者が富裕層顔負けな贅沢な暮らしを享受するのだけど、その様が提示するのは現代社会の平等性の追求が行きすぎた世界への皮肉であり、このまま言葉や思想の自己検閲が過剰に進んでいったらその先にどのような世界が待っているかというある種の思考実験である。
平等、とは辞書で引くとこのように出てくる。
差別がなくみな一様に等しいこと。
つまり差別がないこと。そして現代社会では基本的に平等はいいことと認識され、それが日々追求されている。特に一定の世代以下はこの意識がとりわけ強いように思う。僕自身も平等性が損なわれている状態、例えば裕福な家の子供と貧困家庭の子供の教育機会の不平等など、は解消できるが理想だと思うし平等は基本的にいいことと信じていた。また、人は生まれながらにして幸福になる権利があるとも信じていた。
この小説を読むと「犯罪者は、犯罪を犯すしかない境遇に生まれた同情されるべき存在」であり、「非犯罪者は、犯罪を犯す必要のない恵まれた環境に生まれた存在」なので両者が平等であるために犯罪者を優遇しましょうという論理になっている、そしてそれは一理あるように思えてくる。ただ自分の一般感覚からしたら犯罪者は何かしら刑罰を受けるべきとも思えて、そういった感覚のゆらぎを感じられることがこの本の面白いところだ。
当然、この本で語られている幸福論とその思想は「犯罪を犯した方が裕福な生活ができる」という社会システムを崩壊させかねないものなので現実にはこのようなことは起こらない。起こらないけど、こういった思考実験により「自分にとって何が平等か」「平等はどこまで追求されるべきか」「それはなぜか?」を問うてくれる、とても面白い機会だったように思う。
僕はたまたま「平等性」に注目がいったが、読む人それぞれに面白いテーマだと感じるものが千差万別だろうと思う。ぜひどんなテーマに引っ掛かって、どんなことを考えたのか聞かせてほしい。こんなにも、人によって感じ方が変わりそうな興味深い本に出会えたことに感謝。
ぜひ読んでみてください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
