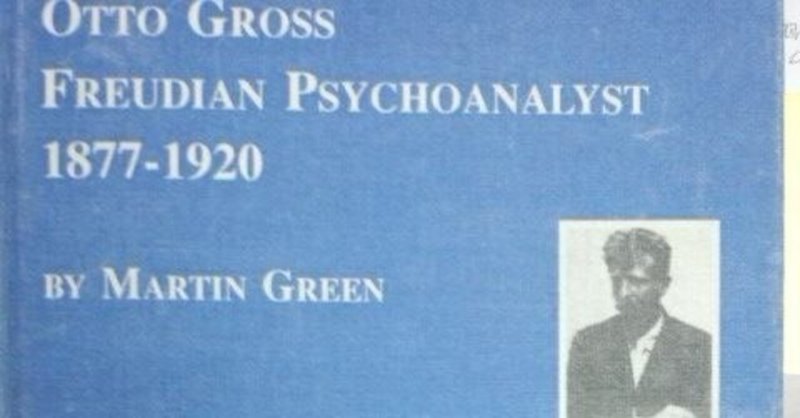
オットー・グロース フロイトによって追放されユングを変えた天才精神分析家
【オットー・グロースのこと(1)】
遅ればせながらクローネンバーグの「危険なメソッド」をDVDで観る。ザビーナ・シュピールラインをめぐるフロイトとユングの物語。世紀末から20世紀初頭のヴィーンの雰囲気がわかる。スイスのブルクヘルツリ精神病院にサビーナが強制的に入院させられる場面があるが、本物のブルクヘルツリであろうか。
フロイトとユングの初対面の場面が面白い。ユングの妻が裕福であることを知った生活に追われる開業医フロイトの反応や、フロイトがユダヤ人であることで精神分析が迫害されることを訴えるのに関心を示せないユングを「プロテスタントらしいな」と皮肉るフロイトなど、後年のふたりの決別とユングのナチズムへの接近まで予見させる演出が凝っている。
それよりも、僕が興味を持っているのは、この映画にも登場するオットー・グロースである。ユングとともにフロイトが自分の最高に優秀な弟子であると認めたグロスは、モルヒネ中毒によってユングの治療を受けることになるが、そこでグロースはユングを自分の性解放運動の思想に染めてしまい、あげく病院を脱走してしまう。グロースによって洗脳されたユングは、意を決してザビーナの誘惑に乗り、以後有名なヴォルフとの関係など、不倫関係をくり返すようになる。それまでフロイトのリビドー理論を拒否していたユングは、それ以後フロイトより深い意味でのエロスの世界へと耽溺(もちろんユング派によれば研究なのだが)していくのである。
このためにオットー・グロースの名は精神分析運動の中では消されていくことになる。(ジョーンズのフロイト伝の中には何カ所もグロースの名前があがっおり、ジョーンズ自身グロースから教育分析を受けていることを書き留めているが、そこに注目する人は少ない。)ユングの治療を逃げ出したことでフロイトはグロースを運動から追放し、映画ではユングに「これで疑いなく君が皇太子、私の息子で後継者だ」と宣言する。だが、グロースによって敬虔なプロテスタントとしての抑圧を解かれたユングは、神秘主義へと走り、フロイトとの決別を早めることになる。したがって、オットー・グロースは精神分析運動の中で決定的な分岐点をつくり出した男なのである。
ところが、この映画の解説の中で、精神分析学史の鈴木晶ですら、知ってのことかどうか知らぬが、グロースについてこう書いてすませている。「映画でヴァンサン・カッセルが演じているオットー・グロースは、精神分析学史にはほとんど登場しない、マイナーな精神病者=精神分析学者だが、「反精神医学」「性の解放」を唱え、ユング心理学に大きな影響を与えた人物である。実際に麻薬中毒で死んだ」と、実にいいかげんな書きようである。映画評論家の柳下毅一郎も、グロースの天才を認めながらも、トリックスター的存在に矮小化している。
実際にはオットー・グロースは、その死後も多くの文学作品のモデルとして登場しているばかりか、カフカに大きな影響を与え、またシュール・レアリズムやダダイズム、当時の前衛舞踏などの思想的基盤をつくったひとりでもある。だが、多くの実践的革命家がそうであるように、後世は書物を多く残したインテリを賞賛し、行動により世界に感染者を残しただけの実践者は忘れられるのである。
当時、急激に都市化が進み、格差社会が拡がり、またハプスブルク家によるオーストリア‐ハンガリー帝国が凋落し、ヨーロッパ各地の父権制が新文化の挑戦を受ける中、多くの芸術家、文化人が集ったスイスとオーストリアの国境の地、アスコーナに集まり一種の文化共同体をつくっていた。さしずめウッドストックのようなところである。そこでオットー・グロースはひとりのカリスマであった。ただし、グロースはカリスマとして君臨したのではなく、その純粋さを皆に愛された存在であり、カリスマと言うにはあまりに反権威的、平等主義であった。
グロースについて言われるとき、鈴木のように「性の解放者」として、例えばライヒが持ち出されたりし、その奔放で野獣的なイメージが宣伝されるのだが、実際のグロースはその正反対の人物であった。映画の中では、ユングはザビーナとSM関係にあったように描かれているが、その後のヴォルフとの関係や本来の意味でのカリスマ性、妻のエマとの偽善的関係を考えれば、映画の解釈のほうが正しく、グロースはむしろ徹頭徹尾女性の崇拝者、女性にすべてを与えようとした人物である。そのあたりも、ユング派とフロイト派というふたりのカリスマをいただく精神分析運動から、徹底的に排除されている理由のひとつがありそうである。組織としての偽善を、グロースの透明な青い瞳が告発するのである。
いくつかグロースの登場する書籍を集めたので、しばらくその紹介をしていこうと思う。

【オットー・グロースのこと(2)】
ザビーナ・シュピールラインの伝記。
「ザビーナ・シュピールラインの悲劇 ~フロイトとユング、スターリンとヒトラーのはざまで」ザビーネ・リッヒェベッヒャー著、岩波書店2009。
映画「危険なメソッド」にもあったように、ザビーナとオットー・グロースは直接には会っていない。しかし、ユングはザビーナにグロースとの会話を語っていたようである。また、この本によれば、オットー・グロースの治療を引き受ける直前のユングは、ザビーナとの治療関係において混乱していたようであり、またユング自身ザビーネへの恋愛感情に苦しんでいたという。そのユングにザビーナは「あなたはご自分の性的コンプレックスに密接に関わっていないことについてであれば全部お話になるのに、精神的に負担をお感じになることについては「講演をする」ようにしかお話になりません。それは、性的コンプレックスがあまりにも強くて、あなたがもはやそれを統制できないためです」という挑発的な手紙を書いている。
このような時にフロイトからグロースの治療を依頼された。ユングはグロースの「治療」、その実はグロースとの思想的対話に夢中になり、あらゆることを中断して日夜治療を行い二週間で治療を終了したとフロイトに報告した。その後すぐにグロースは病院を脱走し、ユングを失望させる。その治療失敗の失望からであろう、ユングはグロースの診断を強迫神経症から早発性痴呆に変えている。診断が攻撃的感情の処理に使われる一例ではなかろうか。
ユングはグロースの治療開始当初から、ザビーナに彼のことを話している。人間の性を規律から解放して自由にするという思想に刺激を受け、ユング自身が一夫多妻制の思想を受け入れ、ザビーナに自分と妻と三人の共同生活をすることを提案した。この時、ユングはエマはこれに同意していると、ザビーナに嘘をついている。
グロースのことはこれくらいにして、最期のザビーナ。1923年に故郷であるロシアのロストフ市に戻り、ロシア精神分析界で重要な役割を果たす。1942年7月にロストフ市はヒトラーのドイツ軍に占領される。そして、ロストフのユダヤ人、共産党員、ソ連兵そして精神病患者は、すぐさま「浄化」の対象とされる。
本書の著者の筆致は、この時のロストフ市の虐殺目撃者の話を淡々と並べていく。無数の残虐行為の目撃者の証言の中に、市のメインストリートを追い立てられていくたくさんのユダヤ人の中にザビーナとその二人の娘をみたという証言を得る。イスラエルのホロコースト記念館には、ザビーナの死について「1942年、ドン河畔のロストフで、他のすべてのユダヤ人とともに死去」とある。

【オットー・グロースのこと(3)】
アスコーナ文化についての年代記を出している、M.グリーンによる、オットー・グロースの伝記。
この本の表紙の写真が、アスコーナの風景である。
オープンダイアローグの翻訳も、あとはゲラ校正という本来何事もええかげんですます性癖の僕には一番むかない作業を残すのみなので、それをやっつけ仕事で終わらせたら、次はこれを翻訳したい、と思っているのであるが、なんせ精神分析学史が抹殺した人物の伝記である。読みたい人など少ないだろうし、そんな本を出してくれる出版社はなさそうである。
それに伝記を訳したとしても、グロースの著書や論文はすべてドイツ語である。ずっと昔、なんとかチオンピやM.ブロイラーをドイツ語で苦心して、しかも読み切れなかった経験から、ドイツ語にはトラウマがある。
やはり引退後の楽しみとっておこう。引退したら、杉田玄白が解体新書で「鼻」を訳すのに一日かかったみたいにしてグロースの著書を読みながら、翻訳するのである。引退も悪くはなさそうだ。

【オットー・グロースのこと(4)】
E.ジョーンズの「フロイトの生涯」は、私が精神科医になりたての頃、当時の私たちにはまぶしく光り輝いていた先輩のひとりである小澤勲が、フロイトを知りたければまずこれを読んでおくといいと勧めてくれた本である。当時の研修医にとっては大枚である1982年当時の4200円を払って、この本を買った。(1990年頃までは日本はまだインフレで物価が上がっていた。それ以降は物価が上がることなく、「金曜日の妻たち」で板東英二がいしだあゆみだったか篠ひろ子だったかと不倫をして飲む居酒屋のメニューの値段が今と同じである。)
このフロイトの伝記にもわずかだがオットー・グロースのことが出てくる。フロイトがグロースとユングを得て研究を進め得たとして「後に不幸にも精神分裂病となった天才、グラーツのオットー・グロースが論文を発表して・・・・フロイトのリビドー理論を、抑圧、象徴などの概念を含めて完全に認めた」と書かれている。「フロイトは自分の後に従う者のうちユングとオットー・グロスだけが真に独創的な精神をもっているという意見を表明した。」
さらにジョーンズは自分とグロースとの関係を告白して、「グロースは精神分析の実際において私の最初の教師となった人であり、私は彼の行う治療にいつも立ち会った」と言う。「教師」というのは、おそらく教育分析をした人という意味だろう。
ところが、大部の本の中にこの数行だけオットー・グロースについて書いたジョーンズは、それにつけられた注釈の中で、「第一次大戦中には彼はハンガリアの連隊に加わったが、戦争終結時に、自殺してその生を終えた」と書いている。これは明らかに事実誤認である。
オットー・グロスが死んだのは1920年であり、コカイン常用による衰弱に肺炎を併発して、パンコフの病院で死亡している。
ジョーンズほどさまざまな資料に当たることができ、多くの信憑性ある伝聞に接していた人物がこのような誤認を、しかも自らの畢竟の大作となる書物の中で犯しているのは、いったいどういう心理機制の働きであろうか。
それほどまでに、オットー・グロースという人物が精神分析運動の中で排除され、記憶が抑圧されついには消去されたことの証左ではないだろうか。
だが、実際のオットー・グロースは、このような扱いを受けるべき狂信的な人物像とはほど遠い、純情な子どものように人を惹きつける力をもった人物だったようだ。これについてはさらに紹介をしていこうと思う。

【オットー・グロースのこと(5)】
「もてない男」(1999)の小谷野敦が、いろいろなところで頻繁にユング心理学をこきおろしてカルトであると言っているのだが、そのネタ本が歴史学者リチャード・ノル「ユング・カルト ~カリスマ的運動の起源」(原著1994)と「ユングという名の<神> 秘められた生と教義」(原著1997)である。ユング派の人たちからは忌み嫌われて当然、蛇蝎のごとくに扱われて当然の書であろうが、ちょうどユングとザビーナ・シュピールラインの仲について「秘密のシンメトリー」や最近の映画「危険なメソッド」の原作本で二人の仲がプラトニックラブではなかったことが暴露された頃に出されており、なおさらユング派からは無視を被っている。しかし、後者はユング派の精神科医である老松克博が訳しており、ノルの著作の学問的価値を認めている。いさぎよい。
実際、タイトルが刺激的であるにもかかわらず、「ユング・カルト」はヴェーバーのカリスマ論を基礎にした、宗教社会学の書として読み応えがある。
ユングの客観的な伝記としては定評のある、エレンベルガーの「無意識の発見」ではユングに関する記述の中では一回もオットー・グロースのことは出てこず、その大著の中にたった一行名前だけがみられるほどノルの両著作以前にはユングとオットー・グロースの関係は無視されてきたのである。
だが精神分析以外の領域では、アスコナ対抗文化の関連でM.グリーンによりオットー・グロースの名は復活していたのもあって、ノルのこの二冊の本では、その人生でユングが最も大きな影響を被った相手としてグロースのことが大きく取りあげられている。
特に1997年の著作では、すでに公表されているユング自身によるオットー・グロースのカルテを詳細に検討し、ユングが後にフロイトに「グロースは実際、傑出した精神を持つとてもすばらしい男です。グロースの中には私自身のさまざまな本性が見えたからです・・・よく彼と双子であるかのように思ったものです」とグロースへの強い転移感情を書き送っているにもかかわらず、その治療中はフロイトに嘘の報告をし続けていたことを指摘している。
「グロースの誘惑にいったん屈するや、ユングのなかでは人生における性と宗教の位置づけに深い変化が生じた。キリスト教の抑圧的な教義は、肉体と性行為を貶めていたから、今や彼にとっては不倶戴天の敵に思われた。性を霊性のなかに取り戻さねばならなかった」ことから、これ以後、ユングは降霊術やオカルトに傾倒し、「抑制のない性という秘蹟を通して人類を再活性化し」ようとそれを他人に(患者にも!)勧めるようになった。
また、ザビーナとの関係はまさにユングがグロースの分析を行った時に始まっており、「ユングの「複婚的要素」(注:後のトニー・ヴォルフとの関係を示唆している)はその人格の中で結局勝利をおさめた。彼はザビーナ・シュピールラインとともにこの衝動に身を任せようと決めてから、生涯複婚を実践することになった」と述べている。(この「複婚」が小谷野敦にはどうにも我慢がならなかったのであろう・・・)
因みに、ユングの「外向」「内向」という有名な概念は、実はオットー・グロースのものであり、ユング自身それを著作の中で認めているという。だが、そうであってすら、教科書の中でも「内向」「外向」はユングの発明であると何の疑問もなく扱われている。カリスマによる集団形成とその排他性、ある力をもった集団が外部に対して事実を隠蔽しねじ曲げていく力というのは、怖ろしいものだ。

【オットー・グロースのこと(6)】
オープンダイアローグの翻訳を通して気づいたこと。オープンダイアローグのキモはそのシステムでも精神療法的側面でもなく、ダイアローグとソーシャル・ネットワークを組み合わせた「共同体づくり」にあると思う。どちらの要素も、近代になって個人が社会に裸で放り出されアトム化するのを食い止めるために、あるいは克服するために、フィンランド社会によって必要なものと認められたものだ。さまざまなレベルのネットワーク同士をダイアローグによってつなぐことで、そのつどそこに共同体ができあがり、それが被膜となってクライシスにある人に安全保障感ができあがる。
西欧の近代に至るこの300年、さまざまなところで共同体づくりが試みられ、その多くが挫折してきた。オットー・グロースが活躍したスイスとイタリアの国境にある美しい村、アスコーナもそのひとつである。19世紀末のプロイセンに代表される急速な工業化、中央集権化のなかですべてのことが合理化され実証化されていく〝鉄の檻〟(ヴェーバー)から逃れて、多くの芸術家、思想家、女性がこの地に集まり、カフカやヘッセの文学の源流となった。
M.グリーンの「真理の山 アスコーナ対抗文化年代記」(平凡社)は1900年から1920年にかけてこの村を訪れ、住まい、通り過ぎていった人々と、そこから現代の例えば緑の党に至るまでの、ここで生まれた思想や文化、芸術についての、とても美しい書物である。
こ の本の中で、代表的なアスコーナ人として詳しくその生涯がとりあげられているのが、オットー・グロース、グスト・グレーザー、ルドルフ・ラーバンである。このうち、ルドルフ・ラーバンはヨーロッパ・モダンダンスの祖として日本でも知られている。舞踏のことはあまり知らないが、昨年末話題になったモーリス・ベジャールの「ボレロ」などは、ラーバンがアスコーナではじめた革新的なダンスがなければ生まれなかったものだろう。
冒頭に取りあげられているオットー・グロースの伝記は、日本語で読めるもっとも詳しいものであろう。プロイセンの官吏を地で行く権威主義の権化のようなグロースの父、ハンス・グロースは、その犯罪学の著書が現在でも読まれており、警部メグレの座右の書ともなっていて有名であり、彼は自分に反抗し、父権主義の糾弾者となり、母権主義の伝道者となった息子グロースを、自らの力で犯罪者として逮捕させ、精神病院に入れたりする。
この伝記によると、オットー・グロースは当時世界的に有名となりつつあったクレペリンの病院に勤めたことがあるようだ。しかし、厳格な禁欲主義者であるクレペリンと自分の父親が重なり、反抗の対象となったようで、クレペリンが精神分析を排斥していることを患者の治療に対する裏切りとして告発している。
1908年にグロースはフロイトの勧めでブルクヘルツリ精神病院に入院しユングの治療を受けることになる。以後、ユングを自分の母権主義的なフリーセックス論に洗脳しフロイトとの決別の原因をつくった男、精神分析をそのために用いている邪道な人物としてグロースは精神分析の世界から抹殺された存在となる。
しかし、その後のグロースはアスコーナで崇拝を集め、グロースの愛人となり女性解放の運動のさきがけとなったフォン・リヒトホッフェン姉妹は、当時の芸術家、知識人のミューズとなる。そのなかに、ロレンスやマックス・ヴェーバーがいる。ヴェーバーは、グロースの思想をニーチェと同じく「貴族政治」の原理と考え、その思想を知性の敵としたが、グロースの人間そのものには高貴な魅力が具わっていると言う。また、カフカは、グロースと自分は同族であると感じたと述べている。
グロースは、近代化の波に襲われ都会で傷ついてアスコーナにやってくる多くの男女にとって、教祖的な治療者となった。アーネスト・ジョーンズが言うように「私がいままでに会った人の中でロマン主義的な天才の概念にもっとも近い人物」であり「他人の心の中を見抜くこれほどの透視力をもった人間を二度とみることはなかった」ような人物であったらしい。ある人は彼について「どんなに蝕まれてしまった肉体の内にも、グロースは球であり、天体であり、形而上学である一人の人間を認める。そして彼は患者ひとりひとりの哲学者となる。グロース博士の治療行為はすべて、どんな人間の内部にも世界に対し果敢に対峙する場所があるという考えに基づいている」と書く。
M.グリーンは、このような彼の資質とその人生ゆえに、グロースは現代の反精神医学の源流になっているという。
グリーンのこの本はグロースの物語ではなく、アスコーナに共同体を夢見て集った多くの無名の男女の物語でもある。そして、「思想史においてさえ変人や愚か者もまた重要であろうということ、どんな試験もやすやすとこなす、非の打ち所のない頭脳をもった人々が必ずしもつねに最も重要な思想の担い手になるとは限らないということ、また思想家といえども人間であり、全身で考えねばならないのだということ・・・」こうしたことをアスコーナの物語が教えてくれるのだという。
西欧の近代史のなかでさまざまな思想や文化の十字路となり、しかしそれがそれとして書かれることがなく、また当時の父権的な権力への反抗であったがために、今はすっかり忘れられてしまったひとつの対抗文化、失われた共同体に対する、哀惜の情に満ちた書である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
