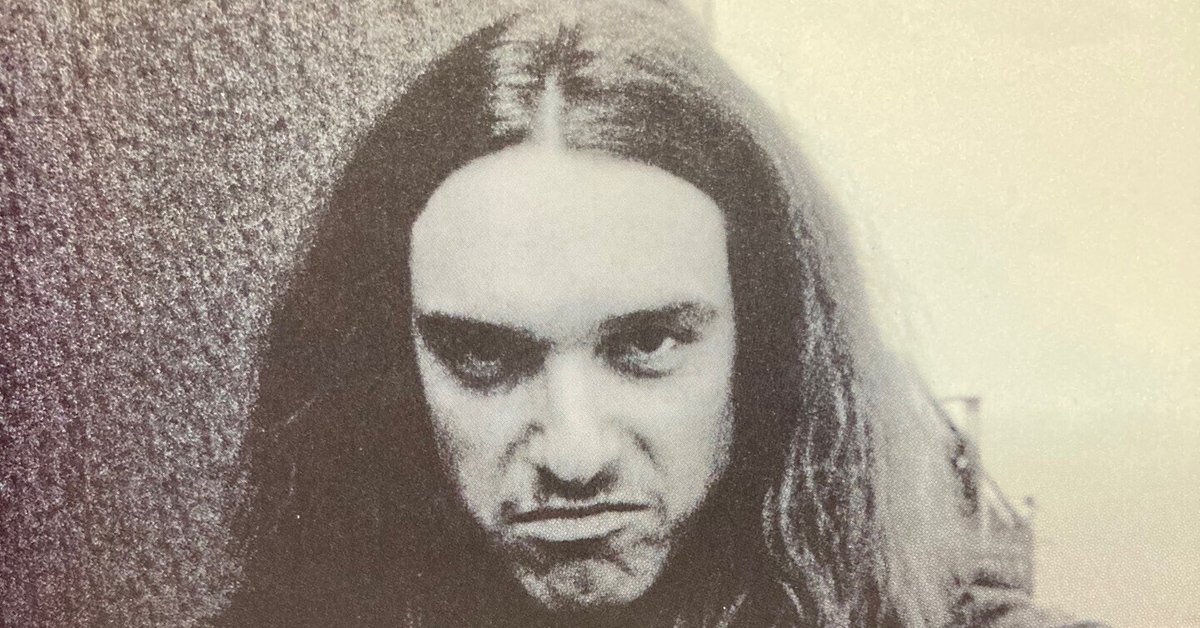
CLIFF BURTONの伝記本「TO LIVE IS TO DIE」について。
毎日、くだらない感情と闘っている。
俺の体内に、脳内に、敵は、いる。
ソイツは、斬っても斬っても増える化け物みたいに増殖しやがる。
とりあえずグダグダ言ってねぇで、行動しろ。
行動こそが最大の処方箋だ。
とまぁ、自分語りはこの辺にして、今回の記事の主題に移る。
皆さん、CLIFF BURTONはご存じだろうか。
(知らねぇよ)
と、思われても勝手に書いていくけど(笑)、ヘヴィメタル界の大立者、METALLICAの2代目ベーシストである。
具体的には1stの「KILL'EM ALL」から3rdの「MASTER OF PUPPETS」までMETALLICAの低音を支えたベーシストだ。
俺がCLIFFのことを初めて観たのは「LIVE SHIT!」というMETALLICAのサンディエゴだか、サンフランシスコのライヴビデオの特典映像だったと思う。
JAMESの紹介で「FOR WHOM THE BELL TOLLS」のイントロを弾くCLIFFに、
(ス、スゲェッ…!)
と、ノックアウトされた。
この時の衝撃は今も覚えている。
技術が更新されていく現代の音楽界の中では、もしかしたら、CLIFFより凄いベーシストはいるかもしれない。
しかし、そのことは意味がない。
JIMI HENDRIXより技術的に上手い奴はいるかもしれないが、誰も彼を超えることはできないように、CLIFFは孤高の存在だ。
そんな彼の24年の短くも凝縮された人生を一冊の本にまとめたのがこちら。

「TO LIVE IS TO DIE」
「生きることは死ぬこと」
という意味である。
このタイトルは、CLIFFの遺作となった曲からの拝借らしい。
俺は(伝記とか自伝はキライだ。ミュージシャンは音で語ればいいんだ)とか思うくせに、元々活字が好きなので、ついつい読んでしまうという矛盾した性格をしている。
洋書を翻訳した本は、大抵読みづらかったりするが、この本はうまく翻訳していると思う。
誤字脱字も無かった。
この本を読むことによって、CLIFFの知られざる一面を垣間見れる。
関係者がこぞって彼を評する言葉に共通したものがある。
それは「CLIFFはイイやつだった」というものだ。
口数は少ないが、礼節があり、知的な人物として、CLIFFは語られることが多い。
・・・というか、本書でCLIFFに会った人たちは、全員口を揃えて「イイやつだった」と異口同音に言っている。
実はこれは個人的に意外だった。
CLIFFのあの演奏スタイルを観ると、てっきり「エゴイスト」で「ワガママ」な人物なのかと、誠に失礼ながら勝手に思っていたのだ。
実像の彼は、そんなことはなく、至って普通の好青年だったようだ。
しかし、演奏するときは、あの鬼気迫るプレイを聴かせてくれる。
CLIFFを知っている人は、そのギャップに驚いたのではないだろうか。
そのくらいCLIFFは、他のベーシストと違っていた。
ベースはその名の通り、楽曲のベース(基音)を支えるもの。
しかし、CLIFFのベースはトレブリーで、高音をブーストさせ、歪ませている。
速い曲だと、指ではおっつかないから、ピックを使うことも一つの選択肢としてあるだろうが、CLIFFは徹底指弾きスタイルだ。
そして、ヘッドバンギングによる激しいステージパフォーマンスと、ジージャンにベルボトムという出立ち…。
どこをとっても、人と違っていて、正直METALLICAの中でも、ファッションの方向性も含め、浮いているように見える時もあった。
本来METALLICAはJAMESとLARSのバンドなのに、1stの「KILL'EM ALL」には「PULLING TEETH」という、ベース主体のインストゥルメンタルが収録されている辺りも、彼の立ち位置を示しているように思える。
メンバーからも尊敬の眼差しで見られていたのだろう。
KIRK HAMMETも「俺もCLIFFのように、尊敬されたかった」といった主旨の発言をしていた。
そんな彼が、作曲やアレンジに携わるようになって、METALLICAはよりプログレッシヴな方向に走るようになった、と個人的には思っている。
曲はより内省的に、複雑で長尺、それでいてスラッシュ・メタルらしいアグレッシヴさを兼ね備えたものになった。
アンダーグラウンドだったスラッシュメタルをメインストリームに押し上げた功労者として、CLIFFは貢献したと思う。
もちろん、JAMES、LARS、KIRKの三人との共同作業においてのものだが、ユニークという言葉が服を着て歩いているようなCLIFFの存在感は、間違いなく異彩を放っていた。
本書は、そんなCLIFFをすこし過剰なまでに褒めたたえている気がしないでもないが、彼の奏法やアレンジを詳細に書いている。
彼のアイディアがバンドの楽曲にどれだけ貢献したか・・・。
本書はCLIFFを徹底して賛辞する。
そんなCLIFFやバンドの想いの極北が、3rdの「MASTER OF PUPPETS」だろう。
単に勢いで突っ走るだけではない、一筋縄ではいかない楽曲構成が、METALLICAを凡百のロック・バンドから際立たせることになった。
チャートアクションも好評で、かつてないほどレコードも売れた。
多くのバンドがそうであるように、新譜をリリースしたら、それに伴うツアーを行う。
バンドはヨーロッパ、アメリカ、そして、CBSソニーと契約を交わした関係で、ここ日本にも来る予定が組まれていた。
以下は、ライヴ前の1986年9月26日の発言。
「MASTER OF PUPPETS」は、クリフ曰く「日本では、前2作より売れている」とのことだった。
「いますぐではないけど、いつか家を買うのが夢だ」
ともCLIFFは生前語っていたようだ。
だが、お金に関しては、あくまで堅実な姿勢を崩さなかった。
「全員に行きわたる金は少し増えたが、アルバムのセールスが入るにはもう少し先だ。これまでは何とかやってきた。ツアーもやり易くなったよ、前よりいいバスに乗れるとかさ。それまでの金は全部バンドの機材を買うために使ったんだ。俺たちにとって、新しい機材を買い、スタジオを借りる時間が増えるのは、もっと可能性が広がることなんだ。俺たちが持っているものをさらに発達させる手段に過ぎない」
徹底した「バンド第一主義」。
CLIFFが、いかにこのバンドに賭けているかの証明のような熱い言葉だ。
そのあと聴いている音楽に言及した。
「演奏している音楽と違い、聴いている音楽はそこまで激しくないんだ。ピーター・ゲイブリエルやロキシー・ミュージック、シン・リジィ、ブルー・オイスター・カルト、ラッシュ、ミスフィッツみたいなパンクも聴く」と言い、サウンド・チェックに呼ばれたCLIFFは、そこでインタビューを切り上げた。
これが、生前最後のインタビューとなった。
METALLICAは、その日、スウエーデンのストックホルムで熱演を繰り広げた。
終演後、バンドは次の開催地であるコペンハーゲンに向かうため、ツアー・バスに乗り込んだ。
CLIFFはギタリストのKIRKと「どちらが寝心地のいいベッドで寝るか」で、トランプでカードを切ったらしい。
CLIFFはバス右手側の寝台、窓の横になった。
バスは、発車した。
1986年9月27日土曜日、午前6時45分に、CLIFFは亡くなった。
ツアーバスが、凍結した路面を乗り上げて、スリップし、バスは横倒しになった。
寝ていたCLIFFは、窓の外に放り出され、バスの下敷きになった。
即死、だった。
この交通事故には不明な点が数多くあり、未だに真相は不明な点が多い。
今みたいにドライヴ・レコーダーが完備されているわけでも、道路に監視カメラが設置されているような時代でもない。
「実際は、路面が凍結なんてしていなかった」とか「バスは改造されていた」はたまた「バスの運転手は、ドラッグを常用していた」云々・・・さまざまな意見が本書で書かれているが、間違いないことはCLIFF BUTTONは、この日亡くなった、ということだ。
悲嘆に暮れたバンドは、停滞する道を選ばなかった。
すぐさま代わりのベーシストJASON NEWSTEDを加入させ、なんと来日公演も実現させたのだ。
(METALLICAには喪に服す、という概念はないのか・・・)と、思わなくもないが、ここで止まらないことが亡きCLIFFの想いである、とバンドは判断したのだ。
そして、それは見事に結実し、METALLICAは更なる躍進を遂げることになる。
それ以降の歴史は、言うを待たない。
激動の坩堝の中でも、CLIFFは有頂天になって、自らを見失なうようなことはなかった。
ある時恋人が
「ロックスターになるってどういう気分?」
と、電話で聞いたことがあったという。
その時、CLIFFは
「二度とその呼び方をするな」
と、珍しく怒ったという。
偶像視を嫌う彼の、実直な人柄を偲ばせるエピソードだと思う。
最後に本書に掲載されていたLARSの言葉を載せて終わりにしたい。
「未来を考えたことなんてなかったと思う。その時のことで精一杯だった。俺が生まれたデンマークでは、アメリカ人がよく考える目標って、大きな意味を持たないんだ。
アメリカでは早い時期から目標を持てって教えられる。
絶対に賛成できないね。
俺たちは、自分たちの小さい世界の中でいつも満足していて、目隠しをしたまま進んでいたんだ」
経営者のセミナーとかでよく言われるような
「大きな目標、夢を持て」
という言葉は、LARS、ないしMETALLICAには通用しなそうだ。
そんなことよりも、自分たちがバンドを楽しめるように、一日一日を精いっぱい生きたことで、今の彼らがいる。
この瞬間を「楽しむ」。
それこそが、METALLICAをMETALLICAたらしめている要素なのかもしれない。

了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
