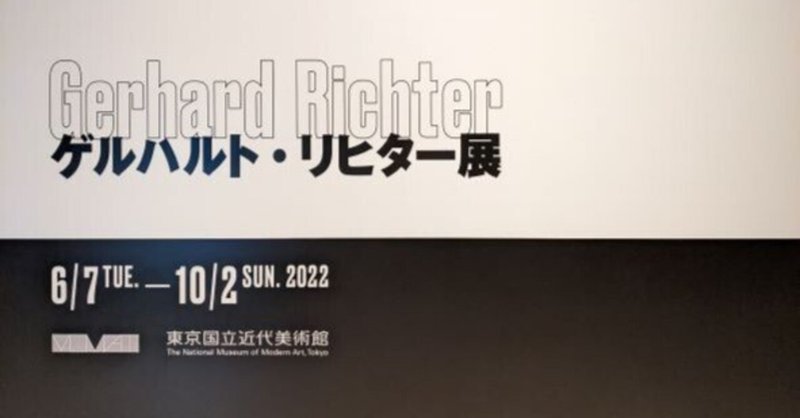
ゲルハルト・リヒター展/Gerhard Richter(東京国立近代美術館)
どれだけぶりだろう、国立近代美術館。美術館レポートもそろそろ復活させていかないと。(だいぶ記事投稿遅くなっちゃった…。とっくに会期おわってるわい)
現代現役抽象画家の中で最も重要視されるというゲルハルト・リヒター。これまでの美術館巡りでもぼちぼち出会っていた。春に行ったポーラ美術館企画展の目玉展示の一つでもあったな。リニューアルなった国立西洋美術館でも見かけ、あの雲の絵(写真?)にはやや感銘を受けかけた。気になる存在にはなってきた。
うーん、しかしそこまですごいひとなのかなあ? これまで目にした作風を考えるとやはり私(抽象画キライ)の天敵になりそうなニオイがプンプンしているのだが。
リヒターをまとめて見るのは初めて。どうもこの人いくつかシリーズ作品(持ちネタ?)があるみたいだ。しかしどれもこれも…。思いもよらず全作品撮影可能であったので画像付きで解説できるのは助かる。
まず、最初に目に入ったのがでっかい色ガラスみたいな作品。春先にポーラで見たインドの前衛作家さん(アニッシュ・カプーアさん)の作品に通じるかな。パクり?(どっちが?)

標題「鏡」って、これなんかまったくただのフツーの鏡じゃねーかよ。これでいいのかほんとに?
そしてマーク・ロスコばりの左官屋さんシリーズ。左官の腕はロスコの方が上だな。パクり?(どっちが?)


日本にはいい道具があるぞ、リヒターさん
カラーチャート。これなんかもう絵じゃねーじゃん…。タイル職人かよ。

これとどう違うんだ
まあ百歩譲って、これは昔からあるいわゆるモザイクだね。伝統的なモザイク技法というより現代人には電子処理のエロビデオでお馴染みのピクセルを大ざっぱにしたモザイクだ。
なんとこれ展示ごとに毎回パネルタイルの組み合わせは変わるそうで、なるほど近付いてよく見たら確かにタイルが剥がれる感じだった。

でもずっとぼ〜っと見てたら、後に触れるペンキの引っかき傷(アブストラクトペインティング)よりかは面白いような気がしてきた。なにやらリズムを感じてきて、琳派のかきつばたなんかにも通じるところがあるのかな。パクり?(どっちが?)

リヒターで一番有名なのはフォトペインティングだろう。少なくとも何が描かれているか分かるからね。写真をキャンバスに投影させてそれをなぞって写真っぽくした絵ということだ。一周回ってまた写真に戻るが写真じゃない? なんてややこしいことしてんだよ。
なるほど、拡大すると筆の跡がわかる。さっきの左官屋さんの技術を生かしている(のか?)

写真技術が出てきた時、多くの画家に「絵とは?写真とは?なんなのか? 写真技術が出てきた後、人の手で描かれる絵画の存在意義とは?」と悩ませた問題をまた蒸し返しているのか?
多くの画家の答えは、写真のようにただ忠実に現実を写すのではなく、現実を歪めてまでも表現すべき描き手のてゃますぃー(魂ね)を絵の中に込めることだった(と思う)。
フォトペインティングの作品群でリヒターは更に問題提起をしている。ロラン・バルトの問い「写真を見る時、人は何をみているのか」と同じ問いかけである。パクり?(どっちが?)
最初の一ページしか読んでいない(定期)
レンズで収集した光を色のドットにした集合体でしかない写真に人はなぜ心を動かされるのか? 写真を見る時、人は写真そのものでなくその背景にある思い出を見ているからだ。では伝統的な人の手による絵画ではそのようなことは起きないのか? では写真みたいな絵を描いたらどうなるのか?
彼は写真のように(だって写真の丸写しだもん)ただあるがままの建物や人物を描き、実はこの家には犯罪者がいるんだとか、この女性たちは連続殺人犯の被害者なんだというその背景を鑑賞者が知ることでまったくそのイメージが変わってくる精神的なだまし絵のような仕掛けを込めている。背景を知らないと鑑賞できない芸術というのはなんか反則ではないかと思うのだが、それもこのひとの仕掛けた罠のようだ。
これはシリアルキラーの被害者として新聞に載った顔写真を絵にしたそうな(でこれはその絵をまた写真にしたと←ああややこし)。

あるいはまた犯罪者が隠れているという建物を描いたり。
(これ写真撮り忘れちゃったみたい…)
その背景情報を出した後に「うっそぴょーん! 誰も死んでないんだよ〜ん」とか言われたらまたその絵の印象も変わるわけだ。どうせならそこまでやって欲しいわ。やっぱりなんか人をおちょくっているところがあるんじゃないか? バンクシーみたいだ。パクり?(どっちが?)
そしていまやほぼ彼の代名詞になっているのではと思われるアブストラクトペインティング。キャンバスにペンキをぶちまけて巨大なワイパーみたいなヘラでそれを引っ掻い剥げた削りかす模様みたいな絵。ダメだコリャ。これこそ私の天敵になりそうな資格確定である。

春にポーラ美術館で見たやつはまだ湖畔や柳の木が垣間見えたが、ここにあるものにまったく具象性はない。リヒターが操るワイパーがペンキをどう削り取るかは予測不可能な部分もあるという。画家の技術とか画力に寄らないハプニング芸術なのかな。
リヒターが最初に衝撃を受けたのがポロックだというからさもありなん。山ほどあるこのシリーズ、描いた本人もそれぞれの作品の区別が付くのかな? 私にはさっぱりわからん。わかんなくてもいいやって雰囲気もあるのだが。
ハプニングに任せたり、展示ごとに色パターンの組み合わせを変えるドットモザイク絵のように一定の型を保持しなくてもいいのなら、アブストラクトペインティングも別に作品ごとに区別がつかなくてもいいとリヒター氏は思っているのかもしれない。
わけわからないながらつらつら見ていて気付いたのが、これって、リヒターさん自身はまったく想定外だったろうが、いま私がこの画風を見るとちょうど「AIが自由に描いた絵」に見える。
*ここ最近は人間が描いたものと見分けもつかない絵もAIに描けるようになったが、ここで言っているのはそれ以前のAIにお任せにした絵です
AIなんてものが生まれる前、絵を描かせてみようなんて誰も思わなかったであろう時代にそれをすでに先取りして描いたのか? んなわきゃないんだが、後に彼の芸術に対する思想やアプローチを知ると、そうでもないような気がしてくる。いつもの私のトンデモ理論なので共感する人は少ないだろうけど。
自然に意思なんてない、ただ細胞に組み込まれた一定の規則に従って成長する樹木草花に、あるいは単なる物質の積み重ねで長時間圧縮された鉱石に、更には光の反射でしかない空や海の碧さに、人は勝手に美や恐れを感じる。いわんやAIアウトプットをや。プログラマーが打ち込んだ計算式に沿ってフラクタルに線を伸ばしたり色を配置しているに過ぎないのだから。
日曜美術館ゲルハルトリヒター特集「ビルケナウ」
リヒターによれば彼のアブストラクトペインティングの到達点が今回の目玉「ビルケナウ」らしい。この作品を仕上げられたことでリヒターは「もう抽象絵画は描かない」と宣言をしたそうだ。
「ビルケナウ」は巨大な4枚のアブストラクトペインティングとそれを写真に撮った同寸パネルを部屋の前後に向かい合わせてる。はあ? そんなことになんの意味が…???

部屋の奥には壁一面に巨大な鏡もあった。私はこれ最初窓だと思っていた。

会場ではそばに小さな4枚の写真も飾られていた。(写真撮影禁止)
記念碑的作品とのことだが、これらを目の当たりにして私はただ戸惑うだけだった。会場で配布されているパンフに「ビルケナウ」制作秘話的な解説があったようなのだが、会場ではそれを見ていなかったためさっぱりわからなかった。わけがわからなさすぎてそのままスルーしてしまったよ。
ところが9月4日放送の「NHK日曜美術館」でちょうどこのリヒター展を特集し、それを見てようやく仔細がわかった。毎週「日曜美術館」を見ているわけでもないのに、たまたま目に入ったのだ。どうやら運命的な繋がりがリヒター氏と私とであるのかなありませんかそうですか。(本当は前の日の私の行動履歴を見てGoogle先生がお勧めしてきたのだろう。これもテクノロジーとアートの幸福な出逢いだな)
「ビルケナウ」はナチスによるユダヤ人虐殺の収容所があった場所。数多くの残虐なホロコーストが行われた。会場にあった4枚の写真は隠し撮りされた囚人への虐待の様子。それをリヒターは当初いつものフォトペインティングの技法で大きくパネルに描き出した。ところがその絵は途中で上からアブストラクトペインティングで上塗りされ隠されてしまう。ピカソのように下描きが見えるようにはせず、どれだけ目を凝らしても最初のフォトペインティングを見つけることはできない。
心の目で見てくれということか? 実は犯罪者が潜伏していたという建物、シリアルキラーの犠牲者であった女性たちの微笑み…その背景を知ればまったく違った影響を与える絵を描いたリヒターにすればこれもその流れなのか。しかし説明書きがないと鑑賞できない絵画はやはり反則だと思うんだよな。
数多くのパクり画風の数々…(?)。いやこうして見ていくと確かに絵画芸術の系譜に乗って、今後考えていかなくてはいけない重要なテーマへの挑戦が見える。なるほど。現在最も重要な画家の一人という評価の理由の一端がわかった気がする。
このリヒター展は名古屋に巡回した。けっきょく追いかけていってしまった(天敵じゃなく大ファンじゃん)。この記事に載せたものは東京と名古屋で撮ったものをちょっと混ぜてある。感想はまた別途記事にするかもしれない。
最初、名古屋は東京と同じように撮影可能なのか危ぶんだ。場所が変わると東京でオッケーだったのに撮影禁止になることもちょくちょくあるし。結果は東京と同じくOKであった。なんでも、ご自分でリヒター財団を作って、作品管理しているので好きにできるようだ。
ただビルケナウの元になった写真はやっぱり撮影禁止なんだよね。これは美術館側の事情ではなかろう。しかしあの写真、誰に著作権があるっていうのか? ただ少なくともリヒター氏の作品ではないし、こんな悲惨な記録をカチャカチャスマホで気軽に撮るんじゃねーよっていうご遺族方への忖度かな。
ビルケナウの背景を知ってから見たらまた違った感想が持てるかなと思ったがそんな変わらんな。ただの絵の具をぶちかましただけの汚れた板を絵と呼んでいいものかという思いをまた強くしただけだ。
だがじっと見てるとその絵の具のシミのあらゆる箇所でいろんな想念がわきあがってくる。そもそも絵とはそうしたものだけど。はたしてこれを絵画の最終段階としていいものだろうか。やはりモヤモヤは残る。私は古い人間なんだろうか?(リヒターさんの方が年上だっつーに)

私にとってリヒターといえばこっちなんだが、ドイツではかなりよくある名前なのかな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
