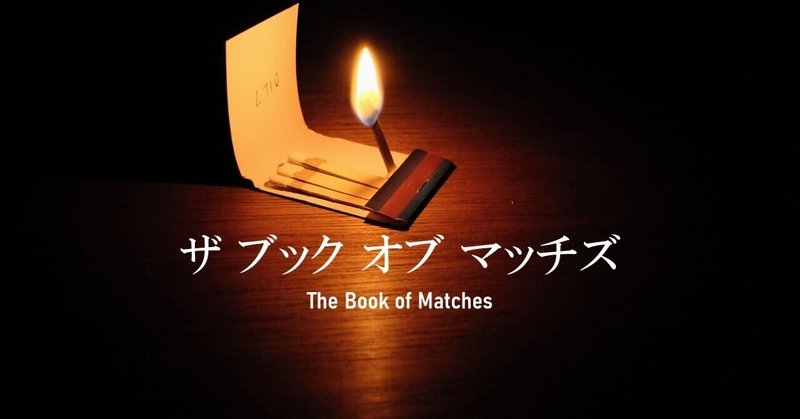
ザ ブック オブ マッチズ 8/16
鉄柵を開いて牛たちを受け入れる準備をした。
ラウンドアップで集めるのは一八〇頭の仔牛だけではない。母牛もいっしょに来てしまうので三六〇頭の大群だ。仔牛だけをきれいに分けて歩かせられるわけではないから、そうなってしまう。
全員を鉄柵の中に入れてから、カウボーイたちが馬をつかって母牛だけを追い出す。馬と牛のバトルロイヤルのような錯綜した状態が生まれる。舞い上がる土埃と、指示を出し合うカウボーイたちの叫び声と、牛たちの咆哮が交錯する。
事態が収拾したあとも、追い出された母牛たちはその場を離れることなく、柵の外から我が子を呼んでべーべーと啼き喚きつづける。子も同様だ。
ここからは、働き手たちは馬に乗る五名と、残りの地上班に分かれて作業を行なう。
鉄柵の一方を開き出口にする。馬に乗った者はロープを回して仔牛の後脚を捕まえる。ロープをサドルの前方に突き出たホーンという部分に巻きつけ、馬の牽引力でもって仔牛を出口のほうへ向かって引きずる。
出口の前では、金属製のヘッドキャッチャーという輪っかを手に構えた地上クルーが待つ。ヘッドキャッチャーはヒモとペグで地面に打ちつけてあるから、素早く仔牛の首にかけると、脚はロープ、首はヘッドキャッチャーに固定され、身動きをとれなくなる。
そこで一気呵成に仕事をやっつける。
焼き印を捺す以外に、水鉄砲のような針のない注射器から駆虫剤の液体を胴体にかける、オスは陰嚢をナイフで切られ、タマを取られて去勢される、角が生えかけている牛は切られて、そこに焼けた鉄棒を当てて潰される。焼き印を捺すのは最後の工程で、だいたいは牧場主である俺がやることになる。
このような一連の流れを、ヘッドキャッチャー三つの三列で行なうので、ここまで来ればあとは数をこなすだけだ。
途中で疲れたらおのおの休憩をとり、大きなバケツに大量の氷といっしょに入れてあるスポーツドリンクや、クーラーボックスの中のビールを飲る。馬に乗ってロープを操る技術のある者は、交代しながら、それぞれの腕前を披露していく。
ダグのふたりの子供たちは、そのほかの子供たちとおっかなびっくり地上班としての作業をたのしんでいる様子だ。
トビーが、カウボーイハットをかぶったドワイトにヘッドキャッチャーの使い方を教えている。トビーは先月、よその牧場に二度ほどブランディングの手伝いに行ったから、ひと通りの流れは心得たようだ。ドワイトはやや腰が引けているが、それでも地面を引きずられてきた仔牛の首にタイミングよく金属の輪をかけた。
仔牛は体の左側を下にして横たわった。BM牧場では、焼き印を仔牛の左肩に入れることになっている。このままでは正しい位置に捺すことができない。
ドワイトは屈んで仔牛の腹の下に両手を差し入れ、ひっくり返そうと試みたがうまくいかない。トビーが、手本を示すように、仔牛の前脚を掴んで向こう側へ放り投げるような仕草で反転させた。
地上クルーが寄ってたかって処置を施す。これはメス牛なので去勢の必要はない。
「グッドジョブ」
俺は、先が真っ赤になるまで熱された鉄のブランド刻印を上から真っすぐに下ろし、しっかりと焼き印を入れた。ジュゥッと音がして、獣毛が焦げるにおいと、仔牛の口からバアァ! という悲鳴が上がった。その拍子にケツから水っぽい糞もビビーッと出しやがった。
強すぎず弱すぎず、長すぎず短すぎず、適切な力の入れ具合で、焼き印を完了させた。
馬上のジェイクに目で合図を送ると、彼は馬を数歩前進させてロープを緩めた。脚が解放された仔牛はすぐに立ち上がり、何事もなかったように出口へ向かって歩いた。牛の皮膚は相当分厚いので、焼き印くらいで大ケガにはならない。
しかし、ストレスにはなるはずなので、できるだけ短時間で終えて、放してやるのがよい。仔牛は鉄柵の外の群れの中から、自分の母親を見つけ出し、再びペアになってぴったりと寄り添った。そして、群れの中に消えていった。
つぎの仔牛は、ドワイトが首を捕まえ損ねて、そのまま後方へズルズルと行ってしまった。ヘッドキャッチャーはペグで地面に固定されているから、ドワイトはそれを手にしたまま追うことができない。
それを見たトビーが、すかさず仔牛の首に飛びかかった。
仔牛と言っても、生まれてふた月も経てば体重は一四〇ポンド程度には育っている。トビーと大差ないだろう。しかし、トビーは首に組みつくと抵抗する仔牛の動きを封じ、ちゃんと左肩が上になるように組み伏せた。
地上班がいつにも増して素早く仕事を終えると、俺の出番だ。
「こいつが暴れるかもしれないが、そのまま動かないでくれ」
トビーに火傷をさせないよう、まずブーツで仔牛の左前肢を踏みつけて押さえてから、慎重にアイアンを押し当てた。牛はビクッと震えただけで、大きくは身動きしなかった。
「よし」
俺の言葉と同時にトビーは仔牛を放し、体を回転させて素早くそこから離れた。
トビーの手際を、ヘッドキャッチャーを手にぶら下げたままのドワイトが目を見開いて見ていた。
立ち上がったトビーのジーンズとシャツは土だらけになった。彼は軽く手で払うと、ハットをかぶり直した。
「つぎはやってみるかい、ドワイト」
「いやぁ、俺はまだちょっと……」
トビーの問いかけに、ドワイトは言葉を濁した。
「チームの大切な二塁手にケガでもさせたら申し訳ないからな。トビー、よく見ていてやってくれ」
俺はそう伝えて、ブランディングアイアンを火の中へ戻すと、革の手袋を外した。
「さぁ、昼のブレイクにしよう」
昼食は、グリルでとにかくパティとソーセージをつぎつぎに焼いて、ハンバーガーとホットドッグを提供する。トビーは手を洗うと、汚れたシャツの上からエプロンを着けて、タマネギを切り、レタスやピクルスを用意した。 各自、好きなだけ食べ物を選び取って、椅子や草の上に腰を下ろす。
空き缶の数を見る限り、かなりのビールがすでに消費されていた。俺も一本もらった。
ついでにもう二本手に取って、ビールが空いた者、なにも持っていない者に、「どうだい」と手渡していく。
ホスト役として、一人ひとりに声をかけ、礼を述べることも大切な仕事だ。ふだんは離れた場所でそれぞれの牧場や農場で黙々と働く者たちが、こうして助け合っておしゃべりに興じる、年に一度の催し物だ。このうちの何人かの牧場には俺たちも駆けつけるから、正確には一度ではないが、今年も主催者になれるのは格別の喜びである。
数々の面倒なトラブルと、雨や泥や油や糞にまみれて働く日々にあって、感謝と誇らしさを感じられる一日なのだ。
ゲストたちに食べ物がいき渡ったのを確かめて、俺は自分のバーガーを取って、ダグの隣に座った。彼の足元には空き缶が四つあった。
「後半戦は、俺もローピングの腕が落ちないよう、馬に乗るから。あんたには焼き印をやってほしい」
「おう、まかせとけ」
ダグは何年もブランディングを経験しているから、焼き印だって信頼して依頼できる。
昼休みが終わると、俺は馬のチーフを連れてきて、脚にはチャップスを、ブーツには拍車をつけて乗った。視界が高くなると、牛たちも地上のひとたちも含めて、ここにあるすべてが俺の支配下にあるような万能感に近い快感に、サドルの上の尻がこそばゆい。
「さぁ、いこう」
ロープで牛の後肢を捕らえるのには、自分のポジションや牛の向きによってさまざまなテクニックがある。基本的には、右利きのローパーに対して、牛が右の胴体を見せている状況がもっとも容易となる。ロープの輪を頭の上を通して前から後ろに回すオーバーハンドから、一、二の三で放る。あまり多く回しすぎても腕が疲れるだけなので、三回までだ。
投げたロープの輪が、牛の後ろ脚に前側から巻きつくように着地すればよい。牛が歩いて、ロープを一本踏み越えて、自ら輪にかかることになる。そのときに釣りのようにロープを引いて輪を小さくすぼめて、脚を完全に捕えれば成功だ。
忘れてはならないのが、ロープをサドル前方のホーンに巻きつけること。これをダリーという。
牛が左を向いているときには、輪を後ろから前へ回すバックハンドで対応することもある。そのほか、そのときどきのシチュエーションによって色々な技巧があるが、基本は牛の動きを見て、つぎを予測して、馬を動かして、自分がやりやすいポジションにもっていくことである。体だけでなく、頭も使って、効率よく、着実に進めるのがカウボーイの仕事だ。
真上にあった太陽が傾いで、地面落ちた影も伸びた。鉄柵の中の仔牛の数も残り少なくなり、終わりが見えてきた。
ヘッドキャッチャーを持ったドワイトがシャツの袖で汗を拭っている。トビーがなにやら話しかけて、ふたりが旧友同士のように笑い合った。
最後の一頭が残り、ほかのカウボーイたちは有終の美は俺に預けるつもりなのか、ロープを構えることもなく、道を譲った。ジェイクはもう馬を鉄柵の外に向け、降りる準備をしている。
俺は仔牛を柵の奥に追い込んで動きを止め、サイドハンドスローでロープを投げた。一発でキャッチ。誰かが囃し立てる声が聞こえた。
「ドワイト、いくぞ」
ヘッドキャッチがやりやすいように、彼の右側を通る軌跡で仔牛を引いていく。
「オーライ」
ドワイトはガシッと確実に首をきめた。
「オスだ」
トビーが去勢係に告げると、ドナルドの部下の男が睾丸で半ば一杯になったバケツを持って走ってきた。彼は膝をつくや、陰嚢をスパッと切り、タマを絞り出した。精管をチョンと切断して、タマをポイとバケツに放り込んで終わり。その間、七秒もない。
「よしよし、最後だ」
ブランディングアイアンをダグが運んできた。三つあるうち、すでに用済みとなったヘッドキャッチャーが地面に放置されていて、それを避けようとしたダグがよろめいた。足元がややおぼつかない。
ダグはブランドを打つ前に、俺に笑いかけ、「今日はここまで」と、授業を終えた大学教授のように宣言した。
仔牛の肩から煙が立ちのぼり、適度な秒数ののち、ダグは押し当てたアイアンを離した。
「おいおい、ダグ、あんた」
できあがったブランドは横棒の上にMではなく、横棒の下にWになっているではないか。
「上下逆さだよ。これじゃあカウボーイハットではなくて、便器にはまった尻みたいだ」
トビーがそれを指さして笑った。
「すまんすまん。ちょっと飲みすぎたかな」
ダグの態度はぜんぜんすまなそうには見えなかった。「まぁ、目印になっていいだろう。今日、最後の生き残りになった勇者の」
「こいつのブランドを確認したいときは、逆立ちでもしてから見たらいいのか」
俺はチーフの上からダグをからかった。
「あぁ、物事、逆さから見ると、たまにはいいこともあるだろう」
彼はなんの根拠もなさそうな口から出まかせを吐いて、悠々と後片づけに向かった。その背中をななめ後ろから夕陽が照らし、ジョン・ウェインの如く堂々として映った。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
