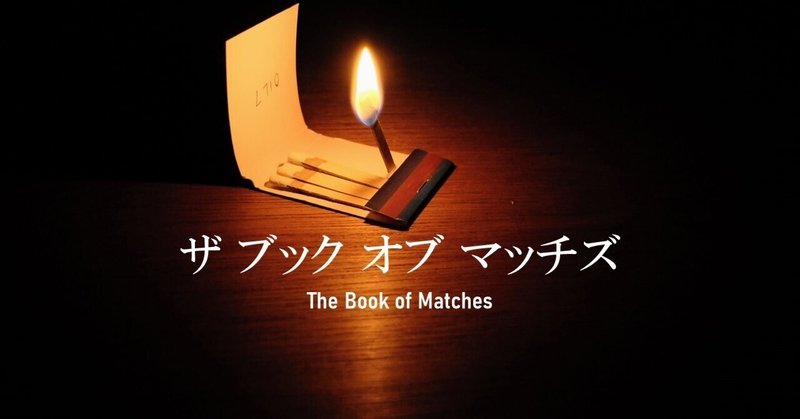
ザ ブック オブ マッチズ 2/16
3
トビーがつくった昼食は、夏野菜を使ったトマトソースのスパゲティだった。
「こんなシャレたものを食うのは何年ぶりかな」
「ふだんが酷すぎるだけですよ。イタリア人は毎日食べてます」
「それを言われると返す言葉もない」
料理には興味も腕前もないが、うまいものはわかる。トビーのパスタは塩味がしっかりしていて、俺たちのような肉体労働者にはぴったりだった。
午後は、来週のブランディングに向けて、家の北側に広がる牧草地に柵を設けた。近隣の、といっても何十マイルも、中には何百マイルも離れたそれぞれの場所からやって来るのだが、カウボーイたちが集まっていっしょに仔牛の焼き印捺しの作業をしてくれる。
トラクターの前方にグラッポー(ツメ)を取り付けて、それに鉄柵引っかけて持ち上げて、半マイルほど運ぶ。
トラクターというのは前や後ろにさまざまなアプリケーションを接続して、多様な仕事をさせるものだ。一台がひとつの仕事をするものではない。
BM牧場にはジョンディアとクボタの二台があり、後者は父親の代からあるもので、相当古い。前者は四年前にローンを組んで購入した。支払いはまだつづいている。
細かい操作が求められるので、俺がクボタを操縦して、トビーは移動のときには同乗してもらい、あとは地上で柵を押さえたり、縛りつけたりと、補助的な作業を行なった。トビーは両手ともそろった革手袋を持っていた。
それにしてもトラクターは遅いので、柵をぐるりと一周の囲いにできるまでいくつもいくつも運搬していると、これまた時間がすぐに過ぎていく。日差しはまだ厳しいが、西からの風が、汗に濡れた横面を撫でていき、すこしは気が紛れる。
つぎに俺たちは、ジョンディアのトラクターの前部に、スワーサーを取り付けた。これはつまり巨大な電動バリカンみたいなものだ。鮫の歯のような細かい刃列が一対、細かく振動して牧草を刈っていく。刃のうしろでは二本のベルトコンベイヤーが中央に向かって回り、刈った草を地面に落とす。そうすると、トラクターの通ったあとには一本の草束ができる。
これをスワースという。なんのためかというと干し草をつくるためだ。夏が終わったあとの牛どもはこれを食べることになる。
やつらは、夏の間はフレッシュサラダが食べられるが、緑の季節が過ぎると乾燥野菜しかなくなる。
年がら年中、焼いたものしか食っていない俺と、どっちがいい身分なのか、微妙なところだ。
トビーと俺は、スワーサーの刃を一つひとつ確認して、ひどく損傷したものは交換した。そして、刃に油を差していく。こういったメンテ作業は面倒だが、結局成果に影響するので、割り切ってやるしかない。
試運転させてみると、コンベイヤーのゴムベルトが怪しい。劣化してきていて、近く破れそうだった。この夏はなんとか持たせて、交換するのは来夏にしたかったが、これもほかに選択はあるまい。
ショップの奥から新品を引っぱり出してきて、取り替えた。
さらに、ジョンディアのエンジンオイルも交換した。俺の手もトビーの手も、油汚れで真っ黒になった。トビーがかぶるクアーズライトの帽子のツバにも、フロリダ州のようなかたちの黒いシミがついた。
最後に、使った工具を元の場所に戻し、スワーサーの古い刃やオイルの空き缶などゴミを捨て、後片づけをして、ショップ内の流しで手を洗って、今日の仕事を終えた。夕方六時を過ぎたが、この季節は九時ごろまで明るい。
俺は、しぶとく留まる西の陽を眺めて、キャメルに火を点した。紫煙が白っぽく光る空に溶けていった。
頭の中でざっと明日の計画を立てる。トビーがタオルで手と顔を拭きながらショップから出てきた。
「帰って、妹を見てやれ」
本来なら七時前まで仕事をすることが多いが、トビーを解放した。彼は照れたような笑みを見せて、「では明日」と帰っていった。
俺はもうしばらくなにかをしておこうと、芝刈りをした。ガソリンで走る芝刈り機に乗って、家の周辺をひと通り巡った。
ひとりでいるとメシを食うのが面倒に感じる。家に帰って食卓に夕食が並んでいる生活というのは、夢のようだとつくづく思う。
母親が生きていたころは、ブレット少年は食事の時間には飛んで帰ったものだ。
父親がいたころは、一瞬なりとも、そのままテレビの中やシリアルのパッケージの印刷に放り込めるような家族団欒の味わいも知った。
いまの俺にとって食事は、体を維持する目的の行為でしかない。土を喰って生きていけるならそれでもいいとさえ思う。
家に上がる階段の前に立ててある、H型の金属の汚れ落としにブーツの底を擦りつけてから家に入った。まず冷蔵庫から缶ビールを取り出して、半分ほど一気に喉へ流し込んだ。缶をテーブルに残したまま、食事は後回しにしてひとまずシャワーを浴びる。
終ってから残りのビールを飲み干した。インターバルをはさんで合計六秒くらいだったのではないか。
電話が鳴った。
「BM牧場です」
「俺だ、ダグだ」
ダグ・ホイットマンは、十五マイルほど南で農家を営む男で、付き合いは古い。彼のほうが三つ年上なので、彼がブッチ・キャシディなら、俺はサンダンス・キッド。やつがワイアット・アープなら、俺はドク・ホリデイ。そういった関係だ。
ダグはいきなり用件を言った。
「頼む。頼むから、いますぐこっちへ来てくれないか」
ふだんなら、どうした。上物のバーボンでも手に入ったか、とでも軽口を返すところだが、彼の声はこれまで聞いたこともないような切実さを孕んでいた。
「どうした」
「リアンが消えた」
「なんだと」
今日は、牛も逃げれば、娘も逃げる。このあたり一帯はそんなに逃げ出したくなるようなひどい場所なのか。
リアンはダグの高校一年生の娘だ。この九月で二年生になる。俺はこの子がまだ、ただの精子だったころから知っているようなものだ。乗馬を教えたのはもちろん父親であるダグだが、小学校に上がった記念に、はじめてのカウボーイハットを買い与えたのは俺だ。
「とにかく来てくれ。頼む」
ダグは繰り返した。こういうとき長々と会話をつづけるべきではない。
俺は「わかった。すぐ行く」とだけ言い残してこちらから電話を切り、ダッジの鍵を取った。
4
ダグの経営する農場へは、南へ十二マイル行ってから、東へ三マイル。飛ばせば三〇分もかからない。
道路から右折して、両脇の芝がきれいに刈り込まれた私道のドライブウェイに入った先に家屋がある。その左手に倉庫と車庫の二棟がひとつになった建物がある。
トラックのエンジン音が聞こえたようで、すでにダグの巨体が扉から出てきた。オーバーオールのストラップを肩にかけ直してから、こちらに向かって手招きをしている。
俺はダッジを車庫のシャッターの前、ホンダ・シビックの隣に停めた。
ダグが家に入るなりしゃべり出すので、俺たちはキッチンで立ったまま話した。俺は勝手に冷蔵庫を開けてペプシを取った。
「今日はあいつだけ家に残っていたんだ」
リアンは夏休み中だ。ダグはトラクターの部品調達のために、片道二時間のビリングスの町まで出かけていた。ホイットマン家には妻のサンドラとの間に、長女のリアンと長男のベンがいる。が、妻と息子もサウスダコタ州の実家に遊びに行っていて不在。リアンは鶏の世話があるからと、ひとり牧場に残っていた。
「俺が家を出たのが朝九時で、戻ったのが三時すぎだ。彼女のクルマはあるのに、姿はない」
リアンは、高校入学時にホンダ・シビックを買ってもらっていた。確かに、それは車庫の前にあった。
「農場は?」
「この広い農場をぜんぶ確認したわけではないけど、きっとちがうと思う。敷地内で行きそうな場所はすべて見回った」
その後、知っている限りの友達の家には電話をし、夜まで帰りを待ったが帰らないので、保安官事務所に電話をしたという。保安官のジムは俺たちの顔見知りで事情を聞いて、すでに捜索に乗り出した。
俺たちは食卓に座った。
「じゃあ、家出なのか誘拐なのかは現状では不明なのだな」
ダグは一瞬目を伏せた。グラスの水を一口飲んだ。
なにかを躊躇するように、手の中のグラスを弄んで、さらに二秒ほど沈黙した。
「どっちなんだ。隠し事をするなら、こんな時間に俺を呼ぶなよ」
「ああ、おそらく家出だと思う」
「その理由に心当たりは」
ダグはグラスの水を飲み干すと、ため息をひとつついた。
「あるんだな」
彼はなおも沈黙をつづけたが、小さく息を吐くと、話した。
「ああ、ボーイフレンドのことだ」
「ほお」
俺はビールを飲みたい衝動を抑えた。目の前のペプシをビールと思い込むことにして、大きく呷った。
「彼氏とちょっと遊びに出かけただけではないのか。大騒ぎすることもないだろう」
「いや、それがな……」
俺はダグが言葉を継ぐのを待った。彼は俺に目を向けたが、そのブラウンの瞳は、救いを求めているようにも、怒りを宿しているようにも受け取れた。
「そいつがな、黒人なんだ」
「ふむ」
アメリカ北西部のこの地域には、黒人の人口は極端に少ない。我々白人のほとんどは、生涯黒人の友人を持つことがない。深南部のようにあからさまな差別があったとは認識していないが、無知からくる偏見は、確実にあると言えよう。
「黒人じゃダメなのか」
俺の質問は少々意地が悪かったはずだ。自分の身に置き換えたら、自分の娘が黒人の彼氏と付き合うこと、そして、泊りがけのつもりで出かけることを許せるだろうか。
さぁな。娘を持ったことも、持ちたいと思ったこともないので、わからなかった。
「ダメかと訊かれれば、ダメだ。そこに理由はない」
「あるだろう。自分でもわかっているはずだ」
「ブレット、お前も結婚して娘を持てばわかるだろう。俺だって自分がレイシストだと認めたくはなかった。制度としての人種差別はよくない。撤廃されるべきだ。それでも、自分の娘が黒人とファックすることは許しがたい」
「あんたの気持ちはわかった。あんたは俺の長い友人だが、あんたが博愛主義者だなんてハナから思っていないし、ラップという音楽がこの世にあるのはいいが、俺の部屋では流してくれるな、という気持ちもわからんでもない」
ダグがなにか言いかけて口を開けたが、俺はそれを制してつづけた。
「ただしな、それはあんたの考えであって、リアンのではない。いい加減、子離れしたほうがいい」
「まだ高校一年なんだぞ。彼女は自分がなにをやっているかわかっていないんだ」
「わかった。俺はあんたと言い争うためにここに来たのではない。どうしたいんだ。俺になにができるっていうんだ」
言いながら、俺は席を立って、キッチンに置いてあったリンゴをひとつ手に取り、そのまま齧った。そういえば、まだ晩メシを食べていない。
キッチンに寄りかかってりんごを咀嚼する俺が、飲み込むのを待つようにして、ダグは言った。
「いまから、いっしょにリアンを探しに行ってほしい」
そう言うのではないかと思っていた。
「しかし、ダグ、あんたが保安官たちより先に見つけたいのは、どちらかと言えば、その黒人のガキのほうなんじゃないのか」
ダグはなにも言い返さなかった。
「俺が『よっしゃ!』と立ち上がって、ショットガンと松明を手に、その少年を殺しに行くと思うか。あんたの頼みでも、それは聞けない」
いまダグの瞳に浮かんでいるのは、失望と憤怒だった。
「でも、安心してくれ。あんたの期待には半分しか応えられないが、いっしょに行くよ。あんたがそいつを殺さないようにな」
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
