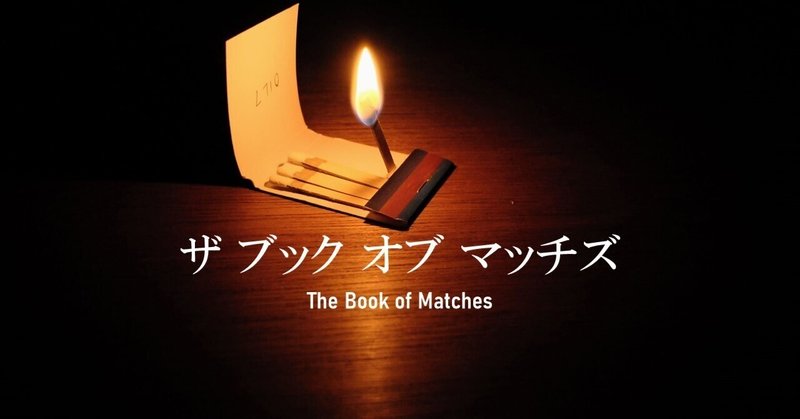
ザ ブック オブ マッチズ 16/16
キャメルを点けた。ここは丘の上で風が強いので、屈みこんで風を遮ってライターを使った。一本喫る間、無言でそこにいた。
またマスタングに乗り、イーサンは川沿いの道を戻るように走ってから、川から離れる小径を左折した。木々に囲まれたカーブの先は円環状になっていて、三軒の家屋が三角を描いて並んでいた。
「ピートに会おう」
オイルセブンのブラックフィート支部にいる男だ。三軒の頂点にあたる位置にある木造平屋の建物は赤いペンキで塗装され、よく目立った。
我々を迎えに出てきたピートは、ほとんど白人といってよい風貌の、四〇代半ばの男だった。肌がやや浅黒いが、黒い髪の毛は短く整えられ、背筋が真っすぐ伸びて、堂々として見えた。この男も部族の中では尊敬を得る立場なのかもしれない。
「ピート・ブルームーンだ。きみのことはイーサンから聞いている」
「ブレット・マクナマス。はじめまして」
俺たちは握手をした。
「父上のことは残念だった」
ピートが俺の肩に手をおいて言った。
「いえ、長い間会うこともなかった父親ですので、むしろみなさんに迷惑をかけました。手厚く葬ってくださり、感謝します」
「ボイドが住んでいたところへ案内するよ」
ピートが先に立って歩いた。イーサンと俺がつづいた。
彼は芝生の上を横切って、家の裏手へとまわった。林と呼んでいいのか、まばらに樹木が生えていた。
四〇フィートほど歩いたところに大きなセコイアの木があり、その陰になっていたが、見えてきた。
それは、ブルーハウスだった。
BM牧場の片隅で忘れられた、ブルーハウスそのままの青い小屋だった。
家の周囲には、バケツが転がっていたり、畑をつくっていた跡があったり、左手の離れたところには父親が乗っていたのであろう、シェヴィーのピックアップトラックが飼い主を喪った犬のように佇んでいた。
「この家は、彼が建てたんだ」
ピートが足元の石を蹴って言った。
「ボイドがあんなふうになってから、なにか打ち込めることがあったほうがいいと考えて、自分の住む場所をつくってみるよう勧めたんだ。彼は喜んで、それなりに熱心に取り組んだ様子だったのだよ」
腕を組んだイーサンがブルーハウスを見つめていたが、彼の目はもっと遠くを眺めているようにも思えた。
ピートが鍵の束を俺に手渡した。
「中を勝手に見ていいから。わたしとイーサンは、家に戻っておく。いたいだけいてくれ。中のなにを持って帰ってくれてもいいし、なんなら家ごと持って帰ってくれてもいい。自由にしてくれ」
そう言って、俺にウィンクして笑った。
俺とふたりは反対方向に歩き出した。
鍵穴に鍵を差すと、コツッと音がしてスムーズに開いた。
父親のブーツが二足とスニーカーが一足あったが、俺は土足のまま入った。
ドアの裏には釘が二本打ってあり、彼が使っていた帽子がふたつ掛かっていた。
右手にベッド、その奥にキッチン、左手奥にシャワー室とトイレのドア。生活に必要な一式が狭い空間に凝縮していた。
父親のにおいがして、彼が確かにここで暮らしていたことがわかった。ベッドの手前側に背の低いタンスがあり、その上にウィスキーボトルが三本並んでいた。
そして、その隣にあるものを目にしたとき、俺は一瞬、視界が揺れたような錯覚を覚えた。
そこには、「ボール・イン・グラヴ」のロゴが刺繍された、ミルウォーキー・ブルワーズの帽子が置いてあった。
ドアに掛けられた帽子とは別にしてあるから、きっとここにずっと飾っていたのだろう。
俺は震える腕を伸ばして、帽子を手にした。
手に取って見ると、青色はかなり退色していたが、確かに、あのとき、俺が大切に持って帰った帽子だ。息を吹きかけると薄くかぶった埃が飛んだ。
俺は帽子を握りしめたまま、ベッドに腰かけ、そのまましばらく動けなかった。
どれくらいの時間が経って、どれだけの想いが過ぎっただろう。わからないことはわからないままで、父親が死んだいま、もう解明されることはない。それでも、ひとつだけわかったことがあり、俺は、それだけで、もうよいと思った。
父親の声が聞こえた。
「ナイフは常に携行しろ」
俺は腰のベルトにクリップでつけた折り畳みナイフを手にした。
外へ出て、建物を回り込んだ。
父親が畑に水をやるために使っていたであろうホースに屈みこんだ。四フィートくらいの長さをナイフで切り取った。
そこに転がったバケツと切ったホースを持って、父親のトラックへ歩いた。ハッチを開けて、キャップを取り、穴にホースを突っ込んだ。
口で勢いよく吸って、ガソリンをバケツに注いだ。
バケツ半分ほどのガソリンを持って、ブルーハウスに戻った。
また父親の声がした。
「途中で間違っていると気づいたら、はじめからやり直せ」
ブルーハウスの中にガソリンを撒き、もう一度トラックへ行って、今度はガソリンを建物の外周にかぶせた。
「あなたは、どうしてやり直さなかったんだ」
惨めにも思える彼の死が、果たして彼に相応しかったのかどうか、いまは怒りも消えてしまった俺の心では断じることはできなかった。晩年に友情を築いてくれたイーサンやピートには感謝すべきであり、一抹の罪悪感が胸にわだかまった。
それでも、遺された息子として、こうすることが俺の責務のように思えた。
ポケットからコブウェブのマッチを取り出し、紙マッチを一本折り、ヤスリの部分と表紙で挟む。指で強く擦ると、発火した。
折った一本のマッチが燃え、ほかの火薬に燃え移って大きくなった。それを俺は、ブルーハウスに放り投げた。
炎は一気に燃え盛った。ブルーハウスはレッドに揺れ、ホワイトに瞬き、ブラックに焦げていった。
俺は部屋で見つけたブルワーズの帽子を自分がかぶっていたことに気づき、それも火の中に投げ入れた。
「さようなら、父さん」
見上げた空が、渦巻く煙も、俺のため息も、すべてを吸い込んでいった。
(了)
*1: ミルウォーキー・ブルワーズの「ボール・イン・グラヴ」ロゴは、二〇二〇年シーズンにメインのロゴとして復活した。
*2: ワシントン・レッドスキンズは、二〇二〇年にワシントン・コマンダーズにチーム名を改称した。
この物語を書くにあたり、カナダの日本人カウボーイであるジェイク糸川氏にお話を聞き、彼のYouTubeを参考にさせてもらいました。謝礼として、ブランディングのシーンにカメオ出演してもらっていますw
筆者はバーのシーンにおりました。
だいたい常にカネには困っていますので、たのしんでもらえましたら相応のサポートをよろしくお願い申し上げます。Thanks in advance.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
