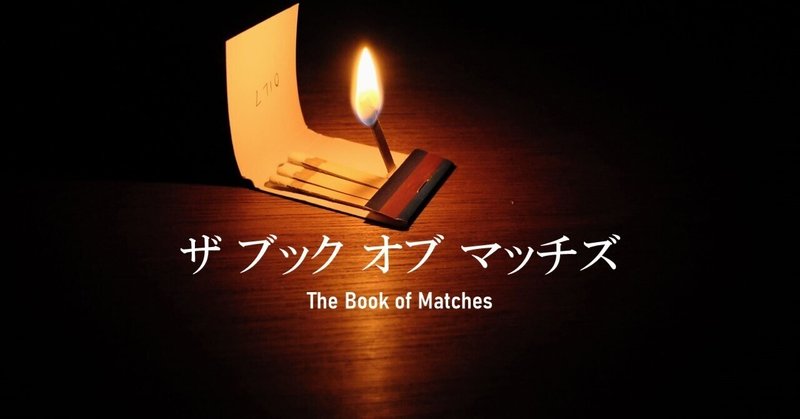
ザ ブック オブ マッチズ 9/16
12
ブランディングのアフターパーティを、ショップの中にテーブルを並べて行なった。ダグの妻、サンディが、リアンとベンの手を借りながら、料理を用意してくれた。
トビーはダグの助けを借りながら、今回去勢した大量のタマをバターとスパイスで煮た。これがカウボーイのごちそうなのだ。
一八〇頭の仔牛への焼き印を完了させたことへの労いの言葉をかけ、帰路の安全を祈り、俺はテーブルの間を縫うように歩き回って、「遠慮なく食べてくれ」と促した。
ドワイトがハットを手に歩いてきた。
「これ、貸してくれてありがとうございました」
「たのしかったか、はじめてのブランディング体験は」
「はい、興奮しました」
「よかった。こちらこそ、手伝ってくれてありがとう。そのハットはお礼にあげるよ」
彼は、医者から「あんたの寿命はあと百年あるよ」と言われたかのように大きく笑った。俺だったら百年はごめんだ。
ドワイトは何度もサンキューと言って、またハットをかぶり、リアンのところへ飛び跳ねて行った。
薄く凝った雲の中にあるが、まだ陽は西の地平線に落ちる前で、家が遠い者から三々五々帰途につく。男たちと、その家族と、再会を誓って握手をした。
パーティが落ち着いたところで、ショップの前でキャメルを喫っていると、ドナルドがこちらへ歩いてきた。カウボーイハットを脱ぐと、白い頭髪は、髭ほどの濃さはなかった。
彼はバンダナで頭と顔を拭うと、笑顔を向けて言った。
「危うく忘れるところだった。きみに渡すべきものがあったんだ、ブレット」
小脇に抱えた上着を差し出した。
「どうしたんですか」
そのツイードのジャケットは、どこか見覚えがあるような気がした。
「ブランドンの上着なんだ」
「父親の。なぜこれをあなたが……」
ドンはひとつ頷くと、俺の目を真っすぐに見た。
「彼が姿を消す半月ほど前だ。うちにひょっこり現れたんだよ。十五年前のあのころに。それでいっしょに家で飲んだ」
「そうだったのですか」
「以来まったく音沙汰はないのだが、あの日、このジャケットをうちに忘れていった」
受け取って見てみると、確かに、父親が町へ出かける際や、めかし込む必要があるときに着ていたジャケットだった。ほぼ唯一の一張羅と言ってよい代物だったから、俺も覚えている。グレーに、薄い茶色や白や黒の細かいネップが入ったツイードだ。
「本当にただ忘れていったのか、形見分けのつもりでわざと置いていったのか、俺にはわからん」
ドナルドは、俺のキャメルを指さしてから、指を二本立てた。意図を汲んで、俺はキャメルを一本箱から抜き出して、ドンに渡すと火を点けた。
ひと口目を吸い込んで、煙を吐きながらドンはつづけた。
「俺にくれても、あいつのほうがだいぶ大きいから俺には着られん。十五年も忘れてクローゼットに放置していたのだが、今回思い出して持ってきた。お前に返そうと思ってな」
「ありがとうございます」
「それから、これを見てくれ」
ドナルドは、俺の手からジャケットを掴むと、胸の内ポケットからなにかを取り出した。
掌の上にあるのは、マッチだった。紙の表紙があって、開くと中に一束の紙マッチが連なっているタイプのものだ。
「マッチには、『コブウェブ(蜘蛛の巣)』とある。店の名前だろう」
「この店は知りませんが、電話番号が書いてありますね」
店名の下にそれは印刷されていた。
「それから、ここも見てくれ」
ドナルドはマッチを開いた。表紙の裏に、手書きの文字で「L710」と読めた。
俺はそれを口に出して読み上げた。
「なんの数字か、これも俺にはわからん」
ドナルドはマッチを閉じて、元のポケットに戻した。そして、ジャケットを再び俺に手渡した。「もしもお前がブランドンを探す気があるなら、なにかの役に立つかもしれん」
それだけ言うと、ドナルドは俺の肩をポンとひとつ叩いて、歩き去ろうとした。
「ドン」
俺の呼びかけに彼は振り向いた。俺はキャメルの箱を投げた。
「まだ半分くらいあります」
ドナルドはそれをキャッチすると、にんまり笑って、後ろ向きに手で礼を示した。
13
あらかた片づけをして、トビーには明日は休めと伝えて家に帰した。テーブルや椅子の片づけは、明日の朝、俺ひとりで充分だろう。
俺は冷蔵庫からクアーズを出して飲んだ。テーブルの上の新しいキャメルのパックを開けた。
一服したあと、俺はジャケットを手に、両親が閨房に使っていた部屋に入った。ここに足を踏み入れることはほとんどない。
ダブルベッドの足の側にクローゼットがある。デスクがひとつ、奥の窓際にあるが、抽斗の中にはなにもない。デスクの上やサイドボードにもなにも残していない。
クローゼットを開けた。ハンガーだけがそこに並んでいた。
俺はドナルドから受け取ったジャケットをそこに掛けた。肩から袖に手を這わせると、古いツイード生地の羊毛がチクチクと皮膚を刺した。
黒人カントリー歌手であるチャーリー・プライドの『アメイジング・ラブ』が頭の中で流れた。
ツイードを着た父親の姿が脳裏に蘇った。黒いカウボーイブーツと薄いグレーのハットをかぶっていた。グリーンのワンピースを着た母親と、抱き合って揺れているのが見えた。
あれは、俺の十三才の誕生日だった。父親が、俺と母親を町はずれのレストランバーへ連れ出してくれたのだった。
ログハウスのような内装で、ステージとダンスフロアもある広い店だった。父親がテーブルへ歩くと、ブーツの踵がゴツゴツと音を立てた。
父親は知り合いを見つけて、握手をしてなにやら笑顔で話していた。あまり表情を変えずに働いている姿ばかり見てきたので、こんなふうにふつうの男のように友人と笑い合うことがあるのかと不思議な気持ちで俺は見ていた。
ウェイトレスに注文を取られ、俺は一丁前にTボーンステーキをたのんだ。全員がTボーンを食べたはずだ。その店ではそれが売り物だった。
その晩、どんな話をしたのかは覚えていないが、父親がフォークでステーキを指し、同じようにステーキを食べるまわりの客を示して、こう言った。
「俺たちはこのひとたちのために仕事をしている。牛肉を食べる幸せそうなひとたちの顔をよく見ておけ」
そのときの父親の顔には誇りのようなものが滲んでいた。少なくとも俺はそう信じた。
ステージにはカントリーバンドがいて、マール・ハガードやウェイロン・ジェニングスのカバー曲を演っていた。食事のあとにはウェイトレスが俺のためにバースデイケーキを運んできて、髭面の男たちのバンドはしゃがれ声でハッピーバースデイを歌ってくれた。
店中のみんなが手を叩いて祝福してくれて、俺は照れくさかったけど、内心ではアカデミー賞でももらった気分を味わっていた。
父親は、ボクシングのレフェリーが勝者にするように俺の腕を掲げて、その場のお客たちに応えさせた。あのときも笑顔だった。
それから、父親と母親はダンスフロアに出て、抱き合って踊った。その曲が、チャーリー・プライドの『アメイジング・ラブ』だった。父親の背中越しに、母親が俺に手を振ってきた。
ふたりの頭上で、ミラーボールが光彩を四方八方に撒き散らし、俺は首をぐるぐる回してキラキラを目で追った。愛がなにかなんて知らない俺の目にも、ふたりは愛に満ち溢れて、光り輝いていた。
踊る父親はおろか、あんなに穏やかに笑う彼をみたことはなかった。
三十一才の俺はいま、「昔はよかった」などと思うことはないが、あの晩のことなら、たまに泥酔したときに頭の中に、ありありと思い浮かぶことがある。ウィスキーグラス越しに、ゆらゆらと漂うふたりの抱擁が、手を伸ばせば届きそうな距離に見えるような気がするのだ。
俺はジャケットから手を離して、クローゼットを閉じた。
もう一度、扉を開けて、ポケットを探った。あのマッチを手に取った。
14
トビーには休みを与えたので、俺はひとりで草を刈った。つまり、スワーサーで牧草をシェイヴィングして、六番の牧草地を畝だらけの縞々にしてやったのだ。先日の雨で、牧草はよく伸びていた。
夕方になるのを待って、マッチに刷ってある店名のコブウェブに電話をした。出てきたのは女だった。
「そちらの店を訪ねたいのだが、住所を教えてもらえないか」
電話口の向こうでは、ガヤガヤとひとが話したり、食器を運んだりするような物音がした。
「ビリングスのローレンス・アヴェニュー4055よ」
女は気安い感じの声音で答えた。
「定休日はあるかい」
「月曜日」
電話を一刻もはやく切りたそうな口調だった。
「わかった。ありがとう。忙しいところすまないね」
「オーライ」
女はそれだけ言うと電話を切った。きっと繁盛している店なのだろう。いまから向かえば、充分に営業時間内に間に合う。
一瞬ダグを誘おうかと考えたが、やめた。この件は彼には関係がない。それどころか、関係者と呼べるのは、俺しかいないだろう。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
