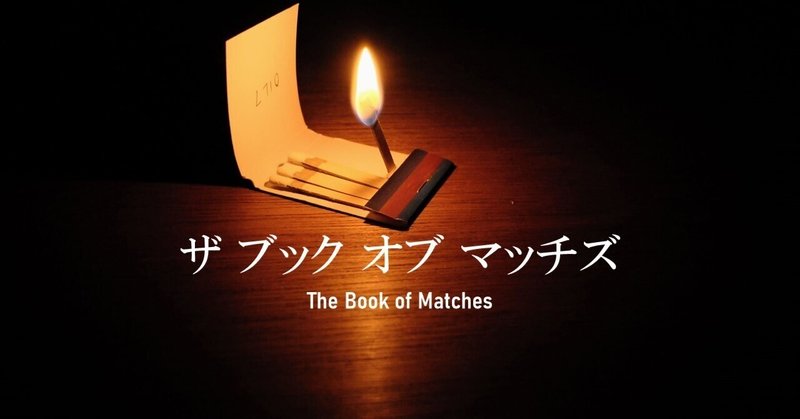
ザ ブック オブ マッチズ 12/16
もう0時もとうに過ぎていた。これから牧場に戻るには遅いし、ここまで来たら明日はさっそくイーサンに会ってみたい。
町のほうへ戻りながら、そういえば、ダグといっしょにこのあたりのモーテルをあちこち当たったな、と思い出した。あのときの捜索がこんなところで役に立てばいいのだが。
コブウェブの前にさしかかった。すでに店の電灯は消えていた。そのまま通り過ぎようとすると、駐車場の端にアリソンが見えた。ちょうど赤いスポーツカーに乗ろうとしているところだった。
俺はそばまで寄って、ピックアップトラックを停めた。夜中に警笛を鳴らすのは憚られたので、二度ほどパッシングライトを送ると、アリソンは不審な目つきでこっちを見た。
俺が窓を下ろすと、認識したようだ。彼女は、夜を昼に、冬を夏に、一瞬で変えちまうようなビッグスマイルを見せて手を振った。
俺はトラックを降りて、彼女の三菱エクリプスのほうへ歩いた。
「あら、ジョージ・ストレイトじゃないの。ロジャーからおもしろい話は聞けたかしら」
「ああ、とても親切な男だった。助かったよ」
「こんな時間にこれからどこまで帰るの」
「いや、モーテルでも探そうかと思っていたところに、きみを見つけたんだ」
アリソンは指に引っかけた車のキーをくるくると回した。
「うちに泊まれば」
庭の鶏が卵産んだんだけど持って帰る? くらいの気安い言い方だった。
俺は咄嗟に返事ができなかった。
「なに期待してんのよ。カウチでよければ寝ていいわよって意味よ。わたしは枕元に九ミリがあるから、おかしな気を起こしたらマジで許さないから」
彼女は手を拳銃のかたちにすると、俺の胸に押しつけた。
「では、ありがたく提案に乗るが、ひとつ謝らせてほしい。俺はさっき、きみの名前を訊いておきながら、自分は名乗り忘れてしまった。ブレット・マクナマスだ」
俺が差し出した右手を、彼女は拳銃をシルクに変えて包んだ。
「ついて来て」
アリソンのエクリプスの後ろを走ること二〇分ほどで、アパートに着いた。俺はエクリプスの隣ではなく、離れたスポットに駐車した。後部ウィンドウのラックにライフルが掛けられたままだったのに気づいて、後部座席の足元に隠した。牧場と町では勝手がちがう。
階段で二階へ上がると、左右に部屋があり、彼女は左側のドアに鍵を差し込んだ。
毛足の長い絨毯が敷き詰められたリビングルームがあり、右手にキッチン。そこから右に入る短い廊下の先にバスルームと寝室があった。
アリソンはブッシュの缶ビールをふたつ手にした。
「座って。約束通り、今夜あなたが発見したおもしろい話を聞かせてもらうわ」
俺は手短に、ここへ至った経緯とロジャーから聞いたことを伝えた。マッチをもう一度アリソンに見せて、上下逆さのタネ明かしをした。
「まぁ、明日、そのイーサンに会わないと、ロジャーの見解が正しいのかどうかはわからないがね」
「お父さんはどんなひとだったの」
父親は一体どんな人物だったのか。アリソンの何気ない問いに、俺はふと立ち止まってしまった。
「言いたくなかったらいいのよ」
「いや、そうじゃない。父親のことを十数年もひとに話すことなどなかったから、そう訊かれて俺自身、彼はどういうひとだったのかと考え込んでしまったんだ」
「生きていたら会いたい?」
アリソンは俺を黙らせるいい質問ばかりしてくる。俺はそれをそのまま伝えた。
「確かにそうだ。本当に会いたいのかどうか、会ったらなにを言うのか、殴るのか、抱きしめるのか、俺は実際のところ、なんの準備も心構えもせずに、牧場を飛び出してきてしまった」
「やっぱり会いたいんだと思う」
俺はアリソンの言葉を胸の底に沈めるように、小さく何度も頷いて、考えた。
「ふらりと帰ってきたりしたら撃ち殺してやる、なんて思ってきた。だけど、俺はただ知りたい。あんなふうに家族を棄てたら、俺たちがどうなるか想像しなかったのか、と。どれだけ深い闇に自分の妻を突き落とすことになったのか、彼女がどれほど精神を病んで死んでいったのか、そして、俺が、十六才の俺が、牛糞の壁に閉じ込められて、ひとが青春と呼ぶような一切を経験しないまま、こんな中年男になったことを、父親に知ってほしい」
最後はすこし声が震えた。アリソンの前で、感情を昂ぶらせてしまったことを恥じた。
「あなたがここでこうしている限り、未来はあったんだよ。あなたのことはなにも知らないけど、立派な人間だとわたしには見えるよ」
「思えば、父親はそう酷い人間ではなかった。俺がいまやっている仕事は、数え切れないくらい多くの技術や知識が必要で、また天候や自然や動物という如何ともしがたいものに翻弄されてキツい目にも遭う。だけど、生き抜く術をぜんぶ教えてくれたのは、ほかならぬ父親だった」
俺はブッシュを飲み干した。
「生き抜かざるを得ない状況に追い込んだのも彼なわけね」
「そうだ。父親に好きなように操られているようで、俺は俺の人生を取り戻したいと思うことがある」
「取り戻すべき人生って」
アリソンが立ち上がって冷蔵庫へ行って、俺に二本目を手渡した。
俺はプルタブを開けながら答えた。
「さぁ。結局、おなじ牧場にいるだろうとは思う。しかし、父と母がいて、もしかしたら俺の妻と子供でもいて、幸せなカウボーイ一家を築いているかもしれない」
俺は一気に半分ほど飲んだ。
「あなたに反対するとかじゃないのよ。いい? お父さんはきっと、なぜか、それを幸せに思えなかったのではないかしら。少なくとも、そのときは」
俺はアリソンを見た。彼女は右肘をカウチの背もたれについて、手で頭を支えて、俺を見ていた。その瞳にはひとへの慈しみが浮かび、その姿は俺の心のどこかを慰撫するようだった。
俺はしばらく彼女を見ていた。正確には、彼女の瞳のずっと奥のほうを眺めながら、「父親は幸せなのだろうか」という、これまで思い巡らしたこともない問いを弄んでいた。
母親はたぶん幸せとは言えない最期だった。これすらも真実はわからないが。
俺はキツい人生ではあったが、それほど不幸とも思ってはいない。自己憐憫に酔うほど落ちぶれちゃいないし、恨みを糧に生きるのも不健康だとわかっている。が、たまにそいつらは顔を出すので、俺は牧場に出没するネズミをライフルで撃つように、胸の中の穴に押し込んできた。
「わからないな、ひとの心の中なんて。父親といえど、他人だ」
「そうね。ひとの心の中になにが渦巻いているか、なにと闘っているかなんて、わからないわ」
「幸せなんて、往々にして本人にもわからない」
俺はビールのもう半分を缶から胃に移した。
アリソンがまた立ったので、その手を掴んで引き留めた。
「ビールはもういい」
「なににする?」
「きみの話も聞かせてほしい」
アリソンはカウチに腰を下ろした。
「わたし? わたしはそんな大したドラマはないわよ。高校を出て、結婚して、離婚して、ロジャーの世話になってバーで働いているだけだもの」
「ロジャーはきみのことを信頼しているようだった」
「お金はちょろまかさないし、手あたり次第男に手を出さないし、前科もないし、信頼に足る人物のはずよ」
彼女がビールの最後のひと口を呷り、テーブルに缶を置くと高い音を立てた。それが質問の時間の終了を告げるベルのように空間に響いた。
もっと質問をしたい気分だったが、あまり質問を重ねるのは礼を欠くような気もした。アリソンが信頼できる人物であるのは、俺自身も勘でそう感じたので、それ以上は知る必要もないと思ったのだ。
会話もない。物音もない。ビールもない。夜だけがそこにあった。
俺は沈黙を脇へ払った。
「俺は朝から労働をして、シャツだけ着替えてそのままここまで来てしまったんだ。すまないが、寝る前にシャワーを借りていいか」
許可を得る前に、俺はすでに腰を半分浮かせた。
「その廊下の左手がバスルームよ。入ってる間にタオルや歯ブラシは用意しておくから」
俺は熱いシャワーを浴びて、明日はイーサンの前に、まずトビーに電話しなくては。明日は戻れそうもない。それから、ガソリンを足して……などと計画を立てた。
シャンプーで泡だらけにした髪を湯で流していると、突然、シャワーカーテンが開いた。
慌てて顔だけ洗い流し振り返ると、アリソンがタブに入ってきていた。素っ裸だった。
「おい、なにしてるんだ」
「わたしね、いっぺんカウボーイとセックスしてみたかったの」
アリソンは、腰に手を当てて堂々と立ち、PKを蹴る前のサッカー選手のような眼をしていた。そして、ニッと笑った。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
