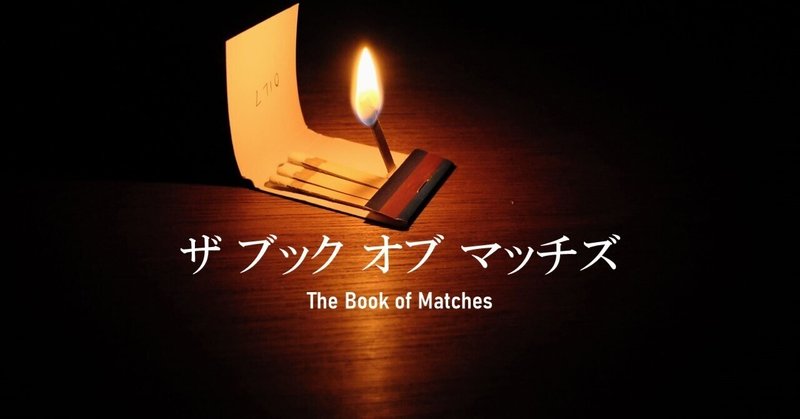
ザ ブック オブ マッチズ 11/16
15
言われた通りの場所にガスステーションはあった。
町の端にあるバーから、さらに町はずれといえる、静まり返った建物がぽつりぽつりとしかない道端に、煌々と光を放って存在した。コンビニが併設されていて、地元のひとたちがビールやスナックを買いに来るようなところだ。
ひと気はなく、もう閉店間際に見えるので、俺は急いで中へ入った。
ロジャーらしき人物を見つけて声をかけ、コブウェブから来た旨を話すと、果たしてロジャー本人だった。黒のポロシャツにはガスステーションの店名のワッペンが胸にある。
ロジャーは、白髪をきれいに撫でつけた小柄な男だが、ポロシャツの袖からのぞく腕は筋肉質で、がっちりした体格だった。
俺はハットを脱いで、牧場から来た旨を手短に自己紹介し、コブウェブでしたようにマッチを見せた。
「そうだ、これは以前うちでつくっていたものだね。もう何年前になるか」
「少なくとも十五年前なのだと思います」
「で、マッチがどうしたのかね」
俺はここで父親の写真を胸ポケットから出して、彼に渡した。
「これは俺の父親で、十五年前に失踪しています。事件性はなく、自分から出ていったのです。その当時、彼が着ていたジャケットが、最近になって彼の友人から俺に戻されまして、ポケットに入っていたのが、このマッチです。唯一の手掛かりと言ってよい代物なのです」
ロジャーは、しばらく無言で写真に見入った。
「わたしは十数年前まではコブウェブにもよく立っていたよ。もうこんな年になったから、客層とも年が離れてしまい、白髪のじいさんがいるよりはスタッフも若いほうがいいだろうと、アリソンたちにほとんど任せている。彼女らはよくやってくれているよ」
彼は碧い瞳がくりくりとして、笑うと愛嬌のある顔立ちをしていた。「ひんぱんに来るお客だったら忘れるはずがない。しかし、きみの父上は、わたしの記憶には残っていないな」
「そうですね、常連だったはずはありません。たまに出かけるくらいで、たいていは牧場におりましたから」
「もう一度マッチを見せてくれ」
彼はそう言うと、写真のほうを返してきた。そして、マッチの表と裏を吟味するように回しながら眺め、表紙を開いた。再び、上にしたり下にしたり、裏返したりして、見たこともない異国のコインでも手にしたみたいに調べた。
「きみ、これは」
ロジャーは表紙の裏に書き込まれた数字を指で示した。
「L710。意味は俺が知りたいくらいです」
俺が答えると、彼は手にしたマッチをゆっくりと横倒しにし、それから下向きにした。
「これは、もしかしたら、L710ではなくて、"OIL 7"と書いてあるのではないかね」
ロジャーが差し出したマッチを俺は手に取り、上下逆さにして、凝視した。

確かに、よく見ると、0をゼロと読むなら、書き出しと書き終わりのつながりが下にあるように見え、そうなると不自然だった。
最後の一文字がアルファベットのLではなく、数字の7であるなら、7の足に短い横棒を加えて書くひともいる。この手書きにはそれはなかった。
しかし、つぶさに見ると、7の最後がやや上に向かってハネているようにも見受けられる。これがLなら書き出しに力が入ったとしても、右側からペンが入ることはないような気もする。ふつうは左から書くから、ハネのように見えるとしても、逆向きになるだろう。
「そ、そうですね。これはOIL 7と走り書きして、なんらかの理由で、こちら向きに書いたのかもしれません……」
俺の頭の中で、「物事、逆さから見ると、たまにはいいこともあるだろう」という声が響いた。BM牧場のブランドを上下逆さに焼き印しながら、およそ悪びれるところのなかったダグの憎たらしい声だ。
あんた、たまにはいいことを言うな、ダグ。これは「オイルセブン」だったのか。
「しかし、ロジャー、それでも俺にはオイルセブンの意味はわかりません」
ロジャーはぽかんとした顔をした。
「きみ、知らんのか。オイルセブンはここいらの石油掘削会社だよ」
「そうなんですか!」
「そうだ。長年バーオウナーと、ガスステーション経営者をやっていれば、多くの人間と知り合う。きっときみのような牧場暮らしとは桁がちがうだろうと想像する。いや、バカにしているんじゃないぞ」
ロジャーは、すこし誇らしげに笑ったが、すぐに真顔になってつづけた。「この州にはインディアン居留地が七つある」
「はい、それは知っています」
「この七つの居留地から石油を掘削して、先住民の経済の役に立てようと志しているのが、オイルセブンという会社だ。インディアンは居留地を与えられて政府から補助金ももらっているが、暮らしは貧しい。僻地の土地を与えられても仕事なんか簡単にはつくれないだろう。だから、観光客を対象とした土産物屋かカジノくらいしかない。若者の失業率は高く、アルコールやドラッグも根深い問題となっている。
その状況をなんとかしたいと思ってその会社をつくったのが、クロウ族のイーサンという男だ」
ロジャーは突然つかつかとその場を離れて、奥の事務所へ歩いていった。
「連絡先がわかるはずなのだが、時間がかかるかもしれん。店のコーヒーを勝手にやってくれ」
事務所から声だけが聞こえてきた。
俺は紙コップふたつにコーヒーを入れた。財布から二〇ドル札を出して、レジカウンターの目立つところに置いた。面と向かって渡すと、ロジャーは断りそうなタイプの人間に思えたからだ。
それから俺は事務所を覗いた。
ロジャーはデスクの抽斗をゴソゴソと捜索していたが、俺を見て手招きした。俺はデスクの前の応接テーブルのソファに座った。棚に並んだファイルと、伝票やらカタログやらが積み重なったデスクしかない、殺風景な事務所だ。
「あなたの分もコーヒーを持ってきました」
「ありがとう。ほんとうはもうビールにしたい時間だが、これで我慢してくれ」
「とんでもない。ビールならさっきコブウェブで一本飲ってきました」
ロジャーは手を止めてコーヒーをひと口啜ると、さきほどのつづきを話した。
「居留地というのは連邦政府の土地なんだ。だから州税は免除されている。イーサンはそこに目をつけたんだな。石油を掘り当てれば、その分高い利益率が見込めるから、居留地に病院を建てたり学校をつくったり、ドラッグ以外に時間を費やせるレクリエーションを充実させられるかもしれない。もちろん雇用も生める。
ところが、どんな組織でもそうなのだろうが、インディアンの中にもさまざまな部族がいて考え方があるから、石油は自然破壊につながるとして反対する者もいれば、イーサンがひとりで儲けようとしていると嫉妬する者もいる。
そもそもインディアンという呼称だって、インド人じゃないんだからアメリカン・インディアンだというひともいれば、ネイティブ・アメリカンだ、ファースト・ネイションズだ、インディジェノス・ピープルだと、意見は一致しない。
肌が赤いと云うのは差別的だという指摘があり、フットボールのワシントン・レッドスキンズは長いこと批判に晒されている*2。しかし、実際は、赤い肌を誇りにしているひとたちもたくさんいる。
話が逸れちまったが、そんなわけでイーサンの描いた理想も、一筋縄ではいかないみたいだ」
ロジャーは両手を広げておどけた表情を見せた。
「ここから東に一時間も行けば、リトルビッグホーンの古戦場があるだろう。一八七六年、カスター中佐率いる第七騎兵隊がスー族に殲滅された戦いだ。
イーサンはクロウ族でな。クロウは、騎兵隊の斥候として白人側についていたんだ。だから、いまでもスー族とは仲が悪い。百年以上も経つのにこのザマだ。信じられないだろうが……、あった!」
ロジャーは手にした紙切れを掲げて、もう一方の手で拳を何度も突き上げた。
「あったぞ。イーサンの名刺だ。明日にでも電話して訪ねてみるといい」
俺はコーヒーを飲み干すと、丁重に礼を述べた。
「イーサンの連絡先を見つけただけで、きみの父上が見つかったような喜び方をしてしまったが、とにかく、なにかの役に立つといい」
「ありがとうございます。神のご加護を」
毎晩神に感謝するような人間でもないのに、思わず口をついて出た。見ず知らずの俺に親切にしてくれたロジャーに対して、本当にそう思ったのだ。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
