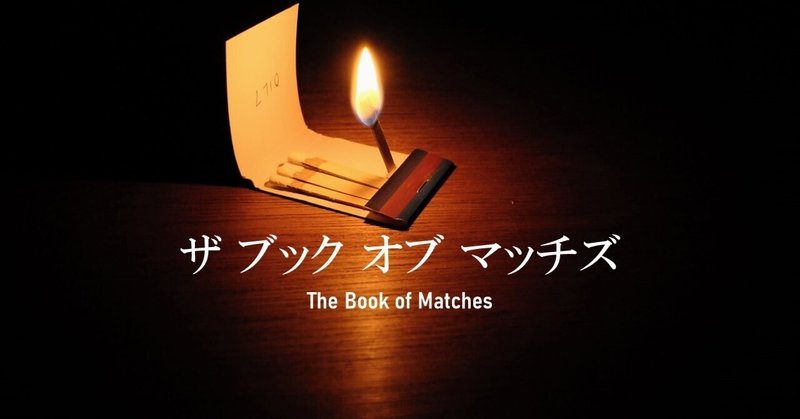
ザ ブック オブ マッチズ 3/16
5
俺たちふたりは、ダグのピックアップトラックであるフォード・レンジャーに乗って、暗闇を走った。このあたりは町からも離れているので、夜は海の底に沈んだかのような暗さと静けさだ。
ダグは実家からこちらに向かっているはずの妻、サンドラに置き手紙を残した。
〈俺はブレットと捜索に行く。保安官から連絡があるかもしれないから、きみはなるべくここにいてほしい。大丈夫だ。リアンは戻ってくる〉
リアンが逃げた先を推測するために、持ち去った荷物を点検した。家のキャンプ道具がなくなっていれば、自然の中のしかし人間が滞在できる湖畔とか、キャンプ場とかをあたるつもりだ。大きなカバンがなくなっていれば、リアンはひと晩どころではなく、より長期間の逃避行を決心しているから、かなり遠くまで行っているかもしれない。
「恥ずかしながら、娘の持ち物なんてほとんど把握していない。俺は彼女のなにを見ていたのだろう……」
ダグは短い髪の毛を搔きむしって悔いていたが、とにかく家にいてもなにも起こらないので、行動することにした。
若者が目指すのはまずは町だと考え、ビリングスへ向かった。しかし、そこは日中ダグが出かけていた場所なので、父親に出くわすかもしれない町をわざわざ選ぶとも思えなかった。なにもしないよりマシ、というだけだ。
「もしも。もしもリアンが戻ってこなかったら……」
ステアリングに手を置いて、闇夜に目を向けたままダグがつぶやいた。
「戻ってくるよ」
ダグの横顔から表情は読めなかったが、抑揚のない声で彼は言った。
「先週の土曜の朝、リアンがサンディに彼氏の話をしているのを傍らで聞いたんだ。彼女らはキッチンにいて、俺はリビングルームでカウチに座って新聞を読んでいた。聞こえていないと思ったのだろう」
俺は先を促すために、相槌の代わりに咳払いをした。
「リアンは、高校の野球の試合を観に行ったら、ドワイトってボーイフレンドが塁に出る度に盗塁をするから、つぎの打席に立ったときに相手チームのピッチャーから故意に当てられたということを話していた。それに対して監督が『うちの息子になんてことしやがる!』と猛抗議して乱闘になりかけたらしいんだ。
そこで俺は『うちの息子?』と気づいた。リアンの高校の野球の監督が黒人だってことは知っていたからな。なんなら、ジョシュのところのバーですこししゃべったことすらある。ディーンといったかな。黒人のくせにでかいベルトバックルなんかしやがって、カウボーイ気取りの野郎だ」
ダグは額の汗を手のひらで拭うと、それをシャツになすりつけた。
「それを聞いて俺は立ち上がった。『なんだと? お前の彼氏はディーンの息子の黒人か』と、本当はもうすこし落ち着いて言いたかったが、自分の口から出た言葉の勢いに自分でも驚いたくらいだ」
俺は苦笑するしかなかった。ダグらしい。あんたは落ち着いてものを言ったことなどこれまでにないだろう。
「リアンは怒ったのだな」
「お察しのとおりだ。俺は彼氏が黒人だということ以上に、サンディはそれをとっくに知っていた様子なのに、俺にはひと言もなかったことにも腹が立った」
「俺にはわからんが、そういう話は父親にわざわざしないのではないか。特にあんたのような父親には」
ダグは黙った。俺の特技は、ダグを黙らせることなのかもしれない。俺が来るとサンドラの機嫌がいい理由がわかった。
「それで、口論になってリアンを叩いてしまったんだ」
「俺なら家出するよ」
ダグは笑わなかった。本来は、笑わせるほうが得意だったんだけどな。
運転席のダグがペダルを目一杯踏み込んだため、一時間半で着いた。リアンの写真を見せながら、念のため安モーテルを虱潰しにあたった。高級なホテルはハナからパスした。
大手チェーンのモーテルにはスタッフがいるが、個人経営の宿では主人はすでに就寝していて、迷惑そうな顔を隠そうともせずに応対された。
「うちは未成年は泊めないからよ。さっさと帰ってくれ」
俺の右腕のハミルトンの腕時計は、深夜十一時を示していた。
「どうする」
「となりのローレルまで行かせてくれ」
どうせ当てずっぽうしかできることはない。今夜は眠れない夜を過ごすであろうダグに付き合うか。
ローレルはビリングスに比べて小さな町で、モーテルは三軒しかなかったため、用事はすぐに済んだ。ここからは、そのままインターステイト90号を西へ進めば、太平洋までつづいてしまうし、国道212号を南へ行けば、先の二股を右ならイエローストーン国立公園、左ならワイオミング州のコーディに出てしまう。その間、ほぼなにもない荒野と岩山がつづく。
先ほどキャンプ道具はダグの家にあることを確認したものの、さほど持ち金もないであろう若者がテント泊をするなら、イエローストーンはなきにしもあらずだ。それでも、野営などそこらの川辺でいくらでもできるから、わざわざ有料の国立公園に行くとは思えない。
バッファロービルが築いた町、コーディだって、俺たちの日常は、インディアンの来襲こそないものの、しょっちゅう馬に乗って、コヨーテを撃って、毎日ワイルドウェストみたいな生活なのだから、そこもありそうもない。
だいたいこんなところで、真夜中に、人探しなど土台無理なのだ。
「今夜はもう帰ろう。サンディだって、あんたが帰らないと心配するだろう」
ダグは渋々従って、フォードを東へ向けた。帰路はさっきほど飛ばさなかった。
6
「失踪といえば、お前は自分の親父さんを探そうとしたことはないのか」
おもむろにダグが訊いてきた。「もう何年だ?」
「十五年になる」
父親は、俺が十六の秋に家を出て、そのまま帰らなかった。まるで、ちょっとビールでも買いに行くかのように出かけ、それきりだ。もちろん捜索願は出したが、年に八〇万人が行方不明になるこの国で、見つかる方が稀なのだ。
そして、俺は自分では探すことはしなかった。俺は棄てられたのだ。
俺を見捨てた人間に、こちらから縋りつくような真似は、自分を惨めにするだけだと考えた。俺は母親とふたりで生きていくために、学校を辞め、とにかく牧場の仕事に邁進するほかなかった。母親を食わせるため、というより、実質は牛どもの命をつなぐために毎日必死だった。八年後に母親が死んでからはなおさらそうだし、いまでもそうだ。
女のおっぱいも触ったことがないのに、難産のメス牛のプッシーに腕を突っ込んで、仔牛を引きずり出す青春なんて、誰が過ごしたいかって話だ。
ロクな教育も受けられず、自分の存在を全肯定してくれるような相手と若者らしい恋をすることもなく、当然、自分の家族を持つこともないまま三〇才を超えた。何人かの女とは出会って別れたが、そう、出会って別れただけだ。
「あのころは、自分と牧場のことで手一杯だったからな。あんたにも世話になったよ、ダグ」
ダグはしょっちゅう訪ねてきてくれては、食い物をくれたり、仕事を手伝ってくれたり、道具を貸してくれたり、メシに誘ってくれたり……、多少粗雑だがいい男なのだ。
俺は、傍から見ればかわいそうな人間なのだろうが、自己憐憫はなにも生まないと知っている。生きる意味とか目的など、俺は考えない。犬や牛と暮らしていると、あいつらにそう教えてもらったからだ。
だけど、父親がのうのうと生きて帰ってきたら、そのときは俺がショットガンを持ち出すかもしれない。一発はプライドをズタズタにされて半ば狂死のように土に還った母のため。もう一発は、家族を捨てたときに、自分は死んだつもりだったはずの父に本当の死とはどんなものか知らしめるため。
俺のためには、ショットガンの装弾よりも、クソでも喰らってくれ。
「お前はよくやってるよ。本当に、よくやっている」
ダグがこちらに慈しみに満ちた眼差しを向けて言った。「十六才の少年が、十五年もほとんど独力で牧場を切り盛りするというのは、大変なことだ。誰にでもできることじゃない」
「さあ、俺にはわからんよ」
「いや、俺にはわかる。お前は本物のカウボーイだよ」
左前方には、横から見たカバのようなかたちで黒々とした山のシルエットがあった。そいつがバカでかいくしゃみをした飛沫のように、夜空には星がびっしりと貼りついていた。俺たちはそこに吸い込まれていくように、ただただ前へ進んだ。
途中の町で燃料を補給して、俺はコーヒーとスニッカーズを買った。結局晩メシにはありつけなかった。
その日はそのままダグの家のカウチで仮眠をとった。寝室でダグとサンドラがぼそぼそと話し合い、すこしだけ言い争うような声が聞こえてきたが、俺は疲れすぎていた。挨拶は朝にしようと思ったか思わなかったかのうちに眠りに落ちた。
翌朝はサンドラが朝食をつくってくれた。
「コーヒーはもう一杯いる、ブレット?」
「もらうよ」
卵二つの目玉焼き、ベーコン、トースト、グリッツ、りんごという、俺にとっては近年稀にみる豪勢な朝メシだ。昨日のトビーの昼食もよかったが、その代わり、晩メシにはありつけなかった。運がいいのか悪いのかどっちなのだ。
皿に残った卵の黄身とグリッツをいっしょくたに、トーストの最後の一切れで拭って食べた。
「昨夜はありがとう」
サンドラはカールの大きな金髪を首のうしろでひとまとめにしていた。やや疲れの見える顔色をして、化粧をしていない肌にはそばかすが目立った。薄いブルーのジーンズと無地の白いTシャツは朝の陽光を反射して眩しかった。
「保安官のジムからなにか連絡はあったのか」
「いえ、なにもないわ」
「ダグを責めないでやってくれ。あいつはあいつなりに反省している」
「まだグーグー寝てるわ」
「では、彼がいない間に伝えておきたい」
俺は声を一段低くした。「この家に拳銃はあるだろう。できれば隠しておいたほうがいい。それからライフルも、ロッカーに鍵などろくにかけたことはないと思うが、鍵をしてほしい」
サンドラのブルーの瞳をまっすぐに見て、これが冗談ではないことを示唆した。
「リアンが戻ったら、ダグがドワイトを撃ち殺してしまうから?」
「戻らなくても殺すだろう」
しまった。「すまん。いつもの減らず口で失言をした」
「大丈夫。心配は心配だけど、私は楽観視しているから」
「サンドラ、きみはなにか知っているのか」
「いいえ、知らない。だけど、私も高校生のころ、親に嘘をついてボーイフレンドと旅行したことならあるわ」
サンドラは当時を思い出したのか、なにかおいしいものを食べたときような笑顔を見せた。それが本心からの笑みなのか、強がりなのか、俺には読み取れなかった。とにかく、俺の前で泣き喚いて狼狽されるよりはずっとマシだ。
「リアンは、嘘はついていないだけ罪は軽いか」
「それはどうかしら。なにも言わずに出ていく方が親は心配するわ」
「きっとすぐに帰ってくるよ。俺はそう祈っておく」
椅子にかけていたシャツを取って、タンクトップの上に羽織った。「では、なにかあったら、すぐに連絡をしてくれ」
「そうするわ」
俺が出ていく間際に、十三才の長男、ベンが起きてきた。
「おはよう、ベン」
母親に似てカールした金髪が、寝ぐせで逆毛だっている。
「おはようございます、ブレット」
俺はその髪の毛を手で撫でつけた。
「どうだ、学校は」
「いまは夏休みです」
そうだった。子供がいないと年間スケジュールを忘れがちになる。
「よいサマーブレイクをな。リアンが戻るまで、お父さんお母さんをたのむぞ」
ベンは寝起きのわりにはしっかりした眼差しで大きく頷いた。
さて、牧場でトビーと牛たちが待っている。俺もブレイクがほしいものだ。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
