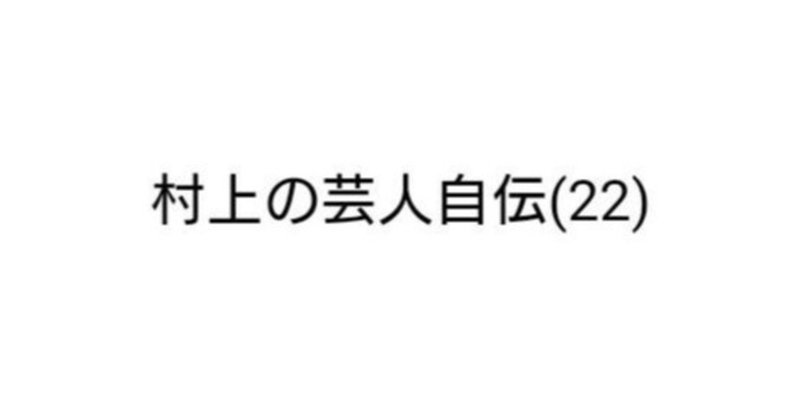
『レッドカーペット』と僕 〜その4〜
芸人自伝、今回で22回目です。
ゾロ目ですね。
僕はゾロ目が好きです。
何故なら、僕が世界で一番尊敬していると言っても過言ではない“キングカズ”の背番号が「11番」だからです。
じゃあ、11回目の時に言えよという声も聞こえてきそうですが…
いずれにせよ、三浦知良というプロサッカー選手のことが僕は大好きです。
そんなカズさんの偉業を話し始めたとしたらキリがありません。
カズさんの人生のどこを切り取っても、それは金太郎飴みたいなもので、どの側面にも“偉業”と書いてあるくらいでしょう。
仮に、カズさんの『プロサッカー選手自伝』なんてものがあったとしたら、1111回でも収まらないに違いありません。
そこで、めちゃくちゃ唐突ですが、カズさんの過去に残した言葉を紹介させてください。
プロとして、スターとしての覚悟みたいなものがそこには詰まっていて、これを今読んでくださっている仕事をする全ての人(学生だって勿論)に刺さる言葉だと思うので、はい。
高校1年生の時に三浦知良少年は、プロサッカー選手を目指すためサッカーの本場ブラジルに留学するという決意を胸にしました。
そのことを当時の監督に相談した時の話です。
「ブラジルでプロになるなんて99%無理だ」
ブラジル挑戦を打ち明けた後、サッカー部(静岡学園)の監督にそう一蹴されたそうです。
しかし、それに対し三浦少年はこう答えました。
「1%あるんですね?じゃあ、その1%を信じます」
当時、弱冠15歳ですよ。
どこでそのメンタルを培ったというのでしょうか。
しかもですよ、その後に有言実行してしまうわけです。
ブラジルで本当にプロサッカー選手になってしまうのです。
なんて、カッコいいのでしょうか。
その後、皆さんもご存じの通りカズさんはプロサッカー選手として大活躍するわけですが、今も尚53歳という年齢で(子どもの歳と同じくらいの選手と共に)現役のJリーガーとしてプロ生活を過ごしています。
その功績によって、最年長プロサッカー選手のギネス記録を自分で何度も更新しています。
そんなカズさんに心のない言葉をかけた記者が過去にいました。
10数年ほど前、カズさんが勿論プロを続けていた時のこと。
ある記者が「カズさんが全盛期の時は…」みたいな話を切り出したことがありました。
そこで、すかさずカズさんはこう返しました。
「全盛期?これからだよ」
痺れることしかできません。
僕も愚かなもので、それを聞くまでは全盛期なんてものは人が決めるものだと勝手に思っていました。
しかし、 それは僕の完全なる勘違いでした。
全盛期、それは自分で決めることなのです。
諦めたらそこで試合終了です。(バスケの話を引用するな、ややこしいな)
とにもかくにも、カズさんの口から放たれた数々の金言に僕は何度も勇気づけられてきました。
僕は仕事をする上で、いつもキングカズという国宝に“プロフェッショナル”の何たるかを教えてもらっています。
と、芸人自伝とはかけ離れた話をしてしまいました… と言いたい所ですが、そうでもないんです。
僕が芸人として、プロとして生きていく上でどうしたってキングカズの不屈の精神の話は切り離せるものではないのです。
カズさんは日本サッカーに幾度となく貢献して来られていますが(勿論これからも貢献し続ける方です)、その内の1つの例が1993年Jリーグ元年の出来事です。
その年、ドーハの悲劇を経験したカズさんはJリーグ初代年間MVPに輝くのです。
それは、三浦知良選手が26歳の時のことでした。
それから14年後。
その時のカズさんと同じ年齢であった26歳の僕は、何をしていたか。
ここからは、僕のお話。
2007年、夏。
場所は、お台場フジテレビ。
僕(しずる)は、生まれて初めてゴールデンのテレビ番組でネタ収録に臨んでいました。
その番組の名前は『爆笑レッドカーペット』。
華やかなパネルセットの裏でスタンバイしていると、司会の高橋克実さんが声高に僕らの名前を呼びました。
「甘酸っぱい青春コント!しずる!」
池田「(村上の手を引っ張り)こっちこいよ、村上!お前ここまで来て逃げるって訳じゃねぇだろうな!」
村上「俺、やっぱりできねぇよ!」
池田「何言ってんだよ!お前がやらなくて誰がやるってんだよ!」
村上「わかってるよ!でも、池田!今の俺にはそんな力どこにも残ってねぇんだよ!」
池田「バ、バカヤロー!(村上、殴る)」
村上「何すんだよ…」
池田「テメェの順番なんだよ、視力検査!(遮眼子を出す)後ろつかえてんだよ!」
村上「でも、やっぱり俺には無理だよ!」
池田「なんでだよ!」
村上「俺、あんな凶器かけたくねぇんだよ!」
池田「凶器って、メガネがそんな怖ぇのかよ!」
村上「そうだよ!俺はもう視力なんてどうでもいいんだよ!ほっといてくれよ!」
池田「おい!そんなこと言うなよ!」
二人もみくちゃになり、村上が倒れポケットから何かを落とし、池田がそれに気づき拾い上げる
池田「ブルーベリー!?視力がどうだっていいって言ってたお前がブルーベリーを生で!?」
村上「(池田からブルーベリーを奪い取り)そうだよ!お前に俺の気持ちわかんのかよ!ブルーベリーに裏切られた気持ち、お前にはわかんねぇだろ!チ、チクショー!(ブルーベリーを蹴飛ばす)」
池田「そうかい、そうかい。じゃあ、俺がやるまでだ!」
村上「勝手にしろよ!(後ろ向く)」
池田「(両手で両目を押さえて)見えません」
村上「何言ってんだよ、お前目良いはずだろ」
池田「見えません!見えません!」
村上「ふざけんなよ!(振り返って池田の様子に気づく)池田ー!」
池田「次左目いきます(両手をクロスして両目を隠す)、見えません」
村上「当たり前だろ!(池田の両手を解く)どういうつもりだ!」
池田「テメェが眼鏡かけるってんなら、俺もかけるまでだ」
村上「池田ぁー!(溢れるように泣き出す)わかったよ、俺やる!やるよ!」
池田「やっと昔の村上に戻ったようだな。おかえりなさい!」
村上「よし。(視力検査しようとするも)見えません… 涙で前が見えません!」
池田、村上を抱き締める
それをきっかけにして、足元のレッドカーペットは動き出し抱き合った僕らを上手袖へと運んでいきました。
程なくしてレッドカーペットが止まり、袖裏に下り立つと感じたこともない興奮が僕を襲いました。
無抵抗の僕はみるみる内にその渦の中に巻き込まれ、溺れる一歩手前まできていました。
それに気付いた僕は慌てて酸素を胸いっぱいに吸い込み、何とか息を吹き返しました。
体全体が心臓になったのかと錯覚するほどに、脈が全身を打ち続けました。
胸が何物かわからないもので占領され、張ち切れそうになりました。
その時、山頂のポテトチップスの袋の気持ちが痛い程よくわかりました。
ボーッとした頭が徐々に正常を取り戻していく中、レッドカーペットの上での記憶がゆっくりと甦っていきました。
すると、さっきまで真っ白だった頭の中にお客さんが手を叩いて笑っている映像が浮かび上がってきました。
ん?
ウケたのか?
恐らく、ウケたぞ。
いや、かなりの確率でウケたと思うぞ。
おいおいおい、こりゃ完全にウケてたぞ!
そのようにして、僕は「しずるはウケたんだ…」と段々と実感していきました。
『視力検査』で間違っていなかった、僕はそう思うとようやく胸を撫で下ろすことができました。
ふと、横を見るとピンクカーペットのネタ見せで最初にネタを見てくれたディレクターの原さんが笑顔でこちらを見ていました。
ありがとう、原さん。
全ての始まりはあなたからです。
なぁ、池田。
ん、池田…?
池田の姿はもうそこにはありませんでした。
彼は、どのタイミングでどこに行ったのでしょう。
わかりませんが、楽屋に戻ってお弁当を食べていたかもしれません。
でも、そんな周りの風景が僕の視界に戻ってくるとようやく気分を落ち着かせることができました。
そこで、僕はあることを思い出しました。
コント中のあるワンシーンです。
それはどのタイミングかと言うと、僕がブルーベリーを蹴った瞬間。
何故その場面が僕の頭を過ったのか、その答えは僕がブルーベリーを蹴ったその先にありました。
視聴者から見て右側に立っていた僕はブルーベリーを蹴る際、画面の右外目掛け足を振り上げていました。
「その方向には誰かいたぞ?」
…
「今田さん…?」
それを思い出したすぐ次には、ブルーベリーを蹴り飛ばした直後の画(え)がバババッとフラッシュバックしました。
振り上げられた僕の右足。
その足の甲にバウンドし、ふわりと浮かんだブルーベリー。
そして、その向こう側には手を叩いて笑う今田さんの姿がありました。
舞台袖でその記憶を確かに手繰り寄せた時に、僕のアドレナリンの中のアドレナリンが爆発的に噴出しました。
素人時代、テレビ画面のあちら側から僕のことを何度も笑わせてくれた“今田耕司”という芸人さんが僕たちのコントで笑っているという事実に鼻の頭がにわかにジュンと音を立てました。
それと同時に、テレビの中の偉大なる人が笑ってくれたことによって僕の体がギューンっとテレビの内側へと引き込まれていく感覚を覚えました。
「あ、俺テレビの中に入れたんだ…」
その前にピンクカーペットに2回出演してはいましたが、テレビに出られたとちゃんと実感できたのはレッドカーペットに流されたその時が初めてだった気がします。
細かく言うとその時点ではまだ収録段階なので、実際にテレビに出たと言えるのはその後の放送でということになるのですが、僕の中ではあのスタジオで今田さんが見せてくれた“拍手笑い”がテレビに出たんだという揺るぎのない証となりました。
オンエア後にそれを確かめたくて、録画してあったそのシーンを111回は巻き戻して煙が上がるまでその目に焼き付けた程です。
こんなことを言ってはなんですが、“満点大笑い”や“大笑い”、“中笑い”という評価は二の次でした。
あの時の今田さんの笑い声と手を叩いた音は、今でも僕の耳に残響しています。
そんな異様なテンションを抱き抱えたまま、僕は喫煙所へと向かいました。
その時に吸い込んだタバコの煙は格別に美味しかったような、何の味もしなかったような、そのどちらでもあった気がします。
そして、僕はまた思いました。
「俺、フジテレビにいる」
しかし、そんな中、ある大事なことを忘れていたことに気付きました。
“カムバックレッドカーペット”の存在です。
この番組ではパネラーさんのコメントなどを参考にスタッフさんが決める“お代わり指名”システムがありました。
これを読んで下さっている皆さんはご存知かと思いますが、1度目のネタの出来が良ければもう1度ネタができるチャンスが巡ってくるというものです。
その時、僕は正直“お代わり”を意識しました。
手前味噌ですが、ウケは確かなものだったという自信がありました。
第一に、今田さんがあれだけ笑ってくれてもいました。
僕は、思い立ったように喫煙所を出るとセットの裏に向かい池田を探しました。
そこで見つけた池田も考えることは一緒のようでした。
僕たちは他の芸人さんから隠れるようにして、スタジオのより奥も奥へと移動しました。
これから二人だけの秘密会議が始まることは、僕も池田もわかっていました。
それと並んで、セット裏の向こう側では芸人さんによるネタ披露の1周目が終わろうとしていました。
それが済んでしまえば、スタッフさんによる“お代わり芸人”決定会議が始まります。
そうです、“カムバックレッドカーペット”に選ばれた芸人が2度目のネタをやる時間がすぐそこまで来ていました。
その上でしずるは何故、集まったか。
その段階で僕たちは“お代わり”が来た場合のネタを最終的に決められていなかったからです。
出番が終わり一息つくまでは、目の前の1本目のコントしか頭になかったのです。
そのせいで、僕らは早急に2本目のネタを決めなければいけませんでした。
僕と池田はスタジオの端っこの暗がりのところまで到着すると、同時に足を止めました。
そして、僕は口を開きました。
しかし、それと同じくして池田の声も聞こえてきました。
「2本目さ…」
「2本目なんだけ…」
僕らは同じタイミングで“お代わり”のネタを何にするか提案しようとしていたのです。
「ん?」
「何?」
互いに、牽制しました。
二人の間に少しだけ不穏な空気が漂った気がしました。
そして、その11秒後。
僕たちはコンビを組んで4年目にして初めてとなる大喧嘩をすることになりました。
と、今回はここまでです。
今思い出しても思い出したくない、スタジオ裏の二人のお話の始まりで今回の記事は終わりです。
その前の至福の喜びからのこれですから、この日の僕の感情の揺れはとんでもないものでした。
ちなみに、この芸人自伝を初めてこうやって最後まで読んでくれた方もいらっしゃるのですかね?
これまでの21回、こんな感じでいつも書いてきました。
以後、お見知り置きを。
果たして、しずるはその後どんな会話をして自分をどう落とし込んだのか。
この続きは23回目の芸人自伝にて。
それでは、また後日。
あなたのお心をもし本当に気が向いたらでいいのでお与えください! そしたら、また自分の言葉に責任を持って皆さんに発信できます! ここを僕の生活の一部にして行きたいと思っておりますので!
