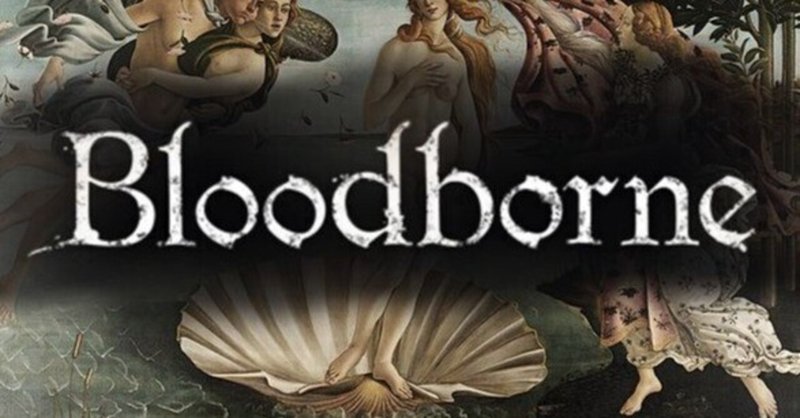
ブラッドボーンと西洋文化の血脈 序
事実など存在しない、存在するのは解釈だけだ。
先日、発売から七周年が経ち、未だファンも多く繰り返しプレイされいるであろう、ブラッドボーン。
しかし実のところこのゲームのストーリーというものを知っている、分かっていると豪語できる人間は、ゲームの難易度という文脈で度々引きあいに出される、同作のガスコイン神父のトロフィーの割合よりもずっと低いのではないでしょうか。
初めてこのゲームをプレイしはじめNEW GAMEを選んでOPをみても、突然見知らぬ車いすの男に話しかけられて輸血をはじめられ、燃える獣の幻覚を見せられるだけです。
デモンズソウルやダークソウルのような導入の話もなく、冒険の指針、あるべき目標として示されるような伝説の存在も、英雄の軌跡も示されてはいません。プレイヤーはちりばめられた断片的な情報を探しながら、この獣の潜むゴシックの尖塔そびえる森の中を、ただ己の力で切り開いていくのみ。
生き残ったかろうじて正気のNPCたちとの会話にも物語と言えるほどの流れは存在せず、この街の由来や少々の身の上を語られるだけで、次に会う時には獣の本性を見せるかもしれません。
こうしたまったく無秩序にも思えるゲーム内容を鑑みて、あるいは自分なりに解釈をし、このゲームの中に物語を見出そうとする考えも、まったくナンセンスとは言えないでしょう。

ほとんどの場合このゲームを始めてプレイする上位者ではない方たちは、武器もないままヨセフカ診療院で目覚め、その入り口で犠牲者を貪る罹患者の獣に殺され、狩人の夢にたどり着きます。
打ち捨てられたように座ったままの人形ちゃんへはこの時点で話しかけることはできず、使者たちに武器を渡されると、工房の中で車いすに座った助言者ゲールマンをOPのヤーナム民と思い込んで話しかけるでしょう。
しかし、この時点で彼はほとんど役に立つことは話してはくれず、仕方なく墓からヤーナムの街へと戻り、半ば獣となり果てたヤーナム民たちを屠っていきます。
先ほど例に出した、このゲームのある種チュートリアルともいえるガスコイン神父。どの時点で啓蒙を得て人形ちゃんにレベルアップをしてもらえるようになるかはそれぞれですが、このボスにたどり着いた時点でも、やはりほとんどの人はなすすべなく彼に殺されてしまいます。

この異教の神父との闘いに学び何度も何度も彼に狩られながら、私たちは人型の相手への戦い方、リズムのようなものを掴んでいきます。
そして、後半からの吹き飛ばし効果のある攻撃の連続。起き上がりからの最速の入力でのローリングを狙っての、いわゆるロリ狩りの飛びかかり攻撃への対処。相手の攻撃を読んで巨躯の相手の懐へと飛び込んでいくような”ヤーナムステップ”を習得し、ようやく私たちはこの町での歩き方を学びます。
この強大な敵の狩りに成功しその先へと進む鍵を得ると、そこが荒々しい人の奥底に潜む生命の力=オド/オドンの眠る、古い墓だと示されます。
そのカギによって奥の格子扉を開け墓の先の梯子を上ると、厳かで小さな教会の内部へと続き、さらに三つの扉へ進むことが出来るでしょう。

一つは暗闇からこちらを窺いつつも、火におびえる獣たちの住まう、旧市街への道。
一つは青ざめた巨躯の男たちが、灯りを頼りにこちらを探して回っている、聖堂街への道。
最後の一つは、車いすの老人や市民の服を着たヤーナム民たちが何かを探している、上層区への道。
多くの場合ではゲールマンの教えにしたがって、まずは獣への扉を進み旧市街へと進みます。彼の助言のとおりにその焼き捨てられた市街を探索すると”トゥメルの聖杯”を得て、今度は「オドン教会を上りたまえ」と助言をうけます。
しかし開いた扉から上層への塔をそのまま進んでいくと、”輝く剣の狩人証”を得ることが出来ますが、さらにその奥の扉は閉じています。我々が道を外れその崩れかけた塔を下へと降りると、ようやく新たな道が開けて聖堂街の奥へと進むことが出来ます。
不吉な三叉の柱を持った教会の使いたちに迎えられ、豪奢な聖堂でヤーナムの教区長と出会いその聖なる獣を狩ると、さらに禁じられた森の失われた学舎への道を開くことが出来、いよいよこの街の影と対峙し先の上位者へとつながる”眷属の死血”を得、そしてこの街の秘匿を破ることが出来ます。
これら”聖杯”と”剣”と”聖なる血”を求める探究は中世の騎士道物語のようなモチーフで、教会からの獣への道、聖なる道、上昇への道とは何か求道的な啓示を表しているようにも考えられないでしょうか。
ただし、その先の物語はそうした物語的なモチーフ、人や獣の境界、理性と狂気、様々なものが崩れていき、ゴシックホラーのように思われた世界観がラブクラフトの書いたような、コズミックホラーの世界観へ。分かりづらいとされるフロムソフトウェアの作品の中でも、屈指の難解なエンディングたちへと続きます。
ヤーナムの夜明け、遺志を継ぐもの、幼年期のはじまり。SF小説をオマージュしたとされる題名のついた三つのエンディングも、それぞれ解釈がなされているのですが、はっきりとその意味が語られることはありません。
なんとなくプレイして感じることが出来るのは、この医療の街とされるヤーナムが何かの病理によって侵されていて、そのためにある種の苦悩を抱えていたという事。彼らはそうした病に穢された人の身を脱ぎ捨てて、精神的な上昇を願っていたという事。
そして、そうした思想の元に作り上げたヤーナムの街が、モデルにしたと思われるヴィクトリア朝のロンドンや百塔の街と呼ばれるプラハ等、現実の街並みよりも病的なまでに多くの石造りの塔や彫刻、悩み苦しむ人々の像に彩られているという事です。

ストーリーの最終ダンジョンとなる、メンシスの悪夢に存在するメルゴーの高楼。その名の通り、天上へと伸びた二つの巨大な建物と、その間を行き来する橋につながれたステージですが、その中腹で次の橋へのカギを守っているボスキャラクター悪夢の主ミコラーシュは、そうしたヤーナムの精神を体現してもいるようにも思えます。
彼は自身の傾倒するメンシス学派の思想によってビルゲンワース学徒の制服を着こみ、自らを探究の徒と気取っています。同時に鳥かごのような、堅牢な塔のような”メンシスの檻”をかぶって、俗世との隔絶を図ろうとしています。
しかし彼自身はもはや狂人のような目つき、ふるまいをし、とても理性的な学びなどできているようには思えません。ふざけているのか、半ばそうなりかけているのか、獣のような遠吠えを上げて主人公である狩人を翻弄し、最後には情けない嘆きの声とともに悪夢から消えていきます。

ああ、ゴース、あるいはゴスム
我らの祈りが聞こえぬか
白痴のロマにそうしたように、我らに瞳を授けたまえ
もはや志していた学びの精神、理性の探究など忘れてしまったかのように、ゴースと呼ばれる謎の上位者の名を叫び、祈り続けているミコラーシュ。彼自身が持っている鍵によってメルゴーの高楼を上り、その上で行われている上位者を呼ぶ儀式に近づくこともせずに、入り組んだ書庫の中をふらふらと彷徨っています。
はたして彼や彼の尊敬するビルゲンワースが望んだ”瞳”とは何だったのか。何が理由で、上位者たちは赤子を失ってしまったのか。いったい何によってこのヤーナムの街は呪われ、そして病んでしまっていたのでしょう。
分かることは、この悪夢の主ミコラーシュがメンシスの儀式を行うよりはるか以前より異変は起こりはじめていて、そしてそれ以降の誰によってもこの悲劇は未だ止められてはいないという事です。

ありうべからざることではないか。かの狂いたる学徒は書庫の中にあって、未だついに耳にしたことがないのである。 ――神は、死んだ! と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
