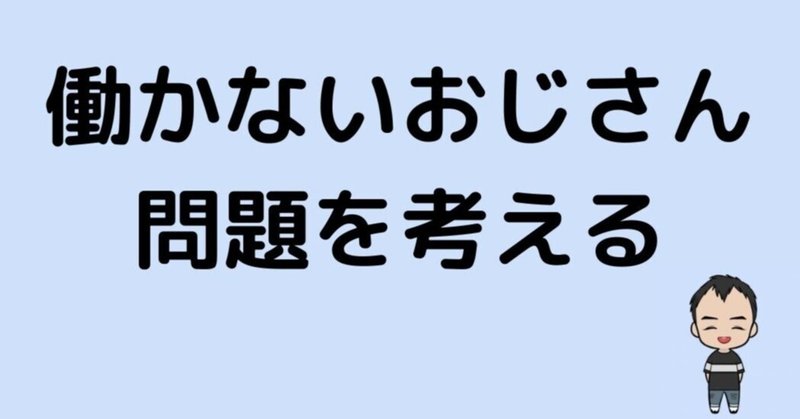
働かないおじさん問題を考える
今回は「働かないおじさん問題」についてです。
働かないおじさん問題については多くの本が出版されていますし、TwitterなどのSNSでもよく出てきますよね。特に若い人にとっては働かないくせに高給をもらっているおじさんに対する怒りは大きいでしょう。
私が若い頃からこのようなおじさんはいましたので、それよりもっと以前から存在していたでしょうし、おそらくこれから先もいなくなることはないと思います。
ではなぜ働かないおじさんが発生するのでしょうか?
ただ単に本人たちにやる気がないだけなのでしょうか?
今も昔も、そしておそらく未来にも絶滅せずに存在するということは、
おじさん達本人のやる気にだけ原因を求めるのは短絡的な考え方であり、そこにはもっと根深い構造的な理由がある
というのが私の見解です。
今回は働かないおじさんが生まれてしまう原因と、今はそんなおじさんに嫌悪感を抱いている人たちも将来自分がそうなってしまう恐れがあるんだよ、ということについて記事にしてみたいと思います。
働かないおじさんが生まれる理由
働かないおじさんという言葉を使ってきましたが、最初に言っておくと「働かないおじさん」というよりは「働けないおじさん」という表現の方が正しいと私は思っています。
「働かない」というと自分から働くことを拒否しているという意味になると思います。この手の働かない人はおじさんに限らず存在しますし、おそらく世間一般に言う「働かないおじさん」という概念とは違うと思います。世間でよく揶揄される「働かないおじさん」というのは「高い給料をもらいながらも何をしてるかわからない窓際族の高齢社員」という意味合いだと思います。であれば、「働かないおじさん」と呼ぶよりは、「働けないおじさん」という表現が正しいように感じています。
なぜそのように思うか。
「働けないおじさん」が生まれる3つの原因に触れながら説明していきます。
体力的な衰えと環境変化が重なる
事務仕事が主な職場ならまだしも、体を動かす職場であれば年齢とともに落ちてくる体力はいかんともしがたいものです。激務で有名な職場であればなおさら、いつまでも若い頃と同じペースで仕事をするのは難しいでしょう。
そうなると今の職場で働き続けることは困難になりますから、職場を変えるか職務を変えるかのどちらかが必要になります。
また、入社してから定年退職を迎えるまでずっと同じ職場で働くという人もそう多くないと思います。その理由は様々ですが、人事異動などによって職場環境が変わります。職場環境の変化にその都度合わせていくことは口で言うほど簡単なことではありません。
別の部署に異動させることによって新たな経験を積んで成長してもらいたい、という名目で人事異動が発令されることは日常的な出来事です。部署の異動はなかったとしても、今までやってきたこととは違う職務を与えられたりします。
ですが、人事異動や職務変更というのは必ずしも明確な目的があって発令されるものばかりではありません。異動をさせることで何か良い効果があったらいいな、とか、彼ならうまく立ち回ることができる、という理由で発令されることがほとんどでしょう。はっきり言うと、もううちの部署では手に負えないからよそにお願いする、という理由であることも少なくありません。
人事異動でよくある理由が、「経験を生かして異なる分野で相乗効果を発揮してほしい」というものです。サッカーで言うところのコンバート(ポジションチェンジ)ですよね。
今まで攻撃をやっていた選手を守備的ポジションに変更することで、相手の攻撃選手が嫌がる守備をできるようになってほしい、というような理由です。ネガティブな理由ではなくても、このようなふんわりとした理由で人事異動がなされることはよくあります。
部署や職務が変わると、そのままの形ではこれまでの経験が使えません。これまでの経験を新しい職場でうまく使えるように変形、変質させていく必要があります。ですが、これが難しい。
どうしても人は従来のやり方で仕事を進めようとしますし、これまでの価値観で判断しようとします。場合によっては今まで毛嫌いしてきた仕事をやらないといけなくなることもあるでしょう。さらに異動先の部署に成長期真っただ中の若手がいたら、自分に重要な仕事が回ってくる可能性はかなり低いと言わざるを得ません。
このように、サラリーマンであれば、自分が望んでいなかったとしても体力的な理由や職場都合による異動や職務変更を命じられることは珍しくありません。
そこでうまく波に乗れる人であればもちろん問題はないのですが、うまく環境変化に対応できずに輝きを失っていってしまう人もいます。このようにしてスパイラルダウンしていってしまった結果、働けないおじさんになってしまうという構図が説明できます。
若い人にチャンスが回っていく
会社側がおじさん達に適した仕事を与えられていないというのも働けないおじさんが発生する大きな原因の1つです。
サラリーマンには2つのステージがあります。成長期と停滞期です。
若い人は成長期を過ごすことになります。人によってその傾きは異なるにせよ、時間が経つにつれて能力、経験値は上がっていきますよね。一方のベテラン社員は停滞期に入っていきます。できることが増えてくる代わりに、あまり大きな成長は望めなくなります。
ここで新しく大きなプロジェクトが発足したとします。もしあなたが上司であれば成長期真っただ中の若手と停滞期に入っているベテランのどちらにこの仕事をやらせるでしょうか?
そつなくこなしてくれそうなベテランに仕事をお願いするという人もいるでしょうが、多くの上司は成長の傾きが小さくなってきているベテランではなく、成長期の中で大きく伸びている若手に任せようとするのではないでしょうか。成長するためには多くの経験を積むことが必要です。上司としては良い経験が成長を促すことを知っているので、できるだけやりがいがあってダイナミックな仕事を若手にやらせようとします。
中には妥協策として若手の補佐役にベテランを付ける人もいます。ベテランの経験値を使って若手の成長とプロジェクトの成功を両立させようとするわけです。ただ、これをやってしまうとあまり良い結果にはならないことが多いと思います。
ベテランが完全に黒子に徹することができればうまくいくかもしれませんが、経験値のあるベテランが何も言わずに黙っているのはなかなか難しいことです。自分ではアドバイスのつもりで若手に話をしているのに、若手からすると何でも口を挟まれてしまうと受け取ってしまうこともあるでしょう。
ベテランに仕事を指示するのは若手にとってもやりにくいでしょうし、事あるごとに口を出すベテランに対して、自分の好きなようにやらせてほしいとうっとうしく感じてしまうのです。
ベテランに対しても大きなプロジェクトを与えられればいいのですが、残念ながら会社にはやり甲斐のある大きなプロジェクトはそれほど多くありません。たいていは同じようなことの繰り返し業務です。自分が成長できていると感じられない仕事を繰り返しやらされたとしたら、やる気が下がってしまうのも無理はないでしょう。
そうなってくると今と同じ部署にいるのがつらくなってくる人もいるでしょう。これから先、ずっと同じことをやらされてしまうと思えば、そのように考えてしまうのも無理のないことです。
また、上司にしてもくすぶっているベテランがいると周囲に対して良い影響を与えませんので、どこか新天地に異動させて新しいチャンスをつかんでほしいと思うはずです。実績があるベテランならなおさらでしょう。そうなると先に説明したように、異動による新しい環境になじめずに働けないおじさんになってしまう、というところにつながってしまいます。
管理職になって戸惑う
人事異動以外で社員に成長する機会を与える方法として昇進があります。つまり管理職になることです。プレイヤーとしての仕事が優秀であるならば、その人にふさわしい地位と報酬が与えられるべきです。それについて異論を挟む人はいないでしょう。
ですが、よく言われるようにプレイヤーとして優秀だったからといって、管理職、マネージャーになっても継続して優秀でいられる保証はどこにもありません。なぜならプレイヤーは使われる側、マネージャーは使う側として、求められる能力がまったく異なるからです。
プレイヤーの頃は自分で直接手を出すことができますし、何も考えなくても上司から仕事を与えてもらえます。一方の管理職は自分で動くよりも部下を動かす力が求められますし、最適な仕事の配分を考えないといけません。そのギャップに苦しむ人は少なくないでしょう。
プレイヤーの時は比較的仕事の目標が明確ですよね。自分が何をやったらいいかわからない、という人はあまりいないと思います(もしそういう人がいたら、若くして働けないおじさんになっているかもしれませんよ)。ですが、私の経験からしても管理職というのはプレイヤーと比較して、答えがわかりにくい仕事が多いんですね。人事なんてその最たるものです。何が正解かなんてわからない。自分が頑張れば頑張るほど良くなるようなものでもありません。そういう中で自分を見失わずに活躍できる人はそう多くないでしょう。
ピーターの法則をご存じでしょうか?
「人は無能になるところまで出世し、やがて無能だらけになって会社は衰退する」
という法則です。
もう少し内容を説明します。
たとえばプレイヤーとして優秀だった人が課長になるとします。課長になったら管理職として今までと違う能力が求められるわけですが、プレイヤーとしては優秀だったのに課長になった途端にそれまでの能力を発揮することができなくなることがあります。その理由はこれまで述べてきました。
課長としてはまだ有能であったとしても、部長ではまた異なる能力が求められるため、そのタイミングで無能になってしまうかもしれません。同じく、部長では有能であったとしても統括部長で無能になってしまうかもしれない。
つまり人は出世するとどこかで能力に合わない仕事をすることになってしまうので、必ずどこかで無能になる、という法則です。そうなると会社の管理層、経営層は無能な人の集まりになり、だから会社が衰退するのだ、という論理です。
こうしてかつては優秀だった人が無能になってしまった結果、働かないおじさん、何をやっているかわからない役に立たない管理職が生まれる、というメカニズムも確かに存在するんだろうなと思います。今は働かないおじさんに見える人でも昔はバリバリ仕事をしていたんだよ、と聞いて驚くということも珍しいことではありません。
特に管理職の場合、優秀な部下に恵まれるかどうかがかなり自分の業績を左右します。部下を動かす立場であるのですから、当然ですよね。部下だけでなく、職場の文化もあります。考え方がしっかりした部署とそうでない部署がありますので、運が良ければこれまでの貯金だけで過ごすこともできるでしょうし、運が悪ければ借金と言ってもいいような負債を背負わされることもあります。
私のような技術系の部署であれば人の問題だけでなく、いつまで経っても新しい設備を買ってもらえず、古くてポンコツな設備をいつまでも使わされているというようなハード面で受難することもあります。そういう恵まれない部署を預かったら最後、どれだけ優秀な人でも日の目を見なくなってしまいます。
個人的な感想ですが、よくサッカーや野球の監督が成績不振でクビになる時のインタビューで
「選手はよく頑張ってくれた。すべての責任は私にある」
というような発言をします。ですが、これって本心から言っているのかなあといつも疑問に思ってしまいます。監督の能力によってチームは良くも悪くもなるとは思いますが、結局戦うのは選手ですし、チームを経営している人たちにだって本当は責任があるわけです。それらの責任を一手に引き受けて辞任させられる監督・・・本当はもっとグチを言いたいんじゃないかなと思ってしまいます。
話がそれましたが、こうして自分が身に付けてきた経験をうまく使うことができなくなり、やがて働けないおじさんとして扱われてしまうわけです。
働かないおじさんにならないようにするためには
ここまで働けないおじさんが生まれる理由を述べてきました。
日本の多くの会社では同じような構造を持っているため、誰しもが働けないおじさんになってしまう恐れがあります。
では、どうすれば働かないおじさんになるのを避けることができるかについて説明していきたいと思います。ここで書いていることは私が実際に働けないおじさんになった人を見てきて感じたことや、働けないおじさんになりそうな匂いがする部下に対して伝えてきたことです。
働かないおじさんになりたくない若手へのアドバイス
私から若手に送りたいアドバイスは、周りの人との良好な関係性を築くことを若い頃から意識する、ということです。
これまで述べてきたように、どんなに優秀な人も自分の考えと会社の考えとの間にあるギャップをうまく超えることができず、働けないおじさんになってしまう恐れがあります。ましてや会社というのはピラミッド構造になっているので、一握りの優秀で運の良い人を除いて、ほとんどの人がピラミッドの外に出てしまうのは仕方のないことでもあります。
そうなった時に偉そうにしていた人はどうなるでしょうか?勢いがある時や権力のある地位にいる時はそんな人の言うことでも周りの人は聞いてくれるかもしれません。ですが、権力がなくなってしまった時にどうなるかというと、できるだけ静かにしていてもらえる職場に異動させられたり、あまり周囲と関わることのない閑職に回されたりします。
優秀な人ほど若い頃から周囲に対して尊大な態度を取ったり厳しい態度で接する傾向があるので、いざその人に力がなくなると周りからは疎ましがられます。
私の知っているAさんは非常に部下に対して厳しい要求をする人でした。Aさんは優秀ではあるのですがあまりに部下に対して厳しいため、体調を壊してしまう人が何人もいたようです。Aさんの下で働いていた何人かに評判を聞いたことがあるのですが、とにかくAさんが嫌いだと言っていました。
そんなAさんですが、海外駐在に出たところまでは良かったのですが、日本に帰ってくるやどう見ても閑職としか思えない部署に配属されました。駐在から帰ってくる時は基本的に元居た部署か、それに近い部署に戻ることが多いと思いますが、受け入れ側から拒否されてしまったのだと推測しています。想像の域を出ませんが、駐在に派遣された理由もAさんを排除するためという思惑があったと思われますし、派遣が決まった時点でこうなることは決まっていたのでしょう。
こうなってしまうと、いくらAさん自身が頑張ろうとしても、Aさんと関わりたくない人が多いのでチャンスすら巡ってこなくなってしまいます。結局Aさんはいろんな部署の定期報告会に用もないのに参加して、「資料に管理番号が書いてないから書いてください」などと小言を言う程度の人になってしまいました。
そうならないためには、日ごろから周囲の人と良好な関係性を持つように努めることが重要です。良好な関係さえ築けていれば、たとえうまく自分の経験を発揮できなくなってしまったとしても、また、階層ピラミッドの外に出たとしても周囲が放っておきません。若手からはアドバイスを求められるでしょうし、周囲の役に立つ仕事を任されるなど、とにかく周りから頼りにされる人になるでしょう。何か自分からやろうとしても周囲の人は協力してくれるでしょうし、上司も好きなことをやらせてくれる可能性が高くなります。
これも実際の話ですが、50歳を超えたBさんは設備操作のプロフェッショナルとして周りからとても頼りにされています。そして、50歳を超えた今でも若手に混じってバリバリと現場で仕事をしています。もう楽にしてくれよー、なんてことを言いながらも若手を教育しないといけないという使命感を持って働いてくれています。
私はいつも40歳を超えたくらいの部下に、「仕事を選ぶな。偉そうにするな。頼まれたことは何でもやれ。そうしないと、自分の居場所がなくなるぞ」とアドバイスを言うようにしています。特に周囲から少し煙たがられているような人には強めに言うようにしています。これはAさんやBさんのような人を多く見てきて得た確信に近い感覚です。
働かないおじさんになりかけているベテランへのアドバイス
次に、すでに自分が働かないおじさんになってきてしまっていると感じている人に対する私からのアドバイスを伝えたいと思います。
それは、とにかく遊べ、ということです。
もちろん、言葉通りに仕事をせずに本当に遊んでいてはいけません。それこそ働かないおじさんになってしまいますから。
ではどういうことかというと、自分の特技や興味、経験を生かして何かを始めなさい、ということです。若い頃からずっと仕事をしてきて、何らかの経験値を積んでいるはずです。俺には新しい職場で生かせる経験値なんてないと思う人もいるかもしれませんが、10年、20年と仕事をやってきて経験値がないなんてことはありません。
もちろん、経験値がそのままの形で使えない場合もあるでしょう。ですが、そこから少しだけでも勉強をして新しい知識を身に付けたり、周囲の人に働きかけて新しい仕事を作り出せば必ず自分でやれる仕事を見つけることができると思います。
先述のBさんですが、実は今の部署に来るまでその設備をちゃんと触ったことがなかったそうです。ですが、他の設備を触ったことがあったのでそこから勉強をしたり、実際に設備を触る機会を増やしていくことで、いつのまにかこの設備はBさんに任せばおけば大丈夫と言われるようなポジションを築くことになったそうです。この設備を触ったことがないからできない、といって努力を怠ればBさんが現在のように周囲の人に頼られる存在になることはなかったでしょう。
自分が新しいことを始めても役に立つかどうかがわからない。そんな状態で始めてもいいのだろうかと不安に思うかもしれません。ですが、自分から動き出して何かを始めたとしても上司に止められることはないと思います。
なぜなら、働けないおじさんの扱いというのは上司にとっても頭を悩ませる課題だからです。働かずにじっと机に座っていられるよりは、役に立つかどうかがよくわからなくても自分で動いてくれることは上司にとっても都合が良いのです。
若い頃にやりたいと思っていたけど忙しくてやれなかったことや、昔から興味があったことに取り組めばいいのです。特に、過去に自分がやってきたことの中で困ったこと、うまくできなかった課題に取り組めば、それが解決できた時に必ず周囲の人にも喜んでもらえるじゃずです。
それがたとえメインストリームの活動ではなかったとしても、遊びだと思って今まで誰もやれなかったことに取り組めば良いと思います。きっとそのような課題は必ず存在するはずです。
まとめ
今回の記事のまとめです。
働けないおじさんは確かにおじさん自身にも原因がありますが、たとえ意欲的に仕事に取り組んでいたとしてもあれよあれよという間に自分自身もそうなってしまう恐れがあるということを述べました。また、そうならないためにどうすればいいのかということも私なりの意見を述べてきました。
「働かないおじさん」になる前に、「働けないおじさん」である期間が存在します。
自分には何もやれないと諦めてしまう人や、あるいは新しいことに手を出す気力がわかないと言う人は本当に働かないおじさんになってしまいます。「働かないおじさん」になってしまったらもう手遅れかもしれませんが、「働けないおじさん」でいるうちは自分の行動次第でその境遇を変えることはできます。
最後に、働けないおじさんを生み出さないために管理職の役割が重要であるということを述べたいと思います。
私が日ごろから思うことは、働けないおじさんを放置してしまっている管理職が多い、ということです。彼らを有効活用しようとせず、あきらめてしまっている。こういう管理職は、めんどくさいおじさんには何も言わず、黙って定年まで過ごしてもらおうと考えているのでしょう。
なぜなら、おじさんの扱いはとても面倒だからです。自信をなくしてしまっていたり、自分の処遇に不満を抱えている場合が多く、時には全然人の話を聞こうとしない人もいるでしょう。だからこそきちんと向き合わない管理職が多いのだと思います。
さきほど、遊べばいい、と書きましたが、実はこれがなかなか難しいことなんです。やらされ仕事をするのはそれはそれでつらいことです。ですが、自由にやっていいよと言われた時に本当に自由に動ける人というのはそう多くありません。自分が何をやっていいのか、何がやりたいのかがわからない人が実際にはかなり多いというのが私の実感です。自由にやらせてあげているつもりかもしれませんが、実際にはその自由を持て余してしまうがゆえに働けないおじさんになっているというのもよく見られる場面だと思います。
彼らを働かないおじさんにしないためには彼らに仕事を与え、自分で動き出せるようになるまで見続ける必要がありますし、彼らの声に耳を傾ける必要もあります。時には強制的に仕事を与えたり、厳しいことを言う必要もあるでしょう。それでもおじさん達に、自分は見ているよということを発信し続けることが求められます。
なんだかんだ言ってもおじさん達には経験があります。そんなおじさん達を有効活用できたとしたら、彼らは必ず良い戦力になってくれるはずです。そんな日が来ることを信じて、おじさん達と向き合える管理職が良い管理職であると言えるでしょう。
最後にもう1冊、本を紹介しておきたいと思います。
この本を読んだ時、俺が言いたかったのはこれだ!!と興奮しました。
働かないおじさんが生まれる理由は必ずしも本人たちのやる気がないわけではなく、構造的な理由があるという私の主張をよりわかりやすく、客観的に説明してくれています。
また、働かないおじさんにならないための処方箋を紹介してくれていますので、ベテランの人、ベテランの域に入ってきている人にとってはとても参考になる本です。自分が働けないおじさんになっていないか、自分でチェックしてみてください。
もしこの記事を読んで良いと思われたようでしたら、 コメントをいただけると励みになります
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
