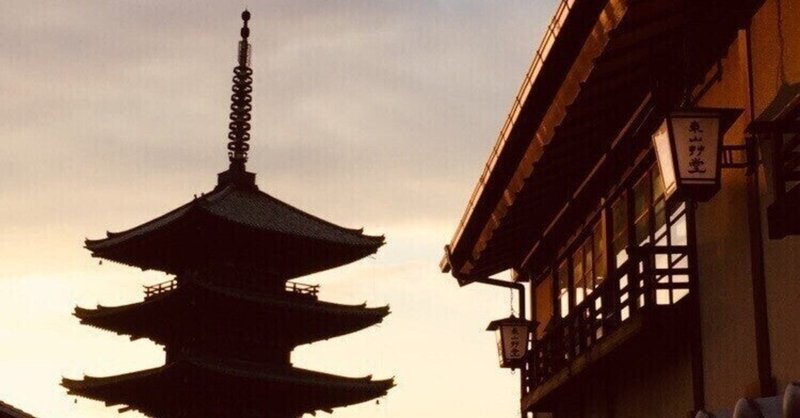
木造構造設計のお約束 その2
今日も、木構造ならではのお約束的なルールを書いていきます。
まず、ルート1なのに偏心率が要求されます。ルートとは、これも構造計算的な用語ですが、計算のやり方のことで、基本はルート1、ルート2、ルート3があります。数字が大きいほど複雑かつ精緻になってきます。RC造やS造のルート1は、偏心率は要求されません。簡易な計算です。ただ木造では、構造計算では偏心率が要求されます。しかもルート2以降は0.15以内に納めるというルールが法令にありますが、木造のルート1の場合は特殊で0.3以下となっています。このルールは在来軸組工法のルート1固有のもので(壁量計算でも偏心率0.3で計算できるが)、同じ木造でもツーバイフォーでは適用されません。
通し柱が強い、というイメージがあるかもしれませんが、木造軸組構法住宅の許容応力度設計では、通し柱に何か優遇的な何かはありません。太くしても同じです。木造の構造計算は壁で地震力を受ける形になっているので、このようになっています。通し柱の若干のメリットといえば、中間階の横架材上下に柱頭柱脚の金物がないことくらいです。おそらくもっと太くなれば話は違うと思うのですが、12センチくらいの通し柱で強くはなりません。むしろ梁を側面から取り付け通し柱の断面欠損が大きくなるので弱くなるかもしれません。
鉄骨などでも強さは違う規格がありますが、木造は同じ樹種でも等級があったり集成材、LVLといった加工によっても強度が違ってきます。また売っている樹種や規格はある程度絞られています。また樹種によって特徴が違います。これらを覚えるのが大変ですが、よく使うものは必ず覚えていてください。柱は木造の場合多く存在するので、強度はそれほど高いものでなくても大丈夫です。比較的強度が弱い杉などでも可能な場合が多いです。梁は、上階の柱を受けたり、スパンが広かったりすると太い材料が必要なうえ、曲げなどに強くなければならないので、ベイマツなどが好まれます。またレッドウッドの集成材も多く使われます。ロングスパンの場合、LVLといった特殊なものを使うこともあります。土台は、湿気に強くシロアリなどに食害されないものが良いです。薬剤が染み込みやすいベイツガなどが好まれますが、若干弱いので、耐水性防蟻性が高い、ヒノキやヒバも有用です。3階建ての構造計算では、土台のめり込みのエラーも頭がいたいので、めり込み重視でベイマツという選択肢もあります。他にも筋交いや母屋、垂木など多くの材料を使います。数が多いので価格も重要になってきます。
鉄骨造やRC造に慣れている方は、木造ならではのルールや、多くの部材に面食らうと思います。しかし計算ではそれぞれ許容応力度が複雑に定められていますので、確認申請後に樹種や規格の変更は難しいです。最初にしっかり定めて計算・設計することが大切です。
サポートしてくださると嬉しいです。 部分的に気に入ってくださったら、気軽にシェアかコメントをお願いします♪
