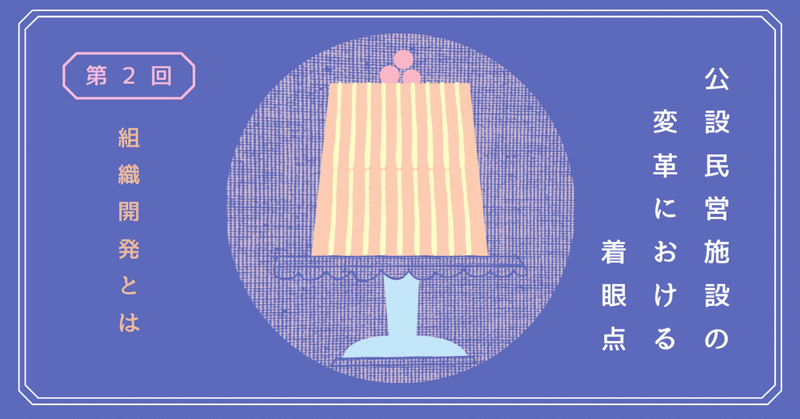
公設民営施設の変革における着眼点〜組織開発とは(第2回)
第1回で「コンソーシアム組織×指定管理者制度」で運営される施設は、「市 VS 指定管理者」という「縦」の構造的困難と、「指定管理者同士のすり合わせ」という「横」の構造的困難の両方に対処することが宿命となることを述べました。
白川は、この困難をなんとかできないかと思う中で「組織開発(OD: Organization Development)」といわれるアプローチに着目し、その実践者(=組織開発プラクティショナー)として何ができるのか、ということを当初から考えていました。
今回は、変革の「肝」となる理論のお話です。
組織とは〜①目標達成のための分業・職能の分化を前提とした概念
組織開発とは、戦略や制度といった組織のハードな側面だけでなく、人や関係性といったソフトな側面に働きかけ、組織を変革するアプローチのことです。
ここでいう「組織」とは「人が集まってなにかをやろうとしている集団」のことで、会社はもちろん、国や行政などのマクロなものから、身近な人間関係集団まで、広い範囲を指す概念です。
組織について、ODNJはこう記述しています。
組織(O)とは?
組織開発の有名な研究者であるエドガー・シャインは1965年に記した著書『組織心理学』の中で、組織を「ある共通の明確な目的、ないし目標を達成するために、分業や職能の分化を通じて、また権限と責任の階層を通じて、多くの人びとの活動を合理的に協働させることである」と定義しています。
共通の目標達成に向けて人々が協働する際に、人々が異なった役割を果たすこと(分業すること、権限と責任の階層化をすること)を通じて、その目標がより達成できるという前提が組織にはあるということです。
重要なことは「人が集まれば組織になるわけではない」という点です。
たとえば、横断歩道を行き交う人々のまとまりは組織ではありません。
組織は、共通の目的(目標)達成のために個々の構成員が自らの役割を果たしながら協働している(それが効果的に機能しているかどうかは別として)ことを前提にした概念です。
組織とは〜②組織とはシステムである
組織開発では、組織を「システム」と捉えます。
しかし、「システム」とは何でしょうか?
同様にODNJの説明から引用すると、こう記述されています。
一方、組織の定義として最も用いられているのは、経営学者のチェスター・バーナードによる「意識的に調整された、人々の活動や諸力のシステム」という定義です。バーナードが言及しているように、組織を考えていく際には、組織を「システム」と捉えることが大切になってきます。
ここでいうシステムとは、一般システム理論(フォン・ベルタランフィ)に由来する言葉で「相互作用する諸要素の複合体」という意味です。外界との境界線の中にある「ひとまとまり」がシステムであるとイメージしてみてください。
システムとは「相互作用する諸要素の複合体」です。
その中でも、組織開発が想定する典型的なシステムは、「人と人が相互作用する」システムです。
これについて、もう少し包括的に述べれば、組織開発ではシステムを「個人レベル」「対人間レベル」「グループ・レベル」「グループ間・レベル」「組織レベル」「組織と環境レベル」の6つに区別します(下図)。

出典:中村和彦「入門 組織開発 活き活きと働ける職場をつくる」
光文社新書(2015)p.67
要は、組織開発では、「同僚との人間関係」という小さな単位から、チーム・部署、組織全体という中〜大規模な関係性の単位、さらには任意の組織を越えて環境との関係性に目を向けるなど、非常に多様で包括的な社会・環境システムが対象になるということです。
組織を「よくしていく(開発する)」のは当事者
ここで、組織開発の「開発(Development)」にもふれておきましょう。
カイハツと聞くと怖いイメージが付きまといますが、本来はそうではないとODNJは述べます。
開発(D)とは?
Developmentは本来、「発達」「発展」「成長」という意味です。したがって、「組織の発達・成長を促す」というのが組織開発の本来のイメージです。
人が発達していくためには、その人自身が自らの発達・成長に取り組むことが大切になってきます。
他者から「変われ」と言われても人はなかなか変われません。その人自身が変わろうとすることが、人の発達・成長には必要です。
それと同じように、組織というシステムが発達していくためには、組織内の当事者が自ら組織を良くしていくことに取り組むことが大切、というのが組織開発での捉え方です。
平たくいえば「よくすること」という意味です。
平たくいえば、組織開発は「組織内の当事者が自らの組織を効果的にしていく(よくしていく)こと」を指します(そのための支援も含む)。
「当事者が取り組む」ということがポイントで、組織開発では、それをしてくれる「救世主」が組織を救ってくれるのではありません。
当事者である組織メンバーが自ら考え、自らの実践で、あらゆるメンバーと一緒に組織をよくしていこうとするプロセスが組織開発なのです。
それはある意味、「誰かがよくしてくれる」と他者に期待・依存するよりも「厳しい」態度かもしれません。
しかし、昨今声高に叫ばれている「持続可能な開発(Sustainable Development)」でも強調されているように、今や私たちには、人々と地球のために包摂的、持続可能な、レジリエント、すなわち強靭な未来を築くことが求められています。
それを実現するためにもっとも身近で重要な取り組みが「他者とうまくやっていくこと」に他なりません。
そして、それを様々なレベルで実践しようとするのが組織開発というアプローチです。
続きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
