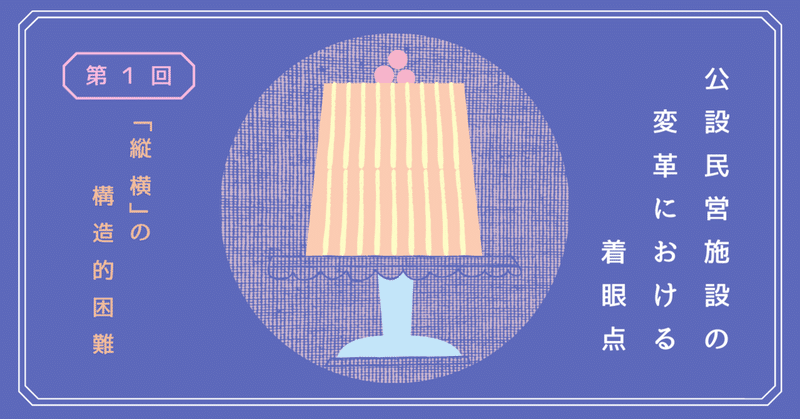
公設民営施設の変革における着眼点〜「縦横」の構造的困難(第1回)
白川は、2015年から名古屋市青少年交流プラザ(愛称:ユースクエア)というところで働いています。
ここは名古屋市の社会教育の流れを引き受けた都市型の青少年教育施設であり、若者の居場所(=家でも学校・職場でもない都市の中の第三の居場所:サードプレイス)となるユースセンターでもあります。
「青少年教育施設」や「ユースセンター」とはどういう場所か、を語るのはまた別の機会に譲るとして、今回は組織変革のお話。
これまでの自分の実践をそろそろ発信していくタイミングだ、と思い、様々な切り口でアウトプットしていこうと思っています。
ユースクエアについて

ユースクエアは名古屋市の施設(公共施設)ですので、その位置付けは条例に書かれています。
ユースクエアは、1970年代から続いていた市内4つの都市型「青年の家」を統廃合する形で、「社会性及び主体性に富み、人間性豊かで活力あふれる青少年の育成を図る」ことを目的に(名古屋市青少年交流プラザ条例)、2007年に新たに設置された青少年のための総合的な拠点施設です。
上項の目的を達成するため、ユースクエアでは「社会参加、世代間交流等の多様な体験・交流を取り入れた事業を行うことを通して、地域やまちで活躍する青少年の育成を目指した事業を展開する」ことをしています(名古屋市青少年交流プラザ年報)。
事業推進の具体的方向性としては、総合支援プログラムと呼ばれる「一層目の『人につながる支援』、二層目の『地域・まちにつながる支援』、三層目の『地域・まちに働きかける支援』、という三層にわたる支援を具体的に展開し、青少年が社会的に自立するために発達段階に応じた切れ目のない連続的、重層的な支援を進める」ことをしています(同上)。
ちなみに、この「総合支援プログラム」という考え方は、全国の社会教育・ユースワークの潮流の中でも、名古屋市が独自に発達させた「独特なアプローチ」で興味深いです。
事業実践の根拠はこれに凝集されるので、それはまたどこかで記述できたらと思っています(今回は組織変革の話なのでふれません)。
指定管理者制度について
さて、ユースクエアは現在「指定管理者制度」で管理・運営されています。
この制度は、公の施設を民間事業者等が管理・運営する仕組みです。
現在のユースクエアの場合、複数民間事業者が連携して1つの大きな組織(「コンソーシアム(=共同事業体)」といいます)となり、それが指定管理者として施設の管理・運営を行っています。
我々の場合、コンソーシアム組織の名称は「名古屋ユースクエア共同事業体(NIK)」といいます。
ユースクエアの沿革ですが、開館日の2007年7月7日から2014年の3月31日までは「直営」といわれる管理・運営をしていました。
それが、2014年4月1日からは指定管理者制度に移行しています。
ここで「直営」とは行政用語で、市の施設を市の職員が運営するスタイルを指します。
公共施設を公務員が運営するので「公設公営」とも呼ばれています。
一方、現在の指定管理者制度で運営するスタイルは「公設民営」と呼ばれています。
これは、施設は市のもので変わらないのですが、運営の主体が民間に移ったので、そう呼ばれています。
ちなみに市内に「名古屋市青少年宿泊センター」という施設もありますが、ここは名古屋市青少年交流プラザの分館として位置付けられ、2009年4月1日からは「直営」から「指定管理者制度」に移行しました。
この施設も我々が管理・運営しています。
まとめます。
現在、ユースクエア(名古屋市青少年交流プラザ)と名古屋市青少年宿泊センターは、「名古屋ユースクエア共同事業体(NIK)」というコンソーシアム組織が、両施設の指定管理者として一体的な管理・運営を行っています。
これらを図示したものが以下になります。

コンソーシアム組織における「縦横」の構造的困難
指定管理者制度の特徴として、一度民間に任せたらずっとその事業者にお任せ、ということではなく、一定期間ごとに公募と選定が行われるということがあります。
そうすると、ある年度を境に施設のスタッフが総入れ替えしたり、運営に関する細かな事項・方針が、選定される指定管理者の違いによって変更される可能性があります。
まさにこの点、すなわち指定管理者・施設利用者双方にとって安定した運営ができる保証がない、という点が指定管理者制度の脆さとして指摘される場合があります。
さらに、指定管理者制度は「民間事業者の活力やノウハウを活用することで、経費の縮減や利用者のニーズに対応した、きめ細やかな質の高いサービスの提供が期待できる」という〈メリット〉があるのですが、そもそも(営利目的の)民間事業者が公共施設運営をすることの親和性に疑問を投げかける論者もいます。
これらの問題に立ち入ることは本稿の趣旨ではありませんので割愛しますが、現場で仕事をする一人のスタッフとして大きく課題と感じたことがあります。
それはこの制度が生み出す「縦横」の構造的困難です。
(1)「縦」の構造的困難
いくら指定管理者制度で「施設の管理・運営の主体が民間に移った!」といっても、施設は市のものです。
つまり、施設の設置目的は条例で明確に定められていますので、民間事業者はその目的に沿った形で管理・運営をしていく必要があります。
それに、そもそも指定管理者の「募集要項」や「選定基準」は市が定めるのであって、民間事業者はそれに応える形で方針を提案せねばなりません。
それは結局、「民間事業者のしたいことが何でもできる」ということにはならないわけです。
この構造のもとでは、しばしば市と指定管理者の間で「見解の相違」が起こります。
「市はこういうつもりで施設・事業のことを捉えている」
「いやいや指定管理者はこういうつもりで捉えている」
こういうやり取りが現場で頻発するんですね。
この困難は、設置者である市の担当者が現場のスタッフでないことから来る「すれ違い」という次元で捉えることもできますが、より問題を複雑化させる要因として、市の担当者が「人事異動」で数年ごとに変わっていく…、という背景も忘れてはなりません。
(2)「横」の構造的困難
「コンソーシアム(=共同事業体)組織」は複数民間事業者の集合体です。
したがって、外からみれば1つの組織として団結しているようにみえても、構成しているそれぞれの組織文化などが異なるので、意思決定が複雑になったり、「一緒になっていく」ために様々な調整が必要となります。
これは、指定管理者制度が導入されたての数年間の運営では特に激化します。
「しなければいけないこと」と「それをどうやってこの組織でやっていくのか」という間(はざま)で、現場の人間は大変に試行錯誤することになるのです。
このように「コンソーシアム組織×指定管理者制度」で運営される施設は、「市 VS 指定管理者」という「縦」の構造的困難と、「指定管理者同士のすり合わせ」という「横」の構造的困難の両方に対処することが宿命となります。
組織開発プラクティショナーとして
白川は、南山大学大学院というところで「ファシリテーション(教育ファシリテーション)」の研究と実践を積み重ねてきました。
自身の研究領域は「サードプレイス」でしたが、人が集う様々な場面におけるファシリテーションに関しても実践を積み重ね、今に至っています。
さて、南山大学大学院はファシリテーションの源流にふれ、学びを深めることができる随一の専門機関として有名です。
最近は特に「組織開発(OD: Organization Development)」という分野で注目されるようになっています。
白川は、上記の「縦横」の構造的困難をなんとかできないかと考え、働き始めた当初から組織開発の発想を有した実践者(=「組織開発プラクティショナー」といいます)として何ができるのか、ということを考えていました。
これからは、それを記述していこうと思います。
まずは、「組織開発」とは何か?という点。
これは、南山大学教授の中村和彦先生の著書「入門 組織開発〜活き活きと働ける職場をつくる」が詳しい(しかも平易に読める)のですが、ここでは「ODネットワークジャパン(ODNJ)」から該当箇所を引用することで、概念理解の助けとしていこうと思います。
続きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
