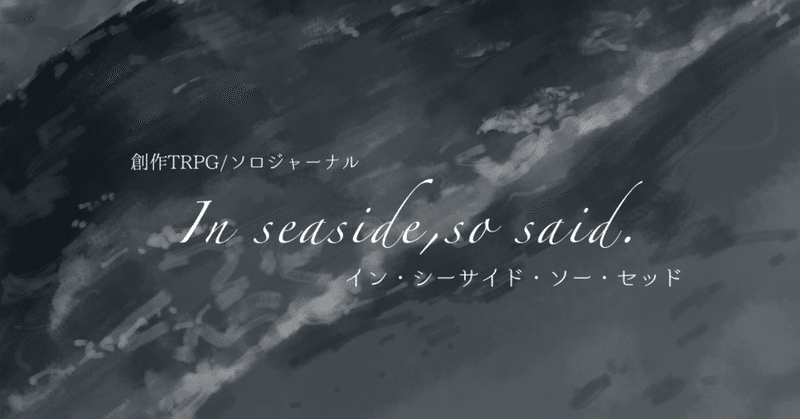
ISSS 小説「In seaside,so said. 」—case:谷生瑞希世—
波の上に、月の光が散っている。少し風のある夜だった。
星がよく見える。上を向いて歩こう……そんな歌い出しは、日本で暮らしていれば自ずと浮かぶフレーズだ。
海のにおいというものは、想像は爽やかなものだが、実際に近づいてみると生き物の匂いがする。というと――やや生臭いということだ。
谷生瑞希世《たにうみきせ》は深呼吸をした。生臭いとわかっているが、どうも癖になる。まだ洗剤の香りが残る生乾きの洗濯物みたいだ。
堤防を乗り越え、瑞希世は砂浜へと降りる。
波の音が近くなった。夜だ。ほぼ墨の世界だ。それでも、波に散る光で海の輪郭は見えた。
あまり寝付けず、旅館から出てきたはいいものの、この付近には海しかない。コンビニまでも遠く、歩いて行ける距離ではなかった。
だから瑞希世は海を歩くしかなかった。
金も節約したい。
さくさくと砂浜を踏みしめる。さくさくと音がしているのかもわからない。すべて波の音にかき消されている。足に触れる砂の感覚が「さくさく」としか表せない。
三百万と三千九十円。
残りは十五万。次と次の給料で返済することが――すべて使い切れば生活がままならないから――できるだろう。
彼に課せられた返済額だ。いつの間にか友人の連帯保証人になっていて、いつの間にか友人は借金を残して消えていた。よくある話だ。瑞希世にとってはフィクションの中で。まさか自分がその登場人物になってしまうとは――そう思い馳せては、やはり現実味はなかった。無意味な借金だけがあった。
波の音が、ため息すら押し流していく。
静かだ。とても静かな夜だ。瑞希世は暗闇と海の境を一人で歩いている。
多くの信頼や、時間失った。後先考えず自分の貯金でまかなった。そのため、自分の生活がままならなくなった。それで自分のために、また他所から借金をすることになった。
「俺のせいじゃないじゃないか……」
飛んだ同僚が悪い。俺は、友達だと思っていたのに、いや、あいつも「友達」だとは思っていたのかもしれない。――『都合のいい』のラベルを付けた。
瑞希世は砂を蹴る。やや湿っていて、砂粒が足首に張り付いた。靴の中にも砂は落ちていく。
ため息をついて振り払う。不意に、辺りが明るくなった。雲が晴れ、月が少し高くなったのだろう。辺りを見回し、瑞希世はふと一点に目を凝らした。
開けた海にふさわしくない、異質な影がある。崖や巨石かとも思ったが、妙に角張り、規則がある。あれは人工物だろう。
そろそろと近づきながら、そう確認した。
「……廃墟、だなあ。でっかい廃墟だ。……なんかの施設かな。……家かなあ」
瑞希世はその建物のうろついた。やはり暗がりでその全容はつかめないが、家であるということはわかる。
「誰か住んでたのかな……物好きだなあ」
瑞希世はスマートフォンを取り出した。フィルムカメラで写したのようになるアプリを起動し、写真を撮る。そしてふと我に返り、
「……まだ誰か住んでたらどうしよ」
少し笑った。スマートフォンを慌ててしまい、廃墟に背を向けた。
さくさく。
さくさく。
またそうとしか表現できない足音で、砂を踏みしめる。夜の海の鳴き声は、大きなため息の様にも聞こえる。
意味もなく笑ったのはいつぶりだろうか。
ここ最近はずっと働き詰めで、愛想笑いばかりで、苦笑いばかりをしていた。
休日は休日らしくない時間ばかりを過ごしていた。その前の過ごし方が思い出せないほど。
車を出して見たものの、一人ではやはり寂しかった。
「またみんな遊んでくれるかなあ……」
ぽつりとつぶやいた言葉は、虚空に吸い込まれる。その先には星だけが輝いていて、海だけがさざめいていた。
こつんと足先に何かが触れた。……ただの空き缶だった。
瑞希世はそれを拾い上げ、手持ち無沙汰に振る。観念して自分の上着のポケットに収めた。砂がポケットの深い位置に落ちていくのを感じる。
誰もいない海だ、捨て置けばいいのに。だがそれをすると、今までの苦労すら否定されそうな気がした。あとで捨てる。正しい場所に。
――当面の目標は、信用回復だ。
瑞希世はしゃがみ込み、海を見つめる。
借金のための借金をする――なんてばかなことだろう。そう思っていたが、「そうせざるを得ない状況」に落ちるのが、借金の怖いところだ。瑞希世は身をもって知った。完済したとしても、友人や同僚や、どんな感情や視線でも「借金」というレッテルは残る。そういう体面を気にしてしまう自分も嫌だった。
はあ、とため息を吐くとともに、がっくりと下を向く。足下になにかもぞもぞと動くものがあった。
「……なんだ?」
指を伸ばしてみる。指の腹に乗ったのを確認し、持ち上げてみる。小さなカニだった。
「お、カニ。……はは、海の生き物最終とか、いつぶりだろう。うちに来る?」
カニの返事はわからない。とりあえず反撃されなかったので、是ととらえることにした。
人間関係について考えるのは、一度うちやめにしよう。
瑞希世は立ち上がる。
とりあえず今は――そろそろ自由になれるのだから、旅行でもいこうか。そんなことを考えた。
旅行は好きだ。好きだった。
借金があるとそれすらも重荷で、どこかに行くということができなかった。単純に、贅沢だったからでもある。
カニを落とさないように指に這わせながら、瑞希世は歩く。先ほどの廃墟の場所に何か入れ物があるかもしれない。少し駆け足でその方向へ向かう。
「……ドア開いてるかなあ」
玄関まで来てみて、カチカチとドアノブを揺らす。開いていないようだ。
どこかから入れそうな場所はないだろうか。ぐるりと回ってみる。薄暗い煤けた窓の向こうに人影が見えて、ぎょっとした。
取り落としそうになったカニの所在を確かめ、改めて窓をのぞいてみた。
……石像だった。かろうじて横顔であるような、そういうシルエットが人に見えたのだ。
「ここって一体なんだったんだろうな。……手がかりがなさすぎる」
瑞希世はまじまじと窓の奥を見ながら、写真を撮る。どうみても不審者。どう考えても人がいれば訴えられるのは自分だ。
もう夜が深い。ちょっとの先も見えなくなってきた。
「いい加減戻るか」
カニに海水を与えてやり、瑞希世は海を後にした。好き放題歩き回った疲労で、随分と気持ちは軽かった。
旅館に戻り、急いで容器に水とカニをいれてやった。そっとテーブルの上に置いてやる。カニは元気そうだ。明日も生きていたら、ちゃんとした部屋を作ってやろう。
上着を脱ぎ、すでに敷いてある布団の上に寝転がった。部屋の電気は消したままだが、薄青い月明かりで天井の木目が見える。
瑞希世はスマートフォンを取り出し、メモアプリを開いた。
借金をしている間、誰かに愚痴を言うのもSNSもむなしいばかりで、メモに日記をつけるのが習慣になっていた。
うつらうつらとしたまま、瑞希世は文字を書き残す。
そうしてぱったり、目を閉じ、力尽きた。取り落としたスマートフォンの画面がふと消えて、本当の夜に包まれた。
『もうすぐ借金が完済できそう。その徒労がやっぱり頭の中にずっとあった日だった。この海は元々何かあったのかな。気になるけれど、ひとまずは残りの借金を完済しなければ。旅館も一泊しかとってないから夜が明けたら帰る。またこよう。』
―― 『あなたは海を去り、また日常へと戻っていきます。この海で何か心境に変化があったでしょうか。
この海はいつでも、あなたのことを待っています。だからいつでも訪れて。
また静かに海を歩いて、思い出を拾いに来てください。』――
In seasde,so said.
瑞希世の拾ったもの
・廃墟の写真
・空き缶(これはゴミ!)
・カニ(名前はまだない)
・石像の写真
この小説はしおのはかた作創作TRPG/ソロジャーナル『In seaside,so said.』のログを元に作成した小説です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
