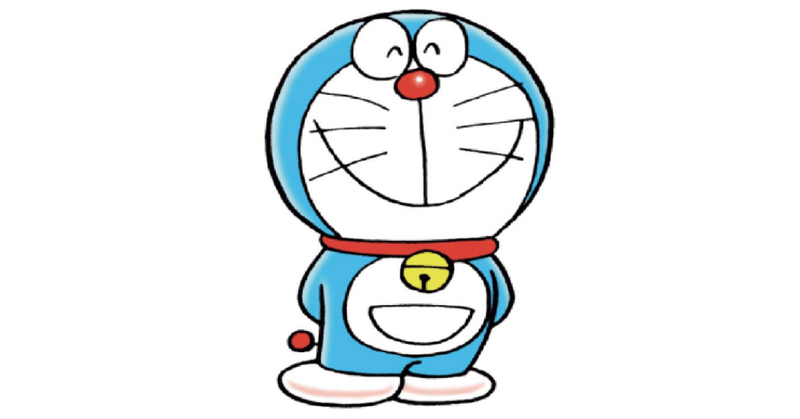
学生寮物語 8
8 四次元ポケット
休日であったが病院内は見舞い客が少なく、広々とロビーを使うことができた。ただ、一人の老人が昼食のパンをかじりながら、満足そうに漫画を読んでいる光景が目に入った。しかも大きなテーブルのど真ん中を占領していた。きっとロビーを独り占めして気分が良かったのかもしれない。いつも混雑しているN病院では、「どえりゃー気分えーぎゃ」状態だったのかもしれない。
老人は安岡を見舞う会の一行が来ても真ん中の席を移動しようとしなかった。(人生経験豊かなんだから、空気読めよ)と翔は思った。すぐにたくさんの見舞い客の視線に気づいたが逆に頑なになった。
老人は視線を浴びれば浴びるほど意固地になっていくようだった。仙人のような大村が優しく説得を試みたが無駄だった。他人に席は譲ってもらっても、自分からは決して他人に席を譲らない人なのだろう。それでも鈴子が見舞いに来てくれたみんなを気遣って、移動してもらうように再びその老人を説得したが案の定動かない。もごもごと老人が何かをいっていたがみんなよく分からなかった。なんで俺が動かなきゃならないのだ、という不平不満が顔つきや態度にあふれ出ていた。
「すみませんでしたね」
と説得をあきらめた鈴子は謝った。
学童保育に携わっている彼女は幼児をいたわるように話をしていた。見舞い客たちはその場の雰囲気を壊さないように静かに場所を変えた。老人はその後も血走った目で菓子パンを食べ続けていた。たぶん味わうこともなく。
ただ翔にはその老人の姿が自分と重なる気がした。だんだんと周りの人の心遣いが見えなくなっていくのだろうか。心遣いに感謝していくか、それを見失って意固地になっていきていくか、大きな違いだと思った。彼は「クリスマスキャロル」の「スクルージ」を思い出した。
入退院を繰り返し、抗がん剤の影響もあって、安岡はすっかり痩せ細っていた。頭には黒のニット帽が乗っていたが、帽子の縁からはすっかり弾力性を失い、わずかに残った髪の毛が顔をのぞかせていた。白い皮膚は全ての青い血管が透き通って見えるかのようだった。
見舞客に再会の挨拶をした安岡は、痩せた頬を少し緩ませ、左手に大切そうに抱えていた黒いあまり大きくないバックの中から、まるでマジシャンのように何やら次々と取り出し、テーブルの上に並べていた。
彼が重い思いをして運んできたもの、それは何か。今からなにが始まるのか、みんな注視した。安岡が黒いバックから、ドラえもんが四次元ポケットから何かを取り出すように、ブックレットと古い新聞を取り出した。そしてそれを彼の同級生たちが大きいテーブルに恭しく並べていった。まるで犯罪現場の重大な証拠物件を順番にならべていくみたいに。
その真剣な作業を横目で見ながら安岡が話し始めた。
「毎日、鈴子以外にも、なぎさの娘が看病に来てくれている。それで俺の身の回りのことはとても助かっている」
「なぎさの娘って?」
翔は初めて聞いたことなので、聞き返した。すると鈴子が説明した。
「松永さんの一学年下に北川なぎささんがいたでしょ。彼女がお医者さんと結婚して、今名古屋に住んでいるの。それで安岡のことを相談したの。そしたら病院を紹介してくれたり、娘さんが私たちの近くの医大に通っているからといって手伝いに寄こしてくれたり……。その娘の瞳ちゃんがときどき病院に来てくれているの」
鈴子は大学時代と同じように、今でも夫を名字で呼んでいるのか、変わんないなーと翔が思っていたら、
「へー、そうなんや。それはごっつう助かるなあ」
と金城が相槌を打ちながらいった。おいどんも、
「それはよかったじゃん」
と長崎弁ではなく、横浜のジャン言葉を使った。二人とも他人の思いやりにまで敏感だった。
「そうなの。なぎささんは一つ年上の先輩なのに、とても熱心に世話をしてくれて、私も精神的に救われているの」
と鈴子がいった。
大村は黙ってみんなの話を聞いていた。翔はその理由を知っていた。学生時代、大村はなぎさに好意を抱いていたからだ。
突然、安岡が叫ぶ。
「ちょびっと俺の話を聞けや! もう!」
話題の中心から自分がいなくなるとすぐに人の話を遮る。これが彼のいつもの調子だ。松永はちょっとうれしくなった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
