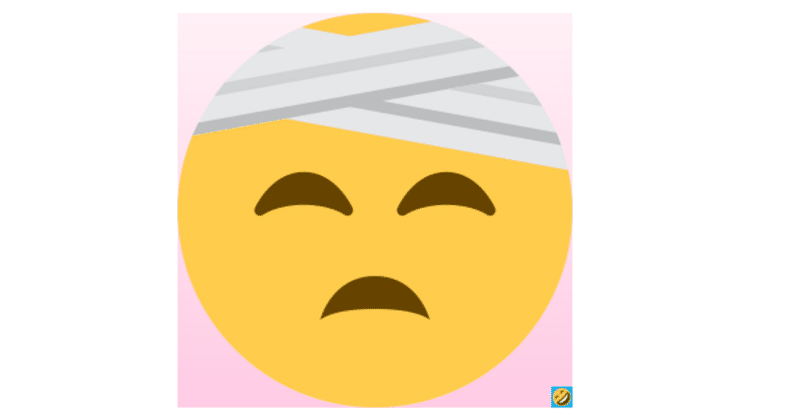
学生寮物語 5
5 ポンコツラガーマン
安岡の見舞いのことは妻のさくらに電話で連絡しておいた。さくらはK町の役場で相談員として働いていた。土、日は仕事が休みなので、二人は一緒に行くことができた。
金城に見舞いに行くことを連絡した日の夕食のとき、翔は自分と同学年の卒寮生何人かに連絡したことをさくらに伝えた。
そうしたらみんなすぐ「行く」といっていたと話した。さくらも当然のような態度で聞いていた。翔は自分がためらったことは恥ずかしくて話さなかった。
さくらも自分が連絡が取れる寮生には連絡をしたといった。
翔も大村に連絡したら、安岡が病気だったのは知っていた。東京にいる後輩たちから聞いていたらしい、と伝えた。その後、
「実は大村とは不思議な縁があるんだ」
と話した。するとさくらは、
「なに、なに?」
と聞きたそうにした。だから翔は食後のコーヒーを飲みながら、30年以上も前のことを思い返しながら、とつとつと話し出した。
自分たちが大学を受験したのは今から35年も前の1972年の2月だった。前の年の1月24日にグアム島で横井正一さんが発見され、日本中が大騒ぎをしていたのを覚えている。
どこかの誰かが、「ヨッコイショ…ういち」と悲しいギャグを飛ばしていた。横井さんにとっては二十八年ぶりの終戦だったのに。ほんとうに僕たちは『戦争を知らない子どもたち』になったのだと実感させられた。
大学入試の時、奇遇にも二人は隣同士の席だった。推薦入試という気楽さもあったのだろう。二人は初対面にもかかわらず、旧知の仲のようにいろいろ話した。
試験が終わった後、大村は受験の緊張を和らげるような優しい顔つきで話しかけてきた。
「どっから来たの」
「静岡から」
とおれは答えた。
「俺は山梨」
「割と近くだね」
「合格したらどうする? 自宅から通うの?」
大村が訊ねた。
おれは合格という言葉を聞いただけで、胸がドキドキした。そして自分の不安な胸中を語った。
「できたら寮に入りたいと思っているんだけど、集団生活したことないから不安で……」
本当は合格後のことまで考える余裕なんてなかった。ところが大村が、
「その集団生活が楽しいらしいぜ。俺も入寮を希望しているんだけど、山梨なんて近いから入れないかもしれない」
といった。
「集団生活が楽しい?」おれは始め何を言っているのかよく分からなかった。だが山梨が近いなら、静岡も。
「そうなの? だったら俺もやばいかな」
と不安そうにいった。
合格よりも入寮できるかどうかを問題にできる立場にないのに、勝手に不安になった昔の自分を笑った。
そして大村が話す内容に驚愕した。
「実はうちの兄貴はこの大学の寮の卒業生なんだ」
「エッ! 本当?」
寮生活に不安を抱いていた俺は思いがけず大村に椅子を向けた。
「家で寮の話をいろいろ兄貴から聞いていたらすごく興味が湧いてきて、それでこの大学を選んだ」
「へえー、そうなんだ」
そのときおれは目を丸くした。
これといった目的もなく、何となくこの大学を選んだ自分にとって、大村の語る明確な志望理由は新鮮で、おおいに自分を勇気づけてくれた。
大村には二つ上の兄貴がいて、自分の目標とする人だった。彼の兄は寮の活動でも、自治会がなくなってしまった大学での活動でも先進的に取り組み、みんなに信頼されていた。だから大村は兄と同じ大学に入り、兄と同じ寮で生活をするのが夢だった。
兄が弁士となり、実家で弟に熱く語る寮での生活の様子やエピソードの数々は、活動写真「大村兄の青春」の代名詞だった。その活劇に弟の自分も出演したかったのだろう。
もちろん大村は1年生のときから入寮希望だったがすぐに入れず、二年から入寮してきた。
どうしてそうだったのか、よく分からなかった。たしかにおれが1年生のとき寮は満室だった。だから単に空きがなかっただけだろう。おれも大村が早く入ってくればいいのにと願っていた。
4月に学内で出会ったとき、大村はしょんぼりして、
「4月に寮に入れなかった。これって、兄の影響かもしれない。わりあい有名だったみたいだから」
といった。
だからおれは、
「それはないんじゃない。高校の担任が『自由教育をめざす小さな実験校』で、管理教育に盾突いてるみたいで、この学校はなかなかおもしろいぞ、っていってたよ」
「どういうこと」
「だから学生の自主性や主体性を簡単に摘むようなことはしないってことさ」
自分が思いついたことを話し、慰めようとした。
「そうかな……」
高山が少しほっとした顔をしたのがわかった。
この大学には自治会がなかった。自治会と名がつくものは「A大学学生寮自治会」だけだった。大学自治会は数年前に消滅したらしい。理由も、経過も知らない。ただ自主的な自治会を再建しようと運動している学生たちがいた。
大村が寮に入れなかった本当の理由は誰にもわからなかった。家の経済状況か、通学距離か、兄のせいか、単に運が悪かっただけなのか。
大村自身には素行の悪さは微塵もなかった。何か超然としていた。ピュアといってもいいかもしれない。彼には似合わない言葉だが。
いつも紙と鉛筆を握ってマンガやイラストを描いていた(漫画とイラストの違いはよく分からなかったが)。授業中にも講義内容を、マンガやイラストでノートにまとめていた。自分はそれを横から眺めているのが講義を聴いているよりも楽しかった。
だが大学でたまに彼に会うと、いつも絆創膏か包帯が体のあちこちに貼られたり、巻かれたりしていた。鼻の軟骨が曲がっていたり、肩の鎖骨が折れていたり、常に擦り傷、切り傷、たんこぶなどが絶えなかった。
彼はプロレスラーや柔術家ではない。ましてや自分をいじめる性癖があったわけではない。単にポンコツなラガーマンだった。
A大学ラグビー部は「ゆるく、たのしく、真剣に」をモットーに活動していた。大村は体は大きくはないが活動的だった。マンガやイラストを描く人間はどこかに引きこもっているという世間の偏見を見事に掃破していた。
まじめにラグビーにも取り組んでいた。彼はいつもまともに正面から突っ込みぶっ壊れた。ただ少々壊れやすくもあった。
彼は山梨にあるお寺の次男坊として生まれた。だから邪念も打算もなく、ただひたすら正直に相手チームの巨漢に突っ込んでいったのかもしれない。
ここまで話すと妻が、
「何宗?」
と聞いた。
「宗派? エッ、そんなこと考えたこともなかったけど」
すると妻は
「身延山だから、日蓮宗かな」
といった。
国語を教えている翔は宗派などというものは考えたこともなかった。さくらは社会の教員免許も持っている。社会の先生はそこが気になるのか。妻に軽く突っ込まれ戸惑った。
大村はこのときから大学を卒業したら、イラストレーターか絵本作家になりたいと言っていた。夢を語る大村の穏やかなその表情は、どこかの山奥に棲む仙人が、青年に化けて下界に降りてきたようだった。
憧れの上の兄が大村家の跡継ぎで、現在は高校の社会の先生をしていた。たった一人の兄のことを大村は嬉しそうに話した。
翔は4人も兄弟がいたのに、なぜか何も話さなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
