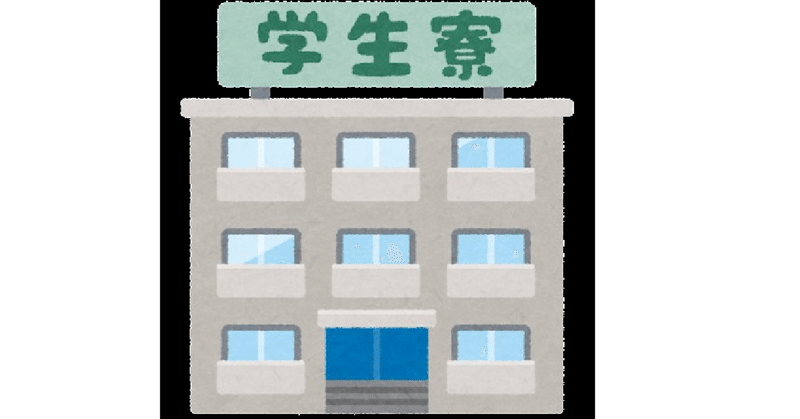
学生寮物語 3
3 入寮宣言
翔には忘れられない出来事があった。
5月の連休を目前にした3か月ほど前に、金城から翔(かける)に電話があったときのことだった。
「安岡な、癌が食道からあちこちに転移して、良くないらしいねん。だからな、今度の連休始めの土曜日に寮生みんなで励ましに行かへんかて、話おうていたんや」
みんなというのは晩酌の気まぐれに金城が電話する寮やサークルの仲間のことだった。
翔は安岡の容態があまり良くないと理解できたがすぐに同意はしなかった。その日は部活の重要な練習試合を組んでいたからだ。
5月に入り、翔は夏の中体連に向けて、チームの最後の強化に努めている最中だった。
「土曜日の練習試合の監督は頼めないけど、日曜なら練習だけだから誰かに頼んで行くよ」
と返事をした。それが自分では精一杯の決断だと思った。
同じく大阪の中学で美術を教え、女子バレー部の顧問をしていた金城にとっても大事な時期であることは分かっている。
「そうか、分かった」
金城は低い声でそれだけ答えた。
「他の寮生への連絡はどうする」
「ワシがするけど、東京方面の寮生への連絡は松永、頼むわ」
「分かった。せっかく誘ってくれたのに、一緒に行けなくて悪かった。みんなとは別になるけど、翌日に行くよ」
と言ったものの、翔は迷っていた。寮生のみんなと安岡が顔を揃えるのはこれが最期かも知れないと考えると夜も眠れなかった。
翔は教員になってから20年以上も野球部の顧問を務めていた。その間、地区大会や県大会で優勝したり、全国大会にも出場したりしていた。そのため簡単に負けられないというプライドもあった。
勝てば官軍、負ければ賊軍、結果がすべてだと思っていた。だから自分が監督をして、県大会に出場するのは当然だとさえ思っていた。
土曜日の練習試合には静岡県東部地区の強豪校が集まっていた。翔はこれを今年の中体連での成績を占う試金石として位置づけていた。
今年のチームは県大会に行けるかどうか微妙な位置にいた。県大会に出場できるのは、地区からは2チームだけだった。去年の新人戦では3位がやっとだった。
だからどうしても自分が采配を振い、チームの戦力を見極め、中体連での戦術や今後の方針を決めたかった。
もともと翔は人間関係が不得手であった。
彼の生まれは北海道阿寒町のY炭坑があった場所だった。
小学校時代は毎年恒例で、「まじめでおとなしい子です。もう少しはきはきするといいでしょう」と通知表に書かれていた。
友達の間を器用に行き来したり、自分の意見をいったりすることができない子どもだった。
中学に入って、大好きだった野球部に入った。
連日行われた説教という名の先輩のいびりがあっても、彼は野球部に残った。それほど野球が好きだった。でも2年になって残ったのは二人だけだった。
残った一人はピッチャーでサウスポーだった。体が大きく、球も速かった。さすがの先輩も自分より大きい彼をいびれなかった。もう一人が翔で、通知表の通り「まじめ」が取り柄の彼はいびりの対象にはならなかった。そしてキャッチャーとなり、キャプテンも務めた。
そんな彼が地区大会で逆転のランニングホームランを打ってY中学校は優勝した。だが翌年、炭鉱が閉山となり、Y中学校も廃校になった。そして彼の家族は今の静岡に来た。
中学時代の思い出は、彼につまようじの先ぐらいのほんの少しの自信を与えた。だが彼の世界は家族とその周辺だけだった。野球部でもチームワークよりは試合に勝つ方法を学習した。
だから彼はいまだに人間関係が煩わしく感じるときがある。冠婚葬祭などの慣習にも無知で、消極的に参加した。よく知らない人のお通夜などは、どんな態度で人間の生死に関わればいいのかよく分からなかった。
彼は大学の合格通知を受け取ったとき、入寮を希望すると家族に告げた。みんなが驚いた。甘えん坊で大人しい弟が、寮生活ができるか心配した。でも誰もその理由は聞かなかった。末の弟が家の経済状態を心配して、費用が安く済むように選んだことを察していた。
だが翔自身は「入寮宣言」をしてから、寂しい冬の夜のとばりが下りるように、心がだんだんと不安と孤独な気持ちに覆われていった。
どんな大学生がいるのだろう。
他人と同じ部屋で暮らせるのだろうか、家族でもないのに。
「変な人」はいないだろうか。
疑問と不安が阿寒湖の「ぼっけ沼」のガスや泥のように次々と湧いた。
入寮して、先輩方が優しいのに驚き、安心した。中学時代の部活の思い出から、先輩というものはみんなが優しくはないのだということを知っていたからだ。
だが翔の不安の一つだった「変な人」はあちこちにいた。それはとてもユニークで個性的で、人間性にあふれていた。そして自分に正直に生きることの大切さを彼に教えた。
翔にとって寮での経験は、忘れられない青春時代の思い出というだけではなかった。本音で人と繋がることができた人生で唯一の時間だった。未熟な者たちがお互いに支え合って、必死に生きていた貴重な時代だった。
四年間も大学の寮で集団生活を送れたことに、翔自身がいちばん驚いていた。
そんな彼が大切な後輩のお見舞いを後回しにするのはやはり間違っているとはっきり思った。自分のことに固執している自分がとても恥ずかしかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
