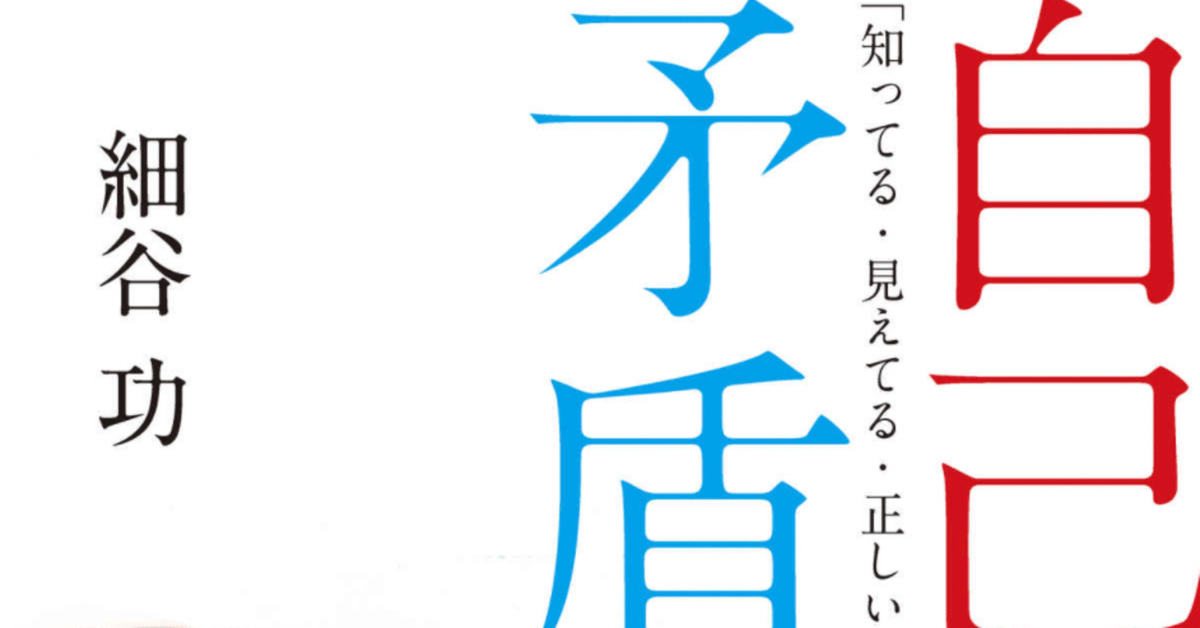
自己矛盾劇場
こんばんは🌙
今日は文化の日でしたね🇯🇵
お天気も良く、緊急事態宣言もとけ、文化的なイベントが色々なところで開催しているようですね。
久々に堂々と祭日を楽しむといった人も多かったのではないでしょうか?
私は昨日でフリーペーパーライター講座が終了し、写真撮影スキルアップのためにオンラインで講座を受講し、家の近所を散歩しながら習った通りに撮影をしてみました。
携帯で上手に撮影する講座を学んだのですが、自分が今までやっていた写真の撮り方にたくさん間違いがあることを知って勉強になりました📷
特に勉強になったのが携帯で対象物を大きく撮りたい場合ズーム撮影していましたが、対象物に近付いて撮影することと、Webで編集して使用するためには縦と横と両方を撮影することを学びました🎓
なんでもそうですが、少しの知識を得ただけでも今まで興味がなかったことに対して興味が湧き楽しくなります。
今はやるべきことが溜まっているので、時間に余裕ができたら写真撮影のために旅行に行きたいなぁと思いました。
さてそれではさっそくいってみましょう!
ーーー
●自己矛盾劇場
今、細谷功さんの著書「自己矛盾劇場」にハマっています。
正直一度読んだだけではきちんと理解できず、今2巡目をしております。
1巡目よりは理解してきています。
しかし2巡目を読み進めているうちに自分が何故理解できないのかということがわかってきました。
まず感じたのがそもそもこの本のタイトル通り「自己矛盾」自体を理解できていないこと、自分のどんな部分が「自己矛盾」なのかを理解できていないからだと思いました。
そもそも「自己矛盾」とは何か?
「自己」というものの中で「矛盾」が生じている状態
本書に書いてある例を取り上げてみます。
例えば「あの人は、他人の批判ばかりしているからダメなんだ」と言ったとします。
これ自体が既に自己矛盾です。
「あの人」について語っているその当人がまさに「あの人」と同じ他人を批判する人」になってしまっています。
細谷さんは自己矛盾について
「この世の中は、笑ってしまいそうな自己矛盾にあふれていて、喜劇顔負けの劇場となっています。登場人物が大真面目であればあるほど、観客の笑いを呼び起こすことも、喜劇と同じです。」
と冒頭に書いています。
さらにこう続きます。
演者を見て笑っている観客(つまり私たち)が座っている(と思っている)観客席は、舞台上のセットの一部であり、私たちも「本当の観客席」から笑われているということです。
「笑っている側だと思っている自分が、実は笑われる対象である」と気づくことで、客観的に自分の行動を見る「メタ認知」への扉が開きます。
先程上げた例は、よく耳にするし、自分自身も知らず知らずのうちに声を大にして言ったり、書いたりしているかもと恥ずかしくなりました。
本書を読んで一番印象に残ったのがメタレベルで見たら「50歩51歩の違い」にすぎない、という言葉でした。
そうとも知らず自分が少し得たことをあの人はわかってないと口には出さずとも感じたことは多々あるなと感じました。
●「知っている・見えてる・正しいつもり」を考察する
本の最初に「モグラ劇場」と題し、4コマ漫画で結構きつい内容をコミカルに伝えています。
モグラは目が見えていない分、「視覚という幻想」にとらわれないという点で「心の眼が歪みまくった人間」の象徴的な対照となっているそうです。
かなりブラックなので苦笑いしながら見ました。
モグラ劇場は6つのステージに分かれています。
内容な以下の通りです。
①気づかない
→自分も同じであることに気づいていない
②知らない
→自分が知らないことを知らない
③気にしない
→気にしていないと口に出していること自体が気にしている
④自分の頭
→「自分の頭で考えろ!」は相手に押し付ける便利な言葉
⑤多様性
→実際は多様性を理解していないのにすぐ口に出す
⑥チームワーク
→競争心から来るチームワークは本来の目的を消失させる
どれも胸がえぐられます😅
しかし上記の内容を意識できるか否かは生きやすさを獲得する上でとても大切だと感じました。
細谷さんは自己矛盾には3つの特徴があると書かれています。
その3つの特徴とは以下になります。
①自ら気づくことはきわめて難しい(が、他人については気づきやすい)
②気づいてしまうと、他人の気づいていない状態が滑稽でたまらない
(滑稽とは本人の自覚がなく意図していないおかしさのこと)
③他人から指摘されると「強烈な自己弁護」が始まる
この3つの特徴からもわかるように、人は自分のことは気づいていないが、他人のことは気づきやすいということ。
これまた細谷さんの例えがとてもわかりやすかったので、その例を元に①について自分で例えをあげてみます。
自ら気づくことはきわめて難しい(が、他人については気づきやすい)
Aさん「私はこう思うんだよね〜。だからこうしようと思う!」
Bさん「え、そんな安易な考えでいいの?絶対に間違えていると思う!」
Cさん「それぞれ個人の考えがあるのだから、間違っているというのは間違
っているでしょ」
Cさんの自己矛盾、お分かりですか?
こういったことって結構日常的にありますよね。
3つの特徴から導き出せるのは
「人の振り見て我が降り直せ」
他人のことには気づきやすいという特徴があるからこそ、実践できると細谷さんはおっしゃっています。
まだこれは序盤の序盤の感想なのですが、既に2,000文字をオーバーしているのでこの辺でやめておきます😅
自分でもちゃんと落とし込みたい内容なので、また明日続きを書きたいと思います。
追伸:「今すぐに知りたい!」という方は是非kindle版で購入して今すぐ読んでくださいませ🤗
ーーー
こうやって言語化して書かれるとその矛盾点やメタ認知についてとても理解できますが、普段普通に生活していると気づくことがなかなかできません。
なので、この本は本当にオススメです🙂
少し毒のある本かもしれませんが、グサリとするということは気づけたという証なので、それは前進したともいえます。
私も、グサグサとナイフで刺されているとわかっていても自分が気づけていなかったこと(未知の内容)だからこそ、興味深々で読み進めています。
本当に久しぶりに読んですぐ2巡したくなる本に出会えました笑
今日はとても長くなってしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました🤗
明日も今日の続きを書きたいと思います。
それではまた明日!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
