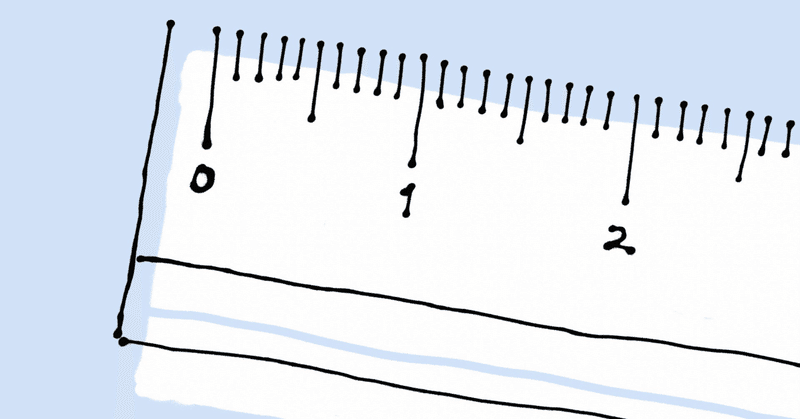
骨格標本の作り方1 標本の計測
山で動物の死骸に出会った。
そんな時は,ぜひ骨格標本に。
そのために,いつでもポリ袋を持っていると便利。
メメントモリ。
死。
汚れやけがれ、避けるものとしがちだけど、身近に感じておくことって大切だと思う。
死を身近に感じられる遊び、趣味。
骨格標本
骨格標本づくりのノウハウまとめのnoteです。
1.標本の計測
標本にしてしまったら、もとの大きさはわからなくなる。
身体の大きさを測れる状態の標本の場合、まず計測する。
使う道具:
・ものさし
・巻尺(大型用)
・コンパス
・ノギス
計測量:
(a)全長:
平らな板の上に背中をつけて、体をのばし、鼻の先から尾の先までをはかる。
尾の先の毛は、計上しない。
体をのばしながら、鼻先と、尾の先にピンを立てて、その間の距離をはかる方法も。誤差が少なくなる。
(b)尾長:
腹を下にして、尾を持ち上げながら、ものさしの片端を尾の先から根元の方へずらしてゆくと、尾の根元でとまる。
この時の長さをものさしで測る。
この場合も、尾の先の毛の長さは入れない。
(c)頭胴長:
全長から、尾長を引いた長さ。

(d)後足長:
かかとから、いちばん長い指の先までを測る(爪は除く)。
爪を入れて測った方がいいこともあるので、両方測っておいた方がいい。
爪の長さが入っているかどうかは、記録しておく。

(e)耳長:
耳の切れこみから耳の先まで。
毛の長さは入れない。
コンパスを使うと便利。
上の5つの他に,食虫類(モグラなどの仲間)では,前足の大きさを測る。

(f)前足(長さ×巾):
手のひらの後端から、いちばん長い指の先(爪を除く)までが長さ。巾は、手のひらのいちばん巾の広い所を測る。
コウモリ類では、さらに次の3ヶ所を測る。

(g)前腕長:
ヒトのひじから手くびにあたる所まで。
(h)脛長:
ひざからかかとまで。
(i) 耳珠長:
耳珠の内側基部から、耳珠の先まで。
なおこの他に、体重も測っておく。
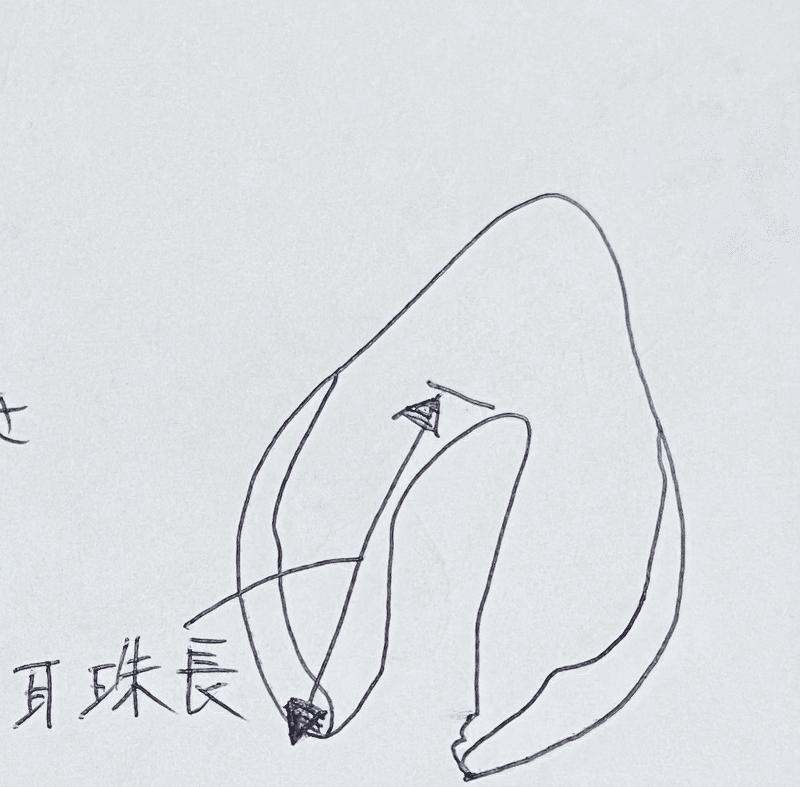
いろんな部分を測りましょう。
次は、解剖と骨にする前の準備です。こちらをどうぞ。
最後まで読んで頂き、感謝です(ぺこり)
透明骨格標本の世界も素敵です。
ぜひ覗いてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
