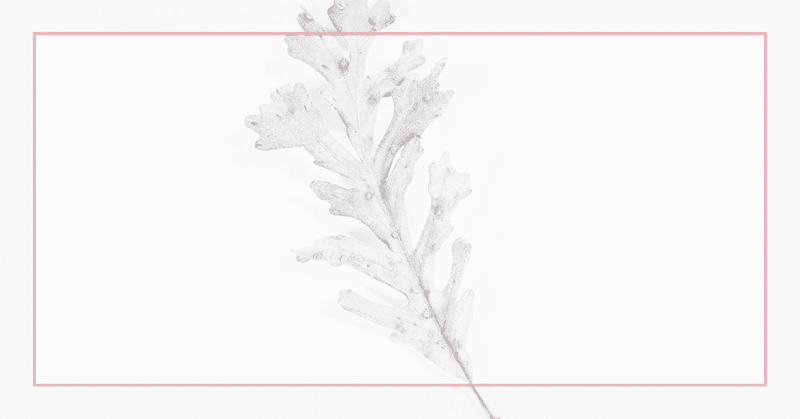
【雑記】言葉が気になる耳
津軽弁コントのyoutube
【津軽弁youtuber】すんたろす さんに去年からハマっています。
「ホチキスなんて言葉は青森にないの」
「これは『がっちゃんこ』」
🤣🤣🤣
訳が分からなくても、ついつい聴いちゃう。
また、「それでいいの」「分からなくていいの」と、くりかえし言ってくれるので、そこも気に入っています。
分からなくても面白い、という作風を選んでいるところが、動画クリエイターとして最高だと思う。頭良い……。
分からなくても面白い。そして、分かるともっと面白い。
っは〜〜結局そこのセンスだわ。さじ加減。
(説明字幕をいれてくれると、理解のとっかかりになるが、全ては説明しきらないほうが楽しいんだと思う。
要は、字幕の量が丁度いいこと。気になる部分を残すくらいのが、人間って興味が持続するんだと思うんです。)
すんたろすは天才。マジで。流行ってほしい。
グッズも可愛い。
言葉が気になる耳・言語獲得のための耳
人は15歳くらいまで『言葉が気になる耳』を発動させているのだといいます。言語獲得のためなのでしょう。誰かがしゃべっている言葉が気になるし、新しい言葉を耳で追ってしまう、自分もマネして言おうとする……などの性質があります。
(もちろん、大人になってもその特性を発動させつづけ、ずっと言葉に貪欲だという人もいるでしょう。ダジャレのネタを考えつづけたりね。言葉遊びは大人になってからも続きます。)
そのためでしょうか。わらべうたも、実に子どもがよく聴いてくれます。
これは、わらべうたが言葉のイントネーションとリズムだけで出来ていることと、密接に関係していると思われます。
──そもそも、わらべうたとは作曲者がおらず、言葉の音の上がり下がり、言葉のリズム感から自然発生したもの。
「よ〜う子ちゃん、あそびましょ♪」と歌うように喋った時の、それ。それがもう、言葉から歌が発生するということ、でしたね。
人間同士が言葉を共有しようとすると、自然に歌が発生する。
トトロでも朝ごはんの場面で、「さーつきちゃ〜ん♪」「はーぁーいー!♪」と、皐月とみっちゃんの間に、問答形式のうたが発生していました。

当たり前の光景すぎて、多くの人は意識したことがないかも……。
言葉が気になる、言葉で遊んでしまう。
言葉をぶつぶつ唱える、共有したくて歌う。
あと小学生なんか、すぐ替え歌をつくりますよね。言葉が好きな時期の特徴です。
15歳まで、とか、12歳まで、とか、年齢の部分は目安にすぎません。言葉に関してはいろいろといわれています。
臨界期としてよく囁かれるのは『12歳まで』という数字ですが……、
これは母国語獲得に関する有力なひとつの説というだけで、言語学習として〝タイムリミット〟や〝手遅れ〟があるという意味ではないことは、👇以下の読書記録📝に書きました。
「言語を習得させたいなら、『言葉が気になる耳』をつくれ。」これが本の著者である斉藤淳氏の主張でした。
「面白がって(考えて)聞く」「かたまり(文脈)をとらえる」これを知らず知らずおこなってしまうように、〝遊び〟として言葉とたわむれさせることが、言語学習の基礎である……といった内容です。
私もこれはその通りだと思います。
つい、聞いてしまう。ついつい面白がって、文脈をつなげてしまう。
聞ける耳をつくること。わらべうたも、言語獲得も、結局それが大事なのです。
聞ける耳とは、聞ける頭です。聞ける耳とは、情報をキャッチできるスキルです。
スキルを身につけさせてあげる、ということ。生涯に渡って豊かに言葉と付き合っていけるかどうかが、そこにかかっています。
わらべうたを歌うと静かになる?
「わらべうたを歌うと、なぜこんなに静かになるの?」と、言われることがあります。
(やってる人は、言われたこと、あるでしょう?☺️)
もちろん我々は、子どもを静かにするためにわらべうたを歌うわけではありませんが。(そういう大人都合のうたには反対です。)
静かになる……というのは、それだけ聞きたいという欲求に真剣である、ということだと思います。
聞きたい、引いては、〝学びたい〟という人間本来の欲求を満足させている。夢中になる瞬間は、穏やかで静かなのです。
「なんでこんなによく聴くの?」
「静かにしなさい! と言ってないのに、なぜ静かになるの?」
〝じっと聴く・じっと見る〟そういう子どもの姿がそんなに新鮮に思えるのは、逆に言うと、それだけ〝心の耳と心の目〟が欠けた世界に、我々はいま住んでいるということかもしれません。
そんな、満ちたりた姿がめずらしいような世界ではいけません。
そもそも子どもというのは、少し程度の高いものを求めています。等身大の自分よりも少しだけレベルの高いものをやりたい、という性質は普遍的です。大人が子ども用に用意したものが〝幼稚〟にすぎると、それを敏感に感じとっているように思います。
ふざけるのは遊びのレベルがその子に合ってない証拠だと、上手いことを言ってくれた教育者もいました。
つまり、子どもが不真面目なのではなく、大人が子どもに対して不真面目すぎるのです。
彼らの要求を満たせていない、考えないで、子どものせいにしているのです。
──先日、その日に初めて会ったばかりの小学生達と「おじろおじろ♪」をしました。
とある地域の子ども文化センターで「何かひとつ…」とその場ムチャ振りをしてもらったので(笑)、よろこんで応じました。
「小学生がこんなに遊ぶなんて……!」と、スタッフさんが喜んでくれました。
爆笑が起きたわけでもなく、活気に沸いたわけでもないけれど、子どもたちの目が輝いた。ただ真剣に子どもが遊んだという、その価値を、きちんと分かってくれる方でした。
話がはやい!!! と思いました😏 こういう大人が見守っている遊び場があると、子どもは幸せだなと思いました。
その場所は、さまざまな体験活動を行っている、それも子どもの自由参加で思い思いのペースで出来る、素敵なところなのです。
「小学生がこんなに寄ってくるなんて、すごいことです、どんな魔法ですか?」
魔法でもなんでもなく、べつに私の声が美しいわけでも、何か秘策をおこなったわけでもなく(笑)
やったのは、ただの『おじろおじろ♪』です。
なんの変哲もないわらべうたを、ただ普通にやること。
不真面目に楽しくはやらないこと。
真面目に、面白がること。
それだけで相手には届きます、人間は本能的に、言葉をキャッチしたがっているのですから。
褒められるべきは私ではなく、〝言葉が気になる耳〟を持っていた子どもたちです。
いや、おそらく全ての人間が、生まれながらにそれを持っているのでしょう。
自分で自分のスイッチを点ける。スイッチを押す日がいつ訪れるか。ただそれだけの事なのでしょう……。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
