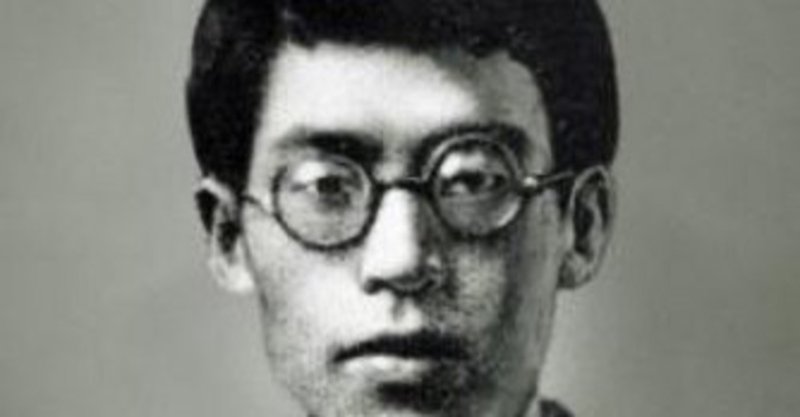
魯と孔子10ー三桓氏の変質ー「牛人」をめぐる国際情勢(2)
前538年、三桓氏の一角である叔孫氏の当主、叔孫豹が死んだ。
豎牛は、叔孫豹の庶子である叔孫婼(しゃく)を擁立してその補佐となった。
この豎牛が、魯の国政を担う叔孫氏をなぜここまで掌握できたのか。
不明な点は、多い。ただ、彼の振る舞いを見ていると、とにかく周囲の者同士を争わせ、結果として自分の立場を強化する、そうした謀略に長けていたようである。では、はたして彼は叔孫豹を追い詰めていく中で、その後のことをどのように考えていたのであろうか。
これは後の結果からの推測でしかないが、豎牛が描いた絵は、2通り推測できる。
一つは、叔孫氏を掌握して国政に介入し、魯国内での自身の地位を確保する。そのために叔孫氏をより増大させる必要がある。そこで、魯国内の利権をさらに、叔孫氏の利権として取り込んでいく必要がある。
とはいえ、かつての叔孫僑如のように、他の三桓氏の利権に手を出せば反撃される。そこで、むしろ彼らと結んで魯公の権力基盤を削ぎ落とすことで、叔孫氏と自己の基盤を強化していく…。
二つは、君主権力と三桓氏のしのぎ合いを利用しつつ、叔孫氏の利権そのものを取引材料として、豎牛自身の地位を確立していく…。後に見ていくが、豎牛の行動に一致しているのは、この二つ目である。
では、果たして豎牛とはなんだったのか。ふたたび叔孫豹死後の豎牛を追跡していくこととしよう。
老いた叔孫豹と2人の嫡子(1人は死亡、1人は斉に逃走)を共倒れに導いた豎牛であったが、まだこの段階では完全に叔孫氏を掌握していなかった。
叔孫豹が死ぬと、今で言う国葬が行われることとなった。
魯の国君である昭公は、叔孫氏の家宰である杜洩(とせつ)にその主催を命じた。少なくとも世間的には、この杜洩が叔孫氏の代表として認知されていたことを物語る。
そして、この杜洩は、亡き叔孫豹に忠実であった。
少なくとも、豎牛はこれを御せる存在でないと判断した。
豎牛は、叔孫氏を完全に掌握するために、この家宰の排除を決断した。
ここで豎牛は、外圧を利用して杜洩の排除を画策する。
そこで彼は、季孫氏の家臣たちに接触を図るのであった。
*ヘッダー画像:Wikipedia「中島敦」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
