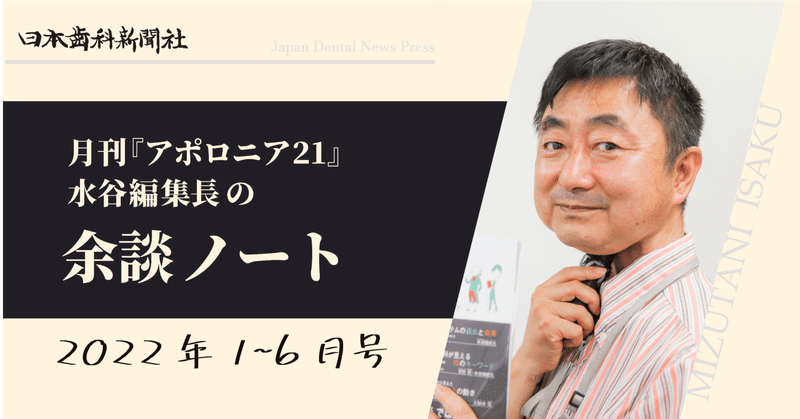
月刊『アポロニア21』編集後記まとめ2022年1月~6月号 水谷惟紗久
こんにちは。月刊『アポロニア21』編集長の水谷惟紗久(みずたに・いさく)です。
本原稿は『アポロニア21』の2022年1月号~6月号の「編集後記」を改変したものです。※2022年7月以降については「こちら」から
1月号
新年に当たり、やや厳しい将来像につながるお話です。オックスフォード大学歴史学部のブライアン・ウォード=パーキンズ氏は、「西ローマ帝国崩壊後」の世界で劇的な社会経済上の劣化が起こり、そこからの回復には、優に800年以上かかったことを明らかにしています(『ローマ帝国の崩壊―文明が終わるということ』、白水社、2014年)。
それによると、経済の縮小は、大規模な建物や豪華な装飾品などよりも、普段使っているオリーブ油を入れる壺、壁の落書きなど、一見些末な物事の変化に表れるとのこと。ローマ帝国のように複雑で大規模な広域経済圏では、それぞれが専門的に限られた業務のみを行いつつ、それらが連携して成り立っていたため、社会秩序がいったん崩れると、皆が何も得られなくなるリスクを抱えていました。これは現代文明にも当てはまるかもしれません。
こうした複雑なネットワークは、庶民階層にも識字能力が広がっていたことで成立していました。ここで言う識字能力とは、高尚な哲学や詩文などではなく、愚痴やジョークのような、些末で下世話なものの量と質で劣化が分かるのだとか。
長引くコロナ禍に伴い、世界経済の退潮を指摘する意見が目立つようになってきました。それ以前から、日本に関しては厳しい見方が四半世紀ほども続いています。危機対応の進んだ現在も、日常の何げない変化から、社会の大きな流れを先取りできるかもしれません。
今回の特集では、急速に業態変化が進んでいる小児歯科のトピックスを扱いました。東京都と岩手県の歯科医院に登場していただきましたが、共通しているのは、「スタッフ主導に切り替えて成功した」ということです。
どの医院でも実践できるノウハウではないかもしれませんが、院長の「この人だ!」と見抜く目が大切なのだと感じました。子ども特有の口臭に関する本田俊一先生のレポートと合わせ、ご一読いただければ幸いです。
2月号
昨年、サンスターがまとめた各国の口腔保健状況のレポート(Sunstar Global Healthy Thinking Report 2021)が話題になっています。
例えばドイツ。21世紀に入って歯の健康指標が急速に向上し、今やオランダと並んで世界の2トップになっていることが知られていますが、その理由の一つはチェックアップ率の高さのようです。調査によると、年2回予防目的で歯科受診をする習慣のある人は45%で、堂々の1位。
しかし、これには続きがあり、「歯科医院が快適な場所とは思わない」という回答も、24%で1位だったとか。
私は、ドイツの歯科医院を何軒か取材で訪れたことがありますが、たいていは地元の団体や企業が推薦してくれる「自慢の医院」が取材対象でした。
そのため、「歯科医院は快適ではない」と思っている人が多いというのは、そうした取材経験からはやや考えにくいのですが、「鬼ババ歯科衛生士がガリガリ歯石を削る」といった医院もあるのでしょうか。
このレポートでは近年話題の、患者が自分で施術する「DIY歯科」についても調査。日本は「試したことがない」という回答が82%で最も多かったのですが、歯科医院を介さずに歯科的処置を自分で行うことができる商品やサービスが、ホワイトニング、矯正を中心として国際的に広がっているようです。
「DIY歯科」が最も広がっているアメリカでは、以前から表面麻酔剤、ミラー、エキスカベーター、グラスアイオノマーセメントをセットにした「むし歯治療キット」がドラッグストアで販売されています。
今回の特集では「痛み」をテーマに、「歯周病はなぜ痛くないのか?」という疑問から生まれる科学的思考、日大松戸病院の痛み外来での実践、ファシア研究を中心とした国際的な最新事情について紹介します。私自身も患者となり、取材を通じて、「痛み」という身近な物事の深さを実感できました。
3月号
旧ソ連製のカメラは、中古市場で「ロシアカメラ」と呼ばれることがあります。しかし、それらの中で高級品に属する「KIEV(キエフ)」というラインナップはロシア製ではなく、ウクライナのアーセナルという国営工場が作っていたものです。
世界最初の自動露出機構(AE)付き一眼レフ『KIEV10』などは珍品に属すものですが、私が愛用していたのは『KIEV2』という距離計連動モデルで、それほどレアなものではありません。ただし、いわくつきの代物です。戦後間もなくして、ドイツ・ドレスデンにあったツァイスイコン(カールツァイス財団傘下の世界最大のカメラメーカー)を接収したソ連軍が、工場と技術者をウクライナまで連行してプロトタイプを作らせたというエピソードが残っています。
こうした「技術分捕り品」は、そろってスターリン死後に品質が劣化してしまいましたが、ソ連崩壊後も作られていたそうです。
ウクライナはもともと同じソ連構成国だったこともあり、ロシアとウクライナを一緒くたにする傾向があるものの、現在の緊迫した状況を考えると、両国の違いを認識する必要があるのかもしれません。パイプオルガンで演奏される正教の典礼音楽は、西欧とは明らかに異質でロシアとの共通項が多い一方、ウクライナ民謡は、むしろポーランドに近いものも多く見られます。
政治やキリスト教などの表層文化ではロシア的であり、生活習慣などの基層文化では、反対側のポーランドなどとも似通った点があるといえそうです。
今回、ロシアで一番売れている歯磨剤『R.O.C.S』の日本法人に勤務するジェーニャさんに、ロシアの健康習慣をレポートしていただきました。近代化の父・ピョートル大帝(在位1682~1725年)の趣味が抜歯だったという歯科の伝統を持つロシアは、日本から最も近いヨーロッパですが、あまり知られていないことも多いことが分かります。
4月号
先日、主治医の先生から「咽頭がんの治療から3年がたちます。よかったですね」と言われました。その先生は当初、厳しい見通しを示していたので、互いにほっとした感じです。
手術と放射線化学療法で3カ月ほど入院しましたが、その間、気になったのが病棟薬剤師の存在意義でした。毎朝の回診で、医師から処方薬の説明は受けるし、実際の服薬上の指導は担当の看護師がしてくれるので、たまに病床に回ってくる薬剤師さんが何をしに来るのか、全く理解できませんでした。
薬の特性や注意事項を説明するためだとは分かりますが、あまり意味がないように感じて、「院内処方が減って暇なのかな?」と思うこともありましたが、もちろん、そんなわけはありません。
長年の業界活動の成果により医薬分業が進み、調剤薬局が増えたものの、メーカーから仕入れた薬品のパッケージ交換が主な仕事で、実際に調合をする保険薬局はほとんどなくなっています。そこで「患者との接点が重要だ」と方向転換して、説明業務を拡充している途上にあるのが現在の状況のようです。
医薬分業自体も、病院と別に薬局に行くことになるなど利便性の面で必ずしも患者利益につながっておらず、薬剤師の職域拡大だけが目的だった感じが否めませんが、病棟での業務も、現場の必然性から生まれてきた感じがあまりしないのはなぜでしょうか。
今回の特集で、デジタル化を踏まえた歯科技工の業態変化の最前線を取材しました。技術革新や制度改革は、それ自体が目的ではなく、歯科技工の発展が患者利益につながってこそ意味があるはずです。薬剤師の現状を見ると、業界の利益を患者利益と整合させて発展することが難しいと感じます。
その意味で、歯科医療関係者への取材記事が中心で、十分な問題提起ができたか不安もありますが、協力していただいた方々は、「どんな歯科技工(医療)にしたいか」が明確だと感じました。ご批判いただければ幸いです。
5月号
今回の特集では、医療法人社団翔舞会エムズ歯科クリニックの荒井昌海氏による、「受付の電話をなくして、コールセンターに集約」「インスツルメントの滅菌を、滅菌センターに集約」という新たな効率化戦略を紹介しています。
「電話をなくして大丈夫なの?」と不安になる院長は少なくないと思いますが、実際に通話内容を分析すると、ほとんどがアポ調整のため、電子予約システムがあれば、受付スタッフが対応しなくても大丈夫なのだとか。
以前、「歯科医師数が過剰だ」と問題になった際、諸外国と人口10万人対歯科医師数を比較すると突出して過剰とはいえないのに、何が問題なのか検討したことがあります。結果、「小規模で重装備の歯科医院が都市部に偏在している」という事実が明らかになりました。
歯科医師1人の医院でも、受付スタッフを常勤雇用するケースが一般的で、海外では病院などにしかなかったパノラマレントゲンが、早くから多くの医院に装備されていました。アメリカの田舎の小規模医院は、院長の携帯電話で予約管理している時代でしたが、「患者数が多い日本では、予約管理に人員が必要なのだ」と、事情に詳しい先生から教えていただきました。DX化により、そうした業務に人手を必要としなくなったということになります。
外線電話だけでなく、受付やバックヤードの業務の多くがDX化や外注・委託で大幅に簡略化できるようですが、次の問題は、「簡略化した分、どのサービスを強化するか」という点です。荒井氏は「患者さんとの生身のコミュニケーションを充実できる」と、一見冷たく感じられるDX化が医療現場に温かみを取り戻す可能性について、期待をにじませていました。
5・6月号では、さまざまな経営モデルを実際に試した実例を紹介する特集を連続してお届けします。取材にご協力いただいた先生方、率直にインタビューにお答えいただき、ありがとうございます。
6月号
感染症対策と社会制度の歴史に詳しい法社会学者の西迫大祐氏(沖縄国際大学准教授)によると、ロックダウン、検疫、統計、衛生パスポートなどコロナ禍で行われたさまざまな施策は、本質的に新しいものではなかったとのこと。今までと違うのは、「自粛」をベースにした統治が行われたことだそうです。
3密を回避し、不要不急の外出を控えるという行動変容を求め続けた政府の在り方は、国民に「リスクマネジメントのプロ」としての振る舞いを求めるものだとする見方です。
大規模な感染対策が行われるようになった19世紀ヨーロッパは、自由・議会制民主主義の揺籃期。むしろ、「隔離は自由を抑制する」という意見も根強く、防疫制度の徹底は難しかったとのことです。
政府が国民にプロとしての振る舞いを求めるようになった現在は、本質的に新たな段階に進んだといえそうです。政府側も、「プロ」にお願いする以上は、相応の対価を支払うことは当然で、一部の業種・業態の事業者には補助金が支払われました。そうなると、厳密には「自粛」ではないのかもしれません。
歯科では、懸念された診療そのものに関わるクラスターの発生はほとんどなく、口腔衛生で感染・重症化を抑制できるとも考えられるようになりました。さらにコロナ対策の一環として、自動釣銭機の導入など受付業務のDX化や、ディーラー営業のルート訪問制限など在庫管理の見直しが進みました。
その意味で、コロナ禍は歯科にとって追い風になった部分も大きいといえるかもしれません。過去の大規模なパンデミックのたびに、社会構造は大きく変化してきました。「コロナ後」の雰囲気も漂い始めた今、何が変わったのか、変わるのかに注目したいと思います。
今回の特集では、「口コミサイトへの回答は診療行為の一部と考える」「患者さんの悩み事をそのままキャッチコピーに採用する」など、これまでになかったマーケティング手法を取り上げてみました。発想のちょっとした転換は、意外なアイデアに結び付くものだと実感しました。
この記事を書いた人
水谷惟紗久(みずたに いさく)
歯科医院経営総合情報誌『アポロニア21』編集長。
1969年生まれ。早稲田大学第一文学部卒、慶応義塾大学大学院文学研究科修士課程修了。
社団法人北里研究所研究員(医史学研究部)を経て現職。国内外1000カ所以上の歯科医療現場を取材。勤務の傍ら、「医療経済」について研究するため、早大大学院社会科学研究科修士課程修了。
主な著書に『18世紀イギリスのデンティスト』(日本歯科新聞社、2010年)、『歯科医療のシステムと経済』(日本歯科新聞社、2020年)など。10以上にわたり、『医療経営白書』(日本医療企画)の歯科編を担当。大阪歯科大学客員教授(2017年~)。
趣味は、古いフィルムカメラでの写真撮影。好きな食べ物は納豆。2018年に下咽頭がんの手術により声を失うも、電気喉頭(EL)で取材、講義を今まで通りこなしている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
