
言いたいことも言えない世の中でどう言ええるようにするんだい? ポイズン
WSD3か月の学びの中で考えたこと。書きながら考えてみる。
思い起こせば、あれは2019年の9月だ。ワークショップデザイナーの養成講座というのがあるというのを知り、説明会にいってみようと表参道にある青山学院大学に行ってみた。 説明会で、苅宿先生がお話されていた。「ワークショップとはコミュニケーションの場づくり」「それぞれの個人は違う。違いを受け入れて面白がる」という言葉。 面白い。もしかしたら今まで自分が経験してきたものを何か別の形で生かせるかもしれない。そんなぼんやりとした動機から受講を決めた。
そこで学んだ事。たくさんある。 ワークショップをチームみんなで考えて実践して。最大の難関は、参加者がどれだけリラックスして、自分のうちなる言葉を発する場を作れるのか。ということ。それが、ワークショップデザイナーの課題だんだなと思った。
子供時代は思ったことをそのまま相手に伝えていた。それがいつしか形式ばったたくさんの鎧をつけた言葉になる。それは一律2980円で棚にずらりと並べられたセーターのように色は違うけどどれも同じような形。特にダサいとかかっこいいとも言われないけど、すっと忘れられていく。なぜ鎧を外せないのか? 自問してみる。「恥ずかしいから」「こんなこと言ったら変だと思われるから」「みんなと違うのがいやだ」「自分の考えを言葉にするのが難しいから」 うむ。でもそれが当然だし、それはなかなか崩せない。
以前、番組に出演してもらった京都芸術大学の齋藤亜矢さんのお話を思い出した。「ヒトはなぜ絵を描くのか」という著書の中でナディアという少女の絵が紹介されていた。https://www.iwanami.co.jp/book/b265853.html

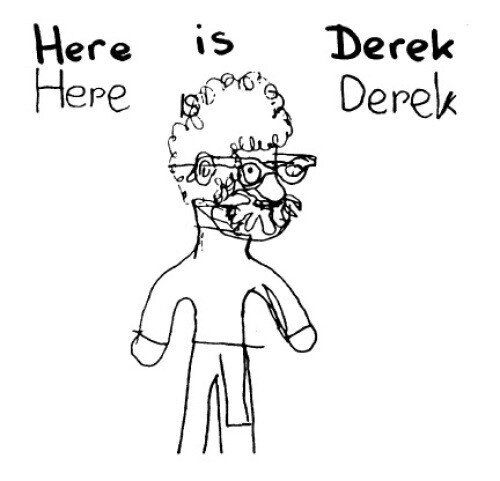
同じナディアという少女が描いた絵。上はナディアが5才の時にかいたもので、下の絵は9才の時に描いたものだ。彼女は小さい頃から言葉とコミュニケーションの発達に遅れがあり、他者のとの繋がりがほとんどできなかった。3才くらいから絵を描くことを覚え、天才的な画力で評判になった。しかし、言葉のトレーニングを重ねてある程度言葉のコミュニケーションを覚えていくと、周りの子供たちが描く絵を真似するようになり、だんだんと写実的な画風から子供ぽい絵を描くように変わっていったという。
言葉の獲得によって、観たそのままを描くのではなく、「顔」と周囲が認識している「顔」を描くようになる。目はまるく、鼻はとんがっていて、口はにっこりという記号として絵を描く。というのは、逆に「言葉」の表現でもおこなっているかもしれない。 世の中で溢れている言葉を切り取って使ったり、本の中で知った言葉をそのまま引用したり。言葉を記号として使っている。
ワークショップは、参加者どうし、他者との違いを楽しめる場作りにできると実り多い機会になると思う。 言葉を記号ではなく自らの内側から発生したものとして炙り出せるのは、どうのような場にしたらよいのだろう。その答えの1つが「肩書きはずし」なのかも。名前や肩書きではなくニックネームで呼び合う。すると話しやすくなる。また、「我を忘れて夢中になる」というのも大事だ。 大人を夢中にさせるのはどんなことだろう・・・
ちなみに、肩書きはずしの例でいうと私は実践1のチームのみなさんから「長官」というニックネームをいただいた。「なんかゆりこさんって長官ぽくない」という一言で。なんで長官なんだろうとは思ったが、長官と呼ばれて、長官になってみると、いろいろと言いたいことも言いやすい。肩書きを外して、自分からある記号になってみるとまた物事の見え方が変わってくるのかもしれない。
そんな事を考えて、これからはワークショップを考えていきたいと思う。まずはいろんなWSに参加することから始めたい。来年の抱負はこれだ!
みなさんメリークリスマス! ハッピーニューイヤー! 良いお年を!
