
【勝手にストーリー】いたずら

『芽愛ねぇちゃーん!』
『あははー、ひっかかったー』
子供の頃から、芽愛ねぇちゃんにはからかわれてばかりだった。
抹茶アイスの中にワサビを混ぜられたり、手書きの「さいばんしょ」と書かれた手紙を見せられて「牢屋にいれられちゃうよ~」と言われたり。
僕が引っかかるたびに芽愛ねぇちゃんは嬉しそうに笑う。
いたずらされるよりも、普通に遊んでくれることの方が多かったけれど、僕は、いたずらが成功した後の芽愛ねぇちゃんの笑顔が好きだった。
☆
「えいっ」
「うわっ!」
突然、首筋にひやりとした感覚。俺はおどろいて情けない声を上げてしまった。
振り返ると、芽愛ねぇちゃんが得意げな顔で俺の方を覗きこんでいた。
ソファに深く沈み込んで画面に集中していた俺は、すぐ後ろに立つ芽愛ねぇちゃんの気配に気づかなかった。
「お、おどかすなよ!」
「相変わらず驚かせがいがあるなあー」
にやにやと俺の顔を見下ろす。手にはジュースのペットボトルが握られており、こちらに差し出されている。それを受け取りながら、俺はまた画面に視線を落とす。
「何見てるの?」
「…Vtuber」
返事を待たず、芽愛ねぇちゃんは俺の耳からイヤホンを片方ひったくって顔を寄せてくる。
「っ…!」
咄嗟に反対側に顔を逸らすが、芽愛ねぇちゃんは気にしてもいない様子で画面を見ている。
「へえー、可愛い声だね。こういう感じの声が好きなの?」
「ま、まあ…」
からかわれるかと思ったが、意外にもそのVtuberが気に入った様子で、画面を見つめたままソファに座りなおした。
そこから、なぜか一緒に俺の推しVtuberを視聴することになり、俺は色々と恥ずかしいやらくすぐったいやらで、気もそぞろだった。
小学生くらいまではこうやって並んでTVやゲームをしていたが、今はもうお互い高校生だ。
俺の声が低くなって、『僕』から『俺』に変わって、身長が彼女を追い越しても、芽愛ねぇちゃんは態度を変えない。
俺の方はと言うと、そんな距離感にいちいちドギマギしてしまうのだ。
「そういえばさ」
不意に話しかけられ、びくっと肩が跳ねてしまう。
「誕生日、なにか欲しいものある?」
「え…別に…」
「つまんない返事だなー、何でもいいんだよ?去年みたいに」
その言葉に、去年を思い出す。中学3年生の時だ。
『switchが欲しい』という母親との会話を聞かれており、誕生日当日、俺の部屋の机に『誕生日おめでとう。switchを贈ります 芽愛』というメッセージと共にギフトボックスが置かれていた。
中には電気のオンオフスイッチが入っていた。
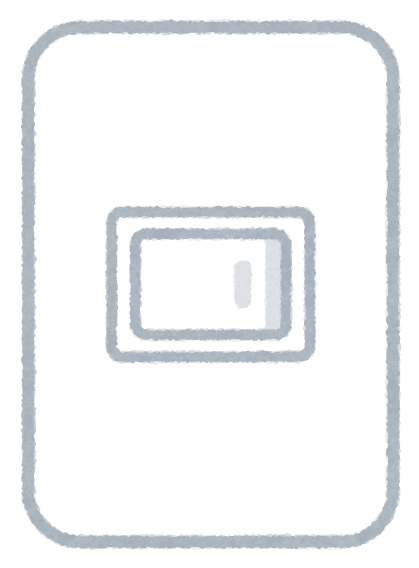
「…何でもいいよ」
Vtuberの配信が終わり、最後の挨拶コメントを打ったところで、俺はスマホをポケットにしまって部屋に戻った。
☆
誕生日当日。両親と共に、以前から頼んでおいたスマホの新機種を契約した。
俺は新しいスマホにワクワクしながら、さっそく部屋に戻ってベッドにダイブし、アレコレと設定を始める。
(おおー、画質やっぱ違うな…これでオープンワールドとかやったら凄そう)
前のスマホで使っていたアプリを一通りDLし、ゲームでもやろうかと思っていると、メールの通知音が鳴る。
「…芽愛ねぇちゃん?」
『16歳おめでとう!ささやかながらプレゼントがあります!
↓↓↓ここをクリック!↓↓↓
http//.........』
誕生日を祝う言葉の下に、URLが添えられていた。
(スパムメールかよ…)
とはいえ、送り主が芽愛ねぇちゃんである以上、おかしなワンクリック詐欺などではないだろう。
中身を想像しながら、URLをクリックしてみる。
「…音声データ?」
サイトに飛ぶと、サーっという小さなホワイトノイズが流れ出す。何かと思っているうちに、芽愛ねぇちゃんの声が聞こえてきた。
『○○くん!お誕生日おめでとう!』
いつもの芽愛ねぇちゃんの声だ。すこし低くて、聞き取りやすい、ハキハキした声。子供のころからずっと聞いていた声だ。
『何を贈ったら喜んでくれるかなって色々考えて、これを贈る事にしました!』
何だろう。バースデーソングでも録音したのかな?
『えー、スペシャルゲストを呼んでいます!◇◇ちゃん!』
「!?」
思わずベッドから上半身を起こす。
『コホン…えっと、○○くん!お誕生日おめでとう!』
録音環境の問題だろうか、ホワイトノイズに紛れてはいるが、俺の推しのVtuberの声だ。
「え?え?」
『これからの○○くんの人生が、もっと楽しくなりますように!これからも、応援よろしくね!』
「…マジ…?」
『というわけで、○○くんの好きな◇◇ちゃんにバースデーメッセージをもらっちゃいました!どう?喜んでくれたかな~?それじゃ、バイバーイ!』
呆気に取られている間に音声データの再生は終わっていた。
「…」
首を傾げ、もう一度再生しようとした、その時。
「○○くん!」
「えっ!?」
扉の方から声がして、顔を上げると、芽愛ねぇちゃんが立っていた。
「…え?」
「えへへー、引っかかったー。どう?似てたでしょ?」
「その声…この音声…あ」
俺の思考はそこでようやく追いついた。
そういえば、昔も芽愛ねぇちゃんの声真似に引っかかった事があった。その時は電話で、芽愛ねぇちゃんのお母さんが掛けてきていると思っていたら芽愛ねぇちゃんだった、というオチだった。
「わざと音質落としてちょっとわかりづらくしたから、余計にわかんなかったでしょ?」
いたずらが成功したことが嬉しくてたまらないといった表情で、俺の顔を覗き込む芽愛ねぇちゃん。
俺は騙されたという気持ちよりも、芽愛ねぇちゃんの意外な才能に驚いていた。
「…正直、わかんなかった」
「んふふー!でしょでしょー!」
ベッドの端に腰掛け、足をばたつかせながら地声とモノマネの声を交互に出して見せる芽愛ねぇちゃん。
「私もVtuber、なってみよっかなー。どう?○○くん、あの声だったらけっこう人気出るんじゃないかなー?あ、はいコレ、ほんとのプレゼント」
差し出されたその包みを受け取って開けると、中にはクッキーが入っていた。形や大きさが違うところを見るに、手作りの様だ。
「…Vtuberになるのは別にいいんだけどさ。あ、うまい」
俺はクッキーを一つ口に放り込み、つぶやく。
「うんうん」
「元の声のままの方が、いいんじゃない?」
少しの沈黙。
(あ…)
言ってしまってから、ちょっと、いや、だいぶ恥ずかしい事を言ってしまったことに気づく。
「あー、えっと」
「んふふー、そっかー、そんなに私の声が好きなのかー」
しまった。またからかわれるネタを与えてしまった。
どうせまた得意げな顔をしているんだろうと、おそるおそる芽愛ねぇちゃんの顔を見る。
「そっかそっかー、なるほどなー」
そういってはしゃぐ芽愛ねぇちゃんの顔は、耳まで真っ赤だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
