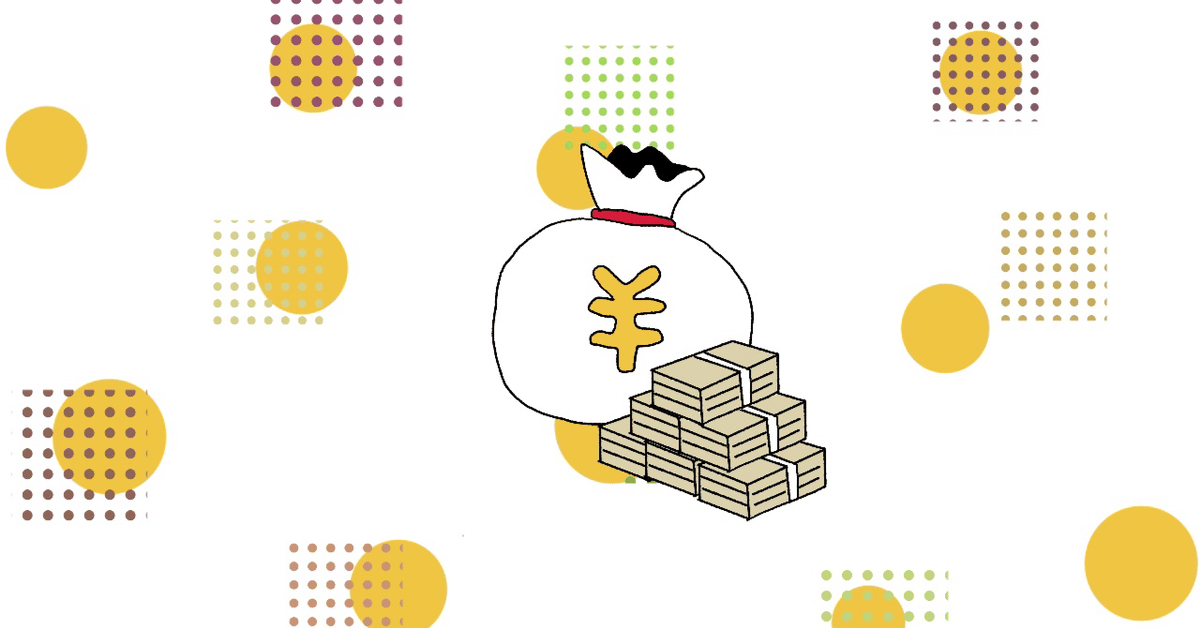
なぜ高利回り?「付加年金」の歴史を考える
こんちは!副業社労士まさゆきです。
前回「自営業者には『付加年金』があり、厚生年金・企業年金・イデコと性質が異なる」と書きました。今回は付加年金です。
付加年金は第1号被保険者のみ加入できる年金です。月400円を国民年金保険料にプラスして40年間納めると、65歳以降「200円×12ヵ月×40年=96,000円/年」年金が増額します。付加年金は国民年金保険料を払っていれば加入できる「付加」される保険です。
支払保険料は「400円×12ヵ月×40年=192,000円」なので、2年間受給すれば元が取れます。
どれだけ高利回りか、計算してみましょう。
仮に、65歳から80歳まで15年間付加年金を受給すると、年金受給額は「96,000円/年×15年=144万円」
付加年金で19.2万円の保険料(元手)が144万円になったので、運用益は
「(144万円-19.2万円)÷19.2万=650%」となります。
支払始め(20歳)から受取終了(80歳)まで60年、よって年平均運用益は
650%÷60年=10.8%
株式投資の平均運用益は6%程度と言われます。10.8%の高利回りが保険料を支払うだけで“確定”、こんな有利な商品は他にないでしょう。前回noteで書いた「自営業者のイデコの掛金上限が少ない」理由は、この付加年金のせいかもしれません。
付加年金とイデコは「両方合算して月68,000円が自営業者の掛金上限」と定められています。しかし、合算する掛金は「月1,000円未満は対象外」なので、付加年金掛金の400円は合算対象外です。実質付加年金とイデコはお互いの掛金上限に影響を与えません。
こんなにお得な付加年金、何故存在するのでしょう?
付加年金は1970年に誕生しました。色々調べると2つの目的で付加年金が出来た様です。
《国民年金の増額要望に応えて》
1965年に国民皆保険制度となった当時、国民年金は「保険料は一律、貰える年金額も一律」でした。金融市場も発達していない中、富裕層が運用手段として「年金を増額する仕組み」を求め、付加年金が誕生しました。
《国民年金の納付を促進する宣伝手段として》
1965年当時、国民年金保険料を支払義務がある人は約3,300万人でしたが、この内650万人しか所得税を納税していなかったそうです。国民皆保険といいながら、制度開始から「保険料免除制度」を作らなければいけなかったほどです。国民の「何故年金保険料を納めなければいけないのか」反発の中、「年金保険料を払うと付加年金という高利回り商品を利用する権利が出来ますよ」という宣伝目的だった、と推察します。
付加年金が始まった1970年10月当時は下記の通りでした。
■国民年金の保険料は月額450円
■付加保険料は月額350円
■老齢基礎年金(=当時は国民年金)の満額の受給額は9万6000円
■付加保険料を40年間、フルに納めていた場合の付加年金の受給額は、200円×40年×12ヶ月=9万6000円
つまり、国民年金の満額と、付加年金の額が「同じ」です。国民年金受給額の増額目的で制度がスタートしたことが判ります。
しかし、付加年金による受給額増額目的は僅か3年で崩れます。
1973年に年金に対して物価スライド制が始まります。同年のオイルショックによる物価高から、年金額にも物価スライド制を導入しなければなりませんでした。
付加年金は物価スライドの対象から外れました。“追加分”だったからでしょう。また、高齢化による年金将来像を危惧する声もこの頃から出ています。高利回りの付加年金を増額すると年金制度が破綻しかねない、と思ったのでしょう。
1974年には国民保険料は900円になり、国民年金受給額は24万円となりました。2024年の国民年金は保険料16,520円、国民年金受給額は77万7800円となっています。他方、付加年金は保険料月400円、年金受給額9万6000円と受給額は変わりません。「この年金の事は忘れてください」なのでしょうか。
普段関心を持たれることがない「付加年金」、歴史を考えてみると、色々見えてくるものがあります。歴史好きの方にも読んで頂ければ幸いです
ではまた次回
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
