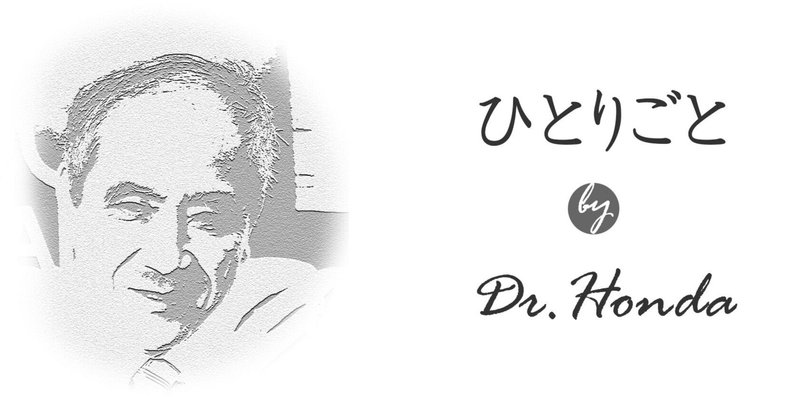
Dr.本田徹のひとりごと(69)2017.5.22
「共生主義」社会ってなんだ? ー西川潤さんとマルク・アンベールさんの本からいただいた啓発ー

1.はじめに
先日、尊敬する開発経済学者で、早大名誉教授の西川潤先生(ここから先は、親愛をこめて「西川さん)と呼ばせていただきます)から、フランスの経済学者マルク・アンベールさんとの共同編著「共生主義宣言 - 経済成長なき時代をどう生きるか」(コモンズ)をお贈りいただきました。
文章は平易ですが、少し横文字の用語もありますし、内容は必ずしも簡単に頭に入るものではありません。一つには、東京のような大都会に暮らして、「外」から与えられた食物や消費財に頼っているだけの私のような人間には、ほんとうの意味で「共に生きる暮らし」をしている自信がなく、実感として「共生主義」を受け入れ、実践することが、まだむずかしいのかもしれません。
しかし、この本に盛られているマニフェスト(宣言)とそれを支える考え方、そして豊富な国内外の事例は、たぶん人類や地球の未来と運命に深くつながる重要なものなのだ、という確信はもてました。ですので、一知半解な知識だし、まちがった理解に基づいたデタラメを言うリスクが大いにあると、思いつつ、この一文を草し、皆さんにも一緒に考えていただければ、嬉しいです。
まず、「共生主義」とは何かについて、フランス発のこの運動のホームページに掲げられた宣言をお読みになってください。原語はフランス語ですし、全体を知るには仏語の理解が必要ですが、要約版は日本語を含むいくつかの言語でも読むことができます。
共生主義宣言(要約版)
ずばり「共生主義」(Convivialisme:仏語)とは何か? アンベ-ルさんは第2章の「共生主義宣言―相互依存宣言」の中で、こう語っています。
「共生主義は、『自然資源が有限であることを十分認識し、この世界を大切にする気持ちを分かち合いつつ、競い合ったり協力し合ったりして人類が生きていくには、どのような原則が必要か』を考える。もちろん、われわれはみなこの世界に等しく属しているということを念頭に置く」
なるほど。得心の行く、考え方ではあります。
2.「いのちの思想」の滔々たる系譜
さて、先日アーユスのNGO大賞を、ありがたく、また慎んでお受けしたときのスピーチで私は、青い地球に生命が宿って38億年くらいの時が経ち、宇宙船地球号は、膨大な<いのち>とそのゲノムを乗せてどこへ向かおうとしているのか、と言った意味のことをお話させていただきました。
核戦争や過度な経済・産業活動によって地球環境自体を滅ぼしてしまう、破壊的な能力を人類が獲得してしまった今、私たちが生命界全体に対して負っている責任の重大さは一層ぬきさしならないものになっています。
アーユス(サンスクリット語の「いのち」)の名を冠するNGOの賞を授与されるという栄誉をいただく以上、そのことにはぜひ触れさせていただきたいと思った次第です。
私の乏しい読書や学習の経験からは、アンベールさんや西川さんの「共生主義」は、古くて新しい、人類共通の生命哲学の系譜を受け継ぎ、危機にある現代にもう一度実践的な知恵として位置づけし直そうという、模索の中で生まれてきたもののようにも見えます。
釈迦、老子に始まり、近現代で人類に大きな知恵を残してくれた、ソロー、トルストイ、チェーホフ、ガンジー、宮沢賢治、南方熊楠、レイチェル・カーソン(「沈黙の春」の著者)、シューマッハ(「スモール・イズ・ビューティフル」の著者)などの人びと。そして、共生主義という言葉の直接の生みの親は、イヴァン・イリッチのConviviality(自立共生)にあることを、私は西川さんの筆になる本書の第1章を読んで初めて知りました。
そう言えば、イリイチの「コンヴィヴィアリティのための道具」(ちくま学芸文庫)の訳者・渡辺京二さんは、「逝きし日の面影」の著者でもあり、「苦海浄土」の石牟礼道子さんの同志とも言える人です。このお二人がどんなに深く人のいのちを見つめ、慈しみ、語って来たかを、すこしだけ、学んできた者として、共生主義の広い裾野を感じることができます。
3.プライマリ・ヘルス・ケアから皆生農園まで - 実践を通して学ぶ
プライマリ・ヘルス・ケア(PHC)は、共生主義を保健・医療の分野で展開したものと考えることもできるな、と私は本書を読んで、改めて感じました。西川さんはかつて、鶴見和子さんらと共に「内発的発展論」を唱えた先駆者でもあります。
彼が同名の書(東大出版会 1989)の第1章「内発的発展論の起源と今日的意義」で紹介しているのは、1977年にダグ・ハマーショルド財団が提言し、当時世界的な反響を生んだ「もう一つの発展(Alternative Development)」論の基本原則でした。
つまり、1)人間の基本的必要に志向(Needs-oriented)、2)内発的(Endogenous)、3)自立的であること(Self-reliant)、4)エコロジー的に健全であること(Ecologically sound)、5)経済社会構造の変化が必要であること(Based on Structural Transformation)。これは、途上国の主導で1970年代に、新国際経済秩序(New International Economic Order)が国連総会で採択され、それに呼応する形で1978年にPHCに関するアルマ・アタ宣言が発布されたのと、軌を一にする動きだったわけです。その意味では、PHCは、より公正で、普遍的な「もう一つの開発」を、保健・医療分野で実現しようとした、試みだったとも言えます。
この「ひとりごと」の45回(2013年6月)で私は、「草木国土悉皆成仏」という天台密教思想の根幹にある(梅原猛さんの説)ことばに触れながら、UNESCOの文化多様性宣言の中のある文章を紹介しました。以下、その部分を引用します。
草木国土悉皆成仏をめぐって
2001年にユネスコは、「文化多様性に関する世界宣言」(Universal Declaration on Cultural Diversity)を出しています。その第1条で、文化多様性は人類共通の遺産(the common heritage of humanity) だとして、「人類にとって文化多様性が必要なのは、自然にとって生物多様性が必要なのと同じだ」(Cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity is for nature) と強調しています。
そして、この宣言は、2005年にユネスコが出したもう一つの宣言「バイオエシックスと人権に関する世界宣言」(Universal Declaration on Bioethics and Human Rights)と「対」になっているものです。
生物多様性と文化多様性の両方を尊重していくことが、人類と地球の生存と発展のために不可欠だという価値観は、この共生主義を貫くものともなっているのです。
本書では、理論的なことにとどまらず、フランスや日本で共生主義に基づく、環境に親和性の高い農業実践と、それを都市の消費者を直接つなぐ運動の成果事例が豊富に紹介されています。またアフリカ学の勝俣誠さんによる、現場と理論をつなぐ丁寧な解説も、たいへん参考になります。
私自身は、元・JVCのスタッフで、ソマリアで「風の学校」の創設者・中田正一さんとの出会いが機縁となって、農業の道に進んだ鴇田三芳さんたちによる「皆生農園」の働きに共鳴し、小さな定期購入者になっています。毎月どんな新鮮野菜が届くのかなと、楽しみにしています。彼のところの農産品はほんとうにおいしく、解説付きできちんと送ってくれますので、皆さんにもお薦めしたいと思います。皆生農園のHPは下記の通りです。
皆生農園のHP
昔、鴇田さんがまだ農園を始めたばかりのころ、小学校入学前の三男の耕(こう)を連れて、当時江戸川区小松川にあったシェアの事務局を支えてくれていた、大嶽さんの息子さんと一緒に彼の農園を訪れ、芋堀りをさせていただいたときの、子どもたちの喜びようはいまだに忘れられません。そういう土になじむ体験を通して、都会の子どもたちが、食べ物を作り、いただくことが、どんなに大変で、でも楽しい営みなのかを、学んでいく機会を増やすことはとても大切です。その意味でも、こうした、志ある農業実践家と、私たちはもっと結びつき、協力していく必要があるのでしょう。

4.結びとして―里山資本主義とSDGs
2011年3月11日の東日本大震災とその直後に発生した、福島第一原発事故は、今に続き、またいつ終息するとも言えないたいへんな試練を日本列島とその住民にもたらしました。その帰結はたぶん、22世紀になっても本当の意味では見えてこないのだろうと思います。
路上生活者支援の週刊誌「ビッグイッシュ―」が2017年5月1日号で、「おーい、里山」という特集をしているのはとても時宜にかなったことでした。この雑誌は一貫して、福島からの避難民のためのメッセージを発信し、事故の被災当事者たちの声を伝え、専門家の意見や助言を掲載し、当事者たちを助ける働きをしてきたからです。同時に、危機に瀕する福島の美しい里山をどう蘇らせるかは、住民と「外からの」協力者や専門家が一致して考えていかねばならない、長期に及ぶ課題なのでしょう。このプロセスで、行政が果たさねばならない役割にも大きなものがあります。
その意味で、私たちが学ばなければならないのは、「里山資本主義」という考え方なのかもしれません。提唱者の藻谷浩介さんと、NHK広島取材班の共著については、以前紹介したことがあります。
「里山資本主義」 藻谷浩介、NHK広島取材班(角川Oneテーマ21)
ひとりごと37:2011年3月
日本哲学会の場で聴く「持続可能性」の思想 - 原発事故と大震災の中で働く哲学者たちの危機意識
「共生主義」は本当に可能なのか、そして、日本の社会で多数派と言わないまでも、きちんと影響力や発言力をもった考え方として、定着し、広まっていくことができるのか。
そんなことを思いながら、この有意義な本の最後のページを閉じたのでした。
最後に、シェアの現場での仕事に関わりの深いSDGsについて。国連が2015-2030年の15年間にわたって世界全体の(途上国だけでなく先進国にも必要なものだから)開発目標として定めたSDGs(持続可能な開発目標)は、まさに共生主義にもとづく社会を創っていこうという野心的な企図でもあるわけです。
SDGsを通して、私たちの暮らしを成り立たせている、モノやカネや情報やサービスによる、世界的なつながりや構造的差別・搾取の関係を見直し、少数者や生態系に対してより配慮し権利尊重を旨とした、生き方が問われてきます。人びとの健康に関わるNGOとしては、シェアはやはりSDGsの中でもUHC(Universal Health Coverage:普遍的医療保健保障)に関する分野において、参加型で、インクルーシブ(包摂的)な活動を目指していきたいと願っています。
さて、今日からは東北タイにでかけ、デビッド・ワーナーさんや、HSF(Health SHARE Foundation)の仲間たち、工藤芙美子さん、広本充恵さんらと活動をともにしてきます。
また帰国したら、ぜひ、この「ひとりごと」で、タイからのつぶやきを皆さんと共有したいと思います。
2017年5月20日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
