
誰が星の王子さまを殺したのか~読書記録10~
「星の王子さま」は、フランスのサンテグジュペリによって書かれたものであるが、日本では1953年に出版された内藤濯(ないとう あろう)訳が有名である。(というよりも、版権の関係で、他の方が訳せるようになったのは最近である。


左は、私が高校生の時に購入した第51版。右は、2005年に倉橋由美子さんが訳されたものである。
実は内藤先生の訳以外を知ったのは昨年で、Amazonで取り寄せ、読み比べてみたのだ。これは、後で細かく比較すると面白いと思うのでこんなところにしておくが。
サンテグジュペリは伯爵家に生まれ、フランスではイエズス会の学校、スイスではベネディクト会の学校にと、カトリック系の学校を出ている。ということで、このメッセージはかなりキリスト教系なのである。最期に蛇に噛まれる。これは創世記の初めに人を誘惑し、罪を犯させた動物は。。。と考えると。など解釈がたくさんある。
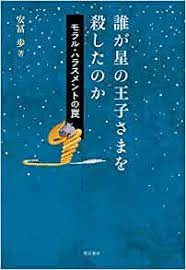
安富歩「誰が星の王子さまを殺したのか」
副題は「モラル・ハラスメントの罠」とある。安富先生独自の「星の王子さま」解釈が面白かった。安富先生は東大教授である。

女装癖で有名。。。

2019年の参議院選挙での記者会見より。
「星の王子さま」が描き出しているものは、人間と言うコミュニケーションなしでは生きられない生き物が取り交わす、そのコミュニケーションそのものに潜んで人間を苦しめる「悪魔」の真相だと、安富先生は考えておられる。サンテグジュペリ自身、この悪魔に取りつかれ、悶え苦しみながらも闘い、死んでいった。
王子さまの星に侵入した薔薇は自意識過剰で王子さまに罪悪感を覚えさせていく。色々な言葉巧みに王子に話しかけるバラ。これこそがモラルハラスメントの典型なのだ。バラに騙されていた事を知り、王子は泣くのだが、バラに対する怒りよりも、「バラを傷つけたりしないか」の自責の念である。深い罪悪感を抱かせるバラの存在。これこそがモラルハラスメントである。
そこに出てくるのがキツネであり、このキツネは「セカンドハラスメント」の役割を持っている。
DVやモラルハラスメントの被害にあっている人が勇気を振り絞り、警官、役所、弁護士、医師などに相談に行くと、そこで更なるハラスメントにあうということがよくある。
「あなたにも隙があった」
「あの人がそんなことをするはずがない」
「このくらいたいしたことがない」
などなど、言う相談員。。。
又、最初の訳者である内藤濯氏の思いがかなりあるのだと、安富先生の解釈から知った。
内藤氏が使っている「飼いならす」という言葉である。
被害者が加害者との関係をお互いさまと思っているならモラルハラスメントは成立する。
八幡洋氏は、「星の王子さまは基本的に善意しか存在しない世界である」と言っている。
これはハラスメントの本質を見事に反映している。
ハラスメントの本質は、被害者が虐待者によって操作され「善意しか存在しない世界」に自分が住んでいると思い込み、苦痛を感じることに罪悪感を抱く。それである。
最期に王子は「ぼくの花に、ぼくは責任があるんだ」と毒蛇に自分を咬ませて自殺してしまう。苦しむ被害者が、加害者の元を離れながらも自らの意志で戻り悲劇的なケースになることがある。それに通じるものがある。
著者のサンテグジュペリ自身も色々あったようだ。。。それは、又別の本を読むことにしたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
