
2月最後の日記
おはようございます!千葉さんのマガジンおもれー。今日までがノートのサブスクの期限なのでおもれーと思いたいというのも多分にそこには含まれていそうで、いんや含まれてねえと言える。
まあいったん具体的な話はおいとくとして、抽象的なよさの話もおいといて、もうすぐバイト先の最寄駅についてしまう。あまりに書き始めが遅い。千葉さんの日記を読み耽っていたのもあるし、今日が三連勤の最終日だというのがもっとも主要な要因としてたぶんある。あとハイキューのサントラ、劇場版のほうをまた聴いている。音はいつも、ほかの音楽を聴いているときより大きい。ボリュームのメーターでいえば2.3つまみくらいは違う。千葉さんの文章はハイキューの、熱烈にドラマチックで、たまにダサっ!ここはダサいぞ!ってなるくらいの熱血、なんというのか青い炎というか、ずっと風は吹いている、それも熱気を伴わない風、風自体は爽やかで、これがなくてはこんなに熱い場所に長いこといられなかった、とツッキーが黒尾哲朗に思ったであろうことと同じようなことを今僕も思っている。腐女子的、あまりに自己本位な見解である。こんなものを考察と呼ぶべきではない?いや考察という言葉自体ぽっと出のように思える、いつから出てきた?僕の身の回りでいえば、なんだろうやっぱりあなたの番ですになるのか、いやそうは思いたくない。ベタすぎて。こんなところを出発点としたら恥ずかしいという絶対的な存在、逆鱗のようなものの存在を確かに我が体内に感じる。
宇宙兄弟版の地球の歩き方が出てる。2月の頭には出ていたらしいけどまったく気がつかなかった。うわっと見つけてすぐ飛びついて父にあげようと思った。このごろ彼は元気がない、カリカリしている。俺もしんどい。それを見ているのがというだけではない、物音に敏感でない母との間に立つのがあまりに辛い。去年もそういえば、父の誕生日の直前に父が激しく気を悪くしている時期があった。当時は貯金なんてまったくなかったから、でもなるべく早いほうがいいと思って、4月が終わる前にこれ買ってあげるよ、ムッちゃんのハンカチ、と好きな色を聞いて5月に注文した。あのタオルは今も父が気に入って使ってくれている。泊まり勤務から帰ってきた日の洗濯物にはかならず、緑色の大きめのタオルハンカチがみえる。今年はちょっと早いけど、2月もまだ終わってないけど、まあ2ヶ月切ってるし言ってることはわからんでもないよな、てかまあ見つけたから買ったでもいいわけだけど、早めの誕生日プレゼントのほうが嬉しくない?嬉しいと僕は思うのでそう言って渡すことにしよう。
そんなこといったらまた収支計算発動しちゃうよ。もういいって。まあ全然俺できますけど。まだやれます。もうできないんですか?って、2月ってなんで31までないんですか?ってプンスカポコスカいってやってもいいくらいの心持ち。うーん。たけえのよ、2400円くらいだったよね税抜で。税込が税抜かでこれほど話が変わってくることもそうないので調べる。まあ歩いたほうが早いという言説もある。5メートルもないところにその本はある。平積みが3冊、縦に平積みが4冊、先頭はバンドで止められているがうしろの3冊は自由に読める。毎度思うがこれなんでなんだ、まあ読むもんじゃないですよ買いもせずに、ってアピールなのかな。できなくしちゃうと反発を招くから、できるんだけど後ろのやつを引っ張り出せば、まあそこまでするかねえ、みたいに言われている気がする。ため息交じりに。とはいえちょっとする。文字が小さい、これはどうしたものか。電子書籍がいいかな、iPadなら1ページずつあの画面に表示できるわけだから。しかし地球の歩き方を電子書籍でってねえ。ホームページやん。という。プレゼントに電子書籍ってのはまあ万歩譲っていいとしても、ちょっとモノとの相性が芳しくない。あとはお金の問題。昨日風呂代が結局1400円しかかからなかったので、もともとたしか1700円と見立てていたからまたちょっと浮いた。しかも驚くべきことに、あっくんへ24万貸してくれたお礼として利子のようなものをあくまで出血大サービス!のような形で渡したい、ただ渡すだけじゃほんでつまらないというわけで、月例の地元のやつらとの(元)株主総会を今月も開催するにあたって、まえまえから告知していたビッグイベントとしてアサダ出資の一万円争奪じゃんけんが行われることになった。ていうか昨日された。俺が買った。ただ買ったんじゃないよ、あっくんには残機3というハンデをつけた、彼にとってもらうための催しだからね。まあ自分で設定しといてなんだけど、たいしてバカがつくほど有利でもないだろうな、じゃんけんって結局確率でいうところの極めて偏ったところだけがなぜか抜き出されてしまうものだから。で、俺が買った。なんなら彼に与えた残機はすべて俺が食い潰した。うち2機は一騎打ちにて息の根を止めたのだった。参加者はあっくんと僕の他に3人いたから、何回勝ったんだ。負け抜け方式のじゃんけんはそれにしても面白かったな。毎度ひとりずつ敗者を決めて、最後の1人が残るまで各ラウンドを戦っていく。つまり一度負けたから負けじゃない。そのルールだとあっくんの残機制わけわからなくならないか?って言ったけど誰もピンときてなかったので、あれそういうもんかと思ったけどやっぱり変じゃね?まあでもあれか、3回そのラウンドでの敗者にならない限り負けない、というやり方を昨日はとったんだよな、それしかないと思えるあたり彼ら負け抜けのじゃんけんに慣れすぎている。そんなにやる機会ないだろう。俺が地元の集まりをサボりすぎているのも大いに関係しているはずだが。いやー、気持ちいいというか何にも変わっていないような、だって来月にも結局同じ一万円使って同じことやるからな。今度はリョートもこれるだろうから6人で、キムラもこれたら7人。いよいよ無理だな。でもほんとじゃんけんってメンタルゲーなのよ、背負ってるもんがあるやつが負けるゲーム。俺たちはふざけて今日チョキが強いな、とかグーの環境だないま、とか言うから相手の出方をある程度筋道立てて伺いやすいというのはある。昨日はチョキの環境だというのが決勝までに皆に認知されていて、最後もチョキで勝った。あんだけ言ったよなあ。
おつかれさまです。いやサマンサ。三連勤終了。サ終である。ここで一枚。

津田沼駅の、ホームの端の方。ガチャガチャしてる。スピルバーグ監督のフェイブルマンズをみたときに、スピルバーグ監督の師匠が水平線を真ん中におくとつまらない写真になる、上か下に置くと面白い写真になる、画だったかな?映像だったかな?そもそも吹き替え版、いや字幕、どちらにせよ日本語に置き換えられたものしか僕は観ていない。端っこの方とはいえ座れない、めちゃんこ空いてはいるものの、てか1号車の乗り口だと書いてあるところから乗ったのだがここほんとに端っこの車両か?二つくらいまだ奥に連なっていた気がする。ホームの幅からしてまだ乗り口はたくさんあったが、15両編成ならばこの辺までなのかなと行きすぎないようにあそこで立ち止まった。15両編成がマックスなのか。まあ座れなくても座れているようなもん、と思えないこともない空きようだ。まさに三連勤のフィナーレにふさわしい、このように都合のいい帰路が現れてくれるなら僕は喜んで、帰るまでが連勤であるといわせてもらおう。
さて、ドリップバッグも買ってきてしまった。これは父から頼まれて定期的に10パックずつ、5パック入りのものをふたつ社割をきかせて買っていっているいつものやつである。費用は実費でいただいているのでなんの問題もないようで、クレジットで支払ってPayPayでお題をもらっているから頼まれたときはまたちょっとややこしくなるなと思う。まあどれだけ出費を削っているタイミングだろうと、そのくらいのお願いなら貯金ってつまりそういうもんでもあるだろと喜んでとりあえず買って帰るのだが、ややこしくないのに越したことはないからね、月末の収支を管理するにあたっては。またちょっと不安になる、俺は来月引き落とし分として支払うはずが今月現金で払うことになった、そればっかり考えてるけど一応その逆の動きもあるにはある。今回のドリップバッグで1200円が加算されて、無視できないくらいの大きさにもなった。それでもウナギの存在が大きい、そういや鰻を食べに行った日、その前後の雑費含めてウナギという名義で支出のほうに計上しているのだが、えらくこのウナギ、という言い方を僕は気に入っている。村上春樹もうなぎの話をしていた。ひらがなだったと思う。たしか自分の読者の間にうなぎを置くようにして自らの文章を見つめる、というもはや一般的な一般論という感じの第三者の視点についての話だったか、あるいは登場人物として「うなぎ」をかならず登場させることにしている、彼に喋らせて、そう作家-読者間のやり取りとしてしか展開されない文章を彼は「お文学」と呼んでいたが、そうではなく、どちらにせよそういう文脈で、プラクティカルな話としてそれを扱っていたのかは忘れたが、とにかくうなぎという言葉を大事そうに使っていた。ここは端っこじゃねえんかい。乗り口ふたつぶんくらいオーバーした場所に立っていたようだ。よくわからない。グリーン車の目の前に気がついたら立っているあれ、死ぬまでなくならないよな。
イメージモデル 桜井ユイさん(57)、品川スキンクリニック千葉院。ショッキングピンクの広告。若い。何歳にみえたというわけではないけれども57歳には見えなかったということだ。何歳にも見えないな。若くみられたいというより、年齢そのものから解脱したい、という欲望が感じ取れるような気もする。飲み会のおっさん113人インタビュー本の中に、若づくりしているばあさんは君悪がられている、というたしか60歳手前くらいの男の人の解答があった。あれ、そもそもなんて投げかけたらこう答えてくれたって本なんだっけ。まあここまで生きてきて身に染みたこと、教訓を教えてくれ、ということだったはずだけど、言われてみればどうおっさんに話を投げかけたのか、インタビュアー側の言葉も一字一句のせてくれたほうが面白そうではある。より具体的なほうへ、ただし話は無意識のほうへ向かっていくんじゃないか。
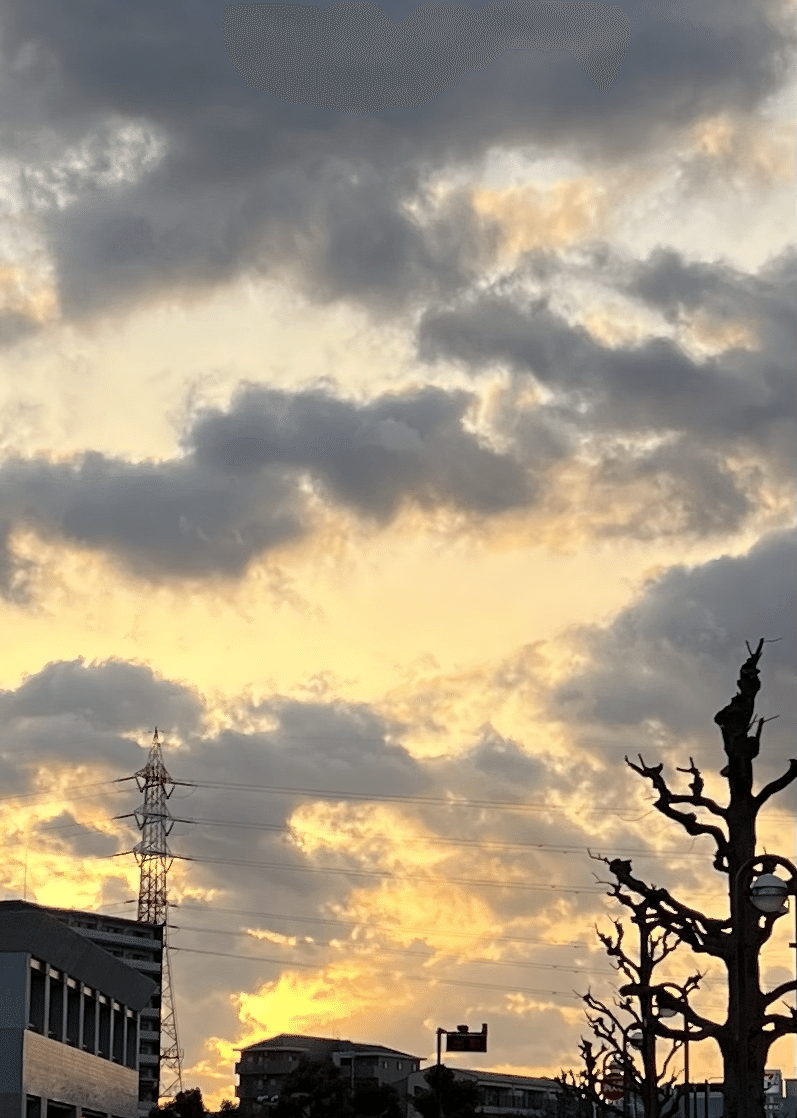

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
