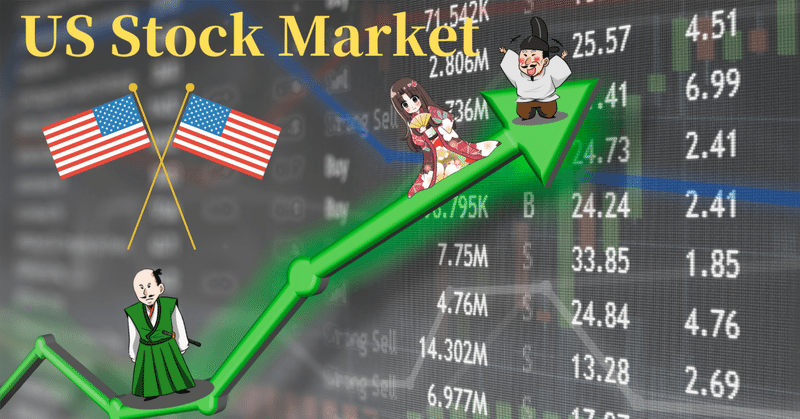
(米国株式市場12月10日〜12月17日)今週の合戦の振り返り!FOMC通過でFTDを迎えUptrendに回帰も不安定な相場が継続。S&P500指数以外50日移動平均線を下回って推移。ラッセル2000は明確に200MAを下抜け50MAとのデッドクロスが目前。FOMCはタカ派的な内容で2022年3月時点での利上げ確率が急騰。Dotchart上も3回の利上げを見込む。アクティブファンドマネージャーはポジションを大幅に落とす。
(全文無料で読めます)

水曜日のFOMCを受けてFollow through Dayを迎えたものの、その後の木曜日と金曜日の下落は相当こたえた衆もおおかったじゃろう。。

今週はFOMCを終えてイベント通過を受けて大きく吹き上がりましたが、その後週後半に大きく失速して引けました。
1.今週の合戦の要約
________________________________________________________________________
・S&P500指数を除いて50MAを割り込んでいる。ダウ平均は200MAが近くなってきておりラッセル2000指数は明確に200MAを割り込み下落トレンドに。
・水曜日にFTDを迎えてConfirmed Uptrendを迎えたが、金曜日にUptrend under pressureに格下げ
・大型テクノロジー銘柄や一般消費財、エネルギーセクターが弱く、ヘルスケアセクターが強い
・FOMCは予測通りテーパリングを加速し2022年3月に終了見込みとなることを発表。インフレが一時的との見方を撤廃。
・ドットチャートは2022年の利上げが3回と事前予想の2回を上回る結果に。
・総じてタカ派的なFOMCとなり実際にFF金利先物が織り込む利上げ見通しは上昇。特に2022年3月の利上げ織り込みが急騰している。(→これが週後半の下落の要因?)
・VIXは引き続き高めに推移
・アクティブファンドマネージャーは大幅にポジションを落としている
________________________________________________________________________
2. 代表株価指数動向(&強気相場 or 弱気相場判定)
□各指数の動き

S&P500指数以外でで50MAを下回る結果となっていますね。ダウ平均に関しては長期的なトレンドを見る200MAが近くなってきています。
中小型指数であるラッセル2000指数は200MAを明確に下回っています。中小型を選好する傾向にある個人投資家には苦しい展開ですね。
もうすぐ50MA(赤)が200MA(黒)を下回るデッドクロスを迎えそうです。

各指数の年初来のドル建リターン推移の比較は以下となっています。
黒:S&P500 +23.02%
緑:ナスダック +17.70%
青:ダウ平均 +17.29%
紫:ラッセル2000 +8.99%

指数だけをみると非常に堅調に見えますがGAFAMに投資していなかったらナスダックの年初来のリターンは▲25%という衝撃な結果となっています。特に3月以降でみると▲40%程度となります。
GAFAMTに投資してなかったら、この1年間下落相場に立ち向かっていたということになる。そりゃ大型株に投資してない個人投資家の成績は悪くなるわいのw https://t.co/hV1JxSkD1J
— 信太郎🏯オニール流投資で再び天下を狙う (@nobutaro_mane) December 13, 2021

GAFAMに投資していなかった場合、大きな調整相場に立ち向かっていたということになるな。本当に一部の大型銘柄が相場を牽引しただけという歪な形となっておる。この点についてはミネルビ二翁も長い経験の中で初めての歪な構造としておる

米国の格差と同じく株にも格差じゃの...。GAFAMTなどによって支えられてる市場。
— 信太郎🏯オニール流投資で再び天下を狙う (@nobutaro_mane) December 13, 2021
ミネルビニ翁役
私の38年の取引経験の中で、今までに見たことのないような二極化した市場となっている。多くの銘柄が40~80%下落しているがS&P500は史上最高値から1%未満しか離れていない。 https://t.co/UDnoIEid9b
それでは主要3指数についてもう少し詳しくみていこうぞ!
□S&P500指数
以下は年初来のS&P500指数の動きです。
赤:50MA
緑:100MA
黒:200MA

今週金曜日の出来高が伸びてるのはSQだからですね。これは全ての指数で同じ現象が起きています。
S&P500指数は50MAと100MAに支えられる形でずっと推移してきました。今週は下落していますが、まだ1つ目の防衛戦でもある50MAに支えられている状態となっています。
現在50MAを上回っている銘柄は約半数となっています。

200MAを上回っている銘柄は依然として64%存在しています。ただトレンドとして下落基調となっていますね。長期下落トレンドに入っている銘柄が増えていることが読み取れます。

Advance-Decline Ratioは株価が上昇した銘柄数と下落した銘柄数がどちらが多いかわかる指標です。
AD line
=
(今日上昇した銘柄数 - 今日下落した銘柄数 ) + 昨日のAD Line
つまりAD Lineが上昇していれば上昇した銘柄数が多く、下落していれば下落した銘柄が多いということになりますね。S&P500指数は11月半ばから頭打ちで現在上昇している銘柄数と下落している銘柄数が拮抗しておりMIXな状態となっています。

□ナスダック総合指数
以下は年初来のナスダック総合指数の動きです。
赤:50MA
緑:100MA
黒:200MA

ナスダックは何度も100MAを下回っていますがが毎回200MAより上で反発してきました。今回も反発できるかが注目されます。前回安値の14,931.06を下回ると再びMarket Correctionになる可能性があり要注意ですね。
50MAを超えている銘柄の比率ですが、ナスダックはナスダック100指数でしか確認できないのでナスダック100指数でみていきます。(QQQということです)

50MAを超えている銘柄は46%と半数を下回っています。10月には一時的10%となっていることを考えると2月前に比べると大分回復しています。
200MAを上回っている銘柄数は58%と60%を下回っています。ただ、先ほどのデータで見る限りナスダック総合指数でみると年初来▲25%であることから200MAを下回る銘柄は更に多くなっていそうです。

AD lineはナスダック総合指数で確認することができます。下落の一途をたどっていることから11月以降多くの銘柄で下落が続いていることがわかります。

□ダウ平均指数
以下は年初来のナスダック総合指数の動きです。
赤:50MA
緑:100MA
黒:200MA

ダウ平均の50MAを上回っている銘柄は59%であり200MAを上回っている銘柄は57%となっています。つまり、50MAと200MAが近くなっている銘柄を多いことを示唆しています。
AD LineはSP500と同様の動きとなっています。

□現在は強気相場?弱気相場?

水曜日のFOMC後の上昇でFollow through dayを迎えてCorrectionからConfirmed uptrendに格上げされました。しかし、金曜日の下落で再び「Uptrend under pressure」に格下げされています。

フォロースルーデイ(=FTD)ってなんぞ!?という衆は以下を参照してくれい。前回9月-10月の下落局面ではFTDを迎えたあと上昇相場に転じておるからな

昨日の大幅上昇でナスダックは10/5から始まるフォロースルーデイ(以下FTD)を迎えたの
— 信太郎🏯オニール流投資で再び天下を狙う (@nobutaro_mane) October 14, 2021
オニール流ではFTDはCorrectionからの回復の最初の絶対条件としておる。注意すべきはFTDを迎えたからといって必ずCorrectionから脱却するとはいえないことじゃ。
では投資家はどう行動すべきか(リプ https://t.co/7ZCl6KCmjU pic.twitter.com/kwlxbLKsbX
ただ、上記のリプライでも指摘しているとおりFTDを迎えたからといって、確実に上昇相場になるとはかぎりません。ただ、FTDなくして上昇相場はありえません。
要はFTDは上昇相場への必要条件ではありますが十分条件ではないということです。FTDを迎えた場合の投資家が取るべき行動は以下となります。
✔︎FTDで一気に市場に飛び込まない
✔︎成長株が買いポイントを超えてブレイクしたときは試し買いをする
✔︎ゆっくり計画的に銘柄を増やしていく

あくまでFTDを迎えた状態で、CANSLIMの条件を満たしてチャートが整っている銘柄があれば徐々に相場に入っていけということじゃ。

私自身はFTDを迎えた日にスクリーニングしましたが上記の条件を満たす銘柄が見つからなかったのでMarket Inは見送っています。
オニール流の銘柄スクリーニングは特に有望銘柄が見つけられなかった故ステイ。強いて言うなら$NTRを監視という感じかの。
— 信太郎🏯オニール流投資で再び天下を狙う (@nobutaro_mane) December 16, 2021
チャートが整ってるKOなどはCANSLIM的に満足できぬ気、CANSLIM整ってる銘柄は直近売り込まれチャート崩れとる感じかの。
また明日も探そうかの
水曜日にFTDを迎えましたが、木曜日と金曜日の下落(金曜日はSP500のみ)によって売り抜け日が追加され、Uptrend under Pressureに格下げされています。
(売り抜け日とは?)
売り抜け日カウントが以下を満たせば天井圏の下落警戒となります。
● 前日より出来高が増加し且つ指数が0.2%以上下落する売抜日カウントが4週間-5週間で3-5日起こる。(上昇中に発生)
● 2-3週間という短い期間で売抜日が4日あっても注意が必要。
(売り抜け日カウント数とは?)
前日比で0.2%以上のマイナスを前日以上の出来高ともなって記録した日を「売り抜け日」とカウント。4-5週間で4-5日あれば天井から下落の可能性あり。2-3週間という短期間で売抜日が4日ある場合も注意が必要。
「フォロースルー日」を迎えたらカウントはリセット。「フォロースルー日」は下落局面で前日比プラスで引けた日から4-7営業日後に出来高を伴って大幅に上昇した日のことを指す。また、カウントから25営業日経過後にも消滅する。
ただ、上位の条件を満たさなくても売り抜け日がカウントされることもあります。これは「指数が失速する」という意味のカウントとなっています。
指数が活発な出来高の中で上昇していくなかで、前日と同じような出来高なのに停滞した場合にカウントがなされることがあります。
3.セクター別(1week)
□ S&P500

TSLA:▲8.30%
MSFT:▲5.47%
AAPL:▲4.63%
GOOG:▲4.24%
MRNA:+14.68%
PFE:+12.69%
LLY:+9.54%
VZ:+5.94%
相場を支えていた大型グロースが総崩れとなる一方、ワクチン銘柄が力強い動きとなっています。
□ セクターETF騰落率 Highlight(1week)

XOP:Oil & Gas Exploration & Production ETF ▲7.83%
XLY:一般消費財ETF ▲4.73%
VGT:情報技術ETF ▲3.91%
QQQ:ナスダック100 ▲3.29%
XBI:Biotech ETF +5.19%
エネルギーや一般消費財、テック系が弱く、バイオテックが強いという状況になっています。
4. FRB動向
(FRBの金利動向に気をつける)過去を振り返ると、FRBの金利が引き上げられたことがきっかけで弱気相場が始まり不景気に突入した歴史があります。弱気相場が終わるのは金利が下げられた時が多いです。最も簡単で役に立つ金融指標はFederal Fund(FF)レート(政策金利)。
コンピューターによる自動売買や様々なヘッジサービスによってリスクの高い弱気相場で発生する株価の下落から資金を守るために、ポートフォリオの大部分をヘッジするファンドが現れました。金利が急騰する場面は相場が下落しやすい仕組みになっています。
□ 先週のHighlight(12月6日〜12月10日)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ CPI結果
11月CPI結果 6.8%/予想6.8%(前年比)
11月CPIコア結果 4.9%/予想4.9%(前年比)
11月CPI結果 0.8%/予想0.7%(前月比)
11月CPIコア結果 0.5%/予想0.5%(前月比)
□ 今週のHighlight(12月13〜17日)
◇FOMC結果
テーパリング速度を倍に。3月終了見込み
ただしパウエル議長はバランスシート縮小時期には言及せず
インフレ一時的の表現削除
2022年利上げ予想中央値:3回利上げ(前回0.5回)
2023年利上げ予想中央値:3回利上げ(前回4回)
2024年利上げ予想中央値:2回利上げ(前回2回)
<経済見通しは以下>
GDP中央値
2021年:5.9%→5.5%
2022年:3.8%→4.0%
2023年:2.5%→2.2%
2024年:2.0%→2.0%
長期:1.8%→1.8%
失業率中央値
2021年:4.8%→4.3%
2022年:3.8%→3.5%
2023年:3.5%→3.5%
2024年:3.5%→3.5%
長期:4.0%→4.0%
インフレ率
2021年:4.2%→5.3%
2022年:2.2%→2.6%
2023年:2.2%→2.3%
2024年:2.1%→2.1%
長期:2.0%→2.0%
コアインフレ率
2021年:3.7%→4.4%
2022年:2.3%→2.7%
2023年:2.2%→2.3%
2024年:2.1%→2.1%
→市場が織り込む利上げ見通しは上昇しており特に2022年3月の利上げ確率が急騰している。イールドカーブには大きな変化はない。株価は当日は急上昇したが翌日に全戻ししている。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
□12月FOMCの纏め
FOMCについては数値的な結果は↑の通りです。翌日に速報として以下の記事を出しているので内容が気になる方はご覧いただければと思います。ドットチャートの前回9月とのわかりやすい比較もおこなっております。
全体として、Statementでは経済への自信を深めてインフレへの懸念を強め、ドットチャートは事前予想よりも特に2022年に引き上げられています。
テーパリングの加速は事前の予想通りだったとはいえ、タカ派的な内容であるといえるでしょう。当日はイベント通過で上昇したものの翌日の株価の下落をみると市場も受け止め方を困惑している感はいなめません。
金利の動きは次の項目で見るとして、市場関係者がFOMCをどう捉えたのかをみていきたいと思います。
<三井住友銀行 チーフストラテジスト 宇野大介氏>
完全にタカ派の内容で、本来は株が売られ金利は上昇してしかるべきだが、市場は逆の動きとなった。利上げは前倒しされたものの、実際にはまだ着手していない。バランスシートへの言及もあったが、これも利上げ後の話なので、現実味がない。アナウンスメントをすることで市場に耐性をつけることができるので、初動としては成功したということだろう。
今後は利上げ局面に入っていくほか、「インフレは一時的」という文言が刷り込まれ過ぎていた面も次第に解消され、イールドカーブはスティープ化していく。米長期金利は1.8%を超えて推移し、ドル/円は来年3月末までは120円に向かって進んでいくとみている。
今後の進め方は示されなかったが、ある程度のインフレを許容し、バランスシートの縮小についても、ゆっくり、もしくは規模感を残した形でやっていく方向に収れんしていくだろう。株高を続けていくことが米国式の資本主義を続けていく話の大前提であり、米連邦準備理事会(FRB)は株式市場にとって都合の良い形で着地させていく。
<野村証券 チーフ為替ストラテジスト 後藤祐二朗氏>
米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果は、テーパリングの加速はおおむね予想通りだったが、来年3回の利上げ示唆は予想よりも若干タカ派化したと捉えている。ただ、パウエル議長の議会証言以降、タカ派シフトの懸念は高まっていたので、サプライズに対するマーケットの備えは進んでいた。その結果、マーケットの拒否反応は非常に限定的となった印象で、株価は上昇し、米国の短期金利も上がりかけたが、結果的には(金利は)あまり動かなかった。

他にも海外のアナリストのコメントをみたが、同様にタカ派的という見解が多かったの。ドルについての言及もあった故参考までにBloombergの記事を抜粋しておくわい!

◎FRBのタカ派転換、リスク選好持続ならドルに追い風に-クレディA
ドルは米連邦準備制度のタカ派転換から追い風を受ける可能性があると、クレディ・アグリコルのバレンティン・マリノフ氏が指摘。米金融当局は一段とタカ派色を強めており、これが高利回りの安全通貨であるドルの魅力を押し上げ続けるはずだ。リスクセンチメントが続く場合、ドル・円とドル・スイスフランでのロングは「ドルに強気な見方を表現する最良の方法である可能性」「さらにオミクロン株が景気回復を妨げると米金融当局が考えていないように見受けられることに市場は勇気づけられたのではないかと思う」
□FF先物金利が示唆する利上げ確率の変遷
FOMCを受けて先週金曜日時点とどれほど変化したかを見ていきたいと思います。
◇ 3月16日時点の利上げ確率:
12月3日時点28.6%→12月10日時点35.9%→本日時点49.2%
◇ 5月4日時点の利上げ確率:
12月3日時点49.7%→本日時点57.9%→本日時点65.5%
◇ 6月15日時点の利上げ確率:
12月3日時点75.3%→12月10日時点79.5%→本日時点87.7%

上記を見てもらえばわかるが2週間前から比べて特に2022年3月のテーパリングが終了する時点での利上げ見込みが急激に上昇しておるな。
FOMC直後の利上げ見通しは41.8%だったのに木曜と金曜で大幅に上昇しているのがわかる。3月利上げ見通しの進展が株価の下押し圧力になっとるのではないかと推察しておる

因みにFOMC直後にワシが見た時は3月時点の利上げ見込みは41.8%じゃったから2日で急激に上昇しておる。
— 信太郎🏯オニール流投資で再び天下を狙う (@nobutaro_mane) December 17, 2021
3月の利上げ織り込みの進展が株価の下押し圧力になっておるのではないか?https://t.co/L4FxAcdipr
やはり債券市場ではタカ派的に改めて受け止められていることが示唆されます。
□ 長期金利(2&5&10年債利回り)
それでは次に米国債市場をみていきましょう。以下ご覧いただければわかる通り明らかに短期債の方がそり上がってきているのがわかります。政策金利の利上げを織り込む動きが活発であるということですね。
2年債

5年債

10年債

以下が年初と先週金曜日と現在のYield Curveの変遷は以下となります。
青:年初
赤:先週金曜
黄:今時点

タカ派的なFOMCを受けても国債市場では大きな動きはみられないどころか、少し全体的に下落しています。
□ ブレークイーブン金利(5&10年債利回り)
ブレイクイーブンインフレ率とは、債券市場が期待するインフレ率を意味します。
この1年間「5年ブレークイーブンインフレ率」と「10年ブレークイーブンインフレ率」は上昇基調で進んできましたが、5月に入り一服、6月に入り下落。横ばいが続いていましたが、11月に入り12月の現在まで下落基調が継続しています。
(2020/01/01-2021/12/17)

FOMCでタカ派のスタンスが示されて期待インフレ率が減少していることが読み取れます。
□ FRBのバランスシート(BS)拡大・縮小動向
BSが拡大するということは、市場に流通する資金が増大して、景気を加熱させることに繋がります。
FRBは金利を引き上げる前に、まずはバランスシート(BS)の縮小(テーパリング、資産買い入れプログラムの変更)を実行します。すでにテーパリングは始まっていますが、グラフではまだクリアにわからないですね。これから縮小していく様が見られると思いますので、楽しみですね(辛い)。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
※資産買い入れプログラムについて、現在では米国債を月800億ドル(約8兆4千億円)、住宅ローン担保証券(MBS)は同400億ドルのペースで買い入れています。こちらのペースを下げることを「テーパリング」といいます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
繰り返しになりますが、12月のFOMCでテーパリングが決定しました。来年3月まで段階的に実行されます。米国債月200億ドル、MBS月100億ドルのペース(ペース調整あり得る)で実施されます。つまりこのベースでは2022年3月にテーパリングが終了することになります。

バランスシートに関しては今後は縮小する時期がいつになるのかという議論が重要性をましてくるな。BS縮小は間違いなく株価には下押し圧力じゃからな。。

5. プットコールレシオ
ここでは年初来からの比率(%)を観察します。直近の投資家心理を確認します。
プットコールレシオ = Put売買金額 /Call売買金額
⑴プットコールレシオ > 1 = Putの売買代金が大きい = 投資家が株式相場下落を期待(悲観的)
⑵プットコールレシオ < 1 = Callの売買代金の方が大きい = 投資家が株式相場上昇を期待(楽観的)
で算出されます。つまりプットコールレシオが1を超えているということはPutの売買代金の方が大きく下落を警戒する投資家が多いことを意味します。これは相場が悲観的なことを意味しており相場の底局面ではプットコールレシオが高くなる傾向があります。
一方、プットコールレシオが1を下回っているということはCallの売買代金の方が大きく上昇を期待する投資家が多いことを意味します。ただ、これは楽観的であるということを意味しており、相場の高値圏ではプットコールレシオは低くなる傾向があります。

プットコールレシオは1.18まで先々週に急騰しましたが、現在は0.91と落ち着いて
推移しています。オプション市場では上昇を期待していますが、そこまで大きな楽観というわけではありません。
⑵プットコールレシオ < 1 = Callの売買代金の方が大きい = 投資家が株式相場上昇を期待(楽観的)
6. Volatility index(VIX指数/恐怖指数)
VIXとは市場で取引されている価格から逆算された「株式市場のボラティリティ」のことを指します。株価指数は上昇時は緩やかに上昇し、下落時は急落します。市場参加者が高いボラティリティを見込んでいるということは、市場に対して不安を抱いていると想像できます。
VIX指数は株価の先行きにどれほどの振れ幅(ボラティリティー)を投資家が見込んでいるかを示す「株価変動率指数」のうち、米国株を対象にした指数。通常、株安が懸念される局面で上昇し、20を超えると不安心理が高まっていると解釈される。その場合、「株価が今後1年間に約7割の確率で上下20%の範囲で変動する」と投資家が予想していることを示す。
2008年の金融危機の際にVIX指数が80超に上昇して注目を集めた。18年2月と10月にもVIX指数の上昇をきっかけに米国株が下落する場面があった。VIX指数の上昇に連動して機械的な株売りを出す「リスク・パリティ」などと呼ばれるファンドが存在するからだ。(引用:日経新聞)
S&P500指数(VIX:青)とNASDAQ(VXN:ピンク)のVIX指数の5年推移は以下となります。

落ち着いてきているとはいえ明らかに10月から上昇に転じているのが読み取れますね。VIXも20を上回って引けています。
7.空売り比率
空売り比率・ショートボリュームはNYSE(ニューヨーク証券取引所)で空売りされている株式の数をNYSEの総出来高との割合で示したものです。
この比率が高ければ投資家が市場をネガティブに見ていることが読み取れます。(「空売残」はShort Interestです。ここでは触れません)
特に暴落局面で注視するのが有効で弱気相場が底をつける時というのは空売りの「急増を示す数値の上昇」が通常2回か3回現れると成長株の巨匠・オニール氏は言及しています。
それではまずS&P500指数の空売り比率は以下となります。S&P500指数で最も取引Volumeが多いETFである「SPY」で見ていきます。

12/9に急騰しています。ただ、その後は落ち着いて推移しています。ナスダックについても取引ボリュームが大きいQQQでみていきたいと思います。

QQQも直近落ち着いていますね。
8. アクティブファンドマネージャーの動向(NAAIM Number)
次にNAAIM Numberです。NAAIM Numberはアクティブファンドの投資動向です。100を超えるということはアクティブファンドがレバレッジをかけていることを意味します。

12月15日時点で52まで急落しています。機関投資家が急激にポジションを落としていることが読み取れます。
果たして今年はクリスマスラリーはあるのでしょうか。。。
9. 注目経済指標の動向
以下が今週の経済指標発表でした(マネックス経済指標カレンダーを参考)。

経済の温度感を図る上で重要な小売売上が大幅に予想比弱含んでいます。
10.来週の決算
決算シーズンではないので閑散としてますがCCLやNKEが控えています。

まとめ
________________________________________________________________________
・S&P500指数を除いて50MAを割り込んでいる。ダウ平均は200MAが近くなってきておりラッセル2000指数は明確に200MAを割り込み下落トレンドに。
・水曜日にFTDを迎えてConfirmed Uptrendを迎えたが、金曜日にUptrend under pressureに格下げ
・大型テクノロジー銘柄や一般消費財、エネルギーセクターが弱く、ヘルスケアセクターが強い
・FOMCは予測通りテーパリングを加速し2022年3月に終了見込みとなることを発表。インフレが一時的との見方を撤廃。
・ドットチャートは2022年の利上げが3回と事前予想の2回を上回る結果に。
・総じてタカ派的なFOMCとなり実際にFF金利先物が織り込む利上げ見通しは上昇。特に2022年3月の利上げ織り込みが急騰している。(→これが週後半の下落の要因?)
・VIXは引き続き高めに推移
・アクティブファンドマネージャーは大幅にポジションを落としている
________________________________________________________________________
ここから先は
¥ 400
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
