
【気づき】Vol.1044(2011年5月12日発行のブログより)
虚実皮膜論。
スピーチにしても著述にしても、本当に魅⼒的に伝えるためには、
事実の羅列では人を惹きつけることができない。
その証拠に、
(今はどうか知らないが)昔の大学教授の授業はつまらなかった。
冗談なくらいにつまらなかった。
単なる事実の羅列だからだ。
黄ばんだノートを毎年繰り返し棒読みしていく豪傑もいたくらいだ。
まあ、「嘘を教えるわけにはいかないからそれも仕方ないじゃないか」
と言われそうだが、だったらこっちとしても、
そのノートをコピーして全員に配布し、すべて休講にして欲しい。
人を魅了する話術や記述というのは、
ホンマとウソが絶妙のバランスで混ざっている。
100%ホンマではあくびが出てしまう。
100%ウソでは単なる嘘つきで信頼されない。
どこからどこまでがホンマで、
どこからどこまでがウソなのかがわからないというのは、魅力になるのだ。
ホンマをより惹きたてるためにウソという調味料を使う。
これが脚色というやつだ。
その意味では歴史上の人物はすべて脚色されている。
司馬遼太郎さんの作品は、
まさに天下⼀品の脚色の集大成だということができる。
明らかに現実を凌駕してる。
小説が単なる事実の羅列よりも遥かに面白いのは、
人間の頭脳だけが許された特権だろう。
⼈形浄瑠璃と歌舞伎で有名な近松⾨左衛⾨の
「虚実⽪膜論(きょじつ・ひまく・ろん)」という芸術論がある。
芸が面白いのは虚(ウソ)と実(ホンマ)との⽪膜にあるということだ。
膜というのは肉のことだ。
つまり皮と肉のようにくっついている状態で、
境界線が見分けがつかないくらいにブレンドされているのがイイ!
というわけだ。
嘘つきは信頼されないが、法螺(ホラ)吹きは大物になる人が多い。
嘘つき
と
法螺吹きの違いは何だろう。
嘘には真実が0%だが、法螺には真実が1%以上含まれている。
最高の面白い話というのは、
すべてが本当のわけがないとわかっていながらも、
すべてが嘘のはずがないと思えるものだ。
フィクションで面白いのは、
「でもこの著者だったらノンフィクションも1%⼊っているのでは?」
と連想させるものだ。
これが人をメロメロにするんだね。
追伸.
ウソとキスの巧い人間は、モテる。
...千田琢哉(2011年5月12日発行の次代創造館ブログより)
↓千田琢哉のコンテンツ↓
🔷千田琢哉レポート
文筆家・千田琢哉が書き下ろしたコトバを毎月PDFファイルでお届けします。

🔷真夜中の雑談~千田琢哉に訊いてきました~
文筆家・千田琢哉があなたから頂いたお悩みに直接答える
音声ダウンロードサービスです。毎月1日と15日発売!
“毎月1回の飲み代を、毎月2回の勉強代に”
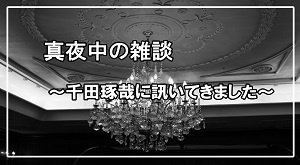
🔷千田琢哉公式チャンネル
「3分の囁き」千田琢哉の独り語りをYouTubeでお楽しみ下さい。
