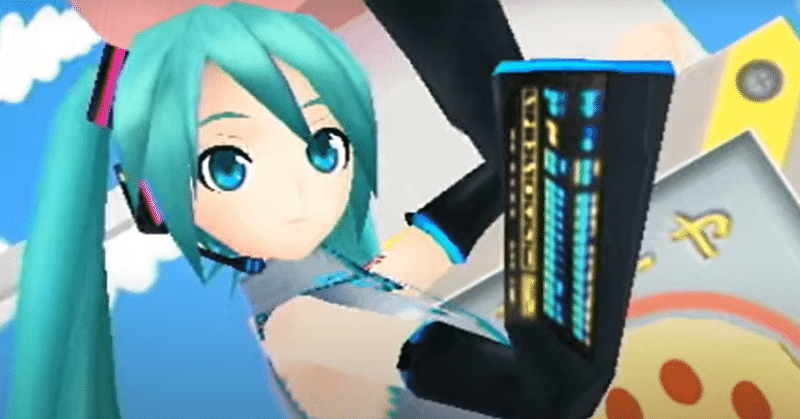
「萌え」は自室で、「推し」は広場で
はじめに
本文は、「推し」の条件から逆算して「萌え」の性質を考えてみた、そのメモ書きである。
先回りして言えば、コミュニケーションの回路を獲得した「萌え」がすなわち「推し」であり、わざわざ「萌え」を発話する機会は減り、結果として「萌え」は消えつつある、と本文では結論づけた。
共通点──実存の理由
これはどちらにも共通していると考えられる。
圧倒的に神不足なメンタリティーにおいて、そこに生きがい/信仰/即自的な実存の理由/充足理由を見出すのは、普通のことだ。
「これさえあれば生きていける」と素朴に思えること。
そういったことが自覚され始め、社会的にも「オタ活」と受け入れられるようになったのが「推し」なのだろう。
「推し」の条件
最初に引用する。若者の「ヲタ活」についての調査の、その結部の文章である。
若者のヲタ活は、心の豊かさやゆとりを大切にしつつ今を楽しく過ごしたいという現在享楽的な欲求と、関心のある相手や社会から認められたいという承認欲求の現れである。 現在享楽欲求と承認欲求が根本にあるからこそ、推しが社会的に認められる過程を自分も伴走しながら楽しむために、 献身的に対象を「推す」のである。
― 享楽志向と承認欲求が支える献身的消費 ―
「心の豊かさ」「ゆとり」というのは、つまり「これさえあれば生きていける」という対象にコミットすることで得られる充足感だろう。
注目したいのは、「推し」が帯びる社会性だ。
これは「オタクコンテンツの一般化/SNSの一般化」の流れとパラレルで(一般化の過程については字数を鑑み省く)、オタクコンテンツを「推し」ていると言っても社会的な地位を大きく損なうことなく、SNS上で一介の個人が様々なコミュニティに触れることができることに起因するだろう。
最早広場と化したインターネット上において「○○推しです」と申告することで、そこにコミュニケーションが発生しうる土壌。それが「推し」の条件だと考える。
それは発話されることばなのだろう。
「萌え」の私秘性
「萌え」は、二重の意味で消えた。
そもそも、初めからそれを発話するタイミングが乏しかった。
そして、社会性を帯びた新しい発話される単語「推し」が普及した。
「萌え」は必ずしもコミュニケーションを開く言葉ではない。間違っても広場で叫んではいけない。
逆に言えば「萌え」は、他者に向かって言う必要が無く、言えば「オタバレの危機」に瀕してしまう可能性のある時代の、小さな信仰の合言葉なのだろう。
あるいはインターネットの片隅に、仄暗い自室から「書き込まれる」言葉なのだろう。
Twitterで「つぶやく」⇔インターネットに「書き込む」という身体性、という指摘も可能だろうか。
推しのように「人に勧める」というニュアンスもなく、そもそも勧めることがリスクとなりえた時代における言葉、それが萌えなのである。
おわりに
「萌え」は言う必要がなくなった。
「二次萌えなんですよ」というのは気心しれたコミュニティにおける古い言い回しで、「○○推しなんですよ」と言う方が、他者に向かってのコミュニケーションとしてはスムーズなのだろう。
そこにコミュニケーションが開くことは、素直に喜ばしいことだ。
同時にまだ、「萌え」にできることも残っているように見える。
例えば「スパチャ」などといった、資本と関係に入った「承認」に回収されるコミュニケーション。
例えば、「広場」と化してしまい、意図せず自室的なつぶやきが他者に伝わってしまうインターネット。
これらをもう一度考え直す視座としての「萌え」という可能性が、どこかに。
※画像は僕の萌えの原点です。これが全てでした。
