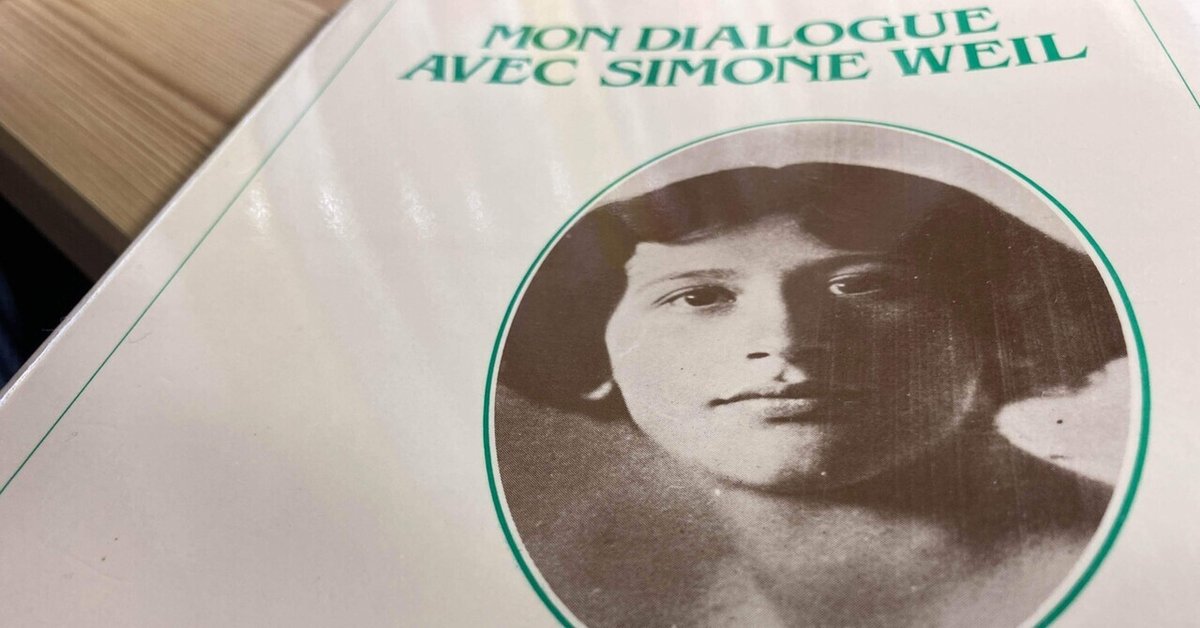
【翻訳】『シモーヌ・ヴェイユとの対話』(2)
『シモーヌ・ヴェイユとの対話』
ジョゼフ=マリー・ペラン 著
関野哲也 訳
本稿は、Joseph-Marie Perrin, « Mon dialogue avec Simone Weil » のフランス語原著からの邦訳である。
ジョゼフ=マリー・ペラン神父は、シモーヌ・ヴェイユと親しく接していた親友の一人であり、彼女が洗礼を受けるか否かを躊躇、熟考するに際して、相談に乗っていた人物である。したがって、我々が生前のヴェイユを知る上で、ペラン神父は欠くことのできない第一証言者である。
訳出しに際して、底本として以下を用いた。
Joseph-Marie Perrin, « Mon dialogue avec Simone Weil », nouvelle cité RENCONTRES, 1989.
なお、訳出しにあたっては、原著テクストの厳密性を重んじる字義通りの直訳ではなく、日本語で自然に意味の通る意訳を心がけている。
ーーーーーーー
第1部
第2章 カトリックとの三つの「接触」
ー ポルトガル、アッシジ、ソレム ー
ポルトガル
シモーヌ・ヴェイユ自身が「霊的自叙伝」と呼んだ手紙(『神を待ちのぞむ』所収、手紙IV)において、彼女が得たカトリックとの三つの接触について私に伝えている。その「接触は真に重要」であり、「キリストが降りてきて、私を捉えたのです」という忘れることのできない、また汲み尽くせない言葉で彼女が要約する大いなる霊的体験を準備するものであった。この三つの接触の重要性は強調してもし過ぎる危険性はないと思われる。特にポルトガルでの最初の接触については。
キリスト者の言い方で述べるならば、キリスト教のうちで最も美しい真理を含む「福音書の貧しき者への告知」を、彼女はそこに見出したのではないかと私には思われる。
キリストと貧しき者に通ずるものを、キリストから最も不幸な人々への呼びかけを、彼女は感受した。彼女自身の筆によるこの言葉を我々が読まずに済ますにはもったいほど、この[ポルトガルでの体験を綴った]言葉はあまりにも透き通っている。ポルトガルにおいて、彼女の美しいテクストのひとつ『神への愛と不幸』で書いているものを、彼女自身が体験したのではないか。
ポルトガル人の友人のおかげで、私はこの場所と日にちを、正確に同定することができた。場所は、ポルトから北へ約80キロに位置する村、ポボア・デ・バルジンである。日にちは、1935年9月15日、七つの悲しみの聖母の祝日である。日曜日であればその日に、もしくは一番近い日曜日に、その祝日は祝われる。その年1935年は、9月15日の日曜日に、その祝日は祝われた。
その時のことについて、彼女は次のように述べている。
「それは海岸でした。漁師の妻たちが列をなし、舟々の周りをろうそくを手にして歩き、明らかにかなり古い、身を切るような悲しみの讃歌を歌うのです。その光景については、他に何も言えません。ボルガの舟唄(訳註1)を除いて、あれほど悲痛な歌を私は知りません。そこで突然、私はある確信に至ったのです。それは、キリスト教とは極めて奴隷たちの宗教である、と。そして、奴隷たちはそれを信ぜずにはいられない、と。そして、私もその奴隷たちのうちの一人なのです」(『神を待ちのぞむ』手紙IV)。
この讃歌がイエスの母・マリアに捧げられたものであったことを彼女は知っていただろうか。十字架の前で立ち尽くし、子の受難をともに受けたマリアに。シモーヌはそれについては言及していない。確かなことは、彼女の中の最も悲痛な部分において、カトリックを見出したということである。子が受けた刑を分かち合い、そのようにして最も不幸な子たちのそばへ行った母、その母の悲劇をこれほど衝撃的に表したものは、あらゆる典礼を見ても、おそらくこの讃歌以外にはない。聖母マリアによるこの非凡な若い一人の女性の迎え入れを、キリスト者は考えずにおれない。シモーヌ自身の大いなる愛が哀れな者たちのために注がれ、彼女は彼らとともにすでにしてあったのだから。
アッシジ
舞台は変わり、その二年後、シモーヌはアッシジへ赴(おもむ)く。我々はおそらく、イタリア旅行において、これほど愉しむ彼女を未だかつて見たことがないはずだ。この旅行期間ほどに、最も生きる喜びを感じ、美にとらわれた彼女を。
アッシジにおいて、彼女は「12世紀、ロマネスク様式の小さなサンタ・マリア・デッリ・アンジェリ礼拝堂」へ入った。「その純朴さの素晴らしさは他に類を見ないその礼拝堂では、[アッシジの]聖フランシスコがしばしば祈りを捧げました」。彼女は続ける。「そこにおいて、人生で初めて、私より強い何かが、私にひざまずくように強いたのです」(『神を待ちのぞむ』手紙IV)。
この告白は重要である。なぜなら、彼女はそれを秘密とし、友人のポステルナクへの手紙にも、両親にも打ち明けていなかったからだ。
彼女の詩「プロローグ」の中で、その教会は「新しく、また醜かった」と言っていることに反して(おそらくお喋りな人をごまかすために[ヴェイユによって、それは]案出されたのだろう)、彼女は次のように述べている。「彼は祭壇の前に私を連れてゆき、言った。「ひざまずきなさい」私は彼に言った。「私は洗礼を受けておりません」彼は言った。「この場所の前で、ひざまずきなさい。真理が存在する場所の前でそうするように、愛を込めて」私は彼に従った。
そこに、聖体の現前(Présence eucharistique)へのシモーヌの最初の心向きを見るべきであろうか。1941年夏以後すぐにその詩が書かれたと知る前には、私はそう考えていた。そこに、不幸によるのではなく、喜びの中における、大いなる聖体の秘跡へのその他の彼女の接近を見るべきであろうか。彼女は何度も言っている。純粋な喜びは、不幸よりも、神への道である、と。ジョー・ブースケへの最後の手紙の中で、彼女はそこだけは強調している。
「一方で不幸、もう一方で完全なる美への全き純粋な信心としての喜びは、ただ二つの唯一の鍵であると、そしてその二つは個人的な実存を消失させることを含意していると私は確信しております。その二つにより、人は純粋な国へ、ようやく息のつける国へ、つまり本当の国へ至るのです」(「ジョー・ブースケへの手紙」)。
ソレム
カトリックとの「真に重要」であった三つ目の接触は、彼女が述べるように、ソレムでのそれであった。1938年、復活祭前の聖週間と復活祭の十日間、彼女はそこに滞在している。彼女自身が明記している。「枝の主日の日曜日から復活祭の火曜日まで、すべての典礼に出席しました」(『神を待ちのぞむ』手紙IV)。
何の解釈も必要ない。なぜなら彼女自身がそれを説明しているからである。一方で、激しい頭痛が彼女を苦しめた。「音がするたびに殴られるような痛みをを覚えておりましたが、注意力を注ごうとする私の渾身の努力が、私の肉体だけをひとりその片隅に縮こませて苦しませることができたのです」。
他方で、讃歌と祈祷の美しさのうちに「純粋で全き喜び」も見出された。アナロジーによって「不幸を通して神の愛を愛しうる可能性」を彼女は理解するに至る。彼女は言う。「この間、キリストの受難の考えが一度に私のうちに入ってきたのです」(『神を待ちのぞむ』手紙IV)。
同時に、秘跡の神的意味を彼女は垣間見た。そこに彼女は好んで常に立ち返っている。その主題について、彼女の生涯の最後の数ヶ月に、大変美しい『秘跡論』が書かれている。彼女は述べている。
「そこ(ソレム)に、ひとりの若いイギリス人のカトリック信者がおり、彼は私に初めて秘跡の超自然的な徳という考えを授けてくれました。それは、聖体拝領の後に身に纏(まと)っているように思われた天使のような輝きによってです」(『神を待ちのぞむ』手紙IV)。
その若いイギリス人こそがシモーヌに「形而上学的と言われている」17世紀のイギリスの詩人たちの存在を教えてくれたのである。それらを読む中で、彼女は「愛[Love]」という題の詩を見つける。その詩が彼女をキリストに捉えられる体験へと導くことになる。[彼女にとって、]すぐにそれは詩から祈りとなった。シモーヌの意識の中で、神の暗々裏な愛は見事に明瞭なものになってゆく。
ーーーーーーーーー
訳註1【ボルガの舟唄】
ロシアの代表的民謡。本来は労働歌で,ボルガ川の舟引き(船曳)労働者たちが歌ったもの。
ーーーーーーーーー
第1部 第2章・了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
