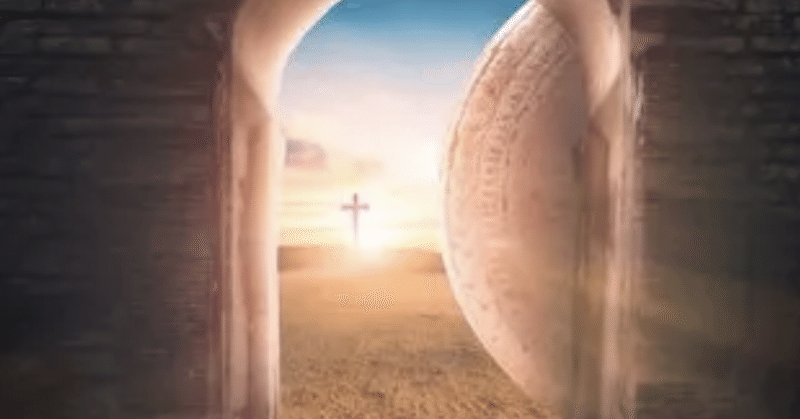
聖フランシスコと味わう主日のみことば〈復活の主日・日中のミサ〉
週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして、墓から石が取りのけてあるのを見た(ヨハネ20・1-9)。
今や、色とりどりの花が咲き誇る、うららかな季節が到来しました。寒い冬は、遠くに過ぎ去り、教会は長い四旬節を終えて、ついに主のご復活を迎えます。
ところで、わたしたちにとって、〈主のご復活〉とは、どのような意味を持つのでしょうか。2000年前の聖書の復活物語から、今を生きるわたしたちは何を読み取ることができるでしょう。復活の主日から始まる〈主の復活の8日間〉で読まれる福音をとおして、わたしたちは、復活のイエスと出会った弟子たちが、段階を追って少しずつ信仰を深め、霊的に成長していく様を見ていくことができます。
その意味で、今日の福音(ヨハネ20・1-9)では、弟子たちはまだ復活のイエスと出会えていません。彼らは「イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉」(20・8)を理解していませんでした。弟子たちは、皆、数日前の〈イエスの受難と死〉という絶望的な体験に、あまりにも深く傷ついていたのです。
しかし、その中で、マグダラのマリア―イエスから七つの悪霊を追い出してもらったと言われている女性(マルコ10・9参照)―は、週の初めの日、つまり日曜日、夜が明けぬうちにイエスが葬られた墓へと急ぎました。そして、墓に着いてみると、墓の石が取りのけられていたのです。
ここで、〈墓〉が象徴的に意味することを、考えてみたいと思います。死者を葬る〈墓〉とは、霊性的な観点から見ると、〈死ぬべき肉的な自我〉のあるところだと言えるでしょう。では、〈死ぬべき肉的な自我〉とは何を意味するのか、ここで、聖フランシスコの言葉に耳を傾けてみたいと思います。
すべての兄弟は、あらゆる傲慢と虚栄を避け、この世の知恵と肉の思いから自分を守らねばならない。肉の霊は、しゃべることを切望し、そのために大い努めるが、行うことを殆ど望まず、努めない。また、内的精神における信心と成聖を求めず、人に見られようとして、外に現れる信心と成聖を憧れ望むものである。このような者こそ、「はっきりあなたがたに言っておく。彼らはすでに報いを受けている」と、主が言われる人である(マタ6・2)。〈『勅書によって裁可されていないもう一つの会則の断片』〉※1
これは、おそらく、使徒パウロのローマの信徒の手紙にある「肉に従って歩む者は、肉に属することを考え、霊に従って歩む者は、霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります」(8・5-6)に基づくものでしょう。
フランシスコによれば、〈死ぬべき肉的な自我〉とは、この世の価値観に引きずられ、虚栄と高慢の心の状態で自己実現を見出そうとする〈人間的エゴ〉のことなのではないでしょうか。そして、この〈人間的エゴ〉は、一度死ななければならないとフランシスコは言います。
(肉の霊に反して)主の霊は、肉が滅ぼされ軽蔑され、無視され投げ捨てられることを望み、謙遜と忍耐を、また清らかな単純と霊のまことの平安を得ようと励むものである。主の霊は、万事に越えて神に対する畏敬と上智を、また父と子と聖霊の神的愛を憧れる。〈『勅書によって裁可されていないもう一つの会則の断片』〉※2
ところで、弟子たちは、〈イエスの受難と死〉を目の前にして、イエスを裏切って逃げてしまいました。それは、あまりにも惨めで貧相なイエスの姿が、彼らの思い描く栄光に輝く〈救い主〉のイメージとはあまりにもかけ離れ、「こんなはずではない」といういたたまれない思いから生まれた、殆ど反射的な行動だったのでしょう。弟子たちは皆、この世の虚栄の中における自己実現にイエスを利用しようとしていたのです。イエスの惨めさは、彼らの傷ついた自己イメージそのものだったのです。
しかし、そうした弟子たちの〈人間的エゴ〉は、〈イエスの受難と死〉という耐えがたい大きな試練によって、徹底的に押しつぶされ、粉々にされ、ある種の〈霊的な死〉を味わいます。しかし、それは、傷ついた自己イメージが癒され、新たな〈霊的な命〉に生かされるために必要な〈死〉だったのです。そして、それこそ、イエスが自らを〈受難と死〉に引き渡した理由でした。パウロは言います。「キリスト・イエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と死の法則からあなたを解放したからです」(ロマ8・2)。
マグダラのマリアは、まさに、そのような〈霊的な命〉に再生した弟子たちの代表として、夜明け前にイエスの墓へ向かいました。しかし、その〈霊的な命〉の目覚めは、しののめの薄明かりにも似て、彼女自身にとって殆ど自覚できないほどのぼんやりとしたものでした。ただ、空っぽの墓のように、彼女自身何も持たずに、自分を満たしてくれる唯一の存在であるキリストを求めて、無我夢中に駆け出していったのです。
※1 『アシジの聖フランシスコの小品集』、庄司篤訳、聖母文庫、1988年、129-130頁。
※2 同書、130頁。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
