
第六回 澤ゼミ「究極のプレゼンテーションを身につける」
開始前QAタイム
Q:上司と客先訪問した際、彼のプレゼンが私から見ても全くかみ合っていなくてダメダメで、お客様もきょとんとしていました。どうやって角が立たないように伝えたら良いですか?
A:本人は自覚していますか?自覚していなかったら、直りません。ビジネスで結果を出すために何とかしたいのであれば、黙らせるのが一番です。「良かったら今回は私にやらせてもらえませんか?」「このパートは私がやります!」などと声を掛けると良いです。また、どこがダメなプレゼンなのかを言語化してみると、すごく勉強になります。
多くのアメリカ人にとって、高いところよりも人前で話す方が怖い
私はプレゼンテーションが得意だ、という方はどれくらいいますか?私はプレゼンテーションが苦手で、正直やりたくない、という方は?
(教室内、苦手な方に手を上げる方が多いです)
アメリカでの調査で、ずっと高所恐怖症が恐怖症ランキングの一位でした。ところが、2014年に逆転し、パブリックスピーキング恐怖症がトップになりました。それくらい、人前で話すということは人類にとって脅威なのです。共同作業には慣れていても、人前で話すのは「ごく一部の人」しかやったことのない作業だった。その機会が、ある意味強制的に与えられているのが現代です。

プレゼンは、高い。
プレゼンをするためには、時間を合わせることと、空間を合わせることが必要です。つまり、移動コストなど、時間と空間を共有するためのコストがかかっています。
プレゼンをするからには、その場で何か提供する、ということを命がけでやらなくてはなりません。その覚悟のない人は、プレゼンをやる資格がない、と断言します。相手の時間を無駄にするだけです。
プレゼンは、リスク。プレゼンは、チャンス。
プレゼンはリスクですが、リスクを取るからこそ、チャンスにつながります。
キング牧師の有名なスピーチ、 ”I have a dream."
12分目に8回くらい言っています。
ヒトラーは「労働者に仕事とパンを」という言葉選びで民衆の心をつかみました。
ウォルト・ディズニーは「大人のための遊園地を」というコンセプトを理解してもらえず、100回以上銀行家の前でプレゼンしました。最終的には模型まで作り、何とか融資を引き出して、今の大きな成功を収めています。
プレゼンだけが世界を変えてきたのです。プレゼンは、成功へのスタートラインになっています。
プレゼンの3つの要素
・ビジョン
・核
・実践テクニック
一般的なプレゼン講習で取り扱われるのは「実践テクニック」です。でもここは全体の「2割」だと考えています。上の二つが空っぽで、いくらテクニックを磨いても、ただの「喋りがうまい人」で終わってしまいます。
Beingとビジョンのつながり
自分が喋る内容と、自分のBeingが近くないと、本気でしゃべれません。自分に嘘をつきながらしゃべらなきゃいけなかった経験はありますか?
もし、プレゼンのテーマに関して、しゃべりたいところがどこかないか?を探して、見つからないようだったら、逃げましょう(笑)それは他の人が喋った方が良いテーマです。
素晴らしいプレゼンと残念すぎるプレゼンの違い
両者とも同じ人類がやっているのに、何が違うんでしょう?
素晴らしいプレゼン
何かを始めたくなる
何かをやめたくなる
何かを変えたくなる
誰かに会いたくなる
誰かに伝えたくなる
残念すぎるプレゼン
帰りたくなる
眠くなる
別のことをしたくなる
他のことが気になる
怒りたくなる
この違いは何で起こるかというと、プレゼンを、人に行動させるためにしているかどうかです。
ビジョン=聴衆のハッピーな未来の姿
こう考えたら、しゃべるのが嫌なわけがないですよね。
そして、「誰が」「どのように」ハッピーになるのか、を具体的にイメージさせるために、「時間」というパラメータを加えます。
一日のどの時間で使う?
毎日触れる?
年に何回効果がでる?
一日あたり何分くらい利用される?
先ほどの例にもどると、
”I have a dream."
時間軸として「未来」に向けたプレゼン。すぐには変わらないことだから。だけど、次の世代の具体的なイメージを見せている。
「労働者に仕事とパンを」
食事を、ではなく、パンという具体的なイメージにすることで、時間軸として「今すぐ」感を出している。
ディズニーランドにおける「夢の時間」
ヤシの木は、ランドの外にある建物が見えて現実に帰ってしまわないように遮っている。非日常の完璧なデザイン。
ビジョンの話にもどると、ビジョンはプレゼンを正しい方向に導いてくれる北極星です。では、プレゼンの「核」とは?
プレゼンがうまい=しゃべりがうまい?
これについて、「ドンペリ」「安い500円のスパークリング」「バカラのグラス」「紙コップ」の組合せでたとえてみます。

「ドンペリ」×「紙コップ」(あ、ドンペリか。でも紙コップいまいち!)
「500円」×「バカラのグラス」(グラスに入れるとまあまあおいしいね)
ここでもし、グラスを10万円のグラスに変えたとしても、味はそこまで変わりません。ドンペリの方がおいしいです。そして、
「ドンペリ」×「バカラのグラス」(うまい!)
「500円」×「紙コップ」(最悪!)
しゃべりを磨く、というのはグラスを磨くということ。
中身が良い、ということには100%勝てないのです。
中身が「あなたはどんな人ですか?」というBeingと一致しているかです。Beingが一致していないとプレゼンに濁りがでます。迷いがでて、言葉の端々にごまかしが入ってきます。そうならないためには、自分はどんな人で、それをどういう風に信じていて、というところを言語化していかなくてはならない。つまり、Beingを言語化するというのがプレゼンの究極のところになります。
己を知り敵を知れば百戦危うからず
です。(聴衆は敵ではありませんが)
あなたのプレゼンの相手は誰ですか?
Beingを言語化したら、プレゼンの相手が誰かをできるだけ具体的にイメージします。冒頭でやったように、アイスブレイクも兼ねた質問をします。今回は、「プレゼンが苦手」という方が多かったので、そちらにフォーカスしてお話しすれば良いな、とわかります。「あるある」な質問、「心を一つにする」質問を考えていくと良いです。
そしてターゲットが変わっても大丈夫なように誰でも歓迎!的な準備をします。そのためには「文字が少ない資料」でプレゼンします。
プレゼンテーションは「プレゼント」です。相手によって最適なプレゼントは変わります。聴いている人の誰も置き去りにしないようにします。
製品・サービスの説明≠参加者の期待値
スーパーカーの素晴らしさを説明しようとして、ついやりがちなのが、「エンジン」「駆動方式」「最高出力」「最大トルク」…といった形でスペックを並べてしまうことです。そうすると何が起こるか?聞いている人は比較を開始します。この出力なら、あっちの車も負けてなかったな…とか。

そうではなくて、
いつもの道の40キロ走行が別世界になりますよ!
といった、普段の車とは違う体験を語るのです。体験が人を動かします。
人を動かす二つのもの 共感と脅迫
「脅迫」は一時的には効果絶大ですが、原因がなくなればおしまいです。下手をすれば真逆の行動を引き出してしまいます。銃を突きつけられてお金を取られたあとに、次の日同じ人に会って「あ、お金を出さなきゃ」と思いますか?警察に突き出しますよね。
「共感」は時間と手間がかかるけれど、確実で、長続きします。ファンになってもらえれば、行動が自動化します。好きなアーティストのCDは、頼まれなくても買いますよね?興味のないアーティストに、CDを買ってくださいと頼まれて、買いますか?
ただ、ファンになってもらうまでが大変なのです。そのため、自分が信じられるもの、Beingに一致したものをプレゼンするのが大事です。

良いプレゼンかのチェックポイント
すべてのプレゼンの主語を「みなさん」に置き換えられますか?置き換えられない場合は、話し手の都合でお話ししている可能性が高いです。主語が「会社」や「製品」になってしまっています。
「一般論」は響きません。人は自分事で動くのです。「自分」を主語にしましょう。
聴衆が持ち帰るものは何ですか?
聴衆が会場を出た後をイメージできていますか?会場を出た後の行動を含めて、コンテンツです。どんな場面で共有されるのでしょう。
プレゼンの核とは、顧客が持ち帰って配れるものです。

ナポレオンなど歴史上の人物は、テレビも、ましてやインターネットもない時代に、どうやって何万人もの人心を掌握できたのでしょうか?
例えば織田信長が、周りの人に「俺、天下統一するわ」と言います。それが口コミで「信長さん、まじやべー」「銃も取り入れるらしいよ。かっけー」という伝言ゲームで伝わり、だんだん盛り上がって、最前線の兵士までが、やる気を鼓舞された状態で戦えたのではないでしょうか。伝言ゲームを制す者が世界を制するのです。
実践テクニック パワポ作成チェックポイント
やばい資料の例を見つけたいならここ…の省庁スライドを投影しながら、やばいポイントを説明します。「極彩色」「文字だらけ」「フォントが全部違う」、やっちゃいけないことの総合デパートです。
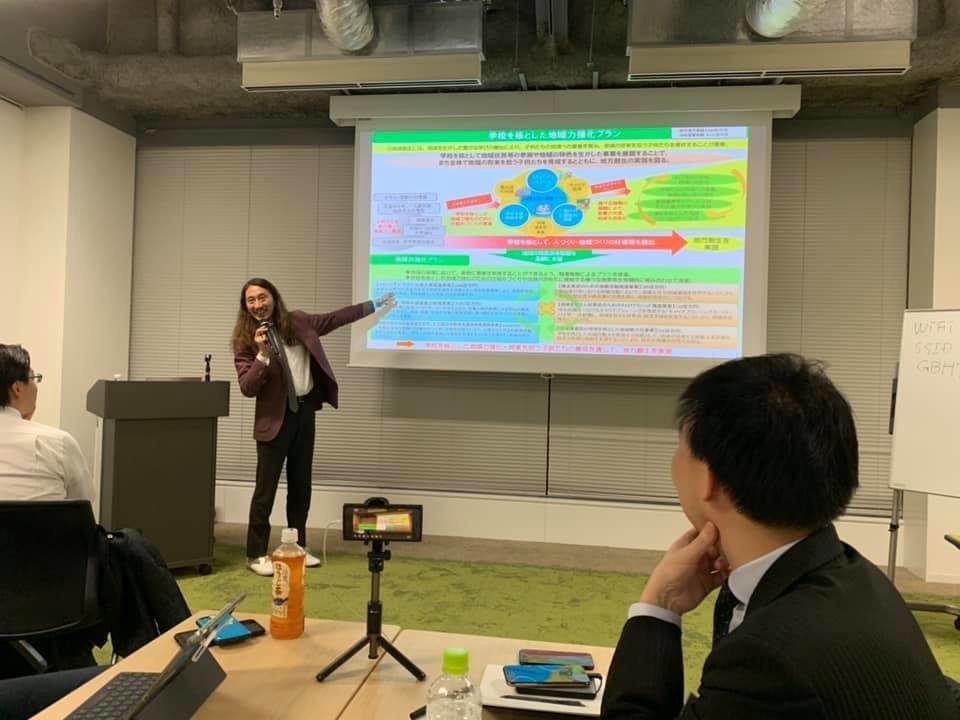
文字で説明する必要はありますか?
選んだ色に意味はありますか?
端から端まで文字で埋めていませんか?
最悪なのは、その文面に間違いがあるとき。「あ、ここ間違ってますねー」と口頭で補足したとしても、見ている人は気になって集中できません。
コツ1:文字を閉じ込める
文字を図形の中に入れてしまうことで、無駄な文章を削ぎ落とします。句読点は要りません。
コツ2:アニメーションを控える
あくまで視点誘導のために使いましょう。
いま話していることより先の文字は出ないように、タイミングを制御しています。最初に文字を全部出してしまうと、話していることが耳に入らないためです。使うパターンもなるべく絞ります。左から右へのワイプを使うことが多いです。
コツ3:改行の位置もとっても大事
こんな形にな
らないように
コツ4:視点誘導の方向は左から右 or 上から下
どこに視点を向けたら良いかをわかりやすくしましょう。
プレゼンの目的は「視線の独占」です。
コツ5:文字は半分より上に配置
スライドの一番下に文章を持ってきてしまうと、前の人の頭で見えなくなるかもしれません。
即興プレゼン資料作成タイム
プレゼンのお題について、まずは画像検索をします。例えば「セキュリティ」というお題で画像検索すると、「鍵」「盾」「パスワード」「ガードマン」などの画像が引っ掛かります。これらのキーワードを軸にロジックを組み立てます。
今回はゼミ生から出た「男梅サワー」で作って行きます。「男」「梅」…
思ったように画像が出てこないときはちょっとずつキーワードを変えます。
キーワードをぱかぱか入れて、画像をひっかけて行きながら、鮮やかな手際で資料ができていく過程を見せてもらいました。
※今回はこの場限りなので、検索結果の画像を使いましたが、普段は使いません!Adobe Stockというサービスを活用しています。
PowerPoint デザイナー機能を使えば、画像を2枚引っ張ってきただけで、どんな配置にするかデザインを提案してくれます。
(Office 365のみの機能のようです…)
また、図形の位置を中央揃えにする「配置」のボタン。これを左上ショートカットにおいて使っています。
ストーリーを前もって考えておくと、50-60枚のプレゼン資料を3時間で作れる、とのこと。自分がどれくらいの時間でできるのか、前もって知っておくことが準備に大事ですね。
でも、紙で説明しなくちゃいけない…
そんなときは、「続きはWebで!」
もしくは、QRコードを張り付けて、紙には全部書きません。
その場でブラウザで直接コンテンツにアクセスしながらプレゼンしたり、ダッシュボードでデータを見せながらプレゼンしてしまいましょう。元データをみる、という習慣のない会議が多いですが、資料化されているのは、資料化した時点の「古いデータ」です。常に最新のデータで会議をしましょう。過去のことをいじりながらやると、無駄はなくなりません。
話し方チェックポイント
1分プレゼンの課題がありました。自分のビデオはチェックしましたか?
立ち姿勢
正解はなく、自由です。かっこ良く立ちましょう。このゼミでは「中心線をちょっとずらす」という立ち方をしています。今回はクローズドのサークルなので、リラックスした姿勢をみせています。
手の位置・動き
手の位置は決めておきましょう。腕を組むと「距離を取っている」、手を後ろに回すと「手の内を見せない」という印象を相手に与えます。
頭の位置・動き
意味のない首の動きはしていませんか?視覚ノイズを減らしましょう
プレゼン本番べからず集
背中で語らない
ずっとスクリーンを見てしゃべっている人は、聴衆の方を見ましょう。好きなアーティストがずっと後ろを向いて歌っていたら、嫌ですよね?プレゼンテーションはファンサービスです。
口角を下げない
特に男性は要注意です。筋肉は使わないと衰えます。口がうまく開けないと不機嫌そうな声になり、悪循環が起きます。笑顔を徹底的に作る練習をしましょう。
ステージ上を漂わない
動くなら、きちんと動きましょう。投影しているスライドにかぶるとノイズになります。
決死の覚悟でギャグを言わない
これは絶対に守ってください!
アイスブレイクはあった方が良いですが、勝負をかけないことです。最初に滑ると、そのあと凍りついた空気の中プレゼンをする羽目になります。ちょっと大げさな表現を使うくらいにとどめましょう。
全部書いてあります!
アンテナを立てましょう
発信することで、周りの人がヒントをくれます。発信する場所はTwitterじゃなくても、Facebook、インスタ、LinkedIn、ブログなど、自分に合うもので良いです。量が増えれば、フィードバックを受ける量が増えます。例えば「会議では自分が最初に発言する」「みんなに同じ質問を投げてみる」などでも良いです。
もう、「本番」が始まってます
最高のプレゼンをして、人生の成功を手に入れましょう。
最後のQAタイム

Q:たとえ話をうまくできるようになるには?
A:実はここはまだ言語化できていない部分です。物事の本質を言葉に落として、共通項を見つけることだと思います。たとえば、「数が少ない」というキーワードであれば、「天然記念物」「珍しい苗字」などを思い浮かべて、そのあとのストーリーが展開できるものを選びます。
Q:質問されたときに、答えを順序だてて話せません。キャパシティを広げるにはどうしたら良いですか。
A:大前提のマインドセットとして、質問には答えなくても良いです。質問に答えなくてはならない、怖い!という気持ちがプレゼン恐怖症につながっています。質問に答えるのはサービスです。答えれたら相手にとって幸せですが、答えられなかったらごめんなさい、で良いです。ファンを作るためには、「良い質問ですね」と言って一旦受け取ります。そして、直接の答えではなく、代わりのものを渡して帰らせる、もありです。たとえば専門家につなげてその人から答えてもらう、なども考えられます。
自分のライブラリに答えがあればよいですが、答えがない時点で準備不足なのです。ライブラリに追加すべき質問をもらった、ありがとう、ということです。
Q:テーマがBeingに近い、ということについてもう少し知りたい
A:普通のプレゼン講習ではあまりBeingの話はしません。今回は、そこが離れていると本物のキャリアにならないよ、ということをお伝えしたかったのです。テーマのなかで自分のBeingに近いところを探しましょう。誰が話しても同じ話ではなく、自分の体験に基づいた話は、生き生きします。
Q:場合によっては「このままじゃだめだ!」という「脅迫」によるプレゼンも必要では、と感じます。
A:「そんなことねーよ!」と反論された瞬間に、説得力のないプレゼンになってしまうリスクがあります。ある程度「成功しているっぽい」プレゼンにはなりますが、極上のプレゼンにはならないと考えています。
Q:声の出し方について教えてください
A:「鼻腔共鳴」を使います。口を閉じた状態で声を出す練習をします。ハミングをしているときの声の出し方です。声が大きくなるので、テレコンのときなどはマイクを調整しましょう。
Q:ストーリーラインの作り方を教えてください
A:スライドに集中してストーリーを考えてはいけません。オーディエンスを見ましょう。お客さんが喜ぶところを想像します。ワイガヤのディスカッションも効果的です。「○○さんはそれ知らないから説明したほうが良いね」など、必要なパラメーターが見えてきます。
最後には良い話で終わります。「AIが進化したら人類はどうなるんですか?」というテーマだとしたら、「未来は自分たちで作るのです。どんな未来にしたいですか?」という終わり方にします。劇場型のストーリーで感情を動かし、泣かせる要素をストーリーに込めます。
Q:核をみつけるには?
A:インスタントにはできません。ずっと考えて、それに興味を持ち続けることです。全然知らないことをプレゼンしなくてはならないとしたら、まずはそれに触れることが必要です。全然興味が持てなければ、誰かに押し付けましょう。
Q:紙一本で勝負しなくてはならないのですが、どうやったら人の気持ちを動かせるかわかりません。
A:そもそも、「紙一本で勝負しなくてはならない」ことはないのでは?物を見ていてはだめです。人を見ましょう。ちゃんと相手の人が見えていますか?ヒアリングが大事です。
50代60代の人に伝えても、できない理由を延々と語られることがあります。立ち止まると、思考が止まります。辛辣なことを言うのも、人生を前に進めるためです。その人に対して興味を持って深入りする。当事者意識をもつ。感情移入できない人に対してはアクションを起こすことはできません。
Q:コミュニケーションでは「相手を変えようとしない」のに、プレゼンテーションでは「相手の行動を変える」のを目指すのでしょうか
A:行動を変えるのではなく、行動を引き出すのです
最後の記念撮影!

そして最高の懇親会!


澤さん!運営のみなさま!ゼミ生のみなさま!
本当にありがとうございましたー!
文:澤ゼミ生 加藤美野、中田皓一
写真:辻貴之、溝口大悟
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
