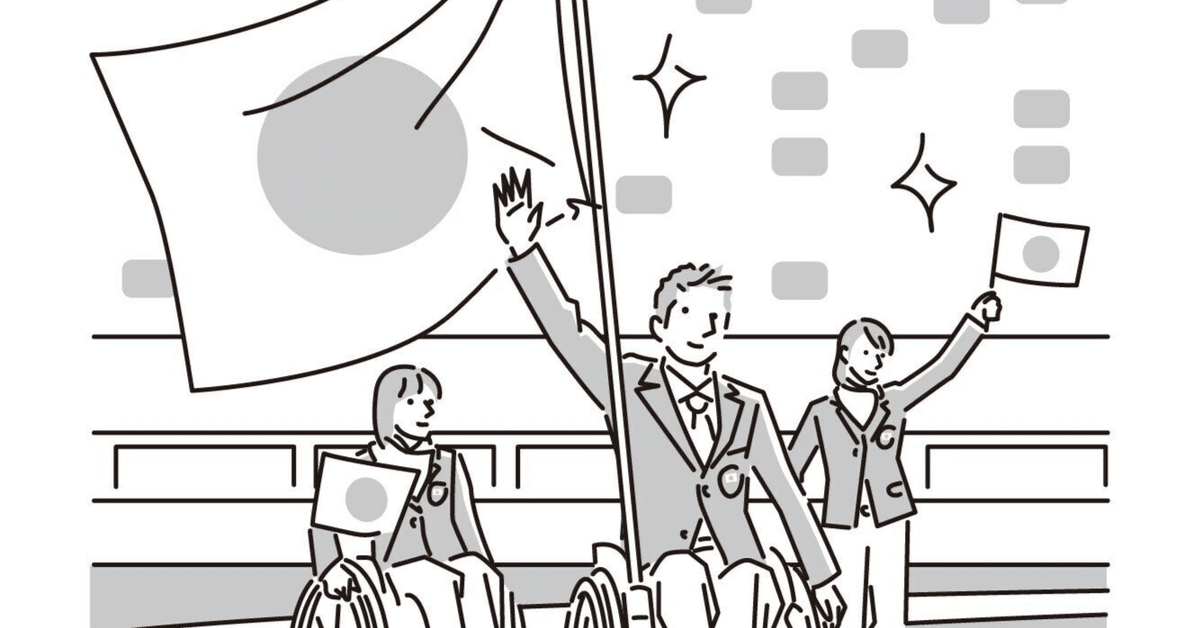
1964→2020いま、再び。その先へ。~オリンピック、パラリンピックの枠を越えて~ 横浜市緑区企画・パラリンピック記録映画上映会/NHK解説委員・竹内哲哉さんと観て
6月26日。長津田の横浜市緑区民文化センター「みどりアートパーク」のギャラリーで、1964年に開催された東京パラリンピックの記録映画(NHK制作)を鑑賞した。
会場には、NHK制作局副部長兼解説委員で、スポーツ、パラリンピック、福祉を担当される竹内哲哉さんが登壇していた。竹内さんは2ヶ月後、NHKの第一線の現場でパラリンピック報道に携わる人だ。
こんなふうに、自国開催前の番組準備でお忙しいなか、週末の時間を使ってご自身の大切なテーマであるパラリンピックについて語る時間をもち、ご自身の車椅子ユーザーの視点や、記者、報道の立場や経験から言葉を地域の人とやり取りする姿は、(上から目線にきこえたら失礼だけど)偉いなというか、いいなと素直に思った。
メディア、ボランティアなどを含む大会関係者は「パラリンピック(オリンピック)・ファミリー」と呼ばれる。世界から大会に携わる人々が飛行機の乗り降りで優先レーンを通ることができるのは、彼らが元々偉いとか身分が高いとかそんなことはない。一人ひとり、大会運営の一翼を担い、国内外で身の回りの人々に大会の意義を広める大きな広報力となるからだと思う。
もちろん、批判されるように、もし大会の運営が商業偏重に行きすぎるとすれば正されるべきで、そういう意味ではオリンピックにおけるパラリンピックの意義は大きく評価されていいと思う。
映画の内容
映画は、モノクロで45分にまとめられていた。東京開催となったパラリンピックは、1948年からイギリスのストークマンデビル病院で毎年開催されていた脊椎損傷者、車椅子の障害者のためのスポーツ大会に始まり、1960年ローマ・オリンピックと同時期に開催された大会を第1回パラリンピックとして位置づけた。
もちろんそこにグッドマン博士の功績があり、いよいよ64年、東京大会では大分の中村裕氏が 選手団長を務め、車椅子だけでなくさまざまな障害に目を向けた第2部大会を開催したことで、もう一つのオリンピックと呼ぶに相応しい枠組みに前進した。
(64年)東京パラリンピックに参加した22カ国のうち提唱国であるイギリス選手の多くは障害のない人と同様にあらゆる職業に就いていた一方、日本選手のほとんどが箱根療養所の利用者だった。リハビリのスポーツどころか、障害者とはみな若くして人生を諦め箱根で余生を送っているような存在だったということに気づかされた。このカルチャーショックのエピソードは、あちこちで聞かれるようになったと思う。
つまり、64年は「リハビリ」「医療」のためのスポーツの重要性が認識され、健康になることによって、障害のない人同様に働くことができることを証明した。
64年パラリンピックはオリンピックとセットで行われたことで注目を集めたし、海外選手とのギャップ、出場経験をきっかけに、選手や関係者を中心にした意識の変化をもたらし、障害者の医療や就労環境の進歩につながっていった。
そして、今
それから約60年が経とうとする、東京2020パラリンピックで、私たちの課題はなんだろうか。64年に就労の機会の平等性について認識されたことが、いま実際の社会ではどのくらい復旧しているだろうか。
「今年2月、日本の法定雇用率は2.3%になった。」という。ここだけ見ても、日本がお手本にしている欧米社会に比べると、まだまだ低い。
いま日本で「インクルージブ」「ダイバーシティ」と横文字で叫ばれるなか、さまざまな障害の違いについて日常的に馴染みのある人は少ない。「違いのある人がいるのは当たり前」という状況が日本社会に受け入れられているといえないと思う。
東京2020パラリンピックはどんなレガシーを残せるのか
1964年から2021年。約60年。
戦後の高度経済成長で先進国の仲間入りを果たした日本。バブルを迎え、バブルが弾け、現在は少子高齢化が進行している時代。
東京2020に向けては、2016年招致活動も含めて2008年あたりから運営準備が始まり、2013年9月のIOC総会で開催が決まった。
政府による「アンダーコントロール」などの嘘は困る。開催国が一つになるのを妨げてしまうし、無理のある行為が世界からも批判されることになる。
同時に、国民を元気付ける解決策の一つを勝ち取った。
現在につながる流れは、2012年ロンドン大会を新たな起点とし直近10年くらいの大会準備で考えたことを、コロナ禍でさらに深く考え、何をどう未来に生かせるかが課題だろう。
日本財団パラサポセンターが業務を担ってきた部分は、パラリンピック教育「I‘m Possible」をパラリンピックとして独立した教材とし、広めていることで、一つレガシーのになると思う。
一方IPCでは、世界中のパラリンピアン、習熟したアスリートたちに協力を求め若いアスリートを対象にした教育のプログラム(Proud Paralympian)を行なってきた。この10年のなかで着手され、今後のパラリンピックムーブメントを担うツールとして鍵となっていくだろう。

(写真・PARAPHOTO/Genki.YAMASHITA 2017年 Dubai Asian Youth Para Games, Proud Paralympian)
パラリンピック教育については、元IPC会長のフィリップ・クレーヴァン氏のときにバンクーバー大会(2010年)から引き継ぎ、ロンドン大会(2012年)で完成させた教育でもある。IPC理事でパラサポセンター長の山脇康氏は、I'm Possibleについて「レガシーは計画することができる」と話していた。
パラリンピック、パラスポーツによるレガシーの計画そのものは、I'm Possible、Proud Paralympianのみではない。
JPC日本パラスポーツ協会が統括する競技団体それぞれの活動、指導者育成活動、自治体の全国障害者スポーツへの派遣などがベースにある。全国障害者スポーツ大会とパラリンピックのクラス分けは連動していない部分は、早く整理していたらよかったのではと思いもする。一方でパラスポーツ全体はパラリンピックだけではない、上映会で竹内さんがいうようにスペシャルオリンピックスやデフリンピックなどまったく違うあり方を示すことで、生涯スポーツとして多様な可能性の土壌となってきたことは大きい。
その多様なベースを活用しつつ、JSC日本スポーツ振興センターなどがオリパラ種目で選手発掘プロジェクトを行なっていることも近年形になってきている。
東京2020パラリンピックは、ベースとなる多様なスポーツ活動の頂点の部分で成り立っていると思う。東京2020後は、培われてきたパラスポーツ全体の積み重ねられた思いをあつめて手を携えていくことが必要なのではないだろうか。
日本のパラスポーツ・コミュニティ
2013年に東京開催が決まってから、日本財団を始め多くのパラリンピック・ムーブメントの担い手といえる個人、コミュニティ、法人が名乗りをあげ、夏・冬2回のパラリンピックを中心に体験交流やアスリート雇用の促進が試みられた。
メディアもこぞってパラリンピックにつながる大会やアスリートに注目して報じるようになった。
ただそれは、自国開催での盛り上がりで一時的な脚光をあびただけの「パラリンピック・バブル」であって、バブルはもうすぐ弾けてしまうかもしれない。
忘れてはいけないのは、そもそもわたしたちは何を目指していたのか?コロナ禍によるオリパラ延期が暗い感染症の禍であるだけではなく、パラリンピックのレガシーや求めてきた社会とは何だったのか?を冷静に見直す時間になっていると思う。
その答え(=パラスポーツのレガシー)を長年探してきた競技団体、障害者スポーツ指導員やコーチ、研究者、体験教育を提供してきた団体などパラスポーツの振興をテーマに現在も多くの人々が活動している。
「94年アトランタパラリンピックの“レガシー“は、どんな障害のある人もスポーツができるようになる」ことを目的にしていたと、当時を知るNPO法人パラキャンの中山薫子さんは話している。
98年初めて知的障害の選手が参加して開催された長野パラリンピックのあと、長野でのウインタースポーツのバリアフリー化が進んだことを、トリノ冬季パラ(2006年)への取材の中で会場運営に携わった人々の話から聞くことができた。

(写真・PARAPHOTO/Genki YAMASHITA 2016 Rio Paralympic games/観戦で訪れた中山薫子さんらパラキャンのメンバー)
フィリップ・クレーヴァン氏とも交友関係にある中山さんは、アトランタオリンピック・パラリンピックに通訳として従事していたとき、車いすバスケットボールに出会い魅了された。日本に帰国して選手たちとパラスポーツ教育をテーマとする「パラリンピックキャラバン(現パラキャン)」の活動を始めた。毎年170校を超える学校、PTAなどと今も活動を続けている。
「ファンのメディア」の活動
私自身は、2000年シドニー大会から、パラリンピックの写真配信、NPOメディアとして大会取材に関わっている。現地へ初めて行ったのは夏はアテネ大会(2004年)からで、すでにパラリンピックが「スポーツ以外のものでない」ことを証明していた。
ここに、シドニーへ行った仲間が持ち帰ってきた映像がある。現地で記者はビデオ撮影を禁じられていたことを知らずにカメラを没収されるなど処分を受けながら撮影した映像だ。
確か私は取材者を派遣したと思うが、そこには、応援する取材者の悲鳴が収録されていた。この人知れず手元にある映像を見て、自分たちの関わり方の本質を計画する上で「ファンのメディア」というあり方を受け入れたと思う。それはもう、パラリンピックはスポーツでしかなく、64年のような社会変革の意識がつよく芽生えたというより、スポーツファンとして楽しまなければ「もったいない!」というごく軽い(?)気持ちだったかもしれない。
現場をじかに見ることで、その場で感じることで、その人自身が確信する。そして、自分の住んでいる社会や環境の当たり前を変える力となることができる。ただパラリンピックを観戦すればいいのだから、ある意味「簡単だ」と思った。
しかし、64年の記録映画の世界を過去のことと笑いとばすことはできない。当初「スポーツそのものでしかなく、ファンとして楽しむだけで“当たり前“の認識が変わるだろう」と、思っていたが、情報として伝えるだけではまだまだ説得力が足らなかった。あらゆる見えない認識の壁がわたしたちの社会にはびこっている。
長期戦となるが、少しでも邪魔な壁の存在が顕在化されていけばメディアとして楽しみながら取材し、パラスポーツの魅力を伝えることができる。

(写真・PARAPHOTO/Manto NAKAMURA 2018平昌取材班)
2013年9月、自国開催が決まり心から安堵した。多くのメディアがテレビや記事で伝えていることを、日本の観客に直接みせることができる。何よりだ、と。しかし、コロナで無観客となってしまえば、自国開催の意味は半減する。
パラリンピックは、多くの人に間近で見てもらい、証人となってもらい、伝えてもらうことが大事だからだ。とても困ったことになっている・・と誤算を認めざるを得ない。
知的障害者のパラリンピック
長津田の横浜市緑区民文化センター「みどりアートパーク」で一緒に鑑賞していた市民の一人はスペシャルオリンピックスのボランティアをされている方で、(パラリンピックは)「知的障害についてはまだ選手基準が曖昧なのではないか?」という意見をぶつけてきた。
竹内さんは「2000年シドニーパラ健常者替え玉事件」について話し、12人中10人までが健常者であったという不正事件で知的障害クラスが出場停止となり、現状では、陸上・水泳・卓球のみがパラリンピックに参加できること、しかし重複障害などでパラリンピック参加資格のある選手はいることなど、また、聴覚障害はパラリンピックへの参加意義について自ら参加を退いた経緯があることなどを説明していた。
事件の原因は「障害が見えない」ことである。プレーヤーがうますぎて確かに障害があるのかどうか、わかりづらい。そこを逆手にとったスペイン選手団による犯罪で、選手はとばっちりを受けた。
知的障害の3競技がロンドンパラリンピックに復帰したが、問題を起こしたバスケットボールは20年以上経った今もパラリンピックへの復帰が見えない。
「シドニーパラリンピック健常者替え玉事件」
現在の知的省害バスケットボールの選手たちはどうしているだろうか。
2000年シドニーへ選手団はじつはこの横浜で活動するチームを中心に強化され、派遣されていた。そのときの選手は今はコーチとなって現在も活動をつづけている。わたしが取材を始めるきっかけとなった事件でもあったため、少し前にも取材しているので紹介しておきたい。
https://www.paraphoto.org/?p=24729
この事件を振り返るスペインの映画「CHAMPIONS」に関するレビューも書いたので、あとで読んで頂けたらと思う。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5e057b47e4b05b08babe1715
そして、今・・・
パラスポーツに関わる人々は、さまざまな経験を経て、東京2020を迎えようとしている。成熟した先進国のクールなオリパラが世界中から求められている。
しかし、コロナ禍で史上初の延期となり、時間を過ごす中で、教育現場で必要なIT化の遅れや、スピードが求められるワクチン接種の遅さ、政府、官僚の汚職、トップのたび重なる退任(JOC竹田会長、安倍首相、東京組織委員会・森会長)・・と、開催都市は良い面ばかりではないとはいえ「ロンドンに習う」など申し訳なく言えないような醜い問題が浮上し、開催国という世界的な注目が裏目に出ることが続いて起きている。
この時期、どんな良いことも、よくない事も、オリパラと結び付けられ、情報が膨れ上がる。大会イメージを直撃することは、覚悟しておかなければならないのだろう。
オリパラやスポーツは社会を良くするさまざまな問題解決策の一つ、スポーツ振興だと思う。コロナ対策がオリパラのためだけに遅れたり、ビールを提供するための忖度で観客の有無が議論されているわけではまったくないと思う。感染症対策はもちろん重要だが、海外からの観客の受け入れがなくなったいま、いずれにせよ観客はほんのひと握りとなるだろう。
ワクチン接種が進んだ欧米では、多くの人々がスポーツを欲している。イギリスではまもなく大きなサッカー大会が観客を入れて開催されるという。チェコではすでに2000人の観客を入れて、パラアイスホッケーの大会が行われ、その様子がIPCのニュースでも報じられている。
日本で欧米と同様にオリパラを運営しようとすれば、現状、日本の国民の理解を得られない可能性が高い。批判モードは簡単に静まらないだろう。ウガンダ選手団9人中2人が陽性だったことをみても、今後コロナ対応は大忙しとなることは間違いなさそうだ。
この時期に、この映画を観た人がパラリンピックの原点を考えたり、単なる昔話ではないことに気づいてくれたら嬉しい。
東京パラを伝えるオフィシャルメディア、そのもっとも重要な竹内さんとこの作品を観る時間をもつことができ光栄です。企画してくれた横浜市緑区役所の皆さんに感謝します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
